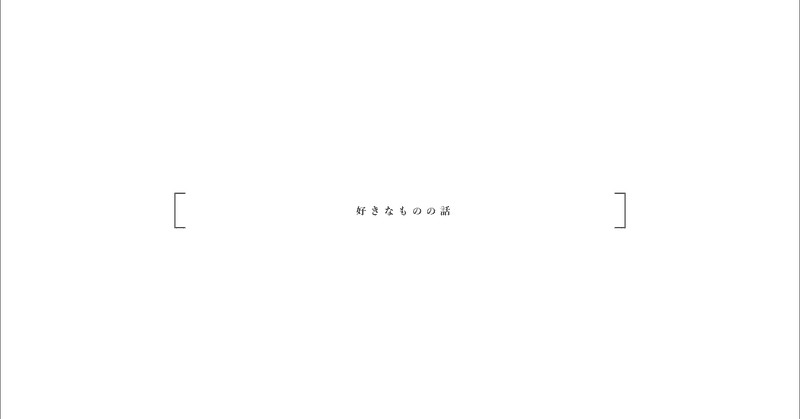
[日録]好きなものの話
June 3, 2021
一番好きな映画を訊かれたら『羅生門』と答えるようにしている。本作が今から凡そ七十年前に海外の映画祭で大暴れしてくれた御蔭で日本映画と云うものが世界中へと広く知られることの契機となった云わずとしれた黒澤明監督の最高傑作の一つであるが、私は其の功績が素晴らしいと云う理由から本作の名を挙げるようにしているのではない。黒澤明の映画のみならず、邦画と呼ばれるもの自体殆ど観ずに洋画許り観ていた大学二回生の私にとって、此の作品を初めて観た時の衝撃は映画祭当時の外国人たちと同様であったのかは分からないが、兎に角とんでもないものを観てしまったぞと慌てふためいてしまったことは真実である。それからというもの、私は洋画だけを観ていた自分を恥じて邦画への理解も深めていこうとし、先ずは黒澤明の全作品を観ることから始め、次に小津安二郎へと手を伸ばしたが最後、原節子に恋をするほどに至った今ではよもや洋画/邦画など関係なく、何れも "映画" として触れ、然う観る目を養うことにも繋がっていったのである。此のように人生を今一度包括した上で捉えると本作は私に大きな影響を与えたことは明らかである為、私は金獅子賞よりも遥かに価値の劣る森乃央歩映画祭名誉作品賞を受賞した映画であると勝手に位置付けているだけに過ぎず、其れと答えたからといって、熱を上げて三船敏郎について喋り始めるほど子どもにも成り切ることがもはや出来ない。自分にとって一番であるものが挿げ変わることなど、四捨五入すれば三十ともなる人生を歩み続けていれば幾度となく経験してきた。無論、だからこそ、賞と云うものが当時の世俗を客観的に感じられる意味でも大切なものと成り得るのであろうということにも頷ける。此の世は諸行無常故に、今此処が何であるのかを理解する為にも然う考える時間は必要なのであり、畢竟、是は移ろい行く日常を確固たるものと認識付ける行いとなるのかもしれない。詰まり、『羅生門』は今尚私の一番好きな映画作品であるが、一番好きという感情自体も常に移ろい行くものにほかならず、であれば私も其の移ろいに身を任せては我が脳内映画祭の最高顧問であることから降り、水無月も始まり心機一転、我が心に宿る嘗ての体験という湖に浮かぶ月でも眺めながら、其の肩肘を付いている "今" の此の私が好きなものを捉えてみようではないかと思い至り、本文章を書き綴っている次第である。では早速、映画/音楽/漫画/小説といった四つのジャンルから其々一作品ずつ、十分程度じんわり考えてみてから簡単に挙げていこうと思う。
*
映画:『五つ数えれば君の夢』(監督・脚本:山戸結希/2014年)
東京女子流なる五人組のアイドルグループを全員主演として扱い、それぞれの少女たちが女子校の女生徒に扮し、女の園で繰り広げられる文化祭の開催までの彼女等の様子を追って行く映画であるが、エンドロールの其の終わりまで、素晴らしい映像感覚で引っ張っていってくれるので、私のような偏屈で無愛想な者でも非常に楽しめる作品である。本作を初めて観たのは三年前で当時の私は映像制作を仕事として行うようにも成っていたが、漸くの休みを楽しもうと何の気無しに選び抜いた此の映画を見るや否や一カット目から其の才能の片鱗に触れ、もしやと思っている内に映った二カット目が目に飛び込んで来た瞬間に "もう映像作るの止めよう"と思わされるほどに衝撃を受けてしまった。其のような冒頭からタイトルコールまでの映像も縦横無尽でありながら正気とは思えないほど流麗且つ綺麗で、其の編集はまるでラース・フォン・トリアーの『エレメント・オブ・クライム』を想起させるほどのスムーズさであり、其の昔、何方かが山戸結希監督を "ゴダール" と形容していたらしいが、此のずば抜けた映像センスを見せ付けられては成程と頷くほかない。私はレオス・カラックスやポール・トーマス・アンダーソンの作品を観ていると、其の何とも形容し難い魅力を見ては "嗚呼、此の人たちは映像に愛されているんだなア" と羨んでしまうのであるが、山戸結希監督には同様の感覚を覚えた。誤解無きよう伝えたいのだが、本作は堅苦しい映画通の為の映画などでは決してなく、いや、本作を取り上げて論文を書くことは単純なるショット分析だけに止まらず物語其れ自体を元にすることも果てはジェンダー論等々に始まり社会学的な見地から書くことも出来得るだろうが其れは当事者が容易に扱える代物だから然うするのではなく自然と然うするに至らしめるほど感情に訴えかける純なるものということの証明でもあり自他ともに非常に有意義なものと成り得るであろうし是非とも私も読んでみたいとも思うのであるが、然ういったことは傍に置いたとして、此の映画は純粋に少女の為の映画であり、其の展開などは萩尾望都先生の少女漫画を思わせるほど淡々とストーリーが進行していく非常に分かり易い映画作品であるとも思う。然し、其れが何よりも恐ろしいのである。監督自身が好きだという "アイドル" と云う方々を演者として扱い、其の見事な映像センスを以てして "映画" を作れば "これ" に成りますの "これ" が常軌を逸するクオリティで、同じ映像制作をする人間としては強く恥じ入るほど身の程を知らされた作品である。私は山本リンダや山口百恵など、所謂 "昭和のアイドル" は好きではあるが、AKB48に始まり "現代のアイドル" と云うものにはさして興味が無い。其のような私が若しアイドルを題材にして映画、はいドウゾ! と云われて仕舞えば、余生を全て費やしたとしても同じレベルの映画を作ることは望めないだろうと痛み入る。其れ程、圧倒的な説得力を持った珠玉の作品である上に、終始、美しい少女たちが奮闘する姿を眺めている内に彼女たちの環境が身に積まされ、遂には他人事とは思えなくなるほど没頭して仕舞い最後のカタルシスへと突っ走って行く見事な青春映画でもあるので、是非とも老若男女問わず皆に強くお勧めしたい映画であります。
*
音楽:『なないろ』(BUMP OF CHICKEN/2021年)
熱心なファンでは無い上に初めて音源を聴いた時は何処か居心地が悪く感じられあまり好きな曲では無いのかもしれないと判断して以来聴くことはなかったが、其の翌日くらいにいつものようにYouTubeのホーム画面を開くと本楽曲のMVのサムネイルが偶々表示されていた為興味本位からどれ見てみようとクリックするや否や4K画質で展開される大友克洋に端を発する超能力ものを想起させるも其の実は少女の邂逅がテーマであり二人は手を取り合う必要があるのだとしている手腕が見事なことに加え一方向に容赦なく落ちていることから来る不自由さと同時に空を飛び回っている自由さをも感じられる設定と其れを支える此のカメラワークと其の演技を指示した監督の演出の妙に素晴らしいというほかなかった。カットバックする回想シーンは美しくも切なく感じられ、とりわけ最後の抱き合って落ちていくシーンは感極まり涙も出そうになるが其処でついと差し込まれる回想シーンが明らかに "楽しい" さまを感じられる躍動感を持っており、美しく切ないながらも良き思ひ出と同じように楽しんだあの日の体験を追憶させられ、詰まりは此のMVは楽曲から受けたインスピレーションのみならずBUMP OF CHICKENが持つ音楽性其れ自体と呼ばれるものすら的確なまでに表現しているなアと感じてしまい、思わず唸ってしまった。音源を聴いた時の居心地の悪さとは、決して音楽が悪いということではなく個人的なものに過ぎず、単に如何いう姿勢で聴けば良いのかが掴めなかったと申した方が適切かもしれない。私は、音の質から魅せる世界が清涼なものであることは分かったのだが、ドリーミーで柔らかなシンセサイザーと思しき音が絶え間なく流れていることに対して受ける印象は徐々に物語が展開していくというよりかは "既に何かが始まり今尚続いている" ということであり其れは簡単に言うと一方向的に無闇に進んでいるように感じられてしまったのであるが、MVで表現されている世界を見たことにより成程と合点がいった。嗚呼、是は落ちているのだなア、其の発想は無かったなア。私には此のような映像は作れないのだろうなア、いや、本当に作れないのだろうか? と、思考の奈落へと落ちていく契機にもなった。そして、つくづく歌詞が素晴らしい。日本音楽著作権協会が此方を見ているような気もするので、あまり触れないが、兎も角歌詞を踏まえて映像を観ると、捉え方というものもほんに色々あるんやなアとまじまじと考えさせられる。空のシーンイコオル冒頭の少女が抱く内的宇宙であることは直ぐに分かるが其処に出てきたもう一人の少女は何者なのかという問いは結論の出ない問題ではあるが敢えて答えようとするのであれば一番安直なものとしては "是は『インサイド・ヘッド』である" と割り切ってしまうことであり、詰まりは二人の少女は其々が何かの感情を意味しているということで順当に考えたならば黄色は明るいイコオル楽しい印象を、青色は冷たいイコオル悲しい印象を皆が受けるだろうし此のような暖色/寒色で感情の別を表すというのは珍しくも無いが故に我々の無意識下にも刷り込まれている部分乃ち或る種の本能に訴え掛けることにも繋がるため我々は否応無しに本作からは感情を直接的に揺さ振られることになるのであろう。本作の表層的なテーマとして私が勝手に感じたことは "内的宇宙でAKIRA乃至クロニクルをやろう" というものだが其の発想自体が既に面白い上に其の更に向こう側で百点満点を叩き出している振り幅の拡さも相まり思わずガッツポーズを取る人がいるであろうことも無理は無い。若しくは彼女たちは今日の僕と明日の僕なのかもしれないし、内的宇宙で起こすプリズム現象に必要な物体同士なのかもしれないが、先述したように結論を出すこと自体あまり意味は無いのだろうし、私も大して興味は無く、私は私の感情も本当になないろなのであれば何度も聴く度に観る度に印象も違ってくるのだろうと思うし其の未来の僕を今消費してしまうのはあまりに勿体無いことなのだという歩き方を知っているんだよと得意げな顔を見せたが、すぐさま是を教えてくれたのはいつかの僕だったことを想ひ出しゐしゐ思ひを馳せるのであった。単純に虹が出てくるのを楽しみに待っている少女ですというふうな終わり方もあたし好きヨ。
*
漫画:『ガラスの仮面』(美内すずえ/1976年〜)
演劇界幻の名作『紅天女』を演じられる此の世で唯一人の女優である月影千草は退屈していた。今や舞台に立つことも無くなった彼女はひょんなことから中華料理屋で母とともに住み込みとして働く少女・北島マヤが公園で子どもたちにお芝居を見せているところを目撃する。一度見ただけの映画を登場人物ごとに完璧に演じ分けるマヤの其の振る舞いは、とても素人のものとは思えなかった。月影千草は退屈していた。此の少女に出会う迄は。時を同じくして、人気女優を母に、映画監督を父に持つ "演劇界のサラブレッド" である姫川亜弓は自分の才能を疑っていなかった。天才でありながらも努力を惜しまない彼女は、いつかは母を超え、やがては『紅天女』を演じられる女優に成るのだと自分を信じて疑わなかった。マヤのことを知る迄は。彼女たちは未だお互いのことを知る由もない。然し、運命の歯車は止まることなく回り続け、いつしかマヤと亜弓は終生のライバルとして『紅天女』を目指して舞台上のみならず、雨の中であれ山の中であれ鎬を削り合うこととなり、其の戦いは今尚続いているのである。最新刊である四十九巻が発刊されたのは二○一二年。未だ五十巻の発売の目処は立っていない。私は、此の作品は "生ける古典" であり "神話" ですらあると勝手に捉えているが、現役の漫画作品を古典と揶揄するなど何事かと憤慨される方もいるであろう。只、連載が始まったのは今から四十年以上も前であり、且つ、本作が如何に "型" の漫画であるか、乃ち "ベタ" であるかは御承知の通りでろうが、其れは本作の物語構造があらゆる作品に見染められ今や教科書的な要素をも含んでいるからであるとも言える。千の仮面を持つマヤであっても役を掴み切れないことも度々あるが、月影千草は其れを分かった上で今のマヤには演じられないであろう役を与えるような真似をし、マヤが上手く出来なければ行き過ぎた熱血的な指導を行うのであるが、其の異常な忍耐力・精神力を以てしてマヤは何とか其れらの苦難を乗り越え、やがては "舞台あらし" と呼ばれようがそんなことには脇目も降らず、其の才能を遺憾無く発揮して駆け上がって行く一方、めきめきと台頭し始めるマヤの存在を亜弓は脅威に感じながらも漸く自分と対等に渡り合える存在が出てきたわと汗を垂らしながらほくそ笑むのである。本作は終始、此の一連の流れを繰り返しているに過ぎない。課題があり、苦難と成り、乗り越えた先に成功があるが、それは同時に課題をもたらし、其れが又苦難と成り……と延々と流転する其の先に『紅天女』があると云う物語構造となっているのであるが、繰り返しているイコオルワンパターンで冗長であるというわけでは決してなく、其の苦難の切り抜け方や次なる課題などは此方の予想通りに成るものもあれば、予想の遥か先を行くなどして驚かされることもあり、我々は紙面で踊るマヤに振り回されている内に繰り返してもいるという謂わば紋切り型の反復の反復という妙技は物語をなぞり続けるということではなく漫画世界の厚みを増幅させ曳いては其の世界が反復するごとに膨張して行くということにほかならず、然う膨れ上がることから齎された効果の中で私が一番度肝を抜かれたのは第四十三巻で紅天女候補として奮闘するマヤの隣に立つ冷血仕事虫である速水真澄が雨の日の歩道橋で "この大都会にいる誰もが紅天女なんて信じない。信じられない。紅天女は劇場の舞台の上にしか存在しない…芝居が終われば一夜の夢のように消える…。紅天女の心と言葉も、この現実の世界の前ではなんのリアリティももたない…。マヤ…! おれに紅天女を信じさせてくれ…! 紅天女のリアリティを感じさせてくれ。この現実の世界に紅天女がいる…と。おれと…きみを観るすべての人に" と語り掛ける名場面である。『ガラスの仮面』というフィクションの中で幻の名作と位置付けられる『紅天女』を作中の人物が現実と見紛うような演技を見せてくれと嘆願するというメタ的な構造を含みながらも速水真澄の其の真摯な姿を見続けている我々読者からすれば単純に切ない恋の物語における泣かせる台詞でもあり、此のようなことを本作ほどまあるく奥行きのある漫画でやられてしまうと何も言うことなど出来る筈がなく、本当に天地がひっくり返るほど衝撃を受けてしまった。ウーム。此処迄何とか書いてはきたが本作の魅力を伝えることは難しすぎると痛感させられた為、取り敢えず此の場は一言で終わらそうと思う。本作は "おそろしい子" です。
*
小説:『結婚者の手記 あるいは「宇宙の一部」』(室生犀星/1920年)
今年に入ってから私の数少ない知り合いが勝手に二人増えた。高校時代の友人二名が子を授かったのである。知らぬ間に生まれ落ちた其の生命等は、知らぬ間に私の世界の小さな小さな一部となっていた。彼等が子に与えられる影響は、こんなものではないのだろうなアといつしか考えてしまうようになってしまっていたのであるが、子に限らず配偶者も同様だろうなアとも考えた。結婚をする気は今のところ無いが、興味が無いわけでは勿論ない。とりわけ本作で読ませられる新婚者の生活は慎ましく、それでいて豊穣さに溢れ、おしるこを食べるところなどは思わず顔もほころんでしまうほどで、私が人生で最も望むものであるのかもしれない。そうしてにやにやと読む内に友人の顔が思い浮かぶも其の厳厳しい二つの顔が良人に重なることは断じて有り得ないと言いながら、彼らも今頃にやにやしているのは同じなのかもしれないなアと思い至ると、少し哀しい夜を味わうことにもなり婚期を急ぐのも悪くないかもしれないゾという逸る気持ちが出てきてしまわないこともない気にさせられてしまうお気に入りの作品である。
*
どの作品も制作年月日などは特に気も留めず、其の時に浮かんだものをつらつらと挙げていったのであるが、いずれもすべてが日本で生まれた作品になるとは思いもよらなかった。此れも『羅生門』の魔力によるものなのかもしれない。とりわけ音楽に関しては、最近はカーペンターズ許りを好んで聴いていたのに対し、いざ選べと迫られては知らぬ間にBUMP OF CHICKENの新曲を思い起こしては語ることにもなった。拙い説明許りで恐縮ではあるが、以上のことは私が私の一瞬一瞬を切り取ってみると其の確かな変化を凝視め直すことが出来るという此の体験の感覚だけを大事にして次なる作品を楽しもうと心に誓うと同時に声高に "好きなもの" といへるものを増やしてゆこうではないかと思った話に過ぎない。然し、嫌いではない。
続
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
