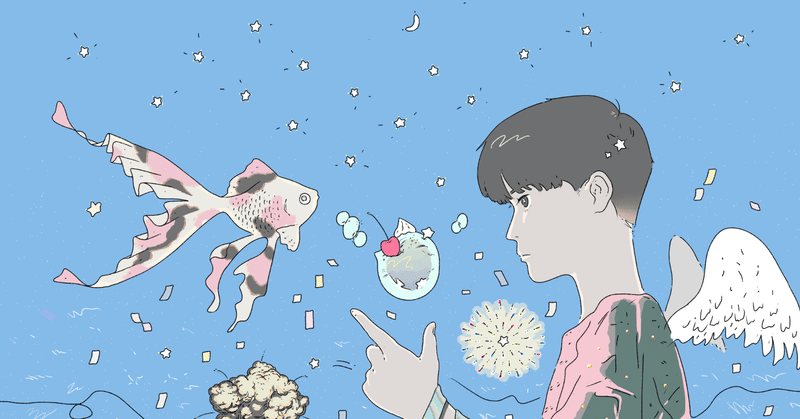
映画『エゴイスト』感想・批評(ネタバレあり)
映画『エゴイスト』を観た。
公開前のビジュアルの雰囲気と、鈴木亮平がゲイを演じるということで気になっていた作品だ。予告などから、2016年公開の映画『怒り』におけるゲイ描写(妻夫木聡と綾野剛が男性カップルを演じ、「発展場」やマッチングアプリが登場した)に近いリアリティも感じ、2023年の今ならさらにどこまで描けるのかという期待もあった。事前に原作小説も読んでいたので、ストーリーはおさえたうえでの鑑賞となった。
あらすじ(ネタバレあり)
14 歳で⺟を失い、⽥舎町でゲイである⾃分を隠して鬱屈とした思春期を過ごした浩輔。今は東京の出版社でファッション誌の編集者として働き、仕事が終われば気の置けない友人たちと気ままな時間を過ごしている。そんな彼が出会ったのは、シングルマザーである⺟を⽀えながら暮らす、パーソナルトレーナーの龍太。
自分を守る鎧のようにハイブランドの服に身を包み、気ままながらもどこか虚勢を張って生きている浩輔と、最初は戸惑いながらも浩輔から差し伸べられた救いの手をとった、自分の美しさに無頓着で健気な龍太。惹かれ合った2人は、時に龍太の⺟も交えながら満ち⾜りた時間を重ねていく。亡き⺟への想いを抱えた浩輔にとって、⺟に寄り添う龍太をサポートし、愛し合う時間は幸せなものだった。しかし彼らの前に突然、思いもよらない運命が押し寄せる――。
小説は2004年から始まり、2000年代後半にかけて物語が進んでいくが、映画は明らかに現代を舞台にしている(はじめは登場人物のファッションから今っぽいなと推察し、スマホの登場で確信に変わった)。
その他はおおむね小説通りの設定・展開だ。実は、龍太(宮沢氷魚)はパーソナルトレーナー以外に「ウリ」の仕事(男性による、男性相手のセックスワーク。いわゆる「ウリ専」)をして自身と母・妙子(阿川佐和子)の生活を支えていた。龍太は浩輔(鈴木亮平)のことをこれ以上好きになると「ウリ」の仕事に支障が出るからと、一方的に別れを告げる。諦められない浩輔は、「ウリ」の客として龍太に会いに行き、今後、龍太と妙子の生活費の一部を自分が負担する代わりに、龍太には「ウリ」以外の仕事をすることを約束させる。かくして、浩輔と龍太の関係は再開し、さらに深まっていくが、ほどなくして過労により龍太は急死してしまう。浩輔は、残された病身の妙子のために金銭と生活のサポートを続け、二人の関係もまた、親子のように親密なものとなっていく。
地獄の「愛」も金次第?
プロットの上で特筆すべきは、浩輔による一方的で献身的な、おもに“金銭面“でのサポートを通して、龍太および妙子との「愛」が継続・深化していくという展開であろう。浩輔が龍太を「買っ」て以降、感情的な面では、映画全体をとおして浩輔と龍太と妙子の関係がこじれることはほとんどない。むしろ、これでもかというくらい理想的で幸福な、ほほえましいやりとりが終始描かれる。ただ、彼らのなにげない、「愛」らしい生活のリズムに挟み込まれる形で、たとえば浩輔から龍太に現金の入った封筒が渡されるとき、われわれ視聴者はなんともいえない違和感を覚えずにはいられない(…ように描かれている。龍太の「ウリ」の仕事のシーンが詳細に描かれていることも効いているだろう。また、妙子が浩輔に話す浩輔の父による金の無心のエピソードは、相手から求めるか自分から差し出すかという違いだけで、行われようとしていることは浩輔から妙子への金銭的支援と何ら変わらない。むしろその違いがこの映画が描こうとしていることの本質でもあるともいえるが)。
この作品は、男性カップルとその親が、一方からの金銭的な援助を通じて「愛」を深めていく姿をとおし、金銭が介在しないことが理想とされがちな「愛」(とりわけ「純愛」)のあり方に疑問を投げかけているように思われる(もちろん、『エゴイスト』というタイトルが象徴するように、ひとりよがりな「施し」が「愛」になりえるかという点も重要なテーマであろう。ただ、こっちを突き詰めるには龍太と妙子があまりにもいい人すぎる。彼らは最初から、あまりにもまっすぐに「愛」を返してくれるのだ。たとえ現実には体を壊し、不幸な事態へと突き進んでいったとしても)。
経済的なつながりとしての婚姻
しかしながら、同性カップルということを抜きにしてストーリーだけを拾うと、実はそこまで真新しい題材というわけではない…というか、これがもし男女のカップルの話だったらなんやかんやあっても最後は結婚すればいいじゃん、となる。
男女のカップルであれば婚姻という関係性において、生計をともにすることが「自然」なこと(もちろん生計が別の夫婦もたくさんいるが)として社会的に認知されている。男女の配偶者の間で、収入の高い方が低い方の生活も経済的に保障することや、相手の親に対して金銭的にサポートをすることは、核家族化が進み夫婦のあり方が多様化した現代においても決して奇異なことではないはずだ。
もちろん、大きすぎる収入の格差とか、セックスワークをめぐる価値観とか、病気になった義親の介護とか、異性愛カップルであっても焦点になりそうなテーマはいくつかある。ただ本作のように、愛する相手とその親に金銭の支援をすること自体が「そもそも愛とは…」みたいな考察までいきついてしまいかねないのは、本作が結婚を許されていない日本の同性カップルを主役としているからこそである。
さらにいえば、婚姻の下の「夫婦」や「家族」はそもそも「経済的なつながり」を内包しているものの、それはあまりにも自明なために、設定さえあればフィクションではあえてつまびらかにする必要のないものとされてきたのだ(男女が結婚して夫婦になる物語なら、両者の経済的なつながりを示すために現金の入った封筒が出てくる必要はない。結婚式とか開いて、一緒に住むとかすればなんとなくそこまで伝わるのだ)。そしてその「経済的なつながり」ゆえに、婚姻というのが「愛」で片づけるには実はけっこうグロテスクな関係だということを、本作は同性カップルを通じて暴き出しているともいえる。
わざとらしくないのにゲイっぽい
プロット以上に優れていると感じたのは演出・演技面だ。
まず、「現代の日常的なゲイ描写」の説得力の高さである。浩輔の(おそらくゲイ男性と思われる)友人たちとの食事の場面は、演者たちの「クィアっぽさ」とそれでいて「どこにでもいそうなかんじ」のバランスが絶妙で、ゲイコミュニティに触れたことがない人が見ても「なんか本物っぽい」という印象を抱くはずである。話しているときの手ぶりや口調、昭和の歌謡曲やアイドル映画の引用、はては飲み帰りにみんなでヴォーギングなど、ある年代にとっては定番のクィアネスやゲイカルチャーを要素として散りばめつつも、それらにわざとらしくフォーカスすることはなく、シーン全体はきわめて日常的で、ありふれた食事の一場面としてすんなりと入ってくる。これはおそらく、ワンカットで撮りきる揺れるカメラワークと台詞を指定していないかのような会話テンポからなるドキュメンタリー的な撮影・演出手法(監督の松永大司は『ピュ~ぴる』(2011)や『オトトキ』(2017)などドキュメンタリー映画の実績がある人だ)、ゲイ当事者の脚本や演出への参画、そして主演の鈴木をはじめとする役者たち(浩輔の友人役には全員当事者が配された)の演技のたまものである(ただ、この「日常的なゲイ描写」も、おそらくはアラフォーと思われる浩輔と同世代のゲイ男性のものである。平成以降に生まれ、SNSやマッチングアプリで出会うことが当たり前の今のアラサー以下の世代の「リアル」なゲイらしさとなると、また違ったものになっていくだろう)。
厳しさを語る美しいものたち
一方、おもに浩輔のマンションで展開する浩輔と龍太のシーンは、幻想的なまでにどこか非日常的な、ある種理想のゲイカップル像を見せてくれる。宮沢氷魚演じる龍太の容姿の美しさと非現実的なまでの性格のまっすぐさもあるが、浩輔の部屋の美術と衣装による貢献が大きい。
ファッション誌の編集の仕事をしている浩輔は、自身もかなりのファッショニスタという設定だ。冒頭で示唆される通り、浩輔はゲイであることを理由に思春期にいじめを受けており、高価な服はいじめたやつらから自分を守るための「鎧」だと考えている。都内としては相当な広さの部屋を借り、高級な家具やスタイリッシュなインテリア・食器をそろえ、「クローゼット」には何十着もの衣服が並ぶ。
浩輔の部屋の美術や衣装は、浩輔がつらい経験をバネに努力を重ねて成功した「勝ち組」のゲイであることを示すと同時に、友人たちとの場面では描き切れない浩輔の多層的な「ゲイネス」の一面を反映している。抜け目なく配され、暗い色でまとめられた家具や壁紙は、美しくありつつもどこか冷たく、部屋の生活感を希薄にしている。これは浩輔がゲイとして生きる中で強いられてきた緊張状態を象徴しているかのようだ。
また、「鎧」としての衣服が並ぶクローゼットは日当たり良好で広さもあり、「カミングアウトできないこと」の象徴として読むには少々オープンすぎる空間として登場する。しかし、浩輔はこの部屋から出るときにはいまだに「鎧」を手放せないのであり、田舎の父親にはカミングアウトできていない。浩輔の部屋の過剰な非日常感は、浩輔が東京に出て、大手出版社に就職し、努力してセンスを磨いてたくさん稼いで…と、「ここまでやってようやく誰にも文句言われることなくゲイとして自由にやれている」という厳しい現実を象徴的に示しているように思える。
こんなゲイたちをもっと観たい!
原作者はエッセイストとして知られる高山真で、映画と同名の原作は彼の自伝的小説といわれている。実話ベースだと考えるとあまりにもドラマチックで美しい展開に驚くが、美しすぎて、現代劇のフィクションとして読むと逆にちょっと嘘くさいと思ってしまう部分もあった。また、こちらも実話ベースなのでどうしようもないのだろうが、ゲイカップルの片方が結局死んでしまういう展開は、今まで散々やりつくされてきたうえに、ゲイ当事者としてはやっぱりつらいものがある。この点については、映画を見てもやはり同じ感想を抱いた。
ただ、演出・演技面でのゲイ描写のリアリティについては、おそらく近年の日本映画やテレビドラマの中でも最高のクオリティを達成していると思う。上には書ききれなかったが男性同士のセックスシーンも美しいだけではなくちゃんとリアルだった(色んな体位やポジションやプレイが描かれていた)し、浩輔や龍太たちが、ちゃんとそれぞれに普通じゃない体験をしていて、ゲイで、そして、それでも「普通」に生きていることが画面を通して伝わってきた。こんな作品が作れるなら、今後、もっとこんな作品もあんな作品も観たい、そんなゲイがたくさんいるだろう。最近つらいニュースが多かったけど、この映画の公開に少し励まされた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
