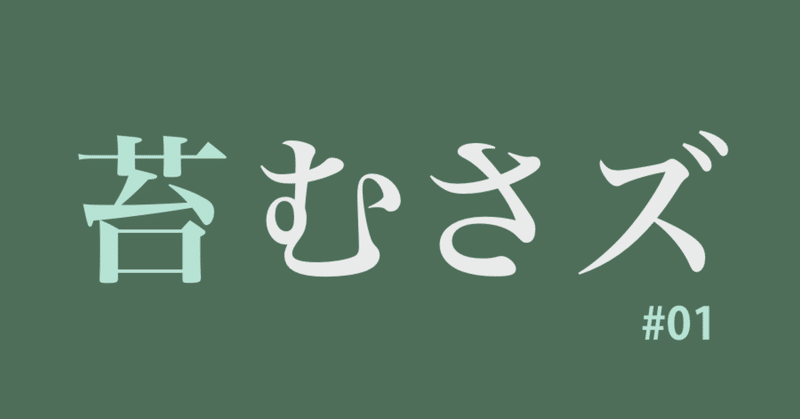
「苔むさズ」#01
そこには、よく見ると全部で6人分のデスクと椅子が向かい合わせに片側3人ずつ座れるように配置された小さなデザインオフィスがあった。
真新しい12階建のビルの8Fを1フロア占領している大手出版社の編集部の片隅。
私がアルバイトで勤める小さなデザイン会社は、そこから港が見える1番大きな窓のある一角にスペースが設けられ、常駐する人数分の席が用意されていた。
このデザイン会社の本社は東京にあるのだが、
出版社では、扱う雑誌によってデザイン会社からリソースを数名常駐させる事は珍しくないらしかった。
私はアルバイトとして雑誌のデザイナー、所謂エディトリアルデザイナーのアシスタントとして採用された。応募時は全く採用される理由すら浮かばないほど絶望的に場違いなポートフォリオと、およそ役に立たないであろう、私の大学時代での専攻ゼミの内容がツラツラと記載された市販の履歴書を、ほんの少しの希望にかけて郵送するしかなかった。幸い面接にも呼ばれ、ディレクターや編集者たちと顔を合わせて、仕事の内容の説明をうけた。また自分の場違いなポートフォリオを更に詳細に説明するというチャンスまで与えられた。
それが1ヶ月前のこと…。エディトリアルデザイナーのアシスタント募集なのに、大学時代に制作した立体造形物と、「Mac使用経験なし」という条件で、提出した書類に目を通し、一体誰が私を雇いたいだろうか、と書類審査と面接を終えた私は心の中で自嘲するほどだった。
当然不合格通知書が自宅に届いており、
「残念ながら、ご希望に添えず…ウンヌンカンヌン」といった事務的な書面で丁重に断られ、それはそうだと、さして落ち込むこともなく納得さえして別のアルバイトを探しに入っていた。
不合格通知書が届いて1週間ほどたった2月の寒い日の日中、その時実家で暮らしていた私に一本の電話が入った。
母が、「〇〇書店の編集部の人だって」と受話器を塞ぎながら私に伝えた。
「もしもし、〇田〇〇子ですけど」
「あ、〇田さんですか?〇〇書店編集部採用担当〇〇と申しまーす。えーっと今お電話大丈夫ですか?」
ノリノリで歯切れの良い、感じは悪くないけどちょっと不躾なな感じの男性の声。面接の時に司会進行的な役をしていた採用担当の男性だと気づく。
「あ、はい…。大丈夫です。」
「あ、あのね、実はエディトリアルデザイナーのアシスタントアルバイト募集ね、〇田さんには一旦お断りしちゃって申し訳なかったんだけどね、実は採用した2名のうち1名が事情があって辞めてしまったから空きが出来たんですよぉ」
「は、はい…。」
「で、3番目の候補に上がってた〇田さんに連絡させて貰った次第っす。これますか?」
なんとなくテレビで見たことがある、
「業界」風とはこんなことか、と感じた瞬間だった。気後れがして、なんだか不安にかられた。どちらかというと苦手な人種の集まりにみえた。本来なら嬉しいと感じる瞬間のはずだったけど、業界であるという以前に、元々自分にはおよそマッチしないであろう仕事。ただ、少し独学で覚えたMacの操作を現場で体験してみたかった、という短絡的な志望動機。自分でもよく分かっていた。
先方としても欠員が出て、スキルも低い即戦力にならない私に連絡をしてきたという事は、少なくとも人格的には気に入られたものの、デザインのメンバーの中で1番ランクが低い、雑用係として期待されている他ないだろうと、22歳のその頃の私にも予想がついた。
「はい、それでは何もできませんが、一生懸命頑張ります!」
兎に角仕事をしたかったのでチャンスは逃せなかった。
「オッケー!じゃあこないだ面接した所わかるね?まってるよー、朝は弱い?11時ごろとかテキトーに好きな時間に来ればいいからさー、あんまり早く来ると誰もいないよー」
そんな軽いノリで、私のエディトリアルデザイナー・アシスタントのアルバイト採用が決定した。
初日、10時ごろオフィスに向かう。
男性の言っていたように、誰もいない。
暫くドアの前で待つと、受付のギャルが15cmはありそうなコルクのハイヒールでとても歩きづらそうに足を引きずるように歩き、日サロで日焼けしたバディをなるべく露出するいでだちで現れた。
「デザインの人でしょ?おはよー。よろしくねー。みんな来るの遅いよー、昼過ぎにノロノロ来る人も居るし。まあ席で待ってなよぉ」
「は、はい。」
とても場違いだ。
私は地味なセーターにコーデュロイの暖かさ重視のズボン。一方で2月なのにミニスカートのコルクちゃん。
コルクのギャルが通してくれたデザイン会社の一角、そこが私の職場だと伝えられた。
どうやら、編集部のアルバイトとして採用されたけど、働くのはこのデザイン会社のアシスタント、という仕組みなのだと、この時に分かった。
コルクちゃんが席に戻ると、
港が一望できる大きな窓を備えた、デザイン会社の一角をよく見渡してみる。
PowerMac 6台。スキャナー二台。奥に何やら四角く白いテントの様なものがあり、人が2人ほど中で作業できる様に小さな机と椅子が2つ置いてある。そこが後で、暗室だと分かった。ライトテーブルにゲラ(デザイン原稿)を置き、ポジフィルムを下に挟んで大体の写真のレイアウトを鉛筆でなぞる作業をする場所だ。
見たこともないものがあたかも当たり前の様に整然と並べられており、そこで一体自分がどの道具を使って何をすれば良いのか、予想すらつかなかった。
私はまず大好きな港の風景を、
2月の寒い灰色の空からほんの少し覗く日光を浴びながら、窓際に突っ立って眺めるだけだった。
1999年2月の寒い寒い日の出来事だった。
[続く]
#小説 #エッセイ #デザイン #デザイン会社 #デザインの仕事 #雑誌 #エディトリアルデザイナー #グラフィックデザイン #20代の苦悩
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
