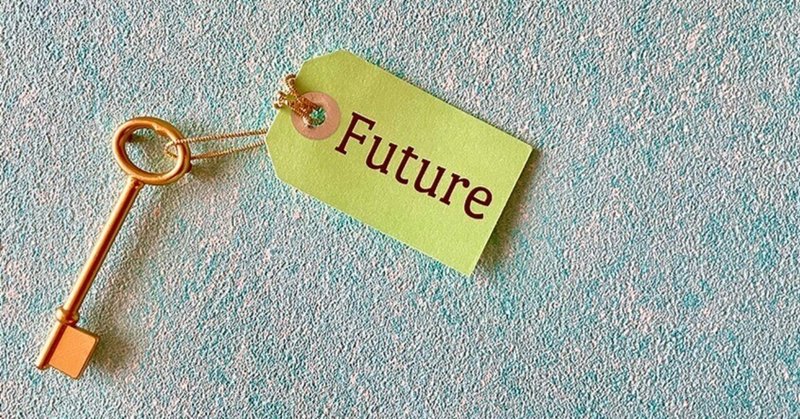
精神障害者雇用を成功させるノウハウとは
※本記事は2023/09/01に株式会社パーソル総合研究所サイト内で公開された内容を再編集したものとなります。
2018年に精神障害者の雇用が義務化された。精神障害者が2006年に障害者の雇用率制度に算入されてから、精神障害者(ここでは、精神疾患の罹患者)を、障害者雇用の枠組みで雇用する例は急速に増加してきた。しかし、その職場定着率は低いことが知られている。
その原因の1つは、「障害によって生じる業務遂行上の困難や、それに対する適切な合理的配慮を、対話を通じてすり合わせ、実行する」ことが他の障害に比べ難しいことにあると言われる。精神障害は、先行して雇用が進んだ身体障害や知的障害と異なり、障害の特性(どのような状況でどのような障害が問題になるのかなど)が個々人で異なっていることが多く、また目に見えて分からないため、正しく理解し対応することが難しい。このような点に対して、身体障害者や知的障害者に行っていたようなこれまでの対応方法では通用せず、悩む担当者も多い。
そこで、パーソル総合研究所では、企業、障害のある個人に対するアンケート調査を通じて、精神障害者の雇用を成功させるための雇用ノウハウを検討した※1。その結果、企業の効果的な取り組みとして、3つのポイントが見えてきた。精神障害者の雇用ノウハウは、すでに行政機関や民間事業者などが情報発信を行っているが、定量的なデータに基づく効果検証はあまり行われてこなかった。現場では、障害のある個人の個別の事情に対応することが重要ではあるが、多くの企業・障害者個人のデータに基づいた一般解を導き出すことによっても、普及・啓発につながるものと考えた。
※1 パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」
本調査における「精神障害者」の定義:
精神障害者の定義は場面によってさまざまだが、本調査では気分障害や神経症性障害、統合失調症、依存症、てんかん、およびそれらの関連疾患を抱えている方(高次脳機能障害、認知症、発達障害、性同一性障害は除く。)と定義。つまり、後天的に発症することが多い心の病気を抱える方を対象としている。
採用選考を強化し丁寧にすり合わせる
パーソル総合研究所の調査では、障害者を3名以上雇用している一般企業(特例子会社などの障害者雇用に特化した企業を除く)にアンケート調査を行い、691社から回答を得た。その回答結果をみると、精神障害者の雇用において、63.6%が「採用選考時の見極めが困難」であることが課題と回答した(図1)。これは、他の障害種(45.8%)よりも大幅に高い数字である。

※括弧内の数値は、回答企業数
出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査[企業調査]」
なぜこのような課題認識になるのかといえば、
1.【過去のケースを活用できない】 障害特性や必要な配慮が個々人で異なることが多い
2.【障害特性の把握が難しい】 障害特性が目に見えないため丁寧な聞き取りが必要、また体調に波があることが多い
3.【合理的配慮の検討が難しい】 障害のある本人・担当者双方が、障害特性によって業務上、生じ得る困難に対する適切な合理的配慮を検討することが難しい
といった大きく3点が考えられる。
では、どのような取り組みを行う企業で、このような課題を解決し、自社で雇用する精神障害者の定着・活躍を実現しているのだろうか。調査から分かったのは、採用時のマッチングを強化している企業で、精神障害者の定着・活躍がうまくいっている、ということだ。具体的には、「採用前の採用計画策定」「職場見学・実習の実施」「障害者トライアル雇用(短時間トライアル雇用を含む)※2の活用」といった施策に統計的に有意な効果が確認できた(図2)。なお、この傾向はその他の障害種では見られなかった。また、精神障害のある個人に対する調査(n=205)では、「就職時の配慮内容の丁寧なすり合わせ」に効果が確認できた。この「丁寧なすり合わせ」は、合理的配慮事項を口頭で伝えるだけでなく、書面の準備や、支援者からも伝えた場合に、より実感される傾向があった。

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」
総じて、一般的な書類選考と面接だけではなく、もう一歩踏み込んだすり合わせの場を設けることが、その後の定着・活躍を促すことが浮かび上がった。
※2 障害者を試行雇用し、適性や能力を見極め、継続的に雇用するきっかけを作ることを目的とした助成金制度。精神障害者は6~12カ月(給付金は最長6カ月)。週10以上20時間未満の短時間就労から雇い入れ、トライアル期間中に週20時間以上の勤務を目指す。短時間トライアル雇用は、3~12カ月(給付金は最長12カ月)の試行雇用が可能。
配属先現場を支援し、受け入れのハードルを下げる
精神障害のある人を採用し、現場に配属した後、具体的に合理的配慮を実行するのは配属先の管理職であることが多い。しかし、管理職に精神障害のある人と関わった経験がある人は少なく、先入観から身構えてしまったり、どうすればよいのか判断に悩んだりすることが多い。企業調査の結果によると、配属先の管理責任者が障害者雇用に意欲的な企業は約2割という結果だった。現場への支援が少ないと、周りの上司・同僚が対応の仕方に戸惑い、疲れてしまうケースもある。
調査の結果、精神障害者の定着・活躍がうまくいっている企業では、人事などの雇用担当者が受け入れ先現場への支援を行っている傾向があった。具体的には、「配属先の管理職の意欲を喚起」「上司・同僚への啓発を実施(コミュニケーション上のポイント共有など)」「雇用管理方法やトラブル対処方法・ルールを明文化」といった施策が効果的な傾向があった。

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」
特に、「管理職の意欲を喚起」については、「現場に配慮事項や障害特性を共有する※3」「業務内容の切り出し・標準化を行う」「上司と障害者の定期的な面談機会を設ける」「トラブルへの対処方法・ルールを明文化する」といった、管理職の負担を減らすような組織的な対応が行われていることが、意欲を高めることにつながっていた。そして、配属先の管理職が障害者雇用に意欲的であることが、他の障害以上に、精神障害者の定着・活躍を左右していた。
「雇用管理方法の明文化」や「トラブルへの対処方法・ルールの明文化」については、実行している精神障害者雇用企業はそれぞれ4.2%、6.2%とわずかだった。しかし、実行している場合は精神障害者の定着・活躍度が高い傾向が見られた。「明文化」はこれまでも精神障害者の雇用におけるポイントとされてきており、関係する3者にメリットがある。受け入れ先現場の社員にとっては、何かトラブルが生じた時にどうすればよいのかが分かり、抱え込むことが減る。雇用担当者にとっては、障害者と会社が雇用管理上のルールや合理的配慮をあらかじめ書面で取り決めることで、「言った」「言わない」などのトラブルを防ぐことができる。そして、障害者自身にとっては、曖昧な状況に直面することが減り、不安を軽減することができる。本調査結果から、この取り組みはもっと推進されてもよいのではないか。
※3 障害特性や配慮事項の共有については障害者本人の了承を得た上で行う。
定期的な相談機会と働き方の柔軟性によって安定的な就労を支援
精神障害者が必要な配慮は個々人によって異なる。それを前提とした上で、調査データから見えてきた「一般解」としては、「定期的かつ良質な相談機会の確保」と「柔軟な働き方の推進によるセルフケア支援」の重要性が浮かび上がった(図4)。

出典:パーソル総合研究所(協力:パーソルダイバース)「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」
定期的な相談機会は、自分から切り出さなくても相談できる場があることによって心理的な安心感が得られる効果がある。また、症状に波がある場合、事前に悪化の兆候をつかみ、業務量を減らす・休養を促すといった対応もしやすくなる。業務日誌などで日々の体調を記録してもらえば、さらに効果的だろう。
また、「自分の個人的な体験も周囲に話している」ことも、他の障害以上に定着・活躍に影響していた。チームワークが良好な職場では、障害の有無にかかわらず定着・活躍度が高まる傾向があったが、自己開示ができる職場環境は、とりわけ精神障害者にとって重要であることが分かった。
近年増えてきたテレワークや短時間勤務制度、休暇を取得しやすくする制度といった柔軟な働き方も、精神障害者の定着・活躍を高めていた。このような制度は、精神障害だけではなく、育児や介護などで制約を抱える従業員の働きやすさにもつながるだろう。
最後に、障害者雇用については、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所といった行政や専門機関による支援が充実している。企業が外部専門機関と密に連携していると、先述のような効果的な施策の実行度が高まる傾向も見られた。外部からの支援を仰ぎ、情報を集め、自社にノウハウを蓄積することが重要だ。
まとめ
本コラムでは、障害者雇用において注目される精神障害者の雇用について、定量調査の結果から見えた雇用を成功させるためのノウハウについて解説した。本コラムのポイントは以下の通りである。
「採用計画の立案」「職場見学・実習」「合理的配慮の丁寧なすり合わせ」「障害者トライアル雇用の活用」といった「採用時のマッチング強化」が精神障害者の定着・活躍度を高めていた。
「現場への配慮事項や障害特性の共有」「業務内容の切り出し・標準化」といった施策を通じて配属先の管理職の意欲を高めること、また、「雇用管理方法やトラブル対処方法の明文化」といった現場支援が精神障害者の定着・活躍度を高めていた。
精神障害者本人が必要な配慮は個々人によって異なるが、調査から見えた一般解としては、「上司との定期的な相談機会」や「働き方の柔軟性」が、精神障害者の定着・活躍度を高めていた。
本コラムが、障害者雇用に関わる企業や個人の取り組みの一助となれば幸いである。

シンクタンク本部 研究員 金本 麻里
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
