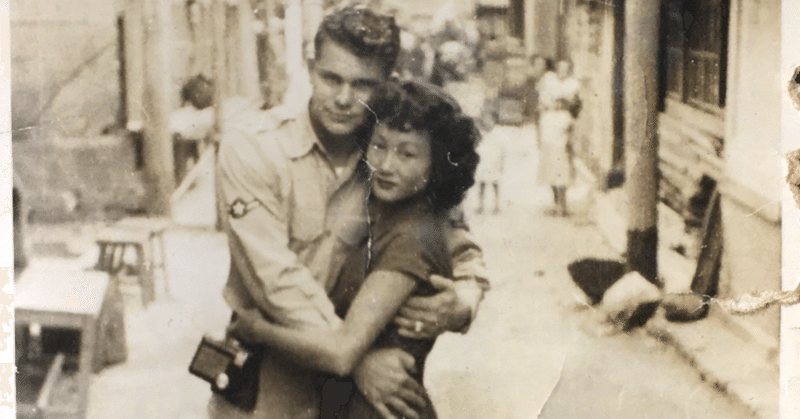
ペーパー・ムーンの詩学~遙かなる二十世紀詩 (4)〈荒地派の悲劇〉
鮎川信夫のモダニズム批判
「……十九世紀においては、詩人は文明からの逃避者として現われ、二十世紀にあっては文明の批判者として現われていることに注意しなければならない。イギリスのエリオット、オーデン、スペンダー、フランスにおけるヴァレリー、アラゴン、エマニュエル等、いずれもそうした近代文明の批判者として現われている。
近代詩から現代詩にいたる約百年間における詩人の社会的役割のこのような変化に注目することは、われわれにとって特に重要である。T.E.ヒュームをイギリスにおけるこうした傾向をつくりだした先駆者として認めるとき、彼の憂鬱なこころ、そして彼の泥の眼が、十九世紀的なボードレールの苦悩やランボーの千里眼などからいかに遠く隔っているかに気づくはずである。」
(鮎川信夫「『燼灰』のなかから――T.E.ヒュームの精神」)
鮎川信夫(1920-1986)は第二次世界大戦後の日本における---いわゆる「戦後詩」と呼ばれる---最も有名と言っていいであろう詩人グループ「荒地派」の代表的詩人でありスポークスマンでした。
彼もまたヒュームやエリオットから強い影響を受け、春山行夫等が編者であった詩誌『新領土』にも参加していますが、戦後は一転してモダニズムを批判する側に回りました。
鮎川は「現実の生に対する源泉的感情を失ったところに、優れた作品が生まれるわけがない」(「現代詩とは何か」)と書いて、春山行夫を始めとする戦前のモダニズムをサロン趣味的、末梢感覚的なものにすぎないとして葬り去ってしまいました。
鮎川は、日本のシュルレアリスト(モダニスト)の表現方法について、「『異質のもの、あるいは異質の<観念>の暴力的結合』であり、そこには<秩序>の意識が全く」なく、「異質なもの、あるいは異質の『観念』を同時的平面的に並置しただけの、一種の型(パターン)があるだけなのです」と批判を加えています。
この鮎川の指摘に対して、北川透は著書『詩的レトリック』の中で、遠く隔たったもの同士の偶然の接近が、互いの電位差により火花を散らし、その火花の美しさでそのイメージの価値は決まるという、ブルトンの「シュルレアリスム宣言」のコトバを引きながら、「しかし、シュールレアリスムにおいて、意味規範が意識的にこわされていても、そこにイメージが創出されていれば、<秩序>の意識がないのではなく、『新しい価値』に貫かれた<秩序>がある、と考えなければならない」として次のように述べます。
「鮎川の指摘には、たしかに正しい一面がある。しかし、<無意識>に自覚的に依拠することで、異質な概念と概念を連結するという方法を、ただ、機能的にあるいは技法的に理解せず、制度や規範によって抑圧されている人間の意識の闇、その危機の表象を探りあてるものだと考えるなら、そこにはパターンそのものを解体する契機も含まれているはずである」
(北川透「詩的レトリック」:思潮社)
この鮎川(および荒地派の詩人たちが共有していたと考えられる詩観)に対する北川透の批判は極めて正当なものであるとして、ぼくの納得できるものなのですが、同時にあまりにも当たりまえであることに驚きます。
いったい鮎川信夫や他の荒地派の詩人たち、たとえば吉本隆明のようなアタマのいいひとたちが、この程度のことに思い至らなかった原因はなんだったのでしょうか。
「自然発生的な詩人の場合は、どんな風景でも心を素通りして、ありのままの写生にちかいかたちで表現されますが、今日の詩の場合、このようなことはほとんどありません。それは、現代の詩人の現実に対する意識が複雑となり、また現代詩が考える詩として発展していった経路からして、次第に作者の「批評的精神」とか「想像力」とかを働かせる領域が広くなっていったためだと思います。したがって、今日の詩人は心で風景をさえぎり、それに手を加えて表現するようになったのだと言えましょう。」
(鮎川信夫「現代詩作法」)
「今日の詩人は心で風景をさえぎ」る、批評意識を持たねばならないと言う一方で、鮎川は次のようにも言います。
「僕たちが書いてきた詩の暗さについては、十年も前から、いろいろな人に指摘されつづけてきた。だが、僕たちは誰から何と言われようと、自分達の詩を決定している要素、それがたとえば暗さというような言葉で安直に言われるものであっても、黙って受入れてきた」
「僕たちの投影の意味が暗く、いつも幻滅的であったということは僕たちの歴史や全生活が暗く、そしていつも幻滅的であったということである」
「僕等の詩は幻滅的な現代の風景を愛撫する。僕等の感受性は、欺かれ易い知性とは違って、現代の暗い都市を正しく心のうえに感じとる。」
(鮎川信夫「現代詩とは何か」)
鮎川は「僕等の詩は幻滅的な現代の風景を愛撫する」とここでは言っています。しかし、「風景を愛撫する」ということと、「風景をさえぎ」る、という厳しい「批評的精神」がどのように両立するのでしょうか?
荒地派、ひいては戦後詩を代表するスポークスマンであった鮎川信夫ですが、その論の進め方に、ぼくの悪いアタマは混乱を起こすばかりです。
鮎川信夫のこの文章について、寺山修司(1935-1983)は「疑似悲劇的」表現のなかで「自分を愛撫している」のが鮎川を始めとする荒地派や戦後詩の書き手である、と言います。
「私は長い間、鮎川信夫の『僕等の詩は幻滅的な現代の風景を愛撫する』ということばにこだわっていた。なぜ、愛撫などするのだろう。自分もまた、幻滅の中にまきこまれている一客体にすぎないことに醒めようとはしないのだろうか、と思ったからである。
私にはこの時代が、決して避けられない必然の下に暗い様相を帯びているとは思えなかった。悲劇的ではあったが、悲劇そのものではなかった」
「私は疑似悲劇的な多くの詩人に、なじみがたいものを感じた。それは、魅力的ではあったが、どこか冷たかった」
「……こうした露出狂的な死の時代の賛歌は、他人に『話しかける』ことは勿論、自分を変えるということさえできなかった。私はここに『幻滅的な現代の風景』の一つの要素として『自分を愛撫している』詩人を感じたのである」
(寺山修司「戦後詩―ユリシーズの不在」:ちくま文庫)
「…自分もまた、幻滅の中にまきこまれている一客体にすぎないことに醒めようとはしないのだろうか」という部分を読んでぼくが思い出すのは、マーシャル・マクルーハンの『メディア論』のなかのギリシアのナルキッソス神話に関する考察です。
マクルーハンはここで、ナルキッソスが泉に映った「自分自身」に恋をした、というような通俗的解釈を退け、彼は、水に映った自分自身のイメージを「他人と見まちがえ」て、その姿に魅せられてしまう。このときナルキッソスはじぶんを見失ってしまった。そのショックが彼の知覚の麻痺を誘発し、水仙と化してしまうのだ、と述べています。
「ギリシアのナルキッソス神話は、そのナルキッソスという名が示すとおり、人間の経験に直接かかわっている。それはギリシア語のnarcosisすなわち「感覚麻痺」に由来する。青年ナルキッソスは水に映った自身の姿を他人と見間違えた。鏡によるこの拡張がナルキッソスの知覚を麻痺させ、ついに自身の拡張あるいは反復されたイメージの自動制御機構と化してしまった。
…この神話の要点は、人間がじぶん以外のものに拡張された自分自身にたちまち魅せられてしまう、という事実である。
…もしそのイメージが自分自身の拡張あるいは反復であると知っていたら明らかに、それに対する感情は非常に違っていたであろう。」
(マーシャル・マクルーハン「メディア論」第4章:みすず書房)
戦後詩=意味の荒地
マクルーハンの言う、自己を映し出し拡張するメディア(詩人の場合はコトバ)を、自己の感覚の延長としてとらえる、という点で鮎川たち荒地派の詩人には大きな欠落があったのではないでしょうか。
荒地派はモダニズムの無意味無内容性を批判して「意味の回復」を強調するあまり、実験を重ねることでコトバそのものの密度を高めていく二十世紀の詩の革新運動からは大きく後退して、「批評性」「思想性」というようなコトバの全体性からは切り取られ限られた一面、どちらかというと散文的働きの方に傾倒していってしまったように思います。
荒地派の詩人たちのコトバの感覚麻痺がいかに重症であったかは、彼らが非常に「隠喩」というものを偏愛したことにも表れているのではないでしょうか。
荒地派はヒュームの言う「新鮮な比喩」の創造を詩人の特権的な能力として極度に強調し、彼らの詩の方法のカナメとしたのです。
片桐ユズルは詩論集『詩のことばと日常のことば』(思潮社)のなかで、荒地派の吉本隆明の「審判」という詩について、「あまりにも自分の表現方法を発明しようとして骨折り損をしている。マチガッタ努力をしてコトバをへとへとに疲れさせている。それよりもコトバ自身の伸びようとする法則を発見し、その線にそって助けてやるだけでよい」と言い、その詩が隠喩へののめりこみによって、コトバの病いに陥っていってしまっていることを批判しています。
「 苛烈がきざみこまれた路のうえに
九月の病んだ太陽がうつる
蟻のようにちいさなぼくたちの嫌悪が
あなぐらのそこに這いこんでゆく
黄昏れのほうへ むすうのあなぐらのほうへ
ぼくたちの危惧とぼくたちの破局のほうへ
太陽は落ちてゆくように視える
…よくワカル。しかし、ちっともオモシロクナイ。ここに非常に問題がある。この詩人は、批評家が非難するような、ひとりよがりのメタファー遊戯にふけっているのでない。詩人と読者の間を埋めようと一生けんめいに身をのり出して説明する。しかし、読者の耳を捕えない。
…このマジメな詩人は、彼の重大な認識を表わすのに、唯一の方法としてメタファーにたよりすぎるくらい、たよっている。」
「荒地の詩人たちは死隠喩(たとえば「春の訪れ」のように日常用語になったもの)と詩的隠喩(「残酷な季節の訪れ」)を区別することが、すなわち、メタファー研究のすべてであるかのごとく精力を傾けている。それでうまく説明しつくせなくなると、擬隠喩というのを中間に設ける(ポスターなどの「高原は招く」やニュースの「冷たい戦争」など)。そして「審判」のつまらなさもこの、文学と非文学、詩のメタファーと日常のコトバ、をあまりにも鋭く区別したがる傾向から来ている、とぼくはかんがえる。そこでは、コトバが生きていない。あるいは、神風タクシーの運転手のように、まちがった方法で酷使され、へとへとに疲れている。これ式のコトバはぼくたちのハナシ言葉の世界から、ずーっと遠いところで、ぼくたちの実感とかかわりなしに、それ自身の回転をつづけている。もはや文語だ。」
「じつは知覚の仕方そのものが、メタファーのプロセスなのだ。ここでアリストテレスのマチガイにもどらなくてはならない。『それは天才のしるしである。なぜなら良いメタファーをつくるには類似を見る目がなくてはならない。』
…バカ言っちゃいけない、机の「アシ」が歩き出し、針の「目」がジロリとにらみ、ノコギリの「歯」がかみつくと誰が思うか。」
「一番わるい迷信は――メタファーはコトバの使い方のうちでも特殊な例外的なものだ、ふつうの使い方からの脱線であると考え、コトバがそれによって生きている法則、として考えないことだ。……(中略)……あらゆるシゲキはその瞬間に過去の類似の経験と比較され、このようにしてあらゆる知覚・認識・思考は、現在の中に過去を見る点で、メタフォリックなはたらきである。」
「われわれが生まれつき持っているメタファーの能力を尊重し、まっすぐに伸ばすこと、そこに新しい思想が生まれるのであり、そのことはF.R.リービスが言う、詩人は彼の時代の意識の先端、意識それ自体が現れるところ、なのだ。なぜなら「考え」は、経験と経験の交流、つまりメタファーにより、進められるものだからである。ここでわれわれは「審判」の失敗へもどってくる。大部分の詩人はいまだにメタファーを「説明」の手段として考え、「発想」のカタチとして考えない。それ故に、自信無げにくどくくり返し、芸術として良いカタチになっていない。これは民衆のメタファー能力を過小評価したバチである。」
(片桐ユズル「詩のことばと日常のことば」:思潮社)
荒地派のコトバの病いは『Xへの献辞』というエッセイにもあらわれているようにぼくは感じます。
『Xへの献辞』は「現代は荒地である」という一節で知られた、荒地派のマニフェストともいうべき文章です。「荒地同人」という署名がされていますが、鮎川信夫によって書かれたものと考えていいようです。
現代は荒地であり、ヒューマニズムの無秩序と混乱と、唯物的な近代の世界観の厚顔無恥により、宗教的倫理的な絶対価値が忘れ去られ、伝統の喪失と権威の崩壊によって、現代は言葉への不信の時代となっている、と鮎川は言います。
言い換えれば、宗教的倫理や伝統や権威をささえるべきものとして「言葉」が考えられているということで、「言葉に対するこの深い信頼と愛が、僕等の必要と要求に応ずるであろう」と語りかけます。
そして、そのためには詩は「言葉の鎧」であったり、「巧緻なからくり装置」であったり、「まして猫に胡弓を取り付けた玩具」のようなナンセンス・ヴァースであったりしてはならない、のだと…。
「親愛なるX…」と鮎川はコトバを重ねます。詩を書くということは「言葉を高い倫理の世界へおしすすめてゆく」ことであり、「一つの調和への希求と、一つの中心への志向」を伴った、たえまのない詩作過程を生活のすべてとする、そのような「詩の規律に服するように、僕等の生活が保たれるとしたら、すべては如何に良きものであろうか」と。
そして、以上のような、コトバの完全なるハタラキへの信頼---それは幻想かもしれないが、幻想は生の賜物なので排斥すべきではない、と鮎川は言う---を取り戻すためには「僕等はただその善きものと悪しきものとを区別する能力を持たねばならないのである」と結論しています。
この高名なマニフェストを読んでぼくが抱くのは、「言葉への敬虔な信頼の念」がなくては成立し得ないのがじぶんたちの詩である、と言いながら、そのコトバに対する態度は不徹底なもので、コトバそのものが崩壊しつつあるのではないか、というような危機意識は希薄なのではないだろうか、という思いです。
問題にされているのは、あくまでもコトバの「意味」の面での荒廃であり、無秩序であり、荒地派の目の前にひろがっているのは、いわば「意味の荒地」にすぎないのではないでしょうか。
ポエジィによる救済
西脇順三郎は「詩的な美」とは何か、について次のように言います。
「その存在は一つの抽象的な、眼にみえない理論的な(譬えれば、原子形のようなもの)フォルムである。それは通常の経験の世界において、遠い関係に立つ二つのものを近く連結し、結合させ、また逆に近い関係に立つものを遠く分離させることである。だから超絶的美感を起させるフォルムはそうした関係のフォルムである」
(「現代詩の意義」)
この「関係のフォルム」とはすなわち「新しいイメージ」のことです。
「ヒュームの説の如く、創造的努力というのは新しいイメージをつくることである。
…イメージの世界が美となる根本的の要素は、通常の経験の世界に於けるイメージの連結を破壊して、新しい連結を行なうことである。この新しい連結をもっているイメージの世界が詩に於ける美の中で最も重大なものであると思う」
(「詩の感覚性」)
新しいイメージをつくることが詩の重要なハタラキであることを強調した先覚者として、ヒュームを評価する西脇ですが、無条件に礼賛しているわけではなく、ヒュームやその後継者とも言えるエリオットの詩学を、なまぬるいものとして不満も持っていたようです。
「ヒュームは詩に対してイメージの世界を主張はしているが、未だメタフォルのことを考えている。
…エリオットの詩は種々の詩人やその他の文学から種々の世界の断片をとってきて、それを新しく連結して新しいイメージの世界をつくろうとしたかなり進んだ詩であった。しかしそれは単に新しい世界にすぎなかった。出来るだけ遠いものを連結したことでないから、詩的な美ということが不幸にして欠けている」
「その理由は、メタフォルのために使用されている間は、イメージの連結に制限を受けることになる。すなわち普通の連想として最も遠い二つのイメージが連結されているにしても、メタフォルを目的とする場合は、それ等の間に相似性をもって連結される必要がある。それが連結に一つの制限を与えることになる」
「未だ表現というようなことを考えているのは昔の詩人芸術家のことのみを考えているからである。表現という意味にはその表現の対象を表現することの条件がある。即ちメタフォルをつくることである。ところが、今日の詩人は(或いは新しい画家も)最早メタフォルをつくることなどはせずに、新しいイメージの世界それ自身をつくることに純粋になっている」
「イメージの世界は最早、表現形態として使用しているのでない。その世界それ自身が詩作の対象である。意味という問題が起こらない。意味ということは表現形態が表象する対象のことであるから、この新しい詩には表現形態というものがなく、直接に対象がつくられている。
…我々は単にそのイメージの世界を感覚すればそれでよい。それで意味が不明であっても、イメージの世界が透明でありさえすればよい」
(「詩の感覚性」)
このように何ものも象徴しない、思いがけない、無意味な、イメージそのものを感覚することが西脇の「モダニズム」でした。
当然、ここには荒地派が求めるような「思想性」も「批評」も「倫理」もなく、あったとしても、詩作の「材料」としての思想やモラルであって、それらは換骨奪胎され、融通無碍に組み合わされ、「新しい関係」というフォルムが形成されてこそ詩になる、というのが西脇の考えです。戦後の荒廃した世界での詩人の社会的役割を模索していた鮎川等がモダニズムを役に立たないものとしたのも、しかたのない面があります。が、西脇にすればそのように一見現実には無力な、社会の改善などには役に立たないからこそ、詩は最終的には人を救うのだ、という思いがあったでしょう。
ポエジイはすべての価値批判を超脱しているから人間の脳髄をよろこばせる。それというのは人間の苦悩の最大な原因は価値批判があるからである。栄誉と富、恥辱と貧乏とか、美と醜、善と悪、真と虚といったものはみな価値批判の結果としての心理である。
ポエジイはこの事実によって人間の精神的な救済であろう。仏教もキリスト教もその真の意味ではそうしたポエジイであると思う。この点はポエジイの無限な効用であろう。
ポエジイは人間の感じ得る最大な哀愁の美である。ただこの淋しい感性によってのみ一般の生物は「永遠」を幾分感じる可能性がある。しかしこれらはポエジイの目的ではなく単なる幸福な結果である。
ポエジイの目的はポエジイである。
(西脇順三郎「詩學」14:筑摩叢書)
由良君美の「回想の西脇順三郎」( http://www.keio-up.co.jp/kup/webonly/art/kaisou/vol3.html )によると英文学者の土居光知がある講演で西脇順三郎のエリオット理解に対して「不真面目」であると批判したという。
その内容は「西脇教授は、『荒地』をエリオットの、全くのふざけたものとして極上のもの、と言っておられる。これは違う。『荒地』はエリオットの、正しく、真剣な、現代批判として読まれねばならぬ。」といったものであったそうです。
土居を怒らせた---西脇による『荒地』翻訳の〈あとがき〉---のは次のような一節です。
「エリオット氏はこの詩に関しては近来稀れにみるparodyの詩人でもある。この点からみても、この詩が現代最大なシャレた詩であるということにもなる」
土居光知や鮎川信夫のようなマジメなひとたちにとっては、『荒地』の詩人は二十世紀の危機を一身に背負って苦悩する存在です。でも西脇順三郎にとっては、エリオットは機知と諧謔の天才的パロディスト、なのでした。
西脇にとって『荒地』はまず、「意識の流れ」の手法を大胆かつ広範に使用した最初の試みという点で最も尊敬されるべき記念碑的作品であり、「正しく、真剣な、現代批判」などというものは材料にすぎません。「意識の流れ」という枠組みを据えることによって「引用と聯想」を縦横無尽に作品に流し込むことができたのでした。
「エリオットの詩の美は一つの場面、一行の文句としての美ではなく、一つのオーケストラの構成美であって場面と場面との結合、思考と思考との結合において構成されているのである。
…遠いものゝ結合の面白味から生じた詩的美である。」
「近代ヨーロッパ社会の精神的瓦解の問題も含まれてはいるが、それはこの詩の直接の目的ではない。
…何か一つの思想をわれわれに語るのでなく、ただそうした組み合わせの効果として読者の感情と態度を統一し、われわれの意志を美的に解放するのである」
「パヴローヴァという有名なダンサーに、そのおどりの意味を説明してくれとたずねた人があった時、彼女は、それが言えるなら、おどれなかったと答えた。それと同じことがこの詩にも言えるだろう。この詩のもつ主な事実は単にこれは詩であるという事実にすぎない」
(西脇順三郎「エリオット」:研究社出版)
「装われた悲劇」の歴史から「途方もない冗談」の歴史へ
『ノンセンスの領域』の著者、エリザベス・シューエルは、「詩的隠喩的な要素」を排除する、ことをナンセンス文学の条件のひとつとしてあげていますが、西脇順三郎の言うことをぼくの興味の向かう方向にずっと延長してゆくとモダニズムとナンセンスがむすびつきそうです。
「総合をめがける傾向は、一切御法度(タブー)とされる。知性における想像力、言語における詩的隠喩的な要素、また主題の上では美、豊穣、聖俗のあらゆる愛が締めだされる。何であれ結びつけるものは、ノンセンスの強敵なのである。万難を排して追放せねばならない。」
「『鏡の国のアリス』の「女王アリス」の章で白の女王が尋ねている。<1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1たす1はいくらになるかの>。アリスには答えられないが、それもそのはずである。総和がいくらかなど、まるで重要ではないのだ。重要なのは、1たす1……という風に組み立てていくことそれ自体なのである。これが即ちノンセンスの宇宙の組み立てではあるまいか」
(エリザベス・シューエル「ノンセンスの領域」[訳]高山宏:河出書房新社)
ありとあらゆる不可思議なことが起こりうるが、そこに隠された意味などなく徹頭徹尾「文字通り」の世界、いっさいが「表面」だけで奥行きのない鏡の中の出来事のような世界---すなわち、ナンセンス・ヴァースの世界。
答えのないなぞなぞ、白紙のルールブックを持った厳格な審判員、シニフィエ無きシニフィアン、言語怪獣たちが跳梁跋扈する世界。
鮎川信夫が、現代の詩は「猫に胡弓を取り付けた玩具」であってはならない、としりぞけたまさしくその世界です。
Hey diddle diddle,
The cat and the fiddle
The cow jumped over the moon;
The little dog laughed
To see such sport,
And the dish ran away with the spoon.
へっこら、ひょっこら、へっこらしょ。
ねこが胡弓ひいた、
めうしがお月さまとびこえた、
こいぬがそれみてわらいだす、
お皿がおさじをおっかけた。
へっこら、ひょっこら、へっこらしょ。
(「まざあ・ぐうす」[訳]北原白秋 )
鮎川は、深瀬基寛がエリオットの「J・アルフレッド・プルーフロックの恋歌」のイメージの飛躍を評して「この表現には、行と行の間を前節と後節のあいだを、また客観的世界と創造的意志との間を繋ぐ接続詞というものがない。近代世界は接続詞のない世界である」と言ったことについて、次のように述べます。
「この『接続詞のない世界』という観念は、たしかに現代詩の一面をついたものです。隠喩の解りにくさも、イメジの腐蝕的、解体的傾向も、根本はこの相互関連性の欠如にあり、そうした現代文明の危機が詩人の鋭敏な感受性に屈折してくるためであると考えられます」
(「現代詩作法」)
しかし、それは「現代文明の危機」などというよりは、エリオットがアリスの世界に近づいたからなのだ、というのがシューエルの意見なのです。
「『荒地』はエリオット氏が醇乎たるノンセンスに一番近いところでした仕事であって、『アリス』作品に、実にこれのみに比べらるべきものである。彼は危険な要素---神話、愛、詩、過去の美---をテーマの中にもちこんでいるけれども、それらをコントロールするのにノンセンスの定石とも言える手法をいろいろ徴用している。
してみるとこの詩の有名な断片化(fragmentation)も、現代世界に対する嘆きと解さるべきものではなく、これこそその材料を個別の単位に---赤の女王の口吻を借りるなら「1たす1たす1」に---分解し、ノンセンス向きに変えるノンセンス詩人一流の骨法なのである」
「詩全体を支えるためにキャロル的な典型的枠組みが利用されている。トランプとチェスである。人間関係というおよそノンセンス的ならざる危険な代物に代えて、数字たちとゲームの指し手があるばかりなのだ。ノンセンスのルールが必要な条件をつくりだす---知性が主題から保つべき距離、材料の分解、融けあわないイメージのパターンの操作。ノンセンスと同じように高度に知的なこの周到きわまるシステムの世界の中に、潜在的には危険そのものであるはずの材料さえ取りこまれてしかるべく所を得、あげく完成した作品はエリオット氏の傑作と称さるべき逸品である」
(「ノンセンスの領域」)
あまりにもマジメすぎ、コトバを窒息させてしまった荒地派の詩人たちによって、いわゆる「戦後詩」とよばれるものは息も絶え絶えの状態になってしまった、というのがぼくの印象です。
ぼくが詩を書き始めた十代---むかしむかし三十年以上も前のことですが---のころは、まだまだ荒地派を中心に現代詩を語るような雰囲気があり、ぼくも彼らの詩を読んでいました。でも、今あらためて読もうとすると、非常にしんどい、というのが素直な感想なのです。
それは、内容が重いから、深刻だから読むのがつらい…というわけではないのです。読んでいてしらじらとなっていく感じ、その「悲劇ぶりっこ」ぶりにヘキエキしてしまうのでした。
ウィキペディアの「現代詩」の項目( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%A9%A9 2011/02/20現在)を見ると「現代詩=戦後詩」という記述になっており、荒地派がその筆頭にあげられています。戦前のモダニズムに関しては完全に黙殺されており、北園克衛や春山行夫はおろか西脇順三郎についてさえ一言も触れられていません。
たかがウィキペディア、しかも他にもつっこみどころが多々ありそうな記事---おそらく荒地派の洗礼を強く受けた世代のひとが主に書いたのでしょうか、コトバに対する荒地派的なマジメさと偏狭さに充ち満ちています---なのですが、ながらく書きかえられる様子もないところをみると、あまり強く異を唱えるひともいないのでしょう。そうすると現代詩って、だいたいこんなものだろう、とみんな思っているのでしょうか。
「法律への違反は論理的に法律の存在なしに成立しえない。さて、ノンセンスの言語はセンスの言語に(反面的に)支えられてしか成立しないという高橋の的確な指摘を、私たちはさらに逆転させてみるべきではないか。
すなわち、私たちの日常言語は、実はノンセンス言語に(反面的に)支えられてはじめて成立しているのだ、と。潜在的ノンセンスこそセンスの必要条件である、と…」
「明治以来私たちの国をおおかた支配しつづけてきた、かぎりなく俗悪な健康をほこる模写説リアリズムの言語観に、ノンセンス言語を対置させてみる。そして、どちらが本当は狂気なのか、どちらが真に健全なのか、と考えてみよう。
その上でさらに、実は私たちのすべてが少しずつ両棲類なのだという事実に気づいてみよう。あるいは、こう言いかえてもいい。ノンセンスの言語は、センスの言語を反面的に支えているばかりではない。鏡の向こうからしみ出して、センスの言語の中に深く滲透してもいるのだ。」
(佐藤信夫「わざとらしさのレトリック」:講談社学術文庫)
われわれがコトバの手足を存分にのばし、その真の健全さをとりもどすためにも、「戦後詩」の書き手たちが生き残るのに性急なあまり、投げ棄ててきてしまったものを拾い集め、現代詩の歴史を「装われた悲劇」の歴史から「途方もない冗談」の歴史へと、書きかえるのをこころみる必要があるように思うのです。
言葉の病いは疎外である。一方、言葉の遊びは異化である。詩人のたくらみは疎外としての言葉の病理を異化の遊戯へと顛倒せしめることにあろう。分析が袋小路に陥ったところから、詩はつねにペガサスの翼を羽搏いて飛び立つのである。
(種村季弘「ナンセンス詩人の肖像」:ちくま文庫)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
