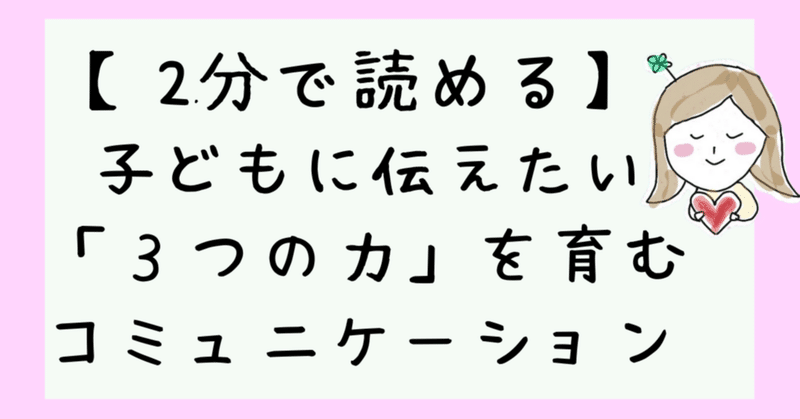
子どもに伝えたい「3つの力」を育む コミュニケーション
子どものコミュニケーション力は、一部の場合をのぞき、生まれつきではなく、環境の中で学び育っていくものです。
特に、一番近くで長い時間過ごす大人の影響を大きく受けます。
毎日過ごすことの多い親が意識しておきたいコミュニケーションについて具体例と共にご紹介します。
子どもに伝えたい「3つの力」とは
今回は子どもに伝えたい大きな3つの力を
①愛する力
②人の役に立つ喜びを知る力
③責任をもつ力
とまとめました。それぞれについて、少し説明します。
①愛する力
とは、自分自身そして他者を愛する力です。
自分の存在そのものをうけいれる「自己肯定感」、
やればできると思う「自己効力感」にも強く影響します。
自分を愛することで、ようやく他者を愛することができ、
自分を信頼することで、他者を信頼できるようになります。
信頼関係を築く力が、目標を達成させたり、人生の幸福度をあげます。
②人の役に立つ喜びを知る力
人の役に立つ喜び=自己有用感と言われています。
人の脳は、人を喜ばせるような利他的行動をとるときに活性化すると言われています。
人の役に立つ喜びを知っている人間は、自然と周りに幸せの輪を広げながら自分もますます幸せになっていくサイクルを作ります。
③責任をもつ力
責任をもつ力を学ぶことで、対応力、問題解決力、論理的思考力が養われます。これは変化と多様化が続く現代を生き抜くために必須の力だと言われています。
人生は予想もしない出来事も必ず起こります。その時に自分で考えしっかりと乗り越えていける力を育むことは親の役目です。
この3つの力を育むコミュニケーションについて、具体的に見ていきたいと思います。
「①愛する力」を育むコミュニケーション
全力で聴く
なんといっても聴くというスーパースキルを使わない手はありません。
子どもの脳は、安心して聴いてもらうことで血流量があがり、活性化されます。ここで大切なのは、
ジャッジ(評価)しない
アドバイスしない
ありのままに受け入れる
ということです。親の心が不安でいっぱいだったり、子どもの未来を信じられない状態だと、ついついジャッジやアドバイスをして、子どもはだんだん本音を話さなくなります。
あなたの未来を120%信じているよ
という姿勢で全力で話を聴くことで、子どもは自己肯定感を高めてゆきます。
誕生ヒストリーを耳タコ

「あなたが生まれてお母さんがどんなにうれしかったか話させてね」
と、おなかにいる時から、出産、産後、その後のことなど耳にタコができるくらいまで話しましょう。
タイミングはお風呂や寝る前のピロートークなど目線が合う状態ですとより効果的です。
「もうそれ何度もきいたから」
というようになっても「自分は愛されてる。望まれてこの世にやってきた」と実感しやすくなります。
「甘やかす」と「甘えさせる」を区別
「甘やかす」と「甘えさせる」を区別していますか?
甘やかす 子どもの物理的・金銭的な要求を満たすこと
甘えさせる 子どもの精神的要求を満たしてあげること
欲しがるものを次から次へと買ってあげたり、自分でできることを親が肩代わりしたり、子どもの宿題をやったりすることは「甘やかす」行為であり、子どもの自立を奪う行動です。
一方「甘えさせる」は、子どもが親から愛されていることや守られていることを確認する行為です。適度に甘えさせることで、親子の信頼関係が深まり、自己肯定感が向上し、安心して外の世界へ自立していきます。
甘え方は子どもによって違いますが、ハグや手をつなぎたいという子もいれば、見てみて、きいてきいてというタイプもいます。逆に甘えるのが苦手で下の子や忙しいお母さんに遠慮している場合もあります。その時は、
「ちょっと抱っこしてもいい?」
とこちらから甘えられる場所を作ってあげるのも一つの方法です。
「あなたは元気の源説」を豪語する
○○ちゃんの話きいてたら、お母さんに元気が湧いてきたぞ~にょーん!!
とかよく言ってるのでちょっとすっかり「また言うとる」という態度になっていますが、やっぱり子どもは嬉しそうです。
誕生ヒストリー耳タコと並んで「元気源説」もぜひ豪語して何ら問題ないと私は思います。ただ「元気にしてあげなくちゃ」とか「笑顔でいなくちゃ」とか気負ってしまいがちな繊細で優しい子の場合はちょっと注意が必要。
ポイントは、テストで100点とったから、とかかけっこで1位になったから、とか特別成果がない時に多用しましょう。
「自分は存在だけでお母さんを元気にできる存在なんだ」
というところに届くように伝えましょう。
「②人の役に立つ喜びを知る力」を育むコミュニケーション
褒め言葉の罠
「褒める」は子どもにとって承認や自己肯定感があがる大切なスキルですが、やり方と状況によって、子どもを支配し、他人軸で生きる傾向に導く罠が潜んでいます。
親の望む行動をした時に「えらい!!」と「評価(ジャッジ)」することは、時に子どもの自己肯定感、自己決定力を奪うことになります。
褒めるときは評価やコントロールになっていないか?のチェックが必要になります。
回りくどく助かった理由を説明する
家事をしたり、自分でできることが増えた時に
「お母さん今日○○と▼▼でいそがしかったから、□□くんがこれやってくれて本当に助かったよ~~」
と子どもにしては回りくどいかな?というくらい理由を説明してみるのもいいでしょう。
他愛のないことでも、子どもにとっては「こんなことでお母さんは喜ぶのか!」と気づきになり、自己有用感を感じます。言葉にすることで、子どもが考えていなかった視点を増やすことができるでしょう。
身近でグローバリゼーション
無理なくできる形で異年齢や色々な立場の人と関わる機会をつくりましょう。自分より年上の子に力になってもらった経験は、年下の子の役に立ちたいという思いにつながっていきます。
お年寄りや障害を持った方、外国人など、色々な立場の人と関わることで、さまざまな形で自分が役に立ったり、自分には気づかない観点が得られます。
縁の下の力持ち探しをする
個々の成果だけでなくチーム内でどんな働きができたかについて、トピックを出してみましょう。
「このチームが成功したのは、〇〇ちゃんのあの言葉(行動)が大きかったよね」
「▼▼くんのあの言葉(言動)がみんなを元気にしたよね」
など、わが子だけでなく、周りのみんなの有用性を話題にすることで、有用性の感覚が自然に身についていきます。
「③責任をもつ力」を育むコミュニケーション
失敗は自分を成長させる宝物!
親子共で、まずはこれを強く認識することが大事です。
親が失敗を極度に怖がると、子どもに伝わり子どもも失敗を怖って挑戦をしなくなります。失敗こそが自分を成長させる宝物だ、という共通の認識をまずしっかり持つことが大事です。
原因と結果をたくさん経験させ、次はどうすればいいか?を考えるプロセスに寄り添う。これこそが、成長速度をあげ、論理的思考力、問題解決力、対応力を育てていきます。
具体的には、自分で起きる習慣がつかないなら、明日は起こさないから遅刻したらちゃんと先生に自分で事情を説明してね、という感じです。
くれぐれも、親の心配で、大切な考える機会、うまくいかない経験を奪ってはいけません。
回りくどく自己決定を承認する
結果の見栄えよりも、子ども自身が考えて自己決定したことについて認めしっかりと承認しましょう。
「○○くんがこの結果をどうしようと自分で考えて、みんなに意見をきいて、よしこうしよう、と決めて行動したということが、〇〇君が成長していくうえでお母さんはとても大事だと思うんだよ」
子どもの年齢によってどこまで理解しているのか?という反応であることもあるかと思いますが、お母さんの言葉から責任の意味や、コミュニケーションを学んでいくでしょう。
まとめ
以上、子どもに伝えたい「3つの力」を育むコミュニケーションについてご紹介しました。
①愛する力 ✅全力で聴く
✅誕生ストーリーを耳タコ
✅「甘やかす」と「甘えさせる」を区別する
✅「あなたは元気の源説」を豪語する
②人の役に立つ喜びを知る力
✅褒め言葉の罠
✅回りくどく助かった理由を説明する
✅身近でグローバリゼーション
✅縁の下の力持ち探しをする
③責任をもつ力
✅失敗は自分を成長させる宝物!
✅回りくどく自己決定を承認する
子どもの一番そばにいるお母さん、お父さんが子どもにとって一番のコーチです。子どものそのものを受け入れつつ、子どもの未来に大切な3つの力を育てる豊かなコミュニケーションを意識していきましょう。
完璧にできなくても大丈夫。まずは「がんばろうとしている自分」をしっかり褒めて、お母さん自身の自己肯定感をあげていくことが何よりも大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2022.2.5更新
「子どもに伝えたい3つの力」を図解しました!

見える化すると印象に残りますね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
