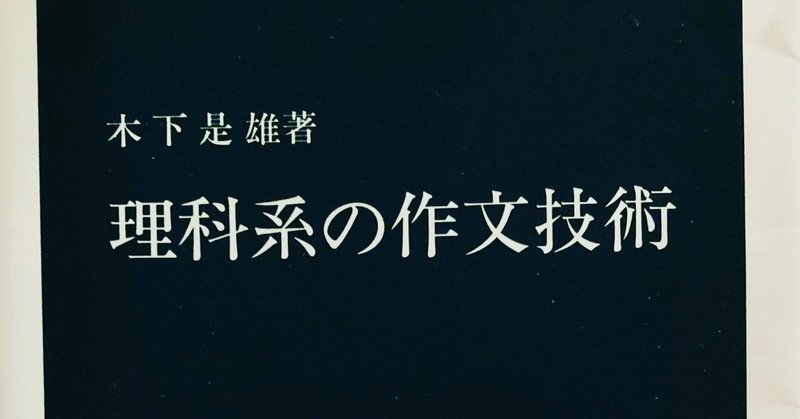
理科系の作文技術
オススメ63。"その意味で文書の死命を制するのは,文書の構成ー何がどんな順番に書いてあるか,その並べ方が論理の流れに乗っているか,各部分がきちんと凍結されているかーなのである"1981年発表の本書は物理学者の著者がアカデミックな文章作成の基準を確立させたロングベストセラーの普遍的名著。
個人的には、何かと書類仕事の多い中、今一度自分の文書を見直そうと思って何十年かぶりに手にとりました。
さて、そんな本書はチャーチルのメモの紹介から始まり"私がこの書物の読者と想定するのは、ひろい意味での理科系の,わかい研究者・技術者と学生諸君だ"と、まるで誌面上で講義をするかのように、繰り返し【事実と意見をちゃんと区別すること】また小説とは違って、論文は読者にとって【明確かつ簡潔な文書を目指すこと】を具体的な参考論文や例題をもとにわかりやすく指摘してくれているわけですが。
まず、約40年前に書かれているにも関わらず、【現在でも充分に通用する普遍的な内容】である事。またそれを、よく【200ページほどでコンパクトに収録している】とあらためて驚きました。もはや私は学生ではなくなって長いにも関わらず、恥ずかしながら今回も目が覚めるかのような指摘をたくさん新たに発見し、大いに勉強になりました。
また、本書では物理学者のベケットによる『日本人の文章組み立て』のエッセイをもとに、しばしば『墨絵のようだ』と欧州の読者が当惑する日本語文書の特異性を紹介するなど【文化論としても楽しめたり】後半になってくると論文の書き方以外にも(こちらも今でも通用する)【スライドの作り方や発表する際の心得まで言及する】など、とにかく隅から隅までサービス精神?旺盛なのも本当に素晴らしいと思いました。
理科系でなくても、これから論文を書く全ての学生さんへ、また学生でなくても業務上や仕事として文書を書く事やスライド発表する機会の多い全ての社会人に『必読の一冊』としてオススメします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
