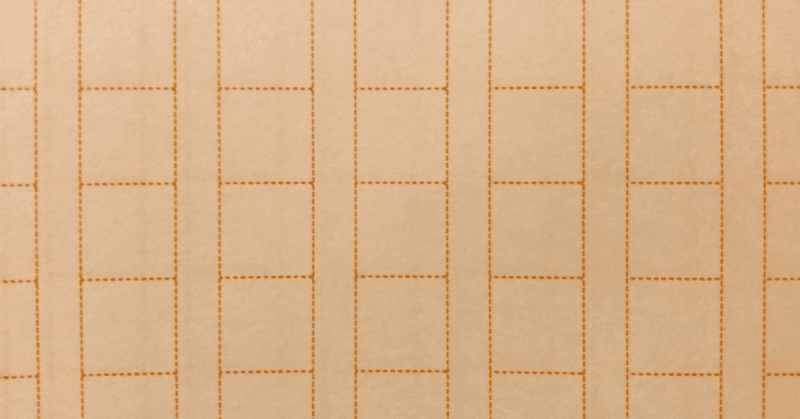
原稿用紙を買う男 (エッセイ×読書の愉しみ)
「……そういえば、本で読んだのか、テレビかラジオのドラマだったのか憶えていないんだけど、たしか『原稿用紙を買う男』というタイトルだった」
酒を呑みながら友人が話し始めたのは、私が自分の創作に触れたタイミングだったかもしれない。大学3年ぐらいだったと思う。
「……主人公は作家志望なんだ。でも、結局何も書けないまま、くたびれたサラリーマンになっている。もう40をいくつか過ぎて、……もちろん、ひとり暮らしだ」
「ふうん……なんか」
── なにか、自分の将来を暗示しているような気がした。
「でね、会社帰りにふと本屋に立ち寄り、新刊をいくつか手に取ってページをめくっているうちに……」
「自分も書きたくなってくるんだな」
「そう」
「書けるような気がしてくるんだ」
「そう。それで、文房具屋に寄って、原稿用紙を買って帰る。そして、ペンを執る」
「……でも」
「そう、でも書けない。1時間ほど原稿用紙を睨んだ後、ため息ついて寝転がる」
「……わかるな、その感じ」
「その主人公の部屋の押し入れには、そうやって買ってきた原稿用紙がうず高く積まれているんだ」
「うーん」
「その本だかドラマだかを最近思い出してね。……そういう人って意外と多いのかもしれない」
── それ、俺の話じゃないの、と内心思った。
大学入学直後から、生協の文具売り場にデザインの新しい原稿用紙が置かれていたり安売りしていると、買って帰ることがあった。
アパートの机の引き出しには、何も書いていない、あるいはタイトルだけ、あるいは本文を2,3行書いただけの原稿用紙がいくセットも入っていた。
友人は軽音楽部でニューミュージック系のバンドをやっており、私はそのバンドに詞を書いていた。長い文章はなかなか進まなかったが、自分もフォークギターを弾いていたその頃、詞ならばいくらでも書けた。
卒業間近の頃、私が作詞、彼が作曲した歌でそのバンドはヤマハのポプコン関東大会まで進んだそうだが、そこまでだった。
彼は文学部で1年留年し、学部を出て就職した。
私もやはり1年留年し、工学部から修士課程を経て就職した。
年月が流れ、定年退職・再雇用の年齢を迎えた頃、彼から小説を出版した、という連絡と共に「著者謹呈」で本が送られてきた。
趣味は音楽専業、とずっと思っていたので少々驚いたが、その小説は、とてもいい香りのする、上質な物語だった。
読み終えた時にふと思った:
── あの時話していた『原稿用紙を買う男』は、ひょっとしたら彼自身のこと、彼が自分で暗示していた未来だったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
