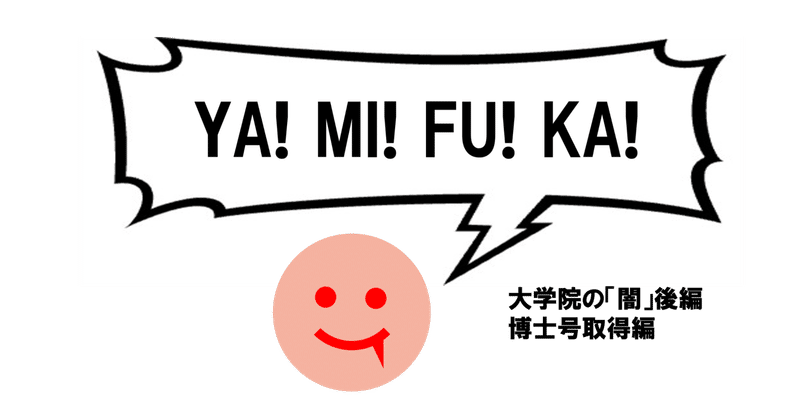
大学院の「闇」に迫る!!(後編)博士課程の深すぎる闇を語る(後半のみ有料)
こんにちは、現役ポスドクの毒太郎と申します。このnoteはあくまで毒太郎のアカデミア研究の体験を元に、偏見に基づいた知見を語っていく場です。ですのでほとんど統計値などは出てきませんので悪しからず。いちポスドクの意見、感想だと思って下さい。
さて、前回は前編として修士号の「闇」と称して、修士課程に進学することを奨励するよくわからん記事になりました。読んでいただけますと本記事の理解も深まると思いますのでぜひご覧ください。
今回はいよいよ本番ですが、本記事の後半は「闇」がとても深いために600円の有料記事にさせていただきます。勿論研究者以外の方が読んでもわかるように配慮はしているつもりですので、研究者以外の方にも読んでいただきたく思います。
前半では博士課程のことを普通に解説しているので、前半だけでも読んでいただければと思います!!
*注意点*
ちなみに有料記事を買っていただいた方にも、外部にネタバレは禁止(Xなど含む)でお願いします。有料記事にしているからという理由もありますが、かなり闇が深いので、無用な情報の拡散を防ぎたいという理由の側面が強いです。
この記事を通して告発したいわけではないのでご注意ください。
また、さながら推理小説のようになっていますので、深すぎる「闇」を推測しながら進むことをお薦めします。ヒントは無料部分で散りばめられています。
答えが知りたい方はぜひ購入お願いします。
博士課程の卒業条件
ではまず前回の続きですが、博士課程の卒業に関してまずは語ります。
博士課程は修士課程と比べると一般的に卒業条件がグッと厳しくなります。それは審査あり(査読「さどく」つきと言います)の国際誌への論文発表が卒業条件になることが多いからです。
詳しくは以前の記事に書きましたが、論文は投稿してから採用されるだけでも半年から1年程度かかります。「査読」という単語を聞き慣れない方はこちら。
論文を書くにはそれなりの結果が必要とされ、生命科学系だと実験が主になる場合少なくとも2年程度はかかるでしょう。しかも研究というのは当たり前ですが、世界の誰も発表していない事象を発見しなければなりません。
ただし実際にはいちから何かを探すわけではなく、一般的には研究室が持っているプロジェクトの続きを行うので、心配しすぎることはありません。ただしもらったプロジェクトがうまくいく保証はなく、これがうまくいかなかった場合、上司に新しいプロジェクトをもらうか、研究室の方針に沿った新しいプロジェクトを自分で立ち上げるしかなく、その場合はかなり時間を要します。
ですので実際は修士課程から博士課程までの2+3=5年間をひとつの研究室で過ごすことをお勧めします。そこで苦労して論文を採用されれば、卒業論文発表会(通称ディフェンス)を行い、クリアできれば晴れて博士号取得です。
博士課程は学部によりますが、3年のところが多いです。極めて早く論文を発表した場合、2年次でも早期卒業できますが、本当にまれです。そもそも3年でこの厳しい条件をクリアするのはとても難易度が高いです。
満期退学について
では3年(もしくは規定の年数)を超えてしまった場合はどうなるでしょうか。
強制退学です。
筆者の知る限り、博士課程に留年はありません。と言ってもここで研究人生終了ではありません。「満期退学」と言って、論文発表以外の単位を満たしている場合がこれに当たります。この場合は、退学後も大学に通い続けて、論文発表を目指します。企業に就職した場合は土日に研究室で実験をする場合がありとても大変です。
ただし、そもそも博士号取得見込みで就活の内定をもらったのに、博士号を取れなかった場合、内定が取り消される可能性もあります。
では満期退学した後、大学に残って研究したい場合はどうなるでしょうか?大学側も、何のポジションもない人間を大学構内に入れて研究させるわけにもいかないので、「研究生」などのよくわからないポジションを与えて研究を続けさせます。一応給料は出ますが、とても安いです。そもそも教授の許可がないと「研究生」として雇ってもらえないので、教授の判断で雇われなかった場合、博士も取れなかった無職が無事誕生します。
一般的に満期退学してから2-3年以内に論文を発表することが出来れば、博士課程3年で卒業した人たちと同じ博士号がもらえます。この満期退学後に博士号を取る方々のことを「オーバードクター」と言います。和製英語なので海外で使わないでください。ルールは大学によって違うのですが、満期退学後、2-3年を超えてしまうと、課程博士は取れません。
まるで経験してきたかのような詳しさだって?そっ、そんなわけないじゃないですか汗。
論文博士について
論文がその後出れば、「論文博士(通称ろんぱく)」となることもあります。論文博士は「論文」を発表した際に、博士課程に在籍していたかどうかに関わらず「博士号」を取れるシステムとなっております。昔は企業に在籍しながら論文を発表した場合などで取得するケースもあったみたいですが、今は制度自体が廃止している大学も多いらしいです。筆者の周りではあまり論文博士はいないので、論文博士が普通の博士と何が違うかはよくわかりません。別に卒業証書に『ロンパク』と書かれるわけではないので特に違いはないでしょう。
卒業できるかは教授の匙加減
また「論文を発表」することで卒業の要件を満たすと述べましたが、厳密には「教授が納得する論文を発表」することが卒業要件です。これはラボの運営方針によって全く異なります。教授がいい研究雑誌に論文を通そうとした場合、卒業のために投稿雑誌のランクを落とすことはしません。そうすると学生は博士課程の3年間で卒業できないこともあります。
知り合いの話ですが、3月までに卒業できるなら、助教のポジションを得ることを他大学と約束していたが、指導教授が投稿する学術雑誌を妥協しなかったため、論文を3月までに発表することができず、ポジションがおじゃんになったと聞いたことがあります。
論文を出していても、教授が「この雑誌じゃあ卒業はさせられない」と言ったら卒業できません。心優しい教授は、学生の卒業のためにまとめるのが簡単なプロジェクトを与えることもありますが、一方で研究者にとって論文は芸術品でもありますので、とても難しい問題です。
筆者が学生時代のボスは言いました。「ポス山さん、IF5以下は論文じゃないからそもそも投稿しないからね」と。その後「私のボスはCNS以外は論文じゃないって言ってたからこれでもだいぶマシだよ」と宣っておりました。ちょっと炎上しそうな発言ですが、実際に学生全員にIF5以上の論文を出させて卒業させたボスの能力は尊敬できます。
このように博士課程は修士課程と全く異なり、入学するのは簡単ですが、学位を取得するのは非常に困難です。
ちなみに今更ですがこの修士、博士課程をまとめて「大学院」と言います。そして修士、博士課程に入学することを「入院」、卒業することを「退院」と言います。まるで患者扱いです。
さらには研究所に入って研究する場合「入所」、出ていくことを「出所」と言います。まるで犯罪者扱いです。
これらは新入生歓迎会や、卒業追い出しコンパなどでよくある定番ネタです。院生の皆さんも早くシャバに戻ることを祈ります。
前述までの説明を見ると、「博士ってすごいんだ。」「国のエリートだ、もっと大事にするべきだ」と思うでしょう。ただしこの博士号取得にも抜け道があります。
博士号取得の抜け道、バグ技
では、ここで本題である二つの抜け道をお教えしましょう。
一つ目は、博士課程を取得する基準となる「論文を発表する」の投稿雑誌の質は、あまり問われないことです。というよりは前述の通り教授の裁量次第であると言った方がいいでしょう。これも以前に述べましたが、論文を投稿する雑誌もNatureなどのトップ雑誌から、誰も読まないようなしょーもない雑誌まで多々あります。なんなら大学が発行している誰が読んでいるかよくわからん雑誌でもいいこともあります。
ですが博士課程取得には、このしょーもない雑誌に論文が採用されたとしても、「論文を発表する」という基準を満たしたことになります。このようなしょーもない雑誌は、投稿すれば審査がザルでもすぐ採用されます。研究室側としても、良い雑誌に論文を載せたいという希望があるので、卒業用の小さなプロジェクトと、卒業には間に合わないかもしれない大きなプロジェクトの両方を学生に行わせることもあります。
お待たせしました、2つ目の抜け道がかなりの「闇深」案件なので有料とさせてください。抜け道というか制度を悪用したバグ技です。繰り返しになりますが、ヒントは上に散りばめられています。答えを見る前に推理することを推奨します。
現場からポス山毒太郎でした。
今記事では大学院博士課程のことを解説しつつ、後半ではほぼ誰でも博士号を取れるバグ技を紹介しました。 さながら小説のように前半からバグ技を推理することも可能だと思います。告発したいとかではないのでネタバレ厳禁でお願いします。https://t.co/ru2pAQtxMt
— ポス山毒太郎 (@pos_dokutaro) May 4, 2024
ここから先は
¥ 600
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
