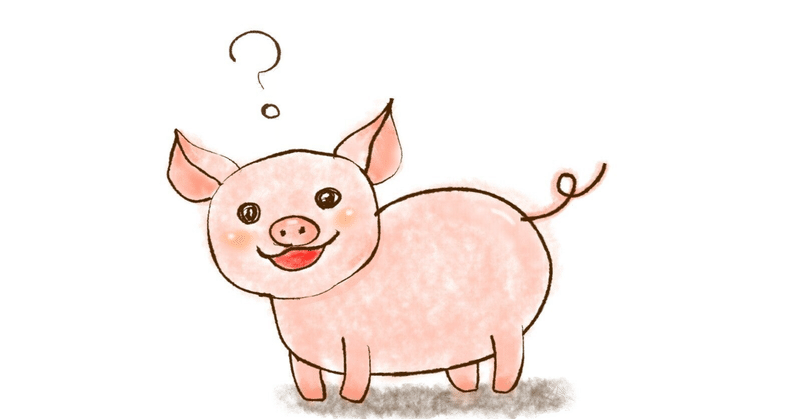
「自分にゃわからん」からしか始まらない
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
仕事の一環で、複数の企業で“採用の仕組みづくり”をお手伝いさせてもらっています。
その中で、「この会社では採用面接でどんなことを聞きましょうか?」という項目を決めるために、その内容を考えるという取り組みもしています。
ただ、この「面接で何を聞く?」というのを、しっかり考えて設計していかないと“思い付き”に任せた項目について質問をして、「よし。これで大体この応募者のことがわかったぞ」と思い込んでしまうなんてことが起きてしまいます。
と言うのも、実際に「何のためにその項目について質問をしているのか?」ということを投げかけてみると、実に曖昧であやふやな理由でその項目を聞いていたり、もっと言えば、「特に何の意図も無い」とか「何となくこういうことを聞いた方がいいんじゃないか」とか「これを聞けば、こういうことがわかると思っていた」という質問者の思い込みを根拠に聞いていた、なんてことが見えてきたりするわけです。
でも、「他者に質問をする」という状況で「なぜ質問をするのか?」ということについて考えてみると、何かが見えてくるような気がします。
例えば、「“面接”においてなぜ質問をするのか?」と考えてみれば、まず出てくるのが「この会社で一緒に働くメンバーとしてこの人が適しているかどうかを確認したい」ということがあるわけです。
そして、“それ”を確認したいわけですから「何を話してもらうと確認ができるのか?」について事前に決定しておくことが重要になります。
とは言え、これは当たり前の話ですが、そもそもの大前提として「その人がこの会社で一緒に働くメンバーとして適しているかどうか?」は、究極的には「働いてみなければ本当のところは確認できない」のは間違いありません。まだ働き始める前の段階で「確実にわかります」ということを断言するのは未来のことなので誰にもわかりません。だからこそ、これだけ様々な情報があふれかえっている令和5年の現在でも“若者の早期離職”というのは企業の規模を問わず問題になっているんじゃないかと思っています。それに、誤解を恐れずに言えば「仕事なんてやってみなくちゃ合ってるかどうかわからないもの」というのが本質的にあるわけです。
だからと言って「じゃあ、面接なんていらないじゃん」と開き直るだけの十分な取り組みをあらゆる企業ができているのか?と言えば「全然そんなことはない」というのが実情でもあります。
何しろ、求職者側に対して出回っている“面接対策”の情報や手段はそれこそ幾らでも無料で手に入るし、ある程度のサポートも無料でしてもらえる状況になっています(学生なら学校のキャリア相談や公共就職支援施設のキャリア相談など)。でも、“面接をする側”の企業向けの情報や手段は、書籍を購入して自分で学び実践する必要があったり、外部のサポートを有料で受けたり、なんてことが必要な状況です。それに、“面接をする側=企業”と“面接をされる側=求職者”では「面接の価値の非対称性」があるわけです。
“面接をする側=企業”にとっての面接は、「複数いる応募者の中から、今回採用するべき人を選ぶ機会であり“今後も定期的に実施するモノ”」です。
一方で“面接をされる側=求職者”にとっての面接は、「自分が働く唯一の企業を決めるための機会であり、基本的には退職しない限りもう参加しない“今回限りのモノ”」です。
もちろん、今の時代は様々な働き方があるので上記に当てはまらないケースも多々あるとは思いますが、それでも多くの人と企業にとっては、まだまだこういう考え方が大勢を占めています。
こうやって両側の事情を踏まえて“面接”というモノを眺めてみると、どうしたって「求職者側の必死さ」と「企業側の鷹揚さ」というのが対比として浮かび上がってきてしまいます(もちろん、「ウチはそんな風に考えてない」という企業もたくさんあるのは知っていますが)。
“面接”というモノの大枠の構造を前提として捉えている僕たちとしては、採用のお手伝いをさせてもらう際に、“面接”を求職者と同じように「今回限り、一度限りのモノ」として実施することを推奨しています。
だからこそ、「面接で聞くこと」というのを、その企業独自の項目として「確認して明らかにしたい事柄を聞かせてもらえるように設定した質問」を作りだして聞いていくという“仕組み”を構築するお手伝いをしているわけです。
これをやると当然のことながら、求職者側が「対策を講じる」ということが出来なくなります。何しろ、「何を聞かれるのか?」がわからないので事前に準備をすることができませんから、その人が面接の場で聞かれたことについて自分で考えたことを話すしかなくなります。
そうなればこれまた当然のことながら、「その人の人となり」が明らかになってきます。ただし、この時に投げかける質問は、面接する人がその時その場で思い付いた“ボクのかんがえたさいきょうのしつもん”などではありません。
その企業が総力を挙げて考えぬいて時間をかけて作りだした「ウチの会社で一緒に働く人に必要なモノを備えているかどうかを明らかにする質問」である必要があります。
企業側は、そこまで準備して、ようやく“人生の大きな一発勝負であり真剣勝負”である面接に臨む求職者と互角に渡り合える状態になるわけです。
「いい人が来ない」とか「いい人が採用できない」とか「人がすぐ辞めちゃう」とか「人が育たない」とか、そういうことで悩んだり困ったりしている企業は、もしかしたら採用の入り口でもある“面接”の段階において、「面接をする人のフィーリングに任せている」なんていう、よくある初歩的なミスをしてしまっている可能性が高いのでそこから見直してみると、今抱えている悩みや困りごとが解消していくかもしれません。
何しろ、日々様々な企業の様々な人達と会って話をさせてもらっているような、いわゆる“キャリアの専門家”である僕たちであっても、たったの1回や2回会ってしばらく話をしただけで「この人だったらこの先ずっと一緒にやっていけそうだ」なんてことを、その場の思い付きの質問やフィーリングだけで確認することはできないコトを自覚しています。
どれだけ“対人支援の経験”を重ねたところで、相手の頭の中をのぞき込んだり把握できるような“テレパシー”の能力は相変わらず身に付きそうもありませんので、これからも地道に「何のために質問をするのか?」「そのために何を質問するのか?」ということをずっとずっと考え続けないといけないなぁと痛感しているところです。道のりは険しい。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
