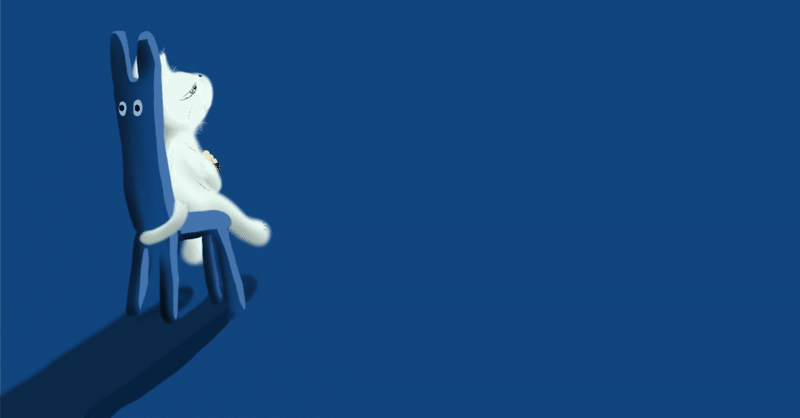
誰もが持つ、一人で抱えていく痛み
こんにちは、ぷるるです。
最近とんぼをよく見かけるようになりました。
夜、聞こえるのは虫の声。
吹き抜ける風にはもう、秋の気配が忍んでいます。
夏の終わりを感じて、ちょっと切なくなりますね。
ところで私は物心ついた頃から、この時期が一年で最も苦手です。
胸の一番柔らかい部分をぐっと掴んでくる痛みに、心がいっぱいになるから。
すべてが流れ過ぎ去ることに、打ちのめされてしまうから。
秋が深まりだせば、この気持ちも薄れていくのですけどね。
しばらくは一緒に、日々を過ごさねばなりません。
この気持ちは物心ついた時、すでに抱えていました。でもどうして良いのかわからなかった。
やがて忙しく賑やかにすることで、誤魔化すことを覚えました。
そして本当に心を寄せ合える相手と過ごすことができれば、消えてなくなるに違いないと信じていたのです。
けれどある時から、これは一人で抱えていくものだと、気づくに至りました。
でもやっぱり時には辛いから、小さな助けが必要です。
私の場合は、物語を読みたくなります。
できれば何度も何度も読み返している、ライナスの毛布みたいな小説がいいですね。
そんなわけで、昨日は久しぶりにこの物語と夜を過ごしました。

主人公は10歳の少年です。
両親が離婚して、普段はママと妹の3人暮らしですが、ひょんなことから作家である父親と過ごすことになりました。
二人は海岸沿いの家で一緒に貝拾いをし、料理を作り、小説を書きながら、暮らし始めます。

父と息子の日常が淡々とつづられているこの物語、大きな出来事は何も起きません。恋愛も人生訓もなし。結論も特になし。
けれど、交わされる会話が本当に素晴らしいんです。
父は主人公を自分に付属する「子ども」ではなく、一人の独立した存在として扱います。だから二人の会話は終始、上下ではなく横並び。
けれど肝心な時には人生の先達として、父は灯台となってくれるのでした。
主人公は父の大きな眼差しの中で、自由に伸びやかに心の世界を広げていきます。
私がこの小説と出会ったのは高校2年の今頃でした。
初めて読んだ時は主人公と一緒に、自分の心が自由に軽くなるのを感じたものです。
またこの小説が作者の息子、アラム・サローヤンに捧げられていたこともあり、私はいつしか、ウィリアム・サローヤンと小説の父親を重ね合わせていました。

けれど、実際のサローヤンはとても良き父親とは言えない人物でした。
息子アラムとも深い確執があり、のちに作家となったアラムはその関係を「ニューヨーク育ち わが心の60年代」に書いています。
アラムの心は深く傷つけられていたのです。あの美しい言葉を捧げてくれた父によって。
私は「ニューヨーク育ち わが心の60年代」を読んでこの事実を知った時、かなり衝撃を受けました。
そして自分の幻想を壊されたことに不快感すら覚えたものです。
しかし時が経つにつれて私は、ウィリアム・サローヤンにも抱えて生まれた大きな痛みと欠損があったと理解するようになりました。
そして、この痛みと欠損があったからこそ、サローヤンは小説家となり、「パパ、ユアクレイジー」のような美しい小説を生み出せたのだということも。
もしサローヤンが小説の中の父親みたいな人物であれば、物語など書く必要はなかったでしょう。
仮に書いたとしても、人の心にそっと寄り添うものにはならなかったと、私は思います。
私たちは多分、誰しも痛みを抱えて生まれたのではないでしょうか。
もちろんその種類や大きさは、人それぞれでしょうけれど。
だからと言って、痛み=克服すべき課題というわけでもない気がします。
なぜならこの痛みがあるからこそ、心を震わせ、感じ受け取る幸福を味わうことができると思うからです。
コインの裏表のように。
私の場合なら、サローヤンを愛する気持ちもその一つ。
この痛みを誤魔化したり消し去った場合、感じる心も一緒に失うのではないでしょうか。それは果たして幸福か・・・。
それならば、抱えて歩きたいと思うのです。
せめて人に八つ当たりしないように、気をつけながら。
何でもないように起きて、働き、笑い、文句を言いながら。
でもサローヤンは、家族にガッツリぶつけていたわけですけどね・・・
自分がアラムだったら、たまったものじゃないけれど(だから彼は本に書いてるんでしょうけど)、でもサローヤンの業を誰よりも理解していたのもアラムではないかと思います。
なぜなら彼は息子であり、また自身も一人の作家なのですから。
ウィリアム・サローヤン
アメリカの小説家・劇作家。アメリカの庶民を明るく書いた。
(中略)
1934年(26歳)、ストーリー誌(Story)に載せた『空中ブランコに乗った若者』によって知られ、以降、庶民の哀歓を平易な文体で明るくほろ苦く綴り続けた。映画の台本も書いた。
1938年、サローヤンが30歳のとき『わが心高原に』と翌年の『君が人生の時』がブロードウェイであたり、1940年、後者に演劇部門のピューリッツァー賞が与えられたが辞退した。同年出版の『我が名はアラム』は各国語に翻訳され、日本でも、真珠湾攻撃直前の1941年11月に清水俊二の訳書が六興出版から刊行された。
1943年(35歳)、シナリオを小説にした『人間喜劇』を2月に出版し、翌月映画(英語版)が公開され、1944年、それによりアカデミー原案賞を受けた。
(以下略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
