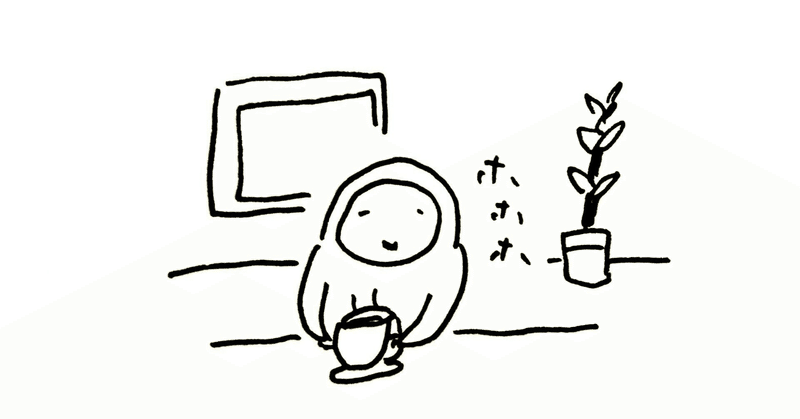
『日日是好日』の解釈のしかたが変わった日
日日是好日
年末の整理整頓中、久しぶりにこの本を手に取った。
一度ページをめくったが最後、はじめから最後の章まで、おまけにあとがきに柳家小三治さんの解説まで、掃除はそっちのけで一気に読んだ。
最近、なんとなく抱いていた心のもやもやが、この本の中で言語化されていた。
そして月並みな表現ではあるが、改めて良い作品だと思った。
でも今回は、前回……といっても相当昔にさかのぼると思うが、以前読んだ時よりも、作者の言葉に深みと重みを感じた。
◇
日日是好日、にちにちこれこうにち。
この言葉はもともと、掛軸でよく見かける禅語である。
エッセイ『日日是好日』は、ルポライター、エッセイストとして活躍されている森下典子さんのお茶にまつわるエッセイだ。
彼女がお茶を始めた20歳の頃から、その後25年の軌跡が綴られている。
彼女がお茶の稽古を通じて学んだ15のことについて、彼女のエピソードとともに、時に面白く、時に悲しく、正直に綴られている。
◇
10年前の私と、今の私
最初にこの本を読んだ10年前、作者のお稽古に対する思い、どちらかといえばネガティブな感情に対し、深く共感を覚えた。
非常に悪いたとえだが、学校で、成績の芳しくない仲間を見つけた気分だった。
当時の私は茶道について今よりも理解が浅く、お稽古に行くことを義務のように感じていた。
社中さんの中では最年少だったので(今でもそうだが…)、できないことを若さのせいにし、失敗から学ぼうとしなかった。
そして大したことができていないわりに外面だけは一人前で、茶道を習っていること自体を鼻にかけているところがあった。
「万年初心者」とはいったもので、きっと、一番質の悪いタイプだ。
日日是好日。
どんな日もよい日。
この解釈は読む人によるだろう。
心地よい間、楽しもう(つまりそれ以外は、適当に)。
当時の私は、そんな風に解釈していた。
日和見主義というか、受け身の姿勢というか。
今でも覚えているのだが、このエッセイには、作者にも後輩ができ、その後輩がぐんぐん成長していく様子を横目に焦りを覚える一面がある。
当時、私はなぜか作者のその焦りを疑似体験し、このままではいけない、と思った。
私もしっかりしようと心を入れ替えようと誓ったことを、ふと思い出した。
しかし、昔の姿勢がそう簡単に矯正されるはずもなく。
万年初心者だから仕方ないと言い放ちながら、失敗しては忘れるを繰り返してきた。
この10年を振り返ると、心地よい環境にばかり目を向ける姿勢でお茶と付き合ってきたところがある。
そう思った瞬間、この10年が「虚」に感じた。
少し脱線するが、最初に感じていた「もやもや」は多分、茶道はもちろん、あらゆる面での自分の能力の限界に対する感情だと整理すると、なんだかしっくりくる。
正直言って、2021年は不完全燃焼に終わろうとしているから――
(完全に脱線)
◇
10年後の私が読んだら、どう思うだろう
私が所属する裏千家には、上級者になるまでのステップがある。
これから10年間、どのような姿勢であれお茶を続けてさえいれば、きっといわゆる「お茶の先生」にはなれるだろう。
でも、今のように付け焼刃のような姿勢でお茶に向き合っていたら、おそらくお茶会が終わってしまえばまた、「万年初心者」に甘んじるのだ。
そしてそれ以降、先生の看板をいただいたとしても、それなりの先生にしかなれないだろう。
正直、それはいやだな。
そうならないためにはどうしたらよいだろうか。
それに対する答えを、この本で見つけた。
もっと正確に言えば、この本を読んで改めて、お茶の先生になった時の感情を疑似体験した、とでも言おうか。
謙虚な気持ちをもってお茶に向き合えるなら、きっと魅力的な先生になれるのではないのだろうか。
そしてこれはお茶に限らず、仕事でもそうだし、対人関係にも当てはまるのではないか。
◇
私は知らないことを、自分でわかっている。
だから、目の前にあることから学ぶこと。
この姿勢をもって生きること。
これこそすなわち日日是好日、の意味するところなのかもしれない。
〜ご紹介した本〜
日日是好日 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ
森下典子/著
文庫版:新潮文庫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
