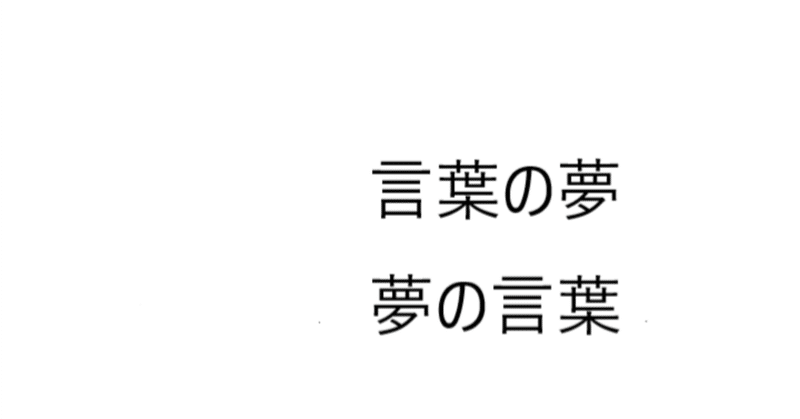
まばらにまだらに『杳子』を読む(07)
反復され変奏される身振り
あるひとつの作品のなかで、または複数の作品のあいだで、ある言葉や身振りや光景が、わずかに移りかわりながら、くり返されることがあります。
ともにふれる、ともぶれ、共振。
ふれる、振れる、震れる、触れる、狂れる。ぶれる。ゆれる。
もたれあう、つりあう、釣りあう、吊りあう、釣り合い・吊り合い。
今回は、以上の言葉の身振りとイメージが、『杳子』という言葉で書かれた作品のなかで反復され変奏されていくさまを見てみます。
*
変奏、変装、変相、返送。
「変奏」を変奏することで返送(送り返す)が出てきました。送り返す、贈り返す。私は詳しくないのですが、返歌とか連歌とか連句を連想しました。
受けたものを受けとめたうえで、さらに送り(贈り)返す。今回は、まさにそういう話をしたいのです。
岩のケルン
いつのまにか杳子は目の前に積まれた小さな岩の塔をしげしげと眺めていた。それが道しるべだということは、その時、彼女はすこしも意識しなかったという。どれも握り拳(こぶし)をふたつ合わせたぐらいの小さな丸い岩が、数えてみるとぜんぶで八つ、投げやりに積み重ねられて、いまにも倒れそうに立っている。その直立の無意味さに、彼女は長いこと眺め耽(ふけ)っていた。
(『杳子』p.19『杳子・妻隠』新潮文庫所収、丸括弧内は原文ではルビ、丸括弧も太文字も引用者による、以下同じ)
「一」という章では、深い谷底で小さな岩を積み重ねたケルンが、以上のように描かれています。
石のケルン
またある日、彼が河原の草の上に平たく寝そべって、地面の温かみの中から冷たい風をとおして空を見つめていると、杳子はいつのまにか川べりに出て、川原石の群がる中にしゃがみこんで、石をひとつひとつ積んで塔をこしらえていた。
砂のなかになかば埋もれた平たい石を土台にして、形さまざまな石が五つ六つ、段々に小さ目に、左に傾いて倒れそうになるまで積まれ、危うい釣合いを取った。
(pp.62-63・「三」)
「三」の章からの引用です。
この川原の場面ではケルンという言葉はつかわれていませんが、「一」の「小さな岩」のケルンとの大きな違いは、誰かが積んだものではなく、杳子が自分の意志と意思で「石」を積んでこしらえていることです。
いし、石、意志、意思。
*
この場面では石という言葉が頻出しますが、これは「一」で石という言葉がかたくななほどにもちいられておらず、岩という言葉があちこちに見られると対照的です。
しばらくして、《泣き疲れて、庭の隅にかがみこんで石ころを見つめている子供の顔だな》と彼はつぶやいた。
(p.11)
「一」に見られる、この「石ころ」は、「彼」が自分の幼い頃の記憶に重ねて、杳子の印象を述べている部分です。
大きな石ころから小さな石ころまで、どれもこれも落ちようとひしめいていて、お互いに邪魔しあってようやく止まっている。
(p.18)
同じく「一」からの引用ですが、この文があるのは、杳子の話が伝聞として記述されている箇所です。杳子が「石ころ」と口にしたとも取れます。そう解するとすれば、大切な箇所です。杳子の言う「大きな石ころ」とは岩ではないでしょうか。
杳子にとって谷底で見つめていたケルンの小さな岩たちは、「彼」が見た岩(異和・違和)ではなく、「石ころ」であり、さらに言うなら意思ではなく意志だった気がします。
「落ちようとひしめいていて、お互いに邪魔しあって」という箇所に、思考というよりも、むしろ力関係としての意志(指向・志向)を感じるのです。
つまり、石を眺める杳子は、目に映る石の思い(心)ではなく、石に内在する志(心指す力)を感じとっていたと考えられるのですが、この点については、別の記事で触れます。
*
「一」の章で「石」という言葉が出てくるのは、以上二箇所だと見られまが、見落としがあれば、ごめんなさい。
*
それにしても、谷底には石があってもいいはずなのに、なぜか「岩」という言葉ばかりが出てくるのには強い意志や意思を感じないではいられません。「彼」ではなく、むしろ作者の意志や意思のことです。
慎重に言葉を選びながら作品をつづっていた、確固とした作者の意志があるはずです。固い意志を維持するためには意地も必要でしょう。そんな作者の意志と意地に、ふれてみたい誘惑を覚えます。
*
念を押しますが、ここでは、あくまでも「石」という言葉と「岩」という言葉に注目しています。私たちが読んでいるのは報告書ではなく、言葉で書かれた作品だということを忘れてはなりません。
とはいうものの、私たちは目の前にある言葉だけでなく、「彼」と杳子の心を読もうとします。言葉にともぶれする、つまり、言葉と、ともにふれます。
ふれる、振れる、震れる、触れる、狂れる。ぶれる。ゆれる。
私もふれてみます。
*
谷底の場面では、「彼」は自然物である岩に人の姿を見て、いっぽうの杳子は人工物のしるしであるケルンに「直立の無意味さ」を感じていたのを思いだしましょう。
そのように解するのであれば、ふたりはともに岩に異和や違和を覚えていたもと言えそうです。
いわ、岩、異和、違和。
ふれたどころか、かなり、ぶれたようです。
*
「石」が頻出する川原の場面で気になった箇所を引用します。
「あたし、石になってやるから」
(p.58)
あの時、杳子の中で、自然に流れすぎるはずだった病気が、他人の目に見つめられて小さな石みたいに凝固してしまったのかもしれない。
(p.60)
彼はふと杳子という存在を感じ当てたような気がして起き上がり、杳子のそばに行って、一緒にかがみこんで石の塔をながめた。
(p.64)
彼は石の塔のそばに行き、「このままじゃ、だめだね」と言って、石をひとつひとつ下ろして下に積み、低い安定した山をこしらえてやった。
(p.64)
ひとつまみの砂利
おなじく「三」にある「街なかの或(あ)る自然公園」(p.65)の場面に移ります。暗い池のほとりのベンチにふたりが腰をおろしているとき、杳子が立ち上がって駆け出し、以下の行動をします。
(……)ふいに立ち止まって、あたふたと引き返してきて、彼の足もとの砂利を両方の手のひらにいっぱいに摑(つか)み取って、気むづかしげに一人でつぶやいた。
「目じるしを置いてこなくちゃ」
(p.70)
(……)なるほど、ところどころにある石のベンチのどれも左手前の隅に、ひとつまみの砂利がきちんとのせてある。遠いところからの、慎ましい、几帳面な信号のような表情をしていた。
(p.71)
「ひとつまみの砂利」はどんなふうにして「石のベンチ」の隅にのせてあったのか気になって仕方がありません。まさかケルンのような形とは考えにくいです。
詳しく描写されていないのですが、私は盛り塩を思いうかべてしまいました。まさか、きれいな三角錐とか円錐ではないでしょう。そんな見事な形をしていれば、そう書かれているだろうと思います。
なにしろ、ぱらぱらこぼれそうな砂利です。おそらく焼香のさいの抹香くらいのささやかに盛った形だろうと理解しておきます。
*
でも、盛り塩とか焼香の抹香なんて連想すると、杳子の行為が意味ありげで儀式めいたものに感じられるので要注意です。これは雑念であり邪念ではないでしょうか。
あなたの連載している記事は雑念と邪念と妄念だらけじゃないか、なんて言われれば、返す言葉がありません。じっさい、そうなのですから。
*
興味深いのは、杳子が石を積み上げたあとと、ひとつまみの砂利をのせたあととでは、ふたりのフィジカルな(身体的および物理的な)接触に違いがあることです。
(……)彼は杳子を右腕の下に包んでやる。重さの感じがすこしも腕に伝わってこなかった。
(p.65)
ここでは、杳子は「彼」に、身体的にも物理的にも、もたれてかかってはいない、つまり力が働いていないようです。
それが、砂利をひとつまみ置いて目じるしをこしらえるという儀式めいた行為の直後になると、「彼」は杳子の唇に自分の唇を近づけます。
杳子の唇は受け止めるでも拒むでもなく、感触をなにか漠としたひろがりの中へぼかしてしまった。彼は杳子の軀を右腕で強く抱きしめかけた。やはり何の反応もなかった。彼は力をゆるめて、杳子と触れるか触れぬかに軀を寄せあった。
そのまま、杳子の唇が固い輪郭を取って、彼の唇にかすかに応(こた)えるまで、彼は杳子の軀を腕の中につつんでいた。
(pp.74-75)
関係が深まったのか相変わらずなのか、迷うところですが、「彼の唇にかすかに応(こた)えるまで」とある以上、最終的にはかすかに応えたのだろうと推測できます。
とはいうものの、砂利の目じるしとふたりの関係につながりがあるとは考えにくいです。たんに時間の経過からこうなっていったとも取れます。
岩、石、砂利
岩 ⇒ 石 ⇒ 砂利
岩が砕けて石になり、それが砂になっていく。そうした自然の流れに沿うかのような展開にも見えます。
それはともかく、石の場合には、杳子が自分の意思と意志で石を積み上げたという点が大切だと思えます。
岩 ⇒ 石 ⇒ 砂
砂の次は何だろう、なんて考えてしまいそうです。
皿とカップのケルン
作品の最終章にあたる「八」を見てみましょう。新潮文庫版だと最後のページの前のページ(裏のページです)に、次の文章があります。
場所は、杳子の自宅の二階で、杳子が自分のものとしてつかっている「かなり広い洋間」(p.153)です。
食べ終えると、杳子は立ち上がって、しばらくためらうようにテーブルの上を見つめていたが、いきなり残酷な手つきで自分の皿と彼の皿を、自分のカップと彼のカップを重ね合わせて、テーブルの真中に置いた。上のカップが下のカップの中で斜めに傾(かし)いで、把手(とって)を宙に突き出しだまま落ち着いた。二人は顔を見合わせた。
杳子は(……)壁際の長椅子(いす)に軀を沈めた。
どうせ続かない釣合いをひと思いに崩してしまおうと、二人は軀を押しつけあい、ときどき息をひそめてはまだ釣合いの保たれているのを訝(いぶか)り、やがて釣合いの崩れ落ちる歓(よろこ)びの中へ奔放に耽りこんだ。
(p.167)
「上のカップが下のカップの中で斜めに傾(かし)いで、把手(とって)を宙に突き出しだまま落ち着いた。」という描写は、のちにつづくであろう性行為の隠喩と前触れにも取れます。
これにつづく箇所には、「長椅子」、「歓び」、「奔放」とあるのですから、まさに性行為を婉曲に述べたものでしょう。
*
この場面でも、「ケルン」という言葉はもちいられていませんが、重ね合わされたカップと皿、釣合い、崩す、保つ――こうした言葉のそのイメージが、岩のケルンと石のケルンとひとつまみの盛られた砂利と、似た身振りを見せています。
異なるのは、ここでは崩れ落ちるものとして描かれているとこです。崩れるのは釣合いだけでなく、その姿もです。
崩れなければならないものと言うべきでしょう。釣合いとふたりのあり方を崩すのです。
釣合っている、たもたれているかに見える、ふたりのありようが、「どうせ続かない釣合いをひと思いに崩してしまおう」という意思によって「釣合いの崩れ落ちる歓(よろこ)び」へと転じるべきものとして書かれているようです。
*
最後のセンテンスです。この章の、そして『杳子』という小説の最後の文です。
帰り道のことを考えはじめた彼の腕の下で、杳子の軀がおそらく彼の軀への嫌悪から、かすかな輪郭だけの感じに細っていった。
(p.170)
ここには、双方向的な「もたれあう」も、一方的な「もたれる」もないかのようです。両者のあいだでは、もはや力が働いていないのです。もちろん、釣合いという力学的な関係もありません。
岩、石、砂、土
最後に重ねられた、つまり積まれたものが、皿とカップであることは象徴的です。岩や石や砂のように自然物ではありません。陶器ですから、陶土をこねて形をつくり、焼いて強度を増したものでしょう。
詳しい定義は知りませんが、陶土は乾けば粉であり、岩の最終的な形態と理解しています。ようするに、土なのです。
岩 ⇒ 石 ⇒ 砂 ⇒ 土
自然物 ⇒ 人工物
塊 ⇒ 粒・粉 ⇒ 塊
いわば土からつくられた陶器は人工物です。似たでき方をしたものは自然にもあるでしょうが、陶器は自然にはないものです。岩や石にくらべて(柔らかい質の岩や石もあるでしょうが)、容易に割れたり砕けそうなイメージもあります。
とはいえ、「だから何?」という図式でしかありません。
まさか、「土に還る」なんて口当たりのいい美辞麗句や疑似麗句を口にするつもりもないです。こういう読み方もできるのではないか、としか言えません。
*
岩 ⇒ 石 ⇒ 砂 ⇒ 土
このような図式は、それに抗う作品の細部を切り捨てた、ずさんな見立てでしかありません。
そうした図式のいかがわしさを十分に意識しながら、作品の細部に目を注ぎつつ、テーマ(Thema)というスキーマ(図式・schema)の限界を、あえてテーマを示そうと装う疑似的な身振りで演じてみせたのが、蓮實重彦だったという気がします。
そうした失望と隣り合わせの演技の姿勢を蓮實は、ジャン=ピエール・リシャールから学んだのではないかという気もしないではありません。*
*「批評、あるいは仮死の祭典――ジャン=ピエール・リシャール論」(『批評 あるいは仮死の祭典』所収・蓮實重彦著・せりか書房)
カップ、皿
気になるのは、土を焼いた陶器――こんな言葉は作品のどこにも書かれていません――というよりも、作品に書かれている、カップがどのように積み重ねられていたかです。
食べ終えると、杳子は立ち上がって、しばらくためらうようにテーブルの上を見つめていたが、いきなり残酷な手つきで自分の皿と彼の皿を、自分のカップと彼のカップを重ね合わせて、テーブルの真中に置いた。上のカップが下のカップの中で斜めに傾(かし)いで、把手(とって)を宙に突き出しだまま落ち着いた。二人は顔を見合わせた。
(p.167)
重ね合わされているのは、ついさっきまで「彼」が唇をつけたカップと杳子が唇をつけたカップです。そして、ふたりが崩して口に運び咀嚼して、いまはそれぞれの胃の中にあるであろうケーキがのっていた皿です。
岩でも石でもありません。
唇はこの章で頻出する語であり、「食べる」はまるで反復の権化のように杳子が嫌悪し恥ずかしいと感じる行為でもあります。
「上のカップが下のカップの中で」(合体や挿入を感じさせる表現です)、斜めに傾いで落ち着いたのですから釣合いが取れています。ただし、いきなり残酷な手つきで積み重ねられた結果としての釣合いなのです。
(この作品では、釣合いは、いわばいびつな釣合いであり、整然としたものではなく傾いていたり、ゆがんだ形や姿でかろうじて立っているものとして描かれています。危うく脆いのです。)
宙に突き出している把手は、手を差しだして救いを求めているようにも、手を差しのべて助けを申し出ているようにも、何らかの突起物が立って(勃って)いるようにも、見えるでしょう。
わざわざ書かれているのですから、読者はあれこれ想像する権利があると思います。想像は人それぞれであるはずです。
*
「いきなり残酷な手つきで」なのは、食べる行為、食べるという人が何度もくり返しに対して、さらには食べている最中に咀嚼(そしゃく)という反復に対して杳子が覚える嫌悪感と関係があるのかもしれません。投げやりでもあります。
この「食べる」と「嫌悪」については、いつか書きたいと思います。この最終章は読み応えのある刺激的な細部に満ちているのです。
「反復」を反復する身振り
岩 ⇒ 石 ⇒ 砂 ⇒ 土
反復され変奏される「ケルン」を追って、冒頭、途中、最後と飛びましたが、急ぐことはないでしょう。
ひとつ気になってならないのは、最終章である「八」には「くり返す」と「反復」という言葉が変奏されつつ、またそのままに何度もくり返され反復されていることです。
*
この章の始まるp.157から最後のp.170までに、以下の言葉が出てくる回数を見てみましょう。
・「反復」:10
・「くりかえす(し)」「繰り返す(し):8
・「癖」:10
・「釣合い」:7
「また」「同じ」「何度も」など反復を示す言葉を含めればもっとあります。
以上の反復が多いと感じるかどうかは人それぞれでしょう。私は多いと思います。というか、やたら目についてなりません。ともぶれしてしまうのです。
上の語句に関連して、私は次のフレーズに目を引かれます。
・「二度と繰返しのきかない釣合い」(p.169)
このフレーズが気に掛かってなりません。
*
「くり返す」をくり返す、「反復」を反復する。
この言葉の身振りは特徴的どころか尋常ではないものであり、それだけに興味をひかれずにはいきません。
作品の冒頭にもどる必要がありそうです。そこには、のちに反復される対象、のちにくり返される対象が必ずあるはずですから。
読みつづけます。まばらにまだらに読んでいきます。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
