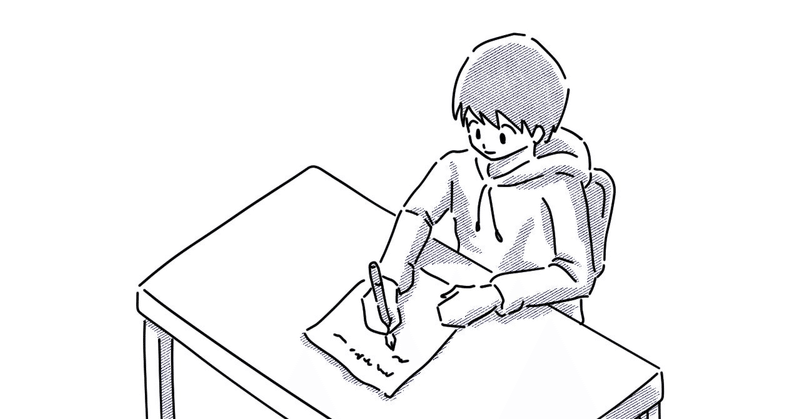
【自伝的小説】手紙
金曜日の夜8時、東京駅。
二時間半の旅を終え、ホームに降り立った私は、ふぅと一息、深呼吸を…する間もなく大量の乗降客の波に流され新幹線用の改札を出た。
さすが東京だ。
解放的な話し声が多く聞こえるのは週末の夜だからだろうか。
平日の通勤時の無表情で速足で歩く人の群れの流れに比べて、幾分の軽い足取りの人が多い気がする。
かくいう私も、関西から仕事で東京に出張をしてきている。
ただ、こちらでの仕事は、月曜に行われる東京本社での会議のみで週末は休み、土日を東京で過ごすために、昼間に大阪での仕事を終えた後、前乗りをしていた。
前乗りをした理由は、埼玉県の川口市へ行ってみたかったからだ。
私は、小学校四年生まで東京のすぐ北側に位置する埼玉県川口市に住んでいた。
元々の出身も関西ではあるのだが、父親の転勤に伴って幼稚園からの六年ほどを過ごしている。
小学校五年生からはまた関西へ戻り、高校までを兵庫で。
大学四年間は東京だったものの、就職も大阪になり、旅行や出張で上京することはあっても、30~40分で行けるはずの川口を訪れる機会はないまま、実に30年もの月日が経ってしまっていた。
きっかけは、大学時代からの友人であるヤマモトと久しぶりに会うことになったことだった。
ヤマモトは、実は小学校時代のクラスメートで、私が転校してしまってからは疎遠だったが大学で偶然再会し、それからは就職した後でもよく連絡は取り合っていた。
「東京来るんだったら、ちょっと飲もうよ」
小学校の頃は埼玉に住んでいたヤマモトも今は結婚して都内に家を買っている。インフラ系の会社で技術職として勤務、転勤もほぼなく、大学の同級生である奥さんと十歳になる娘さんの三人で暮らしている。
私は奥さんとも学生時代からの顔なじみでもあるからか、ヤマモトも休みの日に出てきやすいのだろう、ノリノリで提案してきたことが少し微笑ましかった。
電話で興奮気味に大学時代によく行った店の話で盛り上がり、近況報告なども含めて二時間ほども話してしまったが、電話を切ってからふと川口の話題を全くしていないことに気が付いた。
ヤマモトとは小学校でも同級生だった。
この年になっても小学校時代の話ができる友人などなかなかいない。
本来なら子供のころの話に花が咲くことがあってもいいのだが、不思議とその話題が出なかった。
私は関西に引っ越してからは、兵庫県の郊外ののどかな地方都市に住んでいた。
田畑が広がり、電車の本数も1時間に2本、2両編成が走るだけ。
当時、埼玉県で最大の人口を誇り、東京に隣接していた川口市から引っ越した私は、そのギャップに驚いたものだ。
大型トラックが列をなして走る産業道路、そこにまたがるマンモス歩道橋、10両以上連なった電車が駅に着くとあふれかえる人が改札に殺到していた川口市で育った私は、転校先でできた友人たちに「東京モン」などと呼ばれ、私自身も川口との生活環境の違いを「都会と田舎の違い」としてとらえて、「自分は都会育ちだから」などと思って育ってきた。
自分にとって川口市は思い入れのある街のはずだったのに、なぜ同郷の人間とすら話題にないのだろうか。
不思議に感じた。
「川口に行ってみよう」
特に何か目的や目当ての場所があるわけでもない。
30年ぶりに、小学校四年生まで住んでいた場所にただ行ってみたい。
今は関西に住んでいる自分にとって、こんな機会でもない限り、観光地でもないただの住宅街にわざわざ行くことはないだろう。
郷愁ともまた違う、なにか好奇心に近いような気持ちで週末前乗りの予定を埋める決心をしたのだった。
土曜日。
月曜日の出張先に近い新橋のホテルでゆっくり起きた私は、新橋駅から京浜東北線に乗り、昼ごろに蕨駅を目指した。
京浜東北線には川口駅、西川口駅と、川口市内の駅もあるのだが、私が過ごした芝地区の最寄りは隣接する蕨市にある蕨駅が最寄りだ。
駅の改札の数は昔のまま。
もちろん自動改札に変わってはいるのだが、通勤ラッシュの混雑時を想定した大量の改札口を見て、昔の、切符を買って改札を通る際の並びながらパンチで穴あけしてくれる駅員さんに恐る恐る差し出し、目にも止まらぬスピードで「パチン」と穴あけして返ってくるというやり取りにドキドキしていた記憶が蘇ってきた。
改札を出て、東口のロータリーに降りる。
子供のころの印象と、今の感覚とではさすがに建物の大きさの感じ方にはかなりの違いがあるのはわかっていたが、それを差し引いてもなお、こぢんまりした駅前をしみじみ眺めた。
駅前の薬局には母がパートに来ていたのだが、さすがにその店はない。
小さなロータリーから東へ向かって道が伸びている。ほんの数十メートル歩くだけで、蕨市から川口市へ変わる。建物は変わっても幼い頃に過ごした記憶は健在で、一気に郷愁が沸き上がる。
そうだそうだ、こんな道だった。
駅からの道に沿って流れる小さな川。
周りには当時と変わらずたくさんの住宅が立ち並ぶ。
しばらく歩くと少し大きめの交差点の上に、四方向に陸橋が渡された歩道橋がある。これが私の記憶の中に燦然と輝く「マンモス歩道橋」だ。
私たちの小学校の通学路の「要衝」で、ここをそのまま東に行く人、南へ行く人、斜め向かい側の南東へ降りる人、学校からの下校路はここで各々の自宅の方向へと分岐する。
ここで別れの挨拶をし、翌朝、またここで出会って、連れ立って登校する。
自分たちにとっては「友達と会える場所」の象徴の巨大なモニュメントのように思っていた記憶があったのだが、今、大人になってその歩道橋にまた訪れてみて、イメージの中の巨大歩道橋と、目の前のごく普通の歩道橋とのギャップにまた驚きを隠せなかった。
子供のころに見ていた川口市の景色は、巨大な鉄筋コンクリートの建造物に囲まれた大工業都市のモータリゼーションの一角だったはずなのだが、大人になって見たその街は、普通の住宅地のそれだった。
子供のころとは体の大きさが違うから、などという体感的な理由も多少はあるのだろうが、そんな物理的なものだけではない。
あの頃は、この周囲1~2キロメートルが世界のほとんどだった。
小学校から通学路を通り、歩道橋を渡り、自分の住むマンションへ。
近所の駄菓子屋、友だちと遊ぶ公園、母親のパート先の薬局。
普段はあまり遊ばない上級生の友達に連れられて自転車で向かう5キロ先のゲームセンターへ行くだけでまるで冒険の旅に出かけたような気分だった。
小さな世界で、小さな眼で、必死に見ていたあの頃には感じられていたワクワク感を「大人になった」というありきたりな理由でそれを感じられない自分がとても寂しく感じられてしまう。
子供のころの冒険心を失った自分は、逆に何が見えるようになったのだろうか。
かつての自宅のマンション前、家族と行ったファミリーレストラン、通っていた小学校など、ひと通りのノスタルジーを満喫した後、駅へ向かって戻っている時、見覚えのある街路樹を見かけた。
「あれ、なんだっけ、ここ」
とても懐かしい感覚につい立ち止まる。
変わってしまっている部分ももちろん多いが、向かい側にある交番は当時のままだ。交番の記憶が引き金となって当時の情景が浮かんできた。
「たしか、この角に自販機があって、そこで見知らぬおじさんにガチャガチャのおもちゃを買ってもらったことがある」
何だ、その記憶。
そのおじさんは誰なんだ。
なんでそんなもの買ってくれたんだっけ。
少しずつ記憶の糸を手繰り寄せる、とともに、あの頃感じていた緊張と冒険心が沸き上がってきた。
三年生か四年生の頃だった。
学校帰り、友達のマサカズくんと一緒に帰っていた。なぜかいつもの通学路とは違い、一本西側の遠い道。
小学校の正門を出てまっすぐ数百メートル歩き、この街路樹のある道との交差点に差し掛かったところで、見知らぬおじさんに声をかけられた。
年齢は50代後半くらいだろうか、茶色いジャンパーのような服と作業ズボン、頭髪は薄く、細い目をした小柄の人だったと思う。
「マサカズ君!」
私に声をかけたのではなかった。
おじさんはマサカズ君を呼び止めた。
その声は優しくはなかったが、恐ろしいものでもなかった気がする。
ただ、呼び止められたマサカズ君は素早く反応した。
おじさんの姿を見るや否や、私を振り返り、おじさんには見えない角度で、私に一枚の封筒を渡し、そして「じゃあね!」と言って、走り去っていった。
それを見たおじさんも慌ててマサカズ君を追いかけて走り去る。
残された私は、状況が呑み込めず、渡された封筒が手の中で持て余されていた。
あの人は、マサカズ君の知り合いのおじさんなのだろうか。
追いかけて行ったが、マサカズ君は大丈夫なのだろうか。
さいわい、道の向かい側には交番がある。
今起こったことをおまわりさんに伝えよう。
そう思って歩き出そうとするが、握りしめていた封筒の扱いに困惑した。
白い封筒の中を覗き見ると、一枚の白い紙。
文字が書いてある。
それは手紙だった。
キレイで柔らかな字だが、やや筆圧が弱い。
『マサカズへ、元気で過ごしていますか?
手紙ありがとう。お母さんのことは心配しないでね』
手紙の書き出しを目にして、そこで読むことをやめた。
マサカズ君のお母さんが、マサカズ君に宛てて書いた手紙なのだろう。
お母さんが「元気で過ごしていますか?」や「心配しないで」という内容の手紙を書くということの異様さに面食らってしまったからだ。
一緒に住んでいないのだろうか。いや、一緒に住んでいないことくらいはよくあることだが、その先の「心配しないで」という言葉に極めてシリアスな雰囲気を感じ取ってしまった。
咄嗟に読むことをやめ、急いで折りたたんで元の封筒へねじ込む。
見てはいけないものを見てしまった。と同時に、マサカズ君が謎のおじさんに追いかけられているこの状況と相まって、何かとても重大な局面なのではないかと、驚きすくみ上る。
「隠さねば」
目の前のガチャガチャの販売機の横に落ちている空のカプセルを広い、封筒を丸めてその中に詰め込み、隠せる場所を探す。
すぐ隠せて、後から見つけやすい目印になる場所。
街路樹が目に映った。
ここならば、もしマサカズ君が戻ってきてもすぐに渡せる。
おじさんに問い詰められても、自分は持っていないと突っぱねられる。
ここに埋めよう、何か掘るものを…と辺りを見回そうとした時、3メートルほど先に、息を切らせたおじさんがいた。
最悪の事態だ。
おじさんと遭遇した場所、手紙を託された場所で隠そうとせず、ランドセルにしまい込んで逃げていればよかった。
だが、時はすでに遅し。その手に、見るからに怪しいカプセルを持つ私。
「ぼく、マサカズ君に何か渡されたよね?」
この口ぶりからして、マサカズ君はこのおじさんに捕まりはしなかったのだろう。まずはそこにホッとしたものの、おじさんの次の標的が自分と、この封筒になったことに恐怖した。
おじさんはマサカズ君を追い回した疲れからか、汗だくでまだ息も荒い。
疲れた表情で私を見るその目が、怒っているように見え、恐怖感が倍増する。
緊張でのどが渇いた時につばを飲み込もうとするのは本当だ。
そして、そんな時に限って口の中の水分もカラカラになるもの本当だった。
心臓の鼓動が耳いっぱいに覆いかぶさり、周囲の音が全部聞こえない。
とにかく、とにかく、見ず知らずの大人から自分への視線を逸らせたい。
真っ白な頭のまま、ガチャガチャの自販機を指さす。
おじさんは「何だ欲しいのか?」と言って、躊躇なく販売機に百円玉を入れレバーを回す。
ガタガタッ…ガタン!と派手な音を立て、受け取り口から落ちてきたカプセル。
逃げてしまおうと思う間もなく、おじさんはカプセルを持って私の目の前まで来てしまった。
無言でカプセルを差し出すおじさんの圧力に、ガチャガチャを買わせてしまったことで交渉が成立し、手紙を渡さなければならないような強迫観念にかられてしまう私。
その私の心理を見透かしたかのように、おじさんがクイッと私の方へカプセルを持った手を近づける。
その威圧感から逃れたくて、私はおじさんからカプセルを受け取り、そして代わりに自分の手にあった封筒入りのカプセルを渡してしまった。
おじさんはカプセルを受け取ると中身の手紙を見て、優しく「ありがとう」とだけ言って去っていった。
そうだ、思い出した。
私はこの時、恐怖心に負け、友達を裏切った。
私は、なんということをしてしまっていたのか。
罪悪感で、胸が締め付けられる。
しかし、こんなに鮮烈で後悔を禁じ得ないような経験であるにもかかわらず、今の今まで私は全く覚えておらず、おじさんに「ガチャガチャのおもちゃをもらった」という、そぎ落としすぎた軽い記憶にすり替わっていたことが不思議でならなかった。
そして、思い出した今でさえも、このエピソード以外の記憶は思い出せず、前段階で何があったのか、この後マサカズ君がどうなったのか、この後に私は何をしたのかということも全く思い出せないままであった。
ショックのあまり立ち尽くす私の横を通り過ぎる人たちの不審な視線に押されるように、私はとぼとぼとその街路樹から駅へ向かって歩き始める。
落ち着こう。
蘇った記憶とその前後の記憶を整理しよう。
あそこまで思い出しているのだから一つ一つ順を追って状況を整理していけば何があったのかはいずれわかるはず。
そう思いながら駅へ到着、ホームへ出て電車を待つ。
そもそもマサカズ君が誰だったのか。
私はこのことを誰か親や友人や先生に話したか。
ガチャガチャの中身は何だったのだろうか。
角度を変えて脳にアプローチを続けたが、結局有益な情報は思い出せず。
かろうじて思い出したのは、あの後、向かいの交番へ通報をしようかどうか迷いに迷った挙句、断念したことくらいだ。
手紙を渡したのが自分からだということと、カプセルに買収されたという客観的な事実から、自分には通報をする資格がないとでも思ったのだろう。
単なる昔を懐かしむ小紀行が、とんでもないモヤモヤを残してしまった。
ただ幸いこの後はヤマモトとの会食だ。
彼なら何か知ってるかもしれない。
気を取り直して約束の店へ向かった。
「えー、そんなことあったんだ。初めて聞いたよ、その話」
焼き鳥をほおばりながらレモンサワーを片手に、ヤマモトが聞き取りにくい感想を述べる。
都内の居酒屋にてヤマモトと合流した私は、一目散に川口で思い出した話を彼に伝えた。
彼ならば何か知っているかもしれないと、勢い込んで話す私に、ヤマモトは驚いたように、そして興味深そうにうなずきながら、居酒屋の奥のほう見る遠い視線のまま聞いてくれた。
今までほとんど話さなかった30年前の昔話だから、一生懸命思い出そうとしてくれているのだろう。相変わらずいいやつだ。
「そうなんだよ、俺全然覚えてないのも不思議でさ。お前、覚えてない?マサカズ君のこと」
帰りの電車の中でもずっと考えていたが、彼の事ですら何も思い出せないままだ。
ヤマモトに話すことで何かきっかけになればとも思ったのだが。
「俺はりんちゃんと違ってそんなに仲良くなかったからなぁ」
から揚げにレモンをかけながら、ヤマモトは申し訳なさそうに答える。
「りんちゃん」とは私の愛称だ。本名の「凛太郎」から来ている。
中年と呼ばれる年代になってもちゃん付けで呼ぶのはもはや小学校時代から唯一連絡を取っている友人の彼くらいだ。
「マサカズ君って、あの後どうなったの?」
「え?りんちゃん、そんなことも覚えてないの?記憶喪失みたいになってんじゃん」
そうだ、マサカズ君に関することが、あのカプセル事件以外はすっぽりと抜け落ちている。
あの次の日にも学校へは行ったはずなのに、次の日に何があったか、何をしたかも覚えていないのだ。
「マサカズ君、いきなり転校しちゃったじゃん?先生が、彼は家庭の事情で遠くに引っ越すことになったからって、みんなに挨拶もなくいなくなっちゃったはずだよ」
「ホントかそれ!」
「りんちゃんのその手紙の話、急な転校にすっごい関係してそうだよね」「そうなんだけどさ、そもそも、あの手紙の内容を全部知らないんだ、俺。どんなことが書いてあったんだろ。めちゃくちゃ気になるわ」
「おじさんが手紙を探してたってエピソードがもう、映画とかドラマの話だよね」
「そうだよなぁ。事件だったとしたら、通報しなかった俺はかなりの重罪だなぁ」
自分がその手紙のありかをバラしてしまったからマサカズ君は転校してしまった。
当時の私はそう思っていたから、自分の中でのつらい思い出になって、忘れ去ろうとしていたのだろうか。
「あ、手紙の話で思い出したけど、りんちゃんマサカズ君と仲良かったから、マサカズ君から手紙が来たって言ってたよ」
「それを早く言ってよ!そんなこともあったのか、全然覚えてないぞ」
「今思い出したんだよ。なんか、りんちゃんたち仲良かったやつらも、先生も、マサカズ君のことあんまり話さないからさ、俺たちもいつの間にか話さなくなって、二、三ヵ月もしたらもう完全に忘れ去られちゃった感じだったしなぁ。触れちゃいけないこともあるのかなって思ってたよ。りんちゃんも無意識に記憶から消してたのかもね」
そうなのかもしれない。
彼の存在は今日川口を訪れるまで忘れていた。
あの街路樹や交番を見てたまたま思い出したし、深く思い起こさなければ、私がおじさんにガチャガチャをもらったという浅く短い思い出の、名前しか出てこない脇役でしかなかった。仲が良かった記憶すらないし、ましてや手紙のやり取りがあったなんて思いもしなかった。
本当に私の記憶はどうなってしまっているのか。そちらの方が気がかりになってくるくらいだ。
ただ、ヤマモトのおかげで有力な手掛かりが分かった。
持つべきものは腐れ縁の親友だ。
ありがとう。
お前のことは何があっても忘れないぞ。
家庭から解き放たれて嬉しそうに八杯目のレモンサワーを飲む横顔に深く感謝した。
月曜日。
東京での仕事を終えた私はそそくさと関西行きの新幹線へ乗り込んだ。
当初の予定より早く帰阪し、夜八時ごろに家に着いた。荷物を置くや否や、その足で自家用車に乗って、兵庫県の実家へ向かう。
実家へはだいたい一時間ほど。
高速を降りてバイパスを進む。
田舎の夜九時は静かなものだ。
何も連絡せず、スーツ姿でに急に帰省してきた息子に、うちの両親は驚いた顔はするものの、落ち着いて迎え入れてくれた。
「なんかあったん?」
特に気にしている風でもないが、念のためくらいの軽い感覚で尋ねる両親。
「ちょっと埼玉時代のアルバムとかそんなん探しにきたんやけどさ」
「えらい前のもんやなぁ、どっかにあるけどホコリまるけやで」
祖父の代に建てられた実家は築六〇年以上の古い日本家屋だ。
奥の、物置として使っている八畳の和室の電気をつける。
押し入れに積まれた段ボールの下の段「りんたろう」というマジック書きの箱を引っ張り出した。
フタをしてあった既に粘着力を失ったガムテープをペりぺりはがし、中をのぞく。
信じられないほど下手くそな習字が書きなぐってある半紙の束。
写生大会の時に学校の近くの緑地公園で描いた、なぜか電柱が主役の水彩絵画、ツバが真ん中で折られている赤白帽…。
恥ずかしくも興味深い遺物があふれるパンドラの箱の発掘を続けると、年賀状のゾーンに入る。
郵便物の類だからマサカズ君からの手紙があるとすれば、この箱で間違いはなさそうだ。
ヤマモトからの年賀状もあった。
『おもちの食べ過ぎに注意!』と書いてある。
当時はこんな一言メッセージが流行っていた。クスリと笑いながら年賀状の下をめくると白い封筒があるのを見つけた。
飾り気はないが上質な紙でできているその封筒は二枚。
そのどちらともが開封はされているものの、何度も触れられた形跡がなく、丁寧に開けられ、丁重にしまわれていた。
まぎれもなく、マサカズ君から私宛てに送られた封書だった。
本当にあったのか。
この封筒を目にしてもなお、何も思い出せないでいる自分に心底辟易しながら封筒の中身を確認する。
封筒の中身は二通とも、マサカズ君本人の書いたものであろう子供の字で、ただしっかりと端的に、無駄なことが書かれずに、謝罪と近況報告が書かれていた。
一通目には、突然引っ越してしまったことへの謝罪と、自分が川口市の家にはおらず、お母さんと一緒に遠くへ引っ越していること、そのお母さんは病院に入院していること、そして、私とはお互い連絡を取り合って、また時期が来れば私と会いたいと言ってくれている、そんな内容だった。
そして二通目はとても短く、お母さんが亡くなったことと、葬儀が終わって自分の気持ちの整理がついたらもう一度連絡するから、その時はまた会って色々話がしたいと、綴られていた。
三通目はなかった。
送られて来なかったのかもしれないし、送り先が分からなくなってしまったのかもしれない。
私自身が四年生までで、川口市から引っ越してしまったことも理由にあるかもしれない。
ただ送られてきていた二通とも、当時に仲が良かった私に対して、彼の誠意が込められて伝えられた手紙だった。
もし三通目を受け取っていたら、今の私は彼を忘れ去らず、別の関係性が築けていたのだろうか。
そして、この手紙を受けとった私は、彼に何かを伝えてあげられていただろうか。
そもそも私は彼へ返事は書いたのだろうか。
罪悪感に苛まれて、彼からの真心に、自分は背を向けていたのではないだろうか。
おそらくは何もできていない当時の自分を深く深く悔やんだ。
と同時に、また疑問が浮かび上がる。
彼はおそらく、お母さんと一緒にいたいがために、お母さんからの手紙を隠したのだと思う。
だが、隠す必要はあったのだろうか。
お母さんはあの手紙の時に既にマサカズ君のそばにはいなかった。
川口の家族に内緒で入院していたとは考えにくいし、その後の手紙でマサカズ君とお母さんは一緒に過ごしていると言っていたから、面会ができないような隔離が必要な重篤な状態でもないし、秘密にすべき状態でもなかったはずだ。
あの手紙がおじさんの手に渡ってしまったことが転校のキッカケになったのだとしたら、結果的にはマサカズ君の望みをかなえたことになったのではないだろうか。
そもそもあのおじさんが誰なのかはわからないままだ。
今わかっている事実は、あの手紙事件の後に、マサカズ君は転校してしまったということ。
手紙の内容は不明だが、お母さんからマサカズ君に対する何らかの連絡があって、それをマサカズ君は一度は隠したが、私を介しておじさんが手に渡ったことで、マサカズ君は川口から去ることになった。
だとすると、少なくとも私は彼の人生の岐路に大きな影響を与えてしまったことになる。にもかかわらず、その事実を今まで忘れ去っていた。
おそらくは自分の罪悪感から逃げるために。
彼に対する贖罪の念がとめどなくあふれてくる。
そして、願わくば、自分の行動が彼の人生に悪い影響として作用していないことを確かめたいとも思っていた。
一縷の望みとしては後の手紙で彼はお母さんと一緒に住むことができていること。
あれから三十年経っている。
彼はどこにいるのだろう。
封筒に記載してある住所を見ると、同じ埼玉県だった。
本庄市児玉町〇〇。グーグルマップで見てみると家はあった。
手掛かりはこれだけだ。ここに今彼が住んでいるかどうかはわからないが、ただ会えるのであれば会いたい。
会って、当時のことをしっかり聞いて、しっかり謝りたい。
そして記憶に刻み付けたい。二度と忘れないように。
急に行っても良いのだろうか、と思いつつも、この心境のまま平穏に過ごせる気がしない。
次の休みに私は車を走らせることにした。
一週間後、埼玉県、北部。
川口市のある南部の住宅集積地とは異なり、この辺りは自然が豊かで空が広い。元来、ドライブ好きである私は関西からの八時間にも及ぶ自動車旅をものともせず、前日の夜中に大阪を出発、適度に休憩をしながら快調に高速道路を乗り継いで、関越自動車道、本庄児玉インターを降りた。
田んぼと住宅の入り混じる県道を走り抜け、ほどなく、彼の手紙に記された住所までたどり着く。
車を降り、関西で買った菓子折りを手に門の前へ。
リフォームをしてあるのか、築年数は古そうだがキレイな佇まいだ。どうやら今も人は住んでいそうだ。
表札に名前はない。
このご時世だ、安易に個人情報を出さないのもうなずける。
表札で情報が得られなかったことでやや躊躇しながらも、意を決してチャイムを押す。
ほどなくして「…はい」と不安げなインターホンの女性の応対の声が聞こえた。
突然、見知らぬ中年男性の来訪には困惑するだろう、出てくれただけでもありがたい。
「私、ミヤマドと申します。突然お伺いしてすみません。
私、モギマサカズさんと、川口市の小学校の時に同級生だったのですが、
以前モギさんから、お手紙をいただいた時に、こちらの住所が書いてあり
まして、モギさんは今でもお住まいでしょうか?」
怪しいことを言っている自覚はある。
できるだけ丁寧に、淀みなく話すことを心がけ、緊張とともにゆっくりと話す。
「ミヤマドさん?」
と、お年寄りの優しそうな女性が出てきた。私の言葉を信じてくれたようだ。ありがたいがやや警戒心が薄すぎるのではないかと心配になる。
その女性が言うには、マサカズ君は今ここには住んでいないが、自分は彼の親戚で連絡を取ることはできらしい。
私は、実家で何十年も前にマサカズ君からもらった手紙を見返したこと、会って話がしたいということを伝えると、ありがたいことに女性はすぐに私の話を理解し、とても好意的に受け取ってくれた。
突然の来訪でもあるからと、ひとまず、彼女に私の電話番号を渡し、来る途中に見かけたファミレスで待つので、もし会えなくても連絡をもらえる嬉しいと伝え、その家を後にする。
10分ほど走り、ファミレスに入ると、席に着くなり深いため息をついた。
まずは、三十年前の住所が今のマサカズ君とつながっていたことに安堵する。
そして、私の突然の来訪に快く応対してくれたあの女性にも感謝をしなければならない。
もしかしたら、私の名前が珍しいものであったことが幸いしたのかもしれない。それであの女性は、私が詐欺の類ではないと判断してくれ、好意的に受け取ってくれたのだろうか。
ただ、マサカズくんがどう思っているかはまた別だ。
何せ私は彼を裏切って重要な手紙をおじさんに渡し、その後の彼の連絡にもまともに応じた形跡もない。
連絡が来ずに、このままということも覚悟しなければならない。
今は昼過ぎ2時。夜まで待って、それでも連絡がなければ諦めて帰ろう。
と思っていたら、
「りんちゃん?」
と、私を呼ぶ声。
中年になってもこう呼ぶ人はそうはいない。
顔をあげると、優しい笑顔を浮かべた小柄な男性が立っていた。
彼がマサカズ君なのか。
面影のようなものは全く感じられない。
30年ぶりの、半分消し去ってしまった記憶なのだから、彼への印象はほぼないと言ってもいい。
かくいう私も当時の姿からは到底想像できないような風貌になっている。
彼が私のことを覚えていたとしたら逆に違和感を覚えているかもしれないが。
「りんちゃん、久しぶりだね!って言ってももう何十年も前だし、あまり実感もないんだけれどね」
マサカズ君はそういうと私の向かいの席に座り、まじまじと私を眺める。
「久しぶりだね…突然来ちゃってごめんよ。いきなりなのに来てくれただけでも嬉しいよ、ありがとう」
彼の私を見る柔らかな視線に戸惑いつつ、挨拶と礼を述べる。
「びっくりしたし、正直ちょっと怪しいって思ったよ。どこかで小学校のころの名簿みたいなのが売られたのかなって思っててさ」
「あぁ、よくあるね。ご実家?に行ってしまったし。ごめんね、驚かせてしまって」
「名前がちょっと珍しいからさ、叔母さんも覚えてたみたいで、連絡くれた時は、全く疑ってなかったよ。それはそれで危ないんだけどね」
やはり名前か。この時ばかりは珍しい名前に感謝する。
そして覚えていたという言葉が気になった。
マサカズ君は親戚に私の名前を言っていたということなのか。
私の名前が出るとなると、もしかすると手紙の一件で、親戚を巻き込んだ騒動になったのかもしれない。
「マサカズ君、俺さ、今日は謝りたくて来たんだ。」
少し間をおいて、今日彼を訪ねた理由を話し出す私を、彼は穏やかな笑顔で黙って見守ってくれている。
「まず、なんで今のタイミングになったかってことなんだけど、俺、マサカ ズ君のこと、ついこないだまで全く覚えてなかったんだ。
マサカズ君が引っ越したあとに、俺自身も関西に引っ越しちゃってさ、その後は大学になるまでこっちには来なかったんだ。
ヤマモトってわかるかな?ものすごく給食食べてたあのヤマモトなんだけど、東京の大学に来た時に、偶然アイツと再会して、アイツとは今でも会ったりするんだけど、それ以外は埼玉のこともほとんど忘れてた。
で、一週間くらい前に仕事で東京に来ることがあって、ふと川口に行ってみたくなったんだ。蕨の駅から歩いて小学校とか歩道橋とかウロウロしてて、その時に不意に君のことを思い出した。
五十代くらいのおじさんに追いかけられて、その時、君は俺に手紙を渡した。
お母さんからの手紙。中身は読んでない。
冒頭だけ読んで、そこで止めた。
でも、その時に君に渡された手紙を、俺は追いかけてきたおじさんに渡しちゃったんだ。
その後、君は転校してしまった。
俺、まだ思い出してなくてさ。
それか、詳しいことは知らないままだったのかもしれない。
その時に何がどうなって、なんでマサカズ君が転校したのか、ヤマモトに言われるまで、俺がマサカズ君と仲良くて、転校した後に手紙をくれたことさえも覚えてなかった。
出張の後に関西戻って、実家の物置で君から来た手紙を読むまでは、
転校してここに来てたってことも分かってんかったんだ。
せっかく君が手紙をくれたのに。
お母さんが亡くなったっていう辛いこともしっかり綴ってくれたのに。
こうやって話すだけで、いくつも謝らなきゃいけないことがあるよ。
手紙を渡してしまったこと。手紙をくれたことに対して、何もしてあげられてなかったこと。そして、君のことをずっと忘れ去ってしまったこと。
申し訳ないと思っている。ごめんなさい。」
言いたかったことを一気に話してしまった。
ここまでくる道中、車の中でずっとぐるぐる何をどうやって言おうか回って迷っていた思いは、そのまま何も考えずに口をついて流れ出していた。
マサカズ君は、最後まで黙って聞いてくれた。
私が話し終えて後、どれくらいの間があっただろうか。
話し終わった後、呆然としている私に労うように笑いかけてから話してくれた。
川口市でのマサカズ君の家は、会社を経営していたお金持ちの家だった。
お母さんも家業を手伝って一生懸命働いていたが、マサカズ君が九歳のころ、無理がたたって入院が必要な病気になってしまった。
お母さんは浦和の大きな病院に入院していたが、お父さんは仕事が忙しくてお母さんの見舞いに行くこともほとんどできず、嫁ぎ先の家業を一生懸命手伝って病気になった娘が入院したのにもかかわらず、全く顧みない娘婿の態度に腹を立てた実家の父親が、娘を「空気のきれいなところで療養させる」と言って、無理やりこの本庄市へ転院させた。
もちろん大揉めし、離婚をすることになったが、家業がある川口の家は、一人息子だったマサカズ君の親権を頑として譲らず、マサカズ君はお母さんと離れ離れになってしまう。
お母さんに会いたくて仕方がなかったマサカズ君は、お母さんの病院の住所を何と自力で調べ、お母さんに手紙を書いた。
内容は他愛のないもので、元気ですか?いつか会いに行きたい、といったようなものだったが、それを読んだお母さんは、嬉しさのあまり、ついマサカズ君に返事を書いてしまった。
その手紙の返事を、川口の家族に見つかってしまい、マサカズ君はお母さんからの手紙を奪われる=つながりが奪われると思って、それを隠した。
川口の家族は、まさかマサカズ君が先に手紙を書いたとは思っていないから、お母さんがマサカズ君を呼ぶために手紙を送ってきたのだと思って、その手紙を取り上げようとしたが、マサカズ君はその手紙を渡すことを拒み、肌身離さず、学校まで持ち歩いていた。
マサカズ君と私が二人で下校している時におじさんから声をかけられた「手紙事件」は、そんな時に起こったことだった。
おじさんは、マサカズ君の家の家業の社員だった。
私からおじさんへ渡された手紙の内容を読んで、マサカズ君がお母さんに先に手紙を送っていて、この手紙はその返事であることがわかった川口の家族は、マサカズ君の気持ちと強い意志を知り、マサカズ君を本庄でお母さんと一緒に暮らさせることを決意。
急きょ本庄市に引っ越すことになった。
真相はこうだったが、マサカズ君はマサカズ君で、男の子がお母さんと暮らしたいから引っ越したという理由を話すことが恥ずかしく、また家の中のもめ事を、あまり言いふらしてはいけないという気持ちもあって、詳しいことを伝えなかったのだと言った。
その後、私も関西へ引っ越してしまったのもあり、連絡がつかなくなってしまった。
手紙にあった通り、お母さんは一緒に住み始めてから一年ほどで亡くなってしまった。
私が実家を訪ねた際に応対してくれた叔母さんが、私の名前を知っていたのは、やはり「手紙事件」で私の名前が出たことと、お母さんが亡くなった後、親代わりとしてマサカズ君を育ててくれた時に、マサカズ君が私の名前を何度も言っていたからだった。
叔母さんは、結婚はしていたが子供はおらず、マサカズ君を実の息子のように愛してくれて、マサカズ君も実の母のように思って彼女と過ごし、成人後には川口の家族から家業を継ぐような打診もあったがそれを断って、本庄市内で就職した。
今ではマサカズ君の二人のお子さんは叔母さんのことを「おばあちゃん」と呼んで度々実家を訪ねては、コミュニケーションを重ねているという。
「だから、りんちゃんは何も気にしなくていいんだよ。結果的には僕はこっちで短かったけど母親と暮らすこともできたし、叔母さんっていう素晴らしいもう一人の母もできた。
僕がずっと手紙を隠し続けて、さらに揉めていたら、僕はこっちに来ることができなかったかもしれないし。
あのタイミングでりんちゃんが手紙を渡してくれて、むしろ良かったのかもしれないよ」
気に病む私を思いやってくれて、こう付け加えてくれたマサカズ君は、涙ぐんで話を聞いている私の顔を見て「何で泣くんだよ」とさらに優しく笑った。
そしてもう一つ、私にとって衝撃の一言を放つ。
「あとさ、手紙の返事、ちゃんとくれてたよ。
母が亡くなったことを連絡した手紙の後で、こんな手紙をくれたんだ」
と言って、一枚のくたびれてボロボロの紙を見せてくれた。
『マサカズ君、連絡ありがとう。
お母さんのことはお悔やみ申し上げます。
僕は謝らないといけないと思っています。
マサカズ君のお母さんからの手紙をあのおじさんに渡したことです。
怖くて負けてしまって渡してしまったことが今でも悔しくて仕方がありま せん。
マサカズ君が転校してしまった理由はわからないけど、僕のせいなのもあると思っています。
僕のせいで転校してしまったので、また僕と会ってしまうと君はずっとそのことを思い出してしまうと思います。
それはお母さんとの手紙のことを、ずっと思い出すということなので、お母さんがいなくなってしまった君に、ずっとお母さんを思い出させてしまうと思うので、僕のことは忘れてください。
君は優しいからそんなこと言わないけど、これは僕のケジメでもあります。
だから、悲しみに負けないで頑張ってください。僕も頑張ります。』
読み終えて呆然としている私を見て、マサカズ君がまた声をかけてくれる。
「りんちゃん、すごい優しい子だったんだよ。
決して弱虫じゃないし、ちゃんと自分と向き合ってた。
手紙がボロボロなのは、何度も読み返したからなんだ。
なかなか書けることじゃないよ、小学生に」
心の澱が流れてゆくのを感じた。
小学生の私は、反省し、自分を戒め、そして何より友を想って接することができる子供だった。
拙い文章で、「会わない」などと極端な選択をしているところはいただけないのだが、そんなことよりも大切な事を、しっかり成し遂げていた自分に心の底から安堵し、喜ばしかった。
あれからマサカズ君とは、二時間ほどお互いの今までの人生の軌跡を話し、改めて連絡先を交換してその日は帰途に着いた。
高速道路のSAでの休憩中にヤマモトに電話をする。
「よかったね、すごいいい結果になった」
「そうだね、胸につかえてたものがスッとどこか行った感じだよ」
「ホント、りんちゃん思い悩むとずっと引きずるんだよ、子供のころから。
だから、手紙事件のことは知らなかったけど、マサカズ君が転校したことでずっと元気なくてさ、それで俺たちはあんまりアイツのこと話題にするの避けてたんだよ。
いっそのこと忘れてくれればいいなって。
だから今回のこと聞いて、解決できなかったらしばらく悩んじゃうだろうし、どうやって忘れさせようかって思ってたところだったのよ。だから、悩んでたこと全部結論が出て、俺にとってはそれが一番よかったわ」
持つべきものはやはり竹馬の友だ。
今も昔も、こうやってこのめんどくさい性格の私を思い遣って心を砕いていてくれている。
マサカズ君のことを忘れてしまっていたことは今も悔やまれることではあるが、忘れてしまったことで、今のヤマモトとの関係もあるのかもしれない。そう思うことにした。
時を超えた「手紙事件」で私は単なる思い出話には収まらない多くの収穫を得たと思っている。
もちろん、再び友人として交流をすることができることになったマサカズ君と、改めての大親友ヤマモトの存在の再確認。
そして、過去の自分を通した私自身をちょっと「見直せた」ということ。
不惑に達する自分に「どこが惑わずだよ」という嘲笑も、そこまで自分を卑下せずに、自信を持ってもいいんじゃないかと、少しだけ思えた。〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
