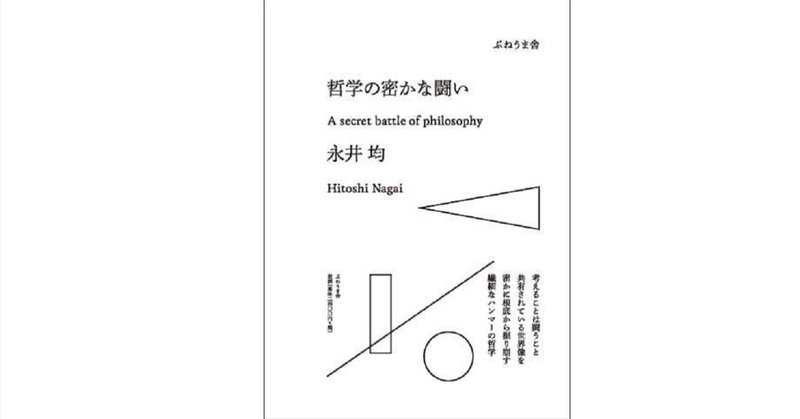
「なぜ世界は存在するのか?」という問いはどういった問いなのか?永井均『哲学の密かな闘い』を読みつつ
問いがもっているべき構造
世の中にはたくさんの謎がある。ある不幸な人はこう思うだろう。「なぜ自分だけこんな目にあうのか?」。また、ある科学者はこう思うかもしれない。「なぜこの世界はこのような物理法則に支配されているのだろうか?」。また、ある人はこう思う。「なぜ世界は存在するのだろうか?」と。
どのような問いも共通の構造をもっている。問われているあり方そのものと、それに対比される他の可能性としてのあり方を背景にもっている。たとえば、「なぜ自分だけこんな目にあうのか?」という問いは、「現実の不幸な自分」と「可能性としての幸せな自分」が対比されている。また、「なぜこの世界はこのような物理法則に支配されているのだろうか?」という問いは、「現実の種々の物理法則が成立している世界」と「可能性としての現実とは異なる別の物理法則(例えば、反重力)が成立している世界」が対比されている。このように、問いには対比される他の可能性が必要であり、もし対比される他の可能性が成り立たなければ問いとして成立しないということになる。
では、「なぜ世界は存在するのか?」という問いの場合はどうだろうか。この問いは、前者二つの問いとは異なるタイプの問いであるといえる。なぜなら、前者二つは世界の内容についての別の可能性を対比している一方で、「なぜ世界は存在するのか?」という問いは、世界の内容についての別の可能性を考慮しているわけではない。世界の内容とはまったく関係なく、そもそも世界そのものが無いということと対比されているのだ。「何かの無」ではなく、「すべての無」なのである。
だが、「すべての無」ということをどのようにイメージするのだろうか?真っ暗なテレビ画面のようなイメージだろうか?だが、真っ暗だとしても、真っ暗な画面やスクリーンのような、「何か」が存在するに違いない。あるいは、少なくとも「暗闇」や「真っ黒い空間」はあるだろう。「すべての無」ということは画面やスクリーンはもちろんだが、いわゆる「暗闇」をイメージすることとは異なることなのだ。では、いったいどういうことなのだろうか?これがわからなければ「なぜ世界は存在するのか?」が何を問うているのかもわからなくってしまう危険性がある。「なぜ世界は存在するのか?」という問いに対比される「すべての無」という可能性が、成立しえないのであれば、「なぜ世界は存在するのか?」という問いは、実は問いとしてナンセンスではないか?
「すべての無」とはどういうことか?
いや、そもそもの問題は、視覚的なイメージとして、私たちの思考を理解することにあるのかもしれない。私たちは、純粋な数学や正百万角形を「像」としてイメージできないながらも理解はできる。「すべての無」は、これら純粋な数学や正百万角形と同様に、像的なイメージを結べない抽象的なものと見なす必要があるのかもしれない。例えば、素粒子が4つだけある世界を想像してみよう。その素粒子が一つずつ消滅していく過程を像として想像することは可能である。そして、4つ目まで消滅させるのである。3つ目までは首尾よく消滅させられるのに、4つ目の消滅だけ考えることができない理由は一見してなさそうである。4つ目の素粒子が消滅した時点と、「すべての無」は何が異なるのだろうか。前者にはまだ背景や空間のようなものが残るのだろうか。もともと素粒子が4つだけの世界なのだから、「4つ素粒子+背景」とは想定されていない。したがって、何ら問題ないように思える。ただやはり、不思議なことに4つ目の「無化」の操作を像としてイメージすることはできない。4つ、3つ、2つ、1つまでは像としてイメージできるものの、0個の状態をイメージすることができない。
こうなると本note冒頭の整理をやり直さざるをえない。私は冒頭に三つの問いの例をあげ、前者二つを同種のもの、最後一つを特殊なものと位置付けた。前者二つは、世界の別様の在り方と対比される問いであり、最後一つは、世界の内容とは関係のない「すべての無」との対比だと区別した。だが、もしかするとこの区分は適切ではないのかもしれない。すべて同じ種類の問いであるとも見做せそうである。なぜなら、1~4個の素粒子が存在する世界と、素粒子が0個になった世界とでは、像としてのイメージの有無という差異はあっても、それ以外の点では違いを見出せないからである。対比される他の可能性が考えられるものであれば、正当な問いであるといえる。
ここまで「すべての無」の二つの解釈の間を揺れ動いてきた。一つ目は、ナンセンスなものとみなす立場。二つ目は、イメージこそできないが理解できるものとみなす立場である。後者が正しければ、「なぜ世界は存在するのか?」という問いは正当な問いでありえるが、前者が正しければ不当な問いである、といえる。
ライプニッツ的な神の世界創造
「なぜ世界は存在するのか?」という問いは、伝統的な哲学の難問の一つである。ここでは伝統的な表象として、ライプニッツが定式化した神の世界創造の思想を導入する。これは、本noteで考えてきた「可能性」を使った考え方である。
ライプニッツは、この世界がなぜ無ではなく存在するのか、という問いに対して、まず「神」が存在し、その「神」が考え得るあらゆるバリエーションの膨大な数の可能性の中から一つ選んで現実化したと考えた。(なお、その中には「何も存在しない」世界の可能性も含まれると主張した代表的な人物は、ピーター・ヴァン・インワーゲンという哲学者である。)
ライプニッツ的な神は、可能世界に「現実性」を与えて現実世界に昇格させることができる。ただ、「現実性」を付与するといっても、世界の内容に対してはいっさい関わらない。神が世界の内部に何かを加えるわけではない。いわば、世界の内部構造を一切変えずに現実世界に仕立て上げる。ゆえに私たちにその違いを識別する術はない。私たちは内部構造の変化のみを変化として気づくことができるからだ。
なお、現在の分析哲学でも、このライプニッツのような「諸可能世界から選ばれた現実世界」という図式は変わっていないようである(選ばれる理由が「神の意志」である点を除いて)。ただ、どういった理由で世界が選ばれるか(何がselectorであるか)は本noteでの関心ごとではない。

これまでの「すべての無」に対する揺れ動きは、上記の図でいう右端の「可能世界 無」を「すべての無」として認めるかにかかっている。「可能世界 無」は、さきほど言及した、「素粒子を一つずつ消していく世界」と同義である。このような、世界の内容物がまったくない「可能世界 無」は「世界はなぜ存在するのか?」という問いに対比されるべき「すべての無」なのか。あるいは、内容物以外の何かを含んでいるような「不純な無」なのだろうか。
永井均の「デカルト的な神」
ここで永井均氏の文章を引き、彼の思考を追ってみたい。永井はライプニッツ的な神すら創造する上位の「デカルト的な神」を措定し、以下のように論述している。
存在が内容を規定する述語ではない以上、世界がそもそも存在しない可能性はある。つまり、世界もまた、究極的には(なくてもよいのに)なぜか在る、という性格を持つ。しかしそれは、単なる可能性にも同じようにある内容的規定性にプラスされる現実性、といったものではなく、可能性を含めた全体がなぜか在るという現実性である。だから、ここで神は、諸可能性の中から一つを選択して現実化するライプニッツ的な神ではなく、諸可能性の全体を初めて創造するデカルト的な神でなければならない。この創造は、創造の後にも、他の諸可能性と対比された一つの可能性の現実化として、世界の内容的規定性の内部に組み込まれることがない。だから、創造という行為において神が(何をしたのかのみならず)何を創造したのか(どういう内容を現実化したのか)さえ、われわれには決して捉えられない。われわれは、ひたすらその内部にいるしかないのだ。
この論述は吟味する点がいくつもある。順番に進めよう。
まず、世界は「究極的にはなくてもよいのになぜかある」という性格があり、これは「可能世界から一つ選択されて現実世界が作られる」という世界創造とは異なる事態なのだという。世界の「内容」についてのあらゆる諸可能性ではなく、世界の「有無」についての可能性を開く、と読める。そして、世界が存在しているということは、その世界は可能世界すべてを含みこみ、可能世界から一つ選択する主体としてのライプニッツ的な神をも含みこんで創造するような、根源的な神を措定せざるを得ない、というわけだ。これを「デカルト的な神」と呼んでいるのである。
デカルト的な神とは、世界を創造したり無化する神のことである。これはデカルトの思考実験を形而上学風に再解釈する文脈で登場する。
『省察』のデカルトは、欺く神である悪霊と対抗した。疑う余地のない確実な知識の根拠を求める彼の動機からは当然のことである。しかし、そのことは彼の議論に認識論的な制限を与えた。もしデカルトの動機が、知っていることではなく在ること確保しようとする形而上学的なそれであって、彼が神と、つまり欺く力ではなく現実に創造したり無化したりする力を持つ神と、対抗していたなら、議論はどのように展開していたであろうか。こうではないだろうか。――かりに無化する神がいま現に(あるいはもともと)世界全体を無化していて、この世界は実は存在しないとしても、なぜか知らないが、現にこのように、少なくとも〈何か〉が、少なくとも〈これ〉が、在ってしまっている以上、彼はすべてを無化することに実は成功していない、と結論せざるをえない。「無くするならば力の限り無くするがよい。しかし、なぜだか現にこのように在る以上、彼は世界を何ものでもないもの(=無)にすることはできていないのだ」。
デカルト的な神は世界を創造したり無くしたりできる。一方、懐疑の果てにデカルトは何であれ何かが存在していることを見出す。つまり、神は無化に実は成功していない。
デカルトが懐疑の果てに〈これ〉を発見したように、この世界は無ではない。このことは絶対に揺らがない。まさに世界は開かれて存在し、無ではない現実がある以上、何者かがこの世界を創造したとみなせる。その創造主をデカルト的な神と呼んでいるのである。ここでは、このデカルト的な神は諸可能性から一つ選択して現実世界を作り出すライプニッツ的な世界創造とは異なり、より上位の創造をしたということになる。ライプニッツ的なあらゆる可能世界は、ある意味では極大の存在である〈これ〉の中で創造されるものに過ぎないからだ。すべての可能世界は〈これ〉の内部の素材をもとにした、水準の低い世界に過ぎない。

永井は明確に「可能世界 無」と「すべての無」を区別していることがわかる。では、この両者は何が違うのか。言ってみれば、「可能世界 無」は「何かの無さ」なのである。素粒子を一つずつ消していく考え方は、世界の内容に対する操作である。一方で「すべての無」は世界の内容に関わらない。在るか無いかしかない。永井は別の著書で内容の側を「本質」、在るか無いかの側を「実存」と言い換えている。
「~である」こと(本質)の水準での対比が尽きれば、残るのは「~がある」こと(実存)の水準の対比である。問いは「なぜおよそ無ではなく、ともあれこれがあるのか」という形をとるだろう(「ともあれ」はそれが何であれ」の意味である)。すなわち、実存驚愕。
ありえる反論と応答
いやいや、デカルト的な神など考えなくても、ライプニッツ的な神が、気まぐれに偶然選んだ世界がこの世界なのである、と言ってもよいのではないか?という疑問が思い浮かぶ。そして、ライプニッツ的な神だけで世界創造は成されるとすれば、「なぜ世界は存在するのか?」という問いに対比される無は「可能世界 無」のことなのではないか?また、仮にデカルト的な神のような「ある/なし」のデジタルな可能性のみを開く神がいたとしても、ライプニッツ的な神との違いは何なのか。単に上位のライプニッツ的な神であると言ってはいけないのか?いったい何がそこまで特殊なのだろうか?
1つ目の疑問をまず解消しよう。少なくとも「すべての無」は「可能世界 無」と単純に同一視することはできない。「可能世界 無」は、あらゆる可能世界A,B,C・・・と並列に対比されるものである。そういう意味では「可能世界 無」は水準としては、あらゆる可能世界A,B,C・・・と同質の世界とみなしてよい。しかし、「すべての無」が対比されるのは「在ること」そのもののみである。同じ「可能性」であっても、「すべての無」が対比されるものにバリエーションはない。可能性は2つしか開かれないのである。「ある/なし」のみの可能性を開くのである。
なぜこのような差異があるのか。「可能世界 無」があくまで世界の内容の欠如であり、内容を含む「何性」の否定形である一方、「すべての無」は部分/全体の概念を適用できない特殊な意味をもつ「これ性」の否定形だからだ。比喩的にいえば、前者は「What」の疑問文の答えが多様な内容を含む一方で、後者は「Be動詞」の疑問文の答えが、YesかNoしかないことに似ている。
2つ目の疑問を解消しよう。デカルト的な神は、結局ライプニッツ的な神と同一視されるのではないか?という問いだ。では試みにデカルト的な神をライプニッツ的な神として理解してみよう。そこで整合性がとれない事態になれば、これらの2つの神を同じものとみなすことはできない、ということになる。
まず、これまで述べてきたデカルト的な神の究極的な創造行為を、諸可能世界から一つ現実世界を選ぶようなライプニッツ的な神のより低位な創造行為であると解釈してみよう。こう考える場合、デカルト的な神は「すべての無」の可能性を想像できなければならない。だが、これは不都合がある。「すべての無」の可能性はデカルト的な神自身の無の可能性でもあるからだ。「すべての無」可能性を選べば自分自身すら存在しないことになるため、まさにこれから創造しようとしているデカルト的な神がまさに存在している以上、矛盾してしまう。むしろ「すべての無」の可能性は常にこのデカルト的な神の外側に存在する可能性として位置づけなければならない。
すると、デカルト的な神より上位の神――すなわち、「すべての無」の可能性と、デカルト的な神が存在する可能性のうち、デカルト的な神が存在するようにした神を想定できる。もちろん、より上位の神自身もデカルト的な神と同様の事態に陥る。
この無限後退は、結局、デカルト的な神がライプニッツ的な神に降格され続けることを意味する。ライプニッツ的な神が自身の存在根拠を知らず、より上位の神を要請しなければなかったように、降格したデカルト的な神もまた、より上位の神が必要になる。神ですらなぜ自分が存在するのか、何者によって存在させられたのか、その根拠はわからない。ライプニッツ的な神はデカルト的な神によってその根拠が与えられるが、そのデカルト的な神がさらに自身が存在する根拠を求めてしまえば、結局のところそれは、第二のライプニッツ的な神の水準におとしめられ、より上位の神が必要になる平凡な存在者になってしまう。だから、最終的には自身の存在根拠を求めない(求められない)種の究極的な創造を行なう神が必要なのである。
とどのつまり、永井が言うデカルト的な神とは、降格運動の無限後退の先に常に現れ続けなければならない、究極的な創造を行なう神のことを指しているのである。
〈神〉と「神」
このように、「神」が世界を作ったとしても、その作った「神」自身はなぜ自分が存在するのかわからない。このわからなさは、「いつかわかる」「科学が進歩すればわかる」というものではなく、構造上、答えを導くことが不可能だということだ。私たちは「創造」の根拠を、世界内部での何者かの創造として理解せざるを得ない以上、世界そのものの創造を理解することはできない。「何かの無」から「何かの有」への転換は理解可能であるが、「すべての無」から「すべての有」への転換は私たちの理解を超えるという意味で、特殊な言語だといえる。
以下の論述を見てみよう。
たとえば宇宙物理学者たちが神の存在を推定するにいたったとしよう。宇宙の現状を最もうまく説明するには伝統的に「神」と呼ばれてきた宇宙の創造者が実在すると考えざるをえないことがわかった、と。そのことで神の存在は証明されるだろうか。意外に思われるかもしれないが、されないのだ。
(中略)彼はこう呟くに違いない。「私は森羅万象の存在理由を知っている。しかし、この私はいったい何なのだ?私自身はなぜ存在するのか?」と。彼は、自分の存在意味をより深い〈神〉に問わざるをえない。(中略)しかし、そのような〈神〉が存在するかしないか、われわれが知りうる可能性はない。もし知りえたなら、それはふたたび宇宙物理学上の「神」と同じ身分に落ちるからである。
だから、そんなより深い〈神〉などは存在しないのだ、とすると、存在している「神」を含む世界全体の存在意味はやはりわからないことになって、「神」を含む世界全体の存在はもはやいかなる説明もされないむき出しの神秘と化す。むき出しの神秘とは、それ自体が〈神〉のごときものだということでもある。その場合、われわれに理解可能な「神」は、すべてその内部に存在するにすぎないことになる。つまり、実は神ではないことに。
「神が存在する/しないことの意味」255-256頁
世界が「神」を含んで存在して、それを創造した上位の存在者を〈神〉と呼ぶとき、その〈神〉は自身の存在意味を知らない「神」の地位に転落する。すると、また別の〈神〉を立てなければならず、またその〈神〉も私たちが知りえるものであれば「神」の地位に転落する…。だから、〈神〉などいないのだといったところで今度は当初から存在するこの「神」を含んだ世界が説明できないものになる。世界が在る以上、その世界の創造の仕組みをわれわれは理解できない。理解できてしまっては、この世界の内部に存在する内容に対する創造になってしまう。すべての問題は、私たちがこういったモデルでしか、理由や意味や根拠、という概念を理解できないという点にある。
「むき出しの神秘」とは「偶然」の別名である。「偶然」といっても、複数の可能世界からランダムで一つ選ばれた、という意味ではない。「根拠がない」という意味である。
「ある/なし」の可能性、つまり神が自身の無の可能性を想定できるのであれば、より上位の神が必要になる。そして、それは無限後退する。現に世界が存在する以上、無限後退し続ける先で登場する神が必要なのであり、それは語りえない〈神〉なのだ。
※参考文献
・永井均(2013)『哲学の密かな闘い』ぷねうま舎
・永井均(2016)『存在と時間 哲学探究Ⅰ』文藝春秋
・伊佐敷隆弘(2015)「なぜ無ではなく何かが存在するのか」研究紀要. 一般教育・外国語・保健体育 = Research bulletin. Liberal arts / 日本大学経済学部 編 (77), 181-200 日本大学経済学部
https://www.eco.nihon-u.ac.jp/about/magazine/kiyo/pdf/77/77-14.pdf
・丸山栄治(2014)「「根本の問い」と形而上学的ニヒリズム : 無は可能世界のひとつか?」愛知 : φιλοσοφια ,26:112-126 神戸大学哲学懇話会https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81010331/81010331.pdf
・丸山栄治(2020)「まったく何もないという可能性とその語法」
https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/D1007830/D1007830.pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
