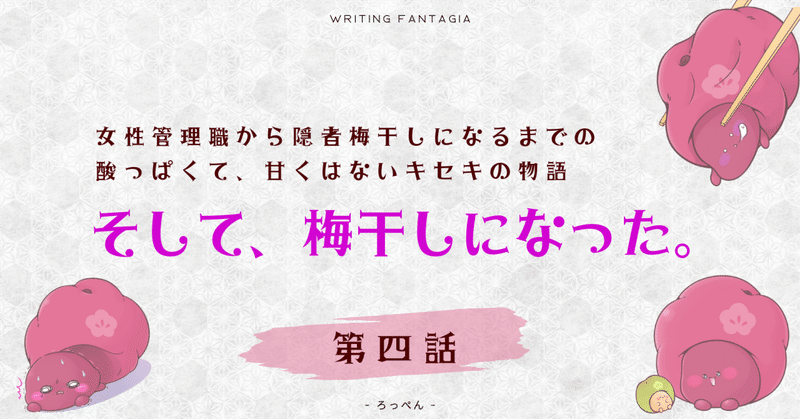
第四話 一時停止ボタン
自分の中に、何か聞かねばならぬ声がある。
でも、どうしたらその「声なき声」を聞けるのか、わからないままだった。
それまでずっと正しいと信じてきた価値観。
今の仕事。
旦那さんと娘の前で泣き崩れたその日、ずっと心のどこかで、ほころびを感じていたのに、手放したくても、手放せる自分じゃないことに深い悲しみを感じていたことに気づく。しかも、それは娘が生まれるずっと前から感じつづけていた悲しみだったはずなのに。
ずっとなかったことにし続けていたのは、一体誰だっただろう。今のままじゃ、嫌だって思うのに、どこにも飛び出せない自分であることが苦しくて、どうしようもなく悲しかったのは、誰だっただろう。
「女性でもキャリアアップできる」
「能力、成果で評価される」
「海外と仕事ができる」
そんな夢と希望を抱いて、大企業にえい!っと転職したのは27歳のこと。この会社で勤め上げるのだと意気込んで、描いたキャリアプランをひとつひとつ叶えて、管理職にまでなっていた。
けれども、肩書きが上がれば、稼ぎが増えれば、自信がつくかと思いけや、むしろ、その危うさに自信を失うことの方が多かった。
周りを見渡せば、私と同じ肩書きを持ちながら、もっとパワフルに仕事をこなす先人たちがいくらでもいる。仕事で成果が出せなければ、人より評価されなければ、私の存在そのものが危ぶまれるのではと不安でたまらなくなる。
ひとたび異動すれば別世界。それまでの自分の知識も経験もまったく通用しない。勝手のわからない世界に放り込まれた途端に「経験」という足場がぐらつき、その不確さに心が揺らぐ。
描いてきたキャリアの望みは叶っているはずだった。けれども、何かを得れば得るほど「心の渇き」は潤うどころか、果てのない不安の闇に飲み込まれ、経験という足場さえも底なし沼のように沈んでいくような気がした。どうしたらこの沼から這い出し、闇の中に光を見出せるというのか。
何かが違う・・・
泥沼のラットレースのような日々に違和感を感じながらも、自分では抜ける勇気も覚悟も持てずにいた私に
ビー!!

と高らかに「一時停止ボタン」を押してくれたのが娘だったのかもしれない。
おひさまに当てた、ぬくぬく布団のような旦那さんをゲットし「電撃・味噌汁婚」じゃなくて「でき婚」だったんじゃないのか?と疑われるほどの速さで、私たちは娘を授かった。
「モタモタするな。早くしろ」と娘が空から蹴飛ばしたんじゃないだろうかとおもったが、娘はそんな胎内記憶は持っていないという。
けれども、子を宿したという喜びとは裏腹に「できればもう妊娠したくない・・・」そう言いたくなるくらい、ひどいつわりと発熱がつづいた。会社のデスクにはいつも氷水を常備し、冷えピタをおでこに貼りながら仕事を続け、自分だって、周囲だって「休んだら?」って言いたかったはずだ。
だけど、私はどうしても離れることができずにいた。そこに自分の居場所があると信じたかったし、手放したくなかったからだ。
そんな諦めの悪い私を突き放すかのように、医師から「切迫流産」という診断が下される。無期限の自宅での安静指示。その後は会社にまともに行けない日々が続いたのだった。
当たり前のことだが、会社という組織は、私が不在でも仕事やプロジェクトは進んでいく。 私の時間は、ぽっかりと空いたというのに、私の業務の穴なんて、まるでなかったかのようになめらかに埋まっていく。人が抜けようが、入れ替わろうが、会社という巨体は動き続ける。そんなことは、管理職になる前から、妊娠する前からわかっていたはずじゃないか。
だけど、少しずつ存在感を増していくお腹と反比例するように、私は会社での存在感をもっぱら薄めることに専念しつづけ、会社という組織における「わたし」というものが、なんて不確かで曖昧なものなのか。わかっていたはずだけど、1ミリもわかろうとしていなかった残酷な事実を、真正面から突きつけられたのだった。
何のために働くのか。
私が存在している意味って、何?
自分の確からしさと拠り所を、必死に仕事や職場に求めていた私は、かつてないほど、とりとめのない「虚さ」に包まれていた。
そんな中「子育てと仕事の両立」社内研修の案内が届く。そこには子育てをしながら、キャリアアップを続け、バリバリと活躍し続ける女性たちの姿が映し出されていた。
会社は、管理職女性たるもの、いや、この会社で働くすべての人に、こんな働き方こそが、最高に理想的なのだと伝えたいのか?
いや、会社にとってはそうかもしれないけれど、 私たち従業員ひとりひとりにとって、本当にこの生き方、働き方が幸せだといえるのだろうか・・・
少し前まで、自分だってこんな管理職を目指していたのではなかったか。けれども自分でも驚くほど、その映像を無表情、無感動に眺めているわたしがいた。そこで映し出された日常が、私とは関係ない世界のように通り過ぎていく。
結局、この研修は、私にとって子育てと仕事の両立の不安を取り除くどころか、他人事のようなストーリーに自分を重ね合わせることができぬまま、違和感と疑問、不安ばかりが渦巻いていった。母となった自分が今後どうしていくのか「向こうの世界」のことは少しもわからずじまいだった。
けれども、その後も在宅勤務が続き、後ろめたい思いをしながら会社にただ「属して」いた私は、正式に産休に突入して「これで、正真正銘休める」と、心の底から安堵したのだった。
仕事のことだけに脇目も振らず奔走していた目が回るような日々からも、働く意義や目的、自分の存在意義に対する不安からも、ほんの少し距離を置くことができる。そして、また戻ってくることもできる。
世間からも会社からも認められた、公式な一時停止ボタンに心から感謝し、私はしばし、不安から目を背けるように、母する喜びだけに専念していた。
そんな私に、向き合うべきものと向き合うことを促してくれたのは、かつて母親に宛てた手紙だったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
