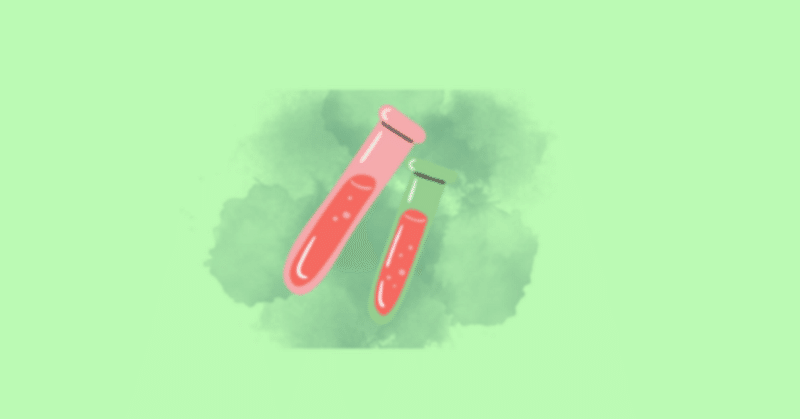
近未来SF連載小説「アフロディシアクム(惚れ薬)」No.4 朋美の事情(2)
Previously, in No.1-3 (月1更新で全12回の予定):
* * *
カムリ(ウェールズ)共和国の首都スウォンジーに住む日本人朋美が、アセクシュアリティ治療の治験プログラム、通称「アフロディシアクム(惚れ薬)プロジェクト」に2053年の4月にエンロールして既に3か月が経とうとしていた。
治験といっても大げさなものではなく、月に1回のメッセンジャーRNAの筋肉注射、週に1回の進捗サーベイへの回答、そしてガーディアン(治験保護人)として登録された人物の要求に応じて面談をすることくらいで、日々、通常の日常生活を続けていた。
治験対象に選ばれたのは、朋美がヘルスケア・ワーカーの看護師であることや監視役のガーディアンも同僚の看護師であることが有利に働いたと思われたが、朋美は自分が申請に書いた治験希望のエッセイがよかったのではと思っていた。
朋美は志望の動機に、看護師としてのこんな経験を書いた。
看護師として、病院に運び込まれてそして入院するティーンの自殺未遂のケースを毎年見てきた。自殺の動機はいろいろあったが、「失恋」という動機があることが自分には理解ができなかった。フラれたら他の人を探せばいいじゃない、そんなことで自分の命を絶とうとするなんて考えられない。そう思っていた。
男女の関係はあくまで社会的なもので、「恋愛感情」というのはそうした社会的な関係の上のケーキのアイシングみたいな飾り付けにすぎないと思っていた。男性の性欲や女性の母性みたいに人間の再生産の仕組みを推し進める原動力みたいに本能的な強いものではなくて、文明が発達していろんな社会的な儀礼が決まっていく中で、「恋愛」は男女を組み合わせる駆け引きの仕組みくらいに思っていた。
3年前のある日、キャリルという16歳の女の子が自殺から一命をとりとめて入院してきた。
一命はとりとめたが、もしかしたら魂のほうは手遅れでどこかへ去ってしまったかのように、当初は無表情、一言も言葉を話さなかった。でも、一週間、三週間、3か月と経つうちに、少しづつ朋美とも会話を交わせるようになっていった。
キャリルが聞く。「トモミー、あなた人を好きになったことある?」
「はいはい、私もう若くないから、何度もありますよ」と朋美は答えた。
「頭の中が彼のことばかりになって、寝ても起きても、彼のことを思っている。彼の前では自分が無力な存在になって、彼にちょっとでも否定されると、どん底に突き落とされた気持ちになる。絶望の底。死んだほうがいいくらい辛い。なんでこんな仕組みを神様は作られたんでしょうなんて思ったこと無い?」
「そうね、若い頃はあったかもね。でも、10代が終わって20代になってそして30代。経験を積むうちに免疫がついてくるものよ。あなたもこれで前より強くなれたと思うわよ」
そんな会話をした。
嘘をついてしまったと思った。
自分にはそんな強い恋愛感情を経験したことがない。
元々、文学や映画などの創作を読むことが好きだったので、いろいろ恋愛ものをみてみた。恋愛ってとても素晴らしく人生を昂揚させるものみたいだけれど、人を迷わせとんでもない悲劇を引き起こしたり、人を死に至らせる怖い病気のようでもある。
そんな感情を、一時的であれ、きちんと管理されたもとで体感してみることは、自分のヘルスケア・ワーカーとしての使命の実行にも有意義だと思う、そんなエッセイを書いた。
さらに、プログラムの条件となっているセラピスト的なモニタリングのガーディアン役についても、同僚の看護師が同意していることも付け加えていた。
* * *
「トモミー、この人どうかしら」同僚の看護師でもある友人のカタルーニャ人のノエリアが画面をシェアしながらきく。
20世紀の米国で発祥のサービス、ティンダーのウェールズ共和国のメンバーがスピンオフして創業した、ウェールズ語の出会いサイト「CWTCH (クッチ)」の検索結果だった。
この子音ばかりでウェールズ人以外は発音に苦しむ CWTCHだが、ウェールズ語で、「ハグする」という出会いサイトの名前としてごくわかりやすい意味だけでなく、「隠れ家を提供する」という深い意味があるという。性欲ぎらぎらの出会いだけでなく、心安らぐ二人だけの隠れ家をというような意味らしい。
更に、ラテンのステレオタイプを自ら表現しているようなノエリアは、毎週のように古今東西のありとあらゆるロマンチックな小説や詩のセリフをチャットでおくりつけてくる。
治療による朋美の脳のドーパミン分泌の増加がごく自然に彼女の恋愛感情を呼び起こすことを、半分、興味津々で煽りに煽っているのと、やはりヘルスケア・ワーカーとして身についた冷静な患者へのケアの気持を持って細かく丁寧にモニターしていた。担当医師がカタルーニャ人でもあることから、定型のモニタリングレビューの他にも、個人的にメールでカタルーニャ語で詳細な観察日記も医師に送っていた。
そんな恋愛への煽りのひとつ。
「トモミー、30年くらい前に書かれた日本の無名作家の小説なんだけどね、メキシコでアセクシュアルな彼女に片思いする優しいストーカーの話でね、その一目ぼれするところの描写がけっこうよくて私なんかには胸キュンとくるのよ。私は自動翻訳のをカタルーニャ語版を読んだんだけど、オリジナルはあなたの母国語の日本語だから、それをここにコピペしておくわね」
すると、その瞬間、その女性の周りの映像がぼやけてみえる。
急に視野が縮んで、周りが霞んでいく。
目を擦る。
ぼやっと霧のように外郭がぼけた視野の真ん中に、はにかみながら踊ろうとしているその女性の姿が、はっきりと見えている。
すると、今度は画像がスローモーションに画像処理されていく。映画のワンシーンみたいに。
網膜にくっきりと刻み込まれる映像。
でも、なぜか、だんだんと腑に落ちてくる。
これは「道を歩いててひと目見て惚れた」やつに違いない。
そんな妙な悟りがシンイチの頭の中を駆け巡って、染み渡っていく。思い込みが加速して行って、一足飛びに結論にたどり着く。
探し求めていた。
やっと会えた。
自分は今、この姿を自分の両眼の中に納めるために、今生を与えられこれまで生きてきたと、そう思う。
大袈裟な結論。
でもなぜか、しっかりとそれが腑に落ちていく。
* * *
ひとつ、問題というか、奇妙なことが起こりつつあった。
それは、朋美本人も、データを監視している医師リュイスにも薄々と違和感として感じられていた。
朋美には、自分の中に抑制された感情を代弁するもう一つの人格、彼女が悪美、Evil Beautyと呼ぶ人格が密かに存在していたのだが、それが以前より強い主張をするようになったというか、前よりも頻繁に朋美の日々に口を挟むようになってきた。
と言っても、別にそれで朋美が外にその人格が吐き出す毒をばらまくわけではなく、あくまでも朋美の頭のなかをかきまわしていくだけであったが。以前は、それがストレス発散のすかっとする瞬間であったのが、最近、その毒というか強い批判がちょっと気になるようになってきていた。それが治療の副作用なのかはわからなかったし、人に内緒にしているその人格については黙っておこうと思っていた。
医師リュイスも、いくつかのレポートで、隠された人格が活発化するかもしれないという予兆のようなものを感じ始めていた。ドーパミンの活性化が抑圧された人格も活性化するのか。EU内で実施されている治験のいくつかでは、治験者がこれまでなかったようにアグレッシブに意見を外に発するようになったケースも報告されていた。
* * *
著名な未来学者のペドロ・マルチネスは、「2040年代の理想に浮かれた熱狂の後には、醒めた頭に二日酔いの頭痛が襲ってくるに違いない」と、新たな独立国家の将来に警告を鳴らしていたことで有名だが、2050年代にはいって、彼の関心はあることに向かっていた。
それは、国家の在り方と民族固有の言語の役割についてだった。
マルチネスはその年、気候が温暖な西アジアの南コーカサス地方のEU加盟国ジョージアで執筆生活を送っていた。執筆の合間に、初めて訪れたこのジョージアという国の歴史について改めて情報を拾い集めてみて、強く印象に残ったことがあった。
人もまばらなトビリシの歴史博物館の、古代から中世の部分をみて思う。
「紀元前から独自性のある文化を守り続けている。2000年以上もの間、ローマ帝国やら、ビザンチン帝国やらムスリムやらペルシャやらオスマントルコやらロシアやらの侵略にさらされても基本的に同化されないで国家として在り続けている」
「国民の大多数が、少なくともここ首都トビリシに住む人たちは、あたりまえのように自分がジョージア人だと思っている。古代から続く独特な文法のジョージア語をしゃべり、独自の33つの文字を読み書き、独自の埋めた壺で発酵させる方法でワインを作ったりして生活している」
「やはり、独自性の保持は、侵略があっても、一方で柔軟に新しいものを取り入れながらも、頑なに自らの独自のもの、おそらくそれは自らの言語というものを必死に守ったからじゃないだろうか?」
「たしか日本という国も、占領は2つ前の世界大戦の第二次大戦の後の米国による10年くらいだけだが、いろいろな外部の巨大な文明からの影響にさらされたが、柔軟に新しいものを取り込みながら独自の言語と文化を保ってきた例だ。案外、空気のように自然に国民に定着している「母国語」というのが文化を軸として独立する国家の在り方のベースとなる軸なのではないだろうか」
そう自問していた。
「ちょっと頭を整理して、来月のロヴァニエミ会議で話してみるかな」
ロヴァニエミ会議とは、20世紀にスイスのダボスで有識者や各界リーダーが集まっていろいろな議論をしていたのがあまりにも拡大してしまったため2035年頃から密かにオーロラの見えるフィンランドの街で開催されている会議であり、そこでは世界の在り方が議論され、とくに参加者の大多数をなすEU加盟国の在り方について議論されるだけでなく、時に、秘密裏に、将来の道筋についてリーダー間での対外非の合意がなされる場所であった。
マルチネスが参加した前回の会議では、EU内で2050年にはいって矢継ぎ早に独立していった、カタルーニャ、バスク、ウェールズの三国について独立後の歩みがレビューされていた。
「やはり、歴史的にルーツであり過去のある時期に母語だったとは言えその後の歴史で伝統芸能のような位置づけになったウェールズ語やバスク語のような言語と、それなりに生活で使われ続けてきた言語では、再母国語化運動の浸透に大きな差があるな」とマルチネスは思う。
各国は再母国語化の政策を推し進めているが、「伝統芸能保存」の域をでていないとマルチネスは思う。唯一、スペイン語とフランス語の系統であるカタルーニャ語だけが、再母国語化に現実的なのではないかとも思っていた。
ロヴァニエミ会議を構成する各国の政治リーダーの重鎮たちの中で、特にEUの保守派の政治家は、母国語リバイバルがうまくいっていないところは独立自体がどうせとん挫するから、EU加盟の大国への再統合化は避けられないと意見していた。EUという、PCでいえばOSの仕組みを完成させた後は、つまり軍備、金融、財政などの基本操作を共通化した後は、個性のある国民国家で「国」を名乗ってオリンピック参加したりするのは国民の自尊心昂揚のためにそのOSの中で動くアプリみたいに自然な仕組みだと思っていたが、どこかでその国家の在り方の最低必要条件に線を引かないといけないとも考えていた。
* * *
2053年9月のある日。朋美とノエリアのところにEメールが届く。
11月にエウスカディ(バスク)共和国首都ドノスティアで開催される脳内治療学会へ、治験者代表とそのガーディアン代表として招待するという内容だった。
さっそく朋美は病院内でノエリアを探す。小児棟に彼女を見つける。
ノエリアは大げさに両手を挙げて笑顔で言う。
「行きましょうよ。バスクってねピンチョスが美味しいのよ。とくにドノスティアのは最高。このリュイスっていう発明者の医者、私と同じカタルーニャのちょっとした有名人なのよ、同郷のよしみで私が仲良くなってそれで朋美に紹介しちゃおうかしら」
(No.5へ続く)
この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとはこれっぽっちも関係ありません。医学的な知識はまったくでたらめで、SFなので政治的な内容はまったくの妄想で幾ばくかの根拠もありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
