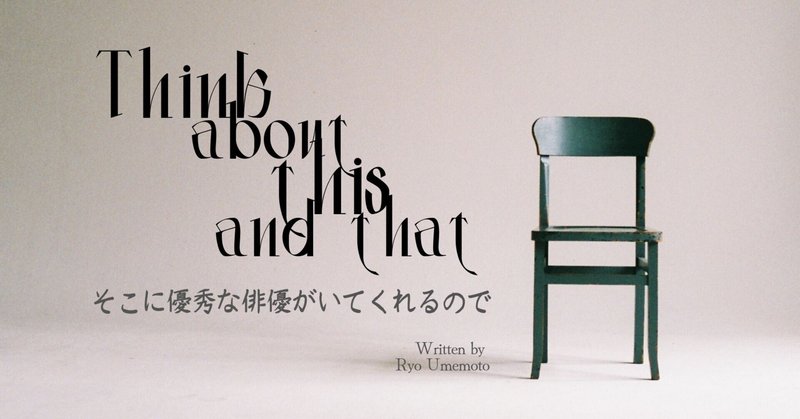
作家にもタイプがあるらしい。あなたは?
目安:約2700文字
ちょっと前に、隙間時間に何かでちらっと見かけて
「へぇ」
とは思ったものの
その時は次があったからそこで一旦打ち切って
けど、あとで探したけどわからなくて
ワーキングメモリーが弱いのに
ブックマークすら付けとかなかった
自分のバカさ加減に苦笑してしまいました
なんか、記憶が曖昧なので
言葉が正しくないかもしれないですが
・論理型作家と
・憑依型作家が
いるらしいですよ?
1.設定を緻密に整えてから書く
論理型という言葉だったかどうか自信ないですけど
つまるところ論理だよねってまとめだったと思うので
「論理型」の作家さん
このタイプの作家さんは
登場人物の詳細
つまり性格や容姿、歴史や個性、癖とか
「この人である要素」を
きっちり緻密に完璧に設定するというのです
そうした登場人物を「架空の人」として
自分でしっかり生み出して
彼らの動きを神のように作り上げていく
そういうタイプの作家さんらしいです
2.キャラクターが動くから
一方、衝撃的だったので、この命名は確かだと思うのですが
「憑依型」の作家さん
このタイプの作家さんは
「キャラが勝手に動く」発言をする特徴があるというのです
ストーリーを動かすのはキャラクターなので
結末が、想定の範囲を超えたりすることもあるそうです
登場人物たちがストーリーを動かしていくので
そのあらゆる登場人物に憑依することができて
それぞれの視点で世界を見ながら書いていく
そういうタイプの作家さんらしいです
3.分析できるのは凄い
なるほどなぁ、と思ってそこはすごく記憶に残っているのですが
どこで見た何というタイトルの何という方が書いた記事なのか
何一つ覚えてなくて
上手く検索することもできませんでした……
とはいえ、こういうタイプを分析して
しっかり納得させるくらいの言語化ができるというのは
凄いなぁと感心して読んでいました。
で、自分はどちらかな?と考えた時
間違いなく「論理型」ではないなと思いました。
4.憑依型の最初の心当たり
生まれていちばん最初に書いた
原稿用紙52枚の作品(学校の課題ですけど)も
課題だからと作品作りに初挑戦しただけの
ただの高校生だったのもあったのか
今思えば作り方は完全に論理的ではありませんでした
小説『先生の机には引き出しがない』で
淀橋矢来が言っていた
「脳内に見える世界を文字に書き起こすだけだよ」
あれは、たぶん自分自身の言葉でもあって
(憑依していたからっていうのもあるのかな?)
最初の課題の時は脳内で再生される映像を
未熟な高校生の語彙力だけで
そのまま書き出したような作品で(つまり粗い)
その時の感覚としては
映画のように突然ストーリーが始まって
その中でキャラクターが勝手に話を進めていくので
それを忘れないうちに
ただ書き留めていたという感じでした
だからと言っては何ですが
本当にただ書き出し作業をしただけで
課題提出まで2週間という期限付きだったのもあって
推敲とか読み直しとかほぼしないで提出しちゃったんです
でも、提出した瞬間に
「これ、全部自分で書いたの?」と驚いてくれて
評価には
「これだけの物語を紡ぐことのできるあなたは
すばらしいストーリーテラーです
このような作品を書き溜めて
いつの日か世の中に発表してください」
なんて、とても嬉しいコメントと共に
A⁺をつけてくれました
課題の条件が「原稿用紙5枚以上」のみという
シンプルなものだったので
その中で「52枚」というのが提出されて
先生はびっくりしたらしく、他のクラスでも
「こんな生徒がいた」と話してくれていたそうです
その時に「粗い」「何が言いたいのかわからない」など
酷評されていなかったからこそ
しかも走り書きの汚い手書きの原稿を全部読んで
しっかりコメントをもらえたという経験を与えられたからこそ
今再び書こうと思えたのかな
なんて考えると、国語表現の先生には感謝しかありません
けど、残念ながら
次々と新しい映像が見えてくるわけでもなく
日々の忙しさで何かを思い描くこともなくなり
しばらくそういうものは書かなくなっていたのです
だけど、自分の中に生まれたコアメッセージを表現する手段として
また小説を書き始めて
この時ほどまではいかないですが
憑依型なんだなと実感することはあるし
課題に添えられた先生の言葉も色褪せることなく
今もわずかな自信を保ってくれています
だからかなぁ
改めてふりかえると
無意識に小説を書くことを
「作品を描く」って言いがちなんです
まぁ、これらを考慮して、ついでに想像すると
『先生の机には引き出しがない』の二人は
たぶん憑依型なんでしょうね
よろしかったらコチラもご覧くださいませ(なんて宣伝)
5.今の軸はコンセプト
とはいえ、今は
【堂々と、ちょうどいい個々を生きる】
というコアメッセージがあって
それに沿ったコンセプトがまずあってから書き始めるので
突然再生された映画を書き留めるというほどの
粗さはないんですけど
だから本筋やラストはだいたい決まっていて
ラストシーンは映像で思い浮かぶので
そこへ向かって登場人物に動いてもらうんですが
ほとんどアドリブなので
筋こそ違えずとも
ラストシーンのワンカットは変わってることが多いです
セリフも、最初思ってた感じと
キャラクターがしゃべったものはやっぱり違うし
頭の中だけで考えてたら
自分の場合完全に「ツクリモノ」になっちゃうな
セリフも描写も不自然になりそう
なんて実感している部分でもあります
だからたぶんですけど
自分自身でコントロールできているのは
「コアメッセージ」と「コンセプト」や
「キャラクター性」
それからかろうじて「本筋」
これだけです
キャラクター個々の性格はしっかり決めます
でも関係性や掛け合いは彼らによって
想定のものから微妙に変わることも多いです
性格みたいな部分や表現したい核の部分は
最初に登場してきてくれた時の設定から
ブレることは今のところないです
だから神的にすべてを作り上げていくような
「論理型」みたいな作り方は
ちょっと自分にはできないかも
全てを自分でコントロールしようという気持ちも
そもそもないんだとも思うんですよね
コンセプトや筋はあって
それに合ったキャラクター設定をしてはいるけど
その中でキャラクターたちが動いてしゃべって
作ってくれる世界をみて自分も楽しい
優秀な俳優さんにコンセプトと世界観だけ伝えて
ほぼアドリブで演じてもらってる
そんな感じかもしれないです
ん?そういうことだと自分は
憑依型なんてちょっとカッコイイタイプじゃなくて
もしやポンコツ監督型……なのか?
新キャラが誕生してしまった
小説を書いてる方
たくさんいらっしゃると思うんですが
みなさん、どんな作り方をしているいのか
気になってしまいました
・論理型
・憑依型
・ポンコツ監督型
よければどんなタイプなのか教えてくださいませ
いつか論理型になれたりするのかな
それでは最後まで読んでいただきありがとう
ではではまたまた
最後まで読んでいただきありがとうございます!
