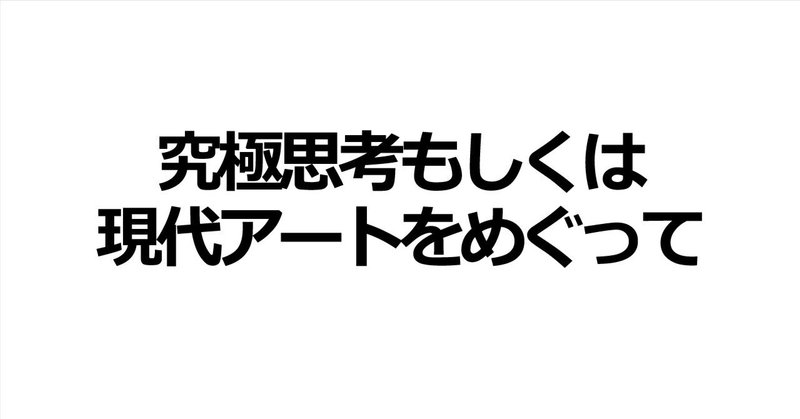
【究極思考00013】
還暦を超えて実感・痛感するのは、テレビ朝日の「じゅん散歩」の主題歌で斉藤和義が「知らないことばかり」と歌う、その知らないことばかり、という境地にほかならない。知っていることと知らないことと忘れてしまったこと知っているつもりで思い違いしていたことが見事に混在しているというのが、自分の正直な感想だ。自分が10代の頃には20代の自分など想像さえできなかったので、60歳以上まで生きるなどとは思いもしなかった。
20歳の頃か数年くらい前か、村上春樹の登場は非常に新鮮だった。その頃、教科書で扱われている作家、大江健三郎や太宰治など、また、1970年代に芥川賞を受賞した池田満寿夫や村上龍の小説など、それなりに読んでいたが、村上春樹『風の歌を聴け』および『1973年のピンボール』は、その断章的な構成と洗練された文章が非常に新しく感じたものだった。ただ、初期三部作と言われる第三作目の長篇『羊をめぐる冒険』に至っては違和感しかなかった。それは、ストーリィの展開の中盤から後半において、説明がほぼ不明な=不可能な超常現象が重要な役割を与えられて登場するからだ。この時期の『中国行きのスロウ・ボート』や『螢・納屋を焼く・その他の短編』でもオカルトな展開は確かなかった筈で、急に『羊をめぐる冒険』で顕現し、その後も特に村上春樹の長篇においてはオカルト的=超常現象的な要素が重要なポイントとなる。結局、数十年も後で、大塚英志の指摘でその変貌は、映画「スターウォーズ」の構成やキャンベルの『千の顔をもつ英雄』に接したことによるらしいことを知って納得した次第ではあったが(大塚英志『物語論で読む村上春樹と宮崎駿 構造しかない日本』)。ラブクラフト的な恐怖小説的要素、生(=性=セックス)と死を必ず含ませることで、村上春樹的長篇小説が確立されたということだ。編集者の希望により書かれた長篇『ノルウェイの森』を例外として。自分としては、『風の歌を聴け』および『1973年のピンボール』をこそ展開してほしかったのだけれど、。
村上春樹に魅かれたのは、主人公が何かを欠落していて喪失感を有していたからだろうと20代の自分を想像する。何が欠落しているかは不明だけれど、明らかに何かが欠落しており喪失感に悩まされているという理由なき強迫観念に陥っていた自分には、村上春樹は非常に魅力的だったのだ。双子や三角関係という設定にも魅かれていたのではなかったか。物事の半分しか言わないようにしていたら物事の半分しか考えられなくなったという内容の指摘も魅惑的だった。何かが失われている、。
主に30代後半あたりから読むようになったのは今では故人ではあるが内田康夫の浅見光彦シリーズ。多分、はじめはテレビシリーズで知って、それを契機に読むようになったのではなかったか。内田康夫は、小説の舞台を選択し、現地での取材はするが、基本的にはプロットを決めずに行き当たりばったりで書き進めるらしい。だから誰が犯人なのかも書き終わるまで分からずに書き進めると。だからか、浅見光彦が初めて登場した『後鳥羽伝説殺人事件』では、浅見光彦の登場を思い付いたのは、小説の中盤以降であり、彼がどういう存在となるかは書き進めるうちに明らかとなったというようなことを「あとがき」などで述べている。だからだろう素晴らしく面白い展開の『後鳥羽伝説殺人事件』や『天河伝説殺人事件』、後の『はちまん』などの幾つもの名作と比べると、まったく面白みのない駄作的な作品も多い。それは、内田康夫のスタイルを鑑みると仕方のないことなのだろう。推理小説やミステリーやサスペンス小説には哲学や思想系の読書と共通するものがあり興味深い。謎が解けて最後にはカタルシスを得てスッキリする。ある意味、哲学も最初から立論を読み解いていけば、作者の設定したテーマが最後には自分のことのように得心されて感動するのと酷似していると思うのだけれど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
