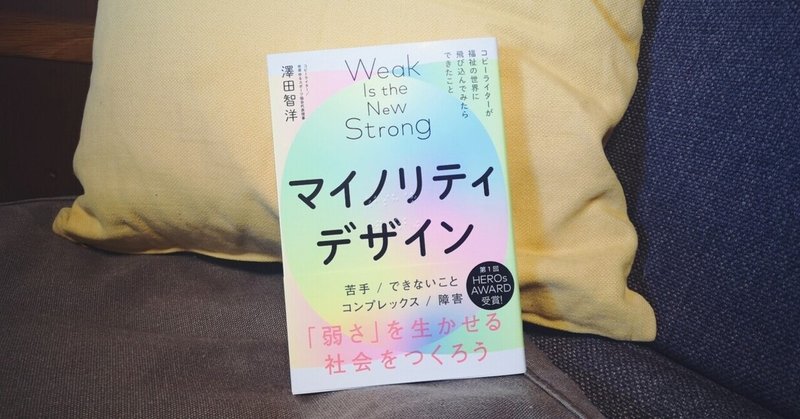
世界を測るものさしはひとつじゃない
構成をお手伝いした澤田智洋さんの著書『マイノリティデザイン』が3/3に出版されました。詳細は澤田さん自身のnoteに譲るとして、この記事では私から見たことを綴ります。
……と、冒頭からサラッと「見た」と書いたものの、私たちはどれほど人の身体や行動、あるいは属性に紐づいた慣用表現を当たり前に使ってしまっているのだろう。視野を広げる、心の声を聞く、足を伸ばす、人生を歩む……
コピーライターで世界ゆるスポーツ協会代表理事の澤田智洋さんは、息子が生まれて数カ月経って、彼の目が見えないとわかったとき、「目の前が真っ暗」になって「頭が真っ白」になったのだといいます。
途方もない絶望を「目の前が暗くなる」と表現するように、「目が見えない」って、想像以上にたくさんの困難があるのだと思う。私たちは当たり前のように、目で見えるものを信じて、目で見えてきた情報に基づいてさまざまな判断をしている。
澤田さんは、それまでプランナーとしてテレビCMに携わっていたものの、自分の仕事を「息子に見せることができない」ことに愕然として、仕事のやり方を180度転換します。それが「マイノリティデザイン」という考え方です。
マイノリティとは「社会の伸びしろ」であって、人はみな、なにかのマイノリティである、と。誰もが大なり小なり持つ弱みを「克服」するのではなく、そのまま受け入れ、誰かの強みとかけ合わせることで、答えを見つけること。その考え方によって生まれたものの一つが、テレビでもよく話題になる「ゆるスポーツ」です。
澤田さんとは、この本の取材に際してはじめてお会いして、何度もお話させてもらって、共感ポイントがいくつもありました。たとえば、澤田さんはご家族の仕事の都合でたびたび転居を余儀なくされたため、ずっと「自分はアウトサイダーだ」と感じていたといいます。私自身も全国転々としていたので、その感覚はいつも心のどこかにありました。澤田さんの場合はイギリスやフランス、アメリカなど海外を転々としていて、その感覚はいっそう強くこびりついていたのだと思います。
澤田さんの経歴を一見すると、帰国子女で慶應卒、大手広告代理店勤務でクリエイター……とキラキラしていてまさに「勝者」と思われそうだけど、幼少期から「マイノリティだ」という感覚を持ちつづけていたからこそ、自分自身の、あるいは他者の弱さを認め、さまざまな人と関わり、互いを尊重しながら、社会を変える方法を見いだすことができたのだと思います。
そう、「弱さを認める」って、なかなか難しい。特に日本では、弱さを認めるとつけ込まれたり責められたりして、「成功できなくなる」と思われている節がある。たぶん何らかの組織に所属して働いている人は特に、そのレースから外れることに怖さがある。だから自分の弱さを認めようとしないし、他人が弱みを見せたら、出し抜くチャンスだと思ってしまう。
でもそういうのって、もうしんどい。そう気づいている人から少しずつ変わりはじめている気がする。既存の枠組みから少し外れようとしている人、外れたいけどどうすればいいかわからない人、違和感はあるけどなんとなくこれまでのやり方を続けている人。そんな人たちに、『マイノリティデザイン』はかすかな光を灯してくれる本だと思います。
(↑このnoteも本書の重要なポイントを惜しみなく明らかにしています。「納品したら終わり」「やらないことを決める」…個人的にもまだまだそういうマインドにとらわれているところがあるからすごく刺さります。反省)
本書を構成するにあたって、私がいったん文章としてまとめたものを、澤田さんがそれはもうバチバチにアップデートしてくださって、ビビッドに伝わるものになりました。さすが言葉のプロフェッショナルだと、本当に勉強になりました。シリアスな物事でも、一貫して感じられるおかしみ(澤田さんは「ユーモラス+チャーミング」と表現しています)がまさに澤田さんならではの書き味だなぁ、と。
本の中で、澤田さんは「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」というトルストイの言葉を引用して、「『弱さ』の中にこそ多様性がある」と話しているけど、いま、さまざまなところで生きづらさを感じる人が多いのは、ある種、世の中のものさしが資本主義や弱肉強食的な思想一辺倒になっているからなのではないでしょうか。その揺り戻しがいま、さまざまなところで生まれている気がするけど、少なくとも「世界を測るものさし」はひとつじゃなくて、もっと多様であっていい。物事の見方を変えるだけで、社会が変わるようなことが、もっともっと起こっていいのではないかと考えています。
読んでくださってありがとうございます。何か心に留まれば幸いです。
