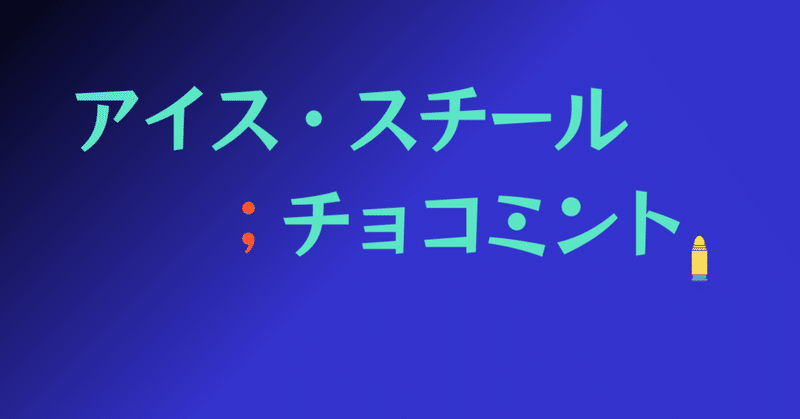
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 二章 5話 子どもでいさせないくせに
5話 子どもでいさせないくせに
シャワーとトイレが一緒というより、トイレのおまけにシャワーがついているといった方がしっくりくる。
ミオはゆっくりする気になれず、最短の時間でシャワーをすませた。
ドア前の、これまた狭いスペースで急いで服を着る。同性とはいえ、会って間もない人たちのそばで裸でいるのは落ち着かなかった。
汚れた服を簡単にたたんでまとめておく。フロントにもらったポケットティッシュは、着替えたシャツの飾りポケットにうつした。持っておくと何かと重宝する。
あとは髪を乾かすだけ。なのにドライヤーが見当たらなかった。コンセントがないことからして、部屋でしか使えないのだろう。戻ろうとしたところで、
——ミオの味方になるのもデメリットがちらついて
——命に関わるかもしれなくても
息が詰まった。
アイスは、報酬額が割に合わなくて関わりをしぶっているのだと思っていた。
後見人になった怜佳の安否はまだわからない。
グウィンまでもが、危険な目に遭うこと承知でいる。
助けようとしてくれる人がみな危険にさらされているのは——遺産のせいだ。
どれだけの遺産を両親から引き継いだのか、正確な額をミオは知らなかった。
けれど、どれほどの大金だったとしても、捕まるようなことをしてまで奪おうとする大人が馬鹿にみえる。アイスやグウィンに、同情してほしいわけでもなかった。
「みんなお金でどうかしてる! こんな人を引っかきまわすお金なんかいらない!」
ミオの訴えなど耳に入っていないように、アイスはグウィンのほうへと視線を振りむけた。
頭に血がのぼる。アイスがなぜグウィンを気遣うような素振りを見せたのか、考える余裕もなかった。
わたしを蚊帳の外におくな。
子どもの声だと軽くみるな。
子どもの歳でも、ミオは子どものままでいられなかった。理性的であろうと頑張り続けてきた反動が噴き出した。
アイスに憤懣を叩きつける。アイスしか見えなくなっていた。
「お母さんには生きててほしかった。父とのあいだでトラブルがあるぐらいわかってた。わたしに相談してほしかった。わたしがいることを別れない理由にしてほしくない。わたしのために身を投げ出すこともしてほしくなかった。お母さんとふたりで逃げたかったのに!」
アイスが静かに応える。
「追い詰められた人間は、当たり前のことすらも考えられなくなる。ミオに相談することさえ思い浮かばないほど、彩乃さんは苦しかったんだよ」
「そんな当たり前を聞きたいんじゃない!」
「ミオにはせめてお金を遺そうとした。お金があれば自由が買える。自由に生きるための下地を用意してくれたんだ」
「クラシックを聴くのに、ステレオじゃなくてラジカセ。この安部屋も守銭奴として選んだ自由ってわけ?」
こんな厭な言葉を吐けるんだ……。
自分の声を他人の声のようにミオは聞いていた。冷静なもうひとりのミオが、アイスの言うとおりだと頷いているのに、罵詈がとまらなかった。
「守銭奴のつもりはないけど、ラジカセも部屋も、選んで得たもののひとつだよ。余分があると重く感じる人間だから、必要分だけのシンプルを選んでるだけ」
アイスの応えに卑屈さはなかった。
「持っているお金の額によって、選択肢は増えも減りもする。持っていなくて困ることはあっても、その逆はない。
お金を遺した彩乃さんの意思は別にしても、簡単に捨てなくていいんじゃない? お金の使い方を覚えるまでおいておいて、ミオが成人したときに、どうするか決めればいい」
「お金があって困ることはない? じゃあいま起きてる、このトラブルはなんのせいなのよ⁉︎ 感傷で守ってもらって、わたしが平気でいられると?」
彩乃と父が〝事故死〟する前の日の朝。
これからも心配ないと彩乃は言ったのに帰ってこなかった。本当のところ、自分のことなど忘れていたのではないかという不審が、ミオにくすぶっていた。
「事故死だって聞いたけど、事実は言われなくてもわかってる。こんなのが、わたしを父から守る最適な方法なの? 勉強も仕事もできたお母さんが、なんで力づくの馬鹿な手段に頼るのよ! そんなお金を遺してなんになるの⁉︎ 気持ちが重くなるだけだよ!」
「力づくでしか方法がないことだってある」
グウィンが不意に口をひらいた。低い声で続けた。
「どんなに働いても生活のための金がない。言葉で訴えても状況が変わらない。なら、力でやるしかないじゃない」
「グウィン?」
「グウィン!」
声が重なった。
ミオは脈絡のない話にどうしたのかと問いかけ、アイスが目覚めさせるように名を呼ぶ。
しかし、ふたりの声がグウィンの耳に入っている様子はなかった。
「言葉では聞こえなかったことにされてしまう。無かったことにされる。なら最後は、力でやるしか手段がない。だから女も、子どもも、神父ですら力で抗うんだよ!」
「ほかに選択肢がなかったんだよね」
肯定の言葉をかけたアイスとは反対に、ミオはうろたえることしかできない。激しい口調に圧倒されていた。
「欲しかったのは贅沢するための金じゃない、金さえあったら死なずにすんだ人間がたくさんいる。金なんかあってもしょうがないなんて言うな!」
アイスが腕をのばす。ここではないところに向かって話しているグウィンの顔を包み込んで自分のほうに向けさせた。
うっすらとしか見ることができないというグウィンの瞳をまっすぐ見つめる。
「グウィンは、やれるだけのことやってきたんだよ」
「でも、死んだ……たくさん死んだ……がっこうにいきたいって……」
「うん」
アイスはグウィンの頭を肩口に抱え込んだ。途切れ途切れに続く悔いの声が、アイスの身体に吸い込まれる。
昂っていたミオの感情は一気にさめた。
どうしていいか分からずにいると、アイスから声をかけられた。
「少し待っててくれる? ミオの話、ちゃんと聞くから。どうするか考えよう」
「う、うん。ごめん、なんでこんなこと言ったのか自分でも……」
「後悔なんかしなくていい。ミオは当然のことを言っただけなんだから」
そう言ってもらっても、言ってはいけないタイミングというものがある。この場にいるのは気まずかった。
「頭冷やしてくる」
「ここのフロアから出ないで。ミオがひとりになりたいのなら、泊まる部屋もあわせて検討するから」
感情のままに出した言葉が頭のなかで反芻され、後悔があふれ出る。ミオの耳には、アイスの言葉が意味のない音としてしか入ってこなかった。
「わかった」
上の空で応え、部屋の鍵を外した。
アサルトライフルを捨てたグウィンが、屋根の下で毎日眠れる生活を送れるようになって久しい。
けれどかつての仲間には、いまも会っていた。血に濡れた顔で、片足をなくした身体を斜めにしたままで、少し離れたところから取り囲んだ仲間が、じっと見つめてくる。
仲間の顔は、はっきり見えていた。どの顔にも苦痛の色はない。むしろ、やわらかく笑んでいて、グウィンもこちらに来いと呼んでくれる。
こちらに来ればもう、痛苦も、悲嘆もないと。
応えて行こうとするのに、近づけなかった。駆け寄ろうとしても、いっこうに距離が縮まらない。それどころか、どんどん離れていく。置いていかれたくなくて必死にもがく。
そうしているうちに目が覚めた。
いつも同じ夢だった。
起き上がると息がはずみ、汗で全身が濡れている。目の前には、あいかわらず白い霧が濃くひろがっていて、よく見えない。悲しくも、苦しくもなかった。ただただ虚無感がグウィンの身体を侵し、内部から崩れ落ちそうな錯覚をおこした。
あるのは、逃げ出してきた罪悪感。
——ここまでよく頑張ったね。
アイスには過去を断片的に話したことがある。それだけでグウィンが抱える事情はわからないはずだが、いつもこの言葉をくれた。
抽象的な答えだから、受け取ったグウィンが自由に解釈する余地がある。だから都合よくとっているだけかもしれない。それを承知で、ただ頷いてほしかったグウィンにとっては、これ以上ない言葉だった。
アイスの声を聞くと、落ち着けるようになっていた。
ミオが出ていった部屋に、窓の外の室外機の音だけが低く響く。
アイスの肩に寄りかかったまま、グウィンは魂まで抜け出そうな苦しい息を吐いた。
「ミオになんて謝ったらいいか、思いつかない」
「身体で苦しいところはない?」
「トラブルの渦中で苦しんでる子に、なんてことを……」
「別の考え方もできるよ。ミオは大人すぎるところがあるからさ、ポンコツなとこを見せてやったことで安心して、年相応になりそう」
「すっごく、きついこと言った気がする」はっきり覚えていなかった。
「ミオを傷つけたりしたら、ますます自己嫌悪だよ」
「たしかに刺さったかもね」
「うっ……アイスが容赦ない」
「放った言葉は戻せないから、あとでフォローいれよ。あたしたちは完璧には遠い。修正しながら進むしかないでしょ。ところで、ミオと買い物してるあいだに何かあった?」
思い出すと、また冷たい汗が吹き出てきた。
「一階フロアにいるとき、電球が破裂した」
「ああ……」
アイスにはそれだけで通じた。
発砲音や爆破音に似た音がトリガーになる。あっという間に銃が支配する暴力の只中に引き戻された。嗅覚までもが思い起こされ、血の一滴も落ちてはいないのに、独特の錆臭さが鼻をついた。
「意思でコントロールできるものじゃない。きつかったね」
腕にやわらかくタッチされた。
「しばらくベッドで休んでいきなよ。仕事の疲れも、たまってたんだよ」
「ありがと。あたしは大丈夫だから、ミオの様子を見てきて。そのあいだにミオへの埋め合わせを考えとく」
狭い部屋では否応なしに相手の姿が目に入ってしまう。同じ部屋にいては気まずくて、ミオは出て行かざるを得なかっただろう。
グウィンを苛む記憶は、見る力を大きく失っても薄らぐことがなかった。過去の視覚情報を新しい視覚情報で上書きして消せないから、記憶に刻まれた光景が薄くなることがない。ちょっとしたきっかけで思い出し、繰り返すことで、消えない記憶として強化された。
けれど、自分を律する意味でいいと思えた。信仰心はないけれど、天の配剤だとしたら納得しているところがある。出てきた国でのことは、忘れてはいけない記憶だった。せめて覚えていることが、死んだ人間への詫びになる。
視力が極端に落ちた原因はわからなかった。
つてを頼ってこの国に逃れ、少しの安心を得たあと、視界に霧が立ち込めはじめ、目でもって見通すことができなくなった。そしてそのまま晴れることなく、グウィンの視界は酷くぼんやりしたままになっている。
この状態には、もう慣れた。視力を取り戻すことにも、あきらめがついた。
ただかなうなら、ひとつだけ望むことがある。
アイスの顔を見たかった。
慌しい足音に、グウィンは我に返る。ドアが乱暴に開けられた。
「ミオがいない」
アイスの声が強張っていた。
「ラウンジ以外も見て回ったんだけど……」
「外に出たってこと?」
触知式腕時計の風防ガラスをあけ、針を指で読んだ。追っ手だけではない。ハメを外した酔っぱらいが出没してくる時間だ。探しにいく用意をしているアイスの気配に、
「あたしも一緒に行かせて」
白杖をとって立ち上がった。
役に立てるのかわからないが、少なくとも移動でアイスの足を引っ張ることがない、とっておきの方法は身につけてある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

