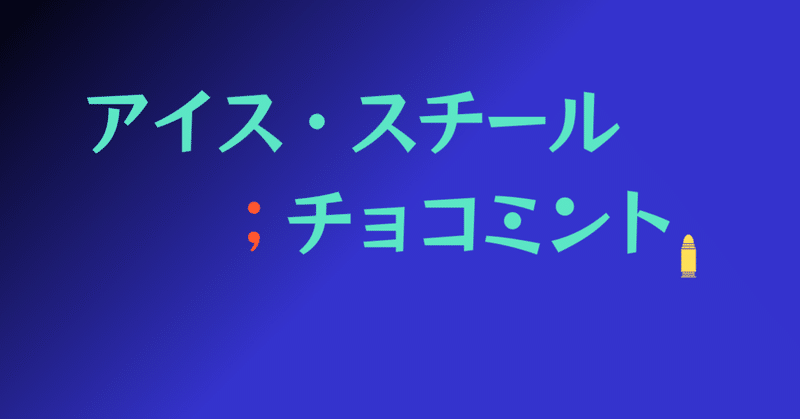
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 三章 4話 追いかける背中
4話 追いかける背中
アイスとの対決を避けた十二村は、<ABP倉庫>に戻るなり浅野の出迎えをうけた。
顔を見れば何を言いたいのかわかる。それでも皮肉と嫌味をたっぷりまぶした苦言を黙って浴び続けた。
言いたいことは全部言わせてやったほうが、あとあとマシだ。最後まで付き合うつもりでいたが、暖簾に腕押しな反応に飽きたか。舌打ちを残して、浅野のほうから離れていった。
十二村に近づいてくる者はいない。
ボソボソとした話し方に喜怒哀楽が乏しい表情は、陰気そのものだ。言葉数も少なく、冗談も通じない。仕事でなければ絡んでくる人間はいなかった。
十二村としてはコミュニケートすることが苦手なだけで、人との関わりがきらいなわけではない。そこをわかっているのか、気にしていないのか不明だが、アイスだけは頓着せず話しかけてきた。アイスの人付き合いは概して淡白なものだったから、親しいというほどでもなかったが。
それでも十二村にとって、アイスは一目置く存在だった。
「アイス」という呼び名も使わない。殺し屋ではあるが、冷淡を連想させるものはなかったからだ。
浅野が離れていったあと、十二村はひとりになれる小会議室に入った。明かりもつけず、パイプイスに腰を落とす。
廊下からもれてくる、ぼんやりとした照明のなか、ジャケットからポケットティッシュをとりだした。ミオが座っていたベンチ付近で拾ったものだった。
包装にはさんである広告は<ゲストハウス・ファースト>。
ここにアイスがいる——。
<美園マンション>にいるというだけで、それ以上はつかめていなかった。このポケットティッシュの報告を直属の上司である、チェ一太にあげていないからだ。
報告すれば、すぐにでも子どもの回収にむかうことになる。子どもを護る側についたアイスは、浅野の報告によって粛清対象となっているから、古参であろうと容赦なく排除される……
ついと立ち上がった。
会議室を出て、ガレージ横の洗車スペースにむかう。夜間の水場に人気はない。周囲に誰もいないことを確かめてから、ポケットティッシュとライターを出した。
タバコをやめて二年になる。走ったときの息切れが酷くなり、自発的にやめていた。
なのにライターだけまだ持っているのは、贈り物としてもらったものだからだ。
話の流れで誕生日プレゼントをもらった経験がないと口を滑らせたことがある。その二日後、誕生日でも記念日でもないのにプレゼントされた。それからずっと持ち続けている。
ケースに細かな傷がついた古ぼけたライターをつけた。タバコを吸わなくなっても欠かかさない手入れで、いまもオレンジ色の火を灯す。
ポケットティッシュを近づけた。小さな明かりに照らされる<ゲストハウス・ファースト>の文字と連絡番号……
火を消した。
ポケットティッシュをライターと一緒に内ポケットに入れる。
連絡番号を覚えさえすれば用ずみだった。ほかの人間に知られたくなければ、燃やしてしまうのが常套だ。
そんな常識をねじ伏せてしまうぐらいの感傷を発揮してしまった。
*
チェ一太が<ABP倉庫>に入ったのは、高校を出てすぐのことだった。
誰に勧められたわけでもない。実父である麻生嶋ディオゴがボスである組織だから。理由はそれだけだった。
そんな一太に対して、ディオゴの眼差しは冷めたものだった。一太が婚外子である故か。組織に入っても配下の一人でしかなく、仕事で実績をあげ、やっと後継候補としてみる視線が入ってきたぐらい。
それはアイスにしても同じだった。加入をアイスに報告したときの応えは、ずいぶんあっさりしたもので、
——そうなんだ。
それだけだった。
一太の目の高さは、すっかりアイスのそれを超え、アイスにしても、もうデザートを食べに連れていってくれた気のいいおばさんではなくなっていた。
一太が成長するにつれてアイスと話す機会は減り、<ABP倉庫>に入った頃には、付き合いらしきものはなくなっている。話すことがあっても、仕事の連絡を事務的にするだけになった。
アイスにしてみれば、親に放っておかれた子どもに同情して、かまっていただけ。大人になれば、創立にたずさわった古参とぺーぺーの新人という一般的な姿に戻ったにすぎない——。
そんな回答を自分に出しながらも、どこか割り切れないものが一太に残った。
一太は、自分の存在をアピールする手段として<ABP倉庫>でしゃにむに働いた。
このやり方にかぶる人間がいる。一太の母だ。
ディオゴとその妻、怜佳の関係は冷め切っているように見えた。そのふたりのあいだに割って入ろうと苦心していた。
しかし母の場合、怜佳に代わって本妻として迎えられる望みがないと悟ると、すぐに身を引いた。ディオゴからの手切れ金の幾分かを家に残しただけで、唐突に姿を消す。一太を家において買い物に行くように出ていき、そのまま帰ってこなかった。
一太は、自分の存在を誰も見ていないと感じるようになる。
年を経るごとに誰よりも気に障ったのは、アイスだ。
彼女も家族というものがない。かといって、そこを気にとめることなく、自然体でいる姿に羨望をもった。同時に、なぜ自分はそのように生きることが出来ないのかという焦りをうんだ。
ふたりで喫茶店をまわり、新しくできたアイスクリーム屋に行ったことも、アイスはすでに忘れているだろう。
そして、そういったエピソードを忘れられない自分が、一太は腹立たしかった。
*
アイスの居場所をあと一歩のところまで突き止めた。そこまでいきながら足踏み状態が続いている。
一太は、命令に逆らって<オーシロ運送>に出向いていた。
すでにアイスがオーシロ社屋に入っていたが、協調する気はなく、直属の部下数人だけをともなって割り込む気だった。
ただ、まずは雇いの外部の人間を先遣にした。怜佳の居場所が簡単につかめたことが、きな臭い。生家という、その人間を探すなら真っ先に候補にあがる場所に長居するには、何か理由があるはずだ。
そうして予見した通り、爆発火災が起きた。
怜佳の経歴を思い出す。理学部か理工学部だったかに在籍していた。爆発物をつくった経験はなくても、扱うための基礎知識がある。怜佳が仕掛けた可能性がなくはなかった。
ミオを連れて出てきたアイスの行動確認は浅野にまかせた。人任せにしたくない未練があったが、怜佳の生死によって、このあとの対応が変わってくる。早く確かめたかった。
果たして、裏口のほうからファイヤーブランケットをまとった人間が転がり出てきた。
ひとりは怜佳だ。そこからの尾行は簡単だった。とんでもないことをやってみせたとはいえ、怜佳は一般人であるし、危地から脱した安堵で気が緩んでいた。
<美園マンション>に入られたときも、本来ならエレベーター移動で見失ってしまう。しかし一太にとって幸運だったのは、怜佳が美園に不慣れだったことだった。
総合案内所を利用した怜佳に続いてカウンターに近づいた一太は、旅行会社スタッフを名乗った。バックパッカーらしき男の大容量リュックのサイドポケットから、かすめとった茶封筒を掲げてみせた。
「先ほどの女性がチケットを忘れたまま行ってしまって」
一太のスーツ姿に身分証の提示を求めることもない。次々にくる利用者をひとりでさばいていた案内係が早口で応えた。
「<ゲストハウス・ファースト>。階数はエレベーター横の案内板で確認できます。次の方!」
美園に入るまえ、出入り口を監視する浅野を認めている。
アイスも美園に入ったか——。
<オーシロ運送>から出てきたときのアイスは怪我をしていたから、地階診療所にいったと考えられた。
くわえて十一階建て、延べ床面積約六万六〇〇〇平米の建物は、人探しをするには巨大で、隠れ処にするにはうってつけだ。そのまま美園に潜伏もありえる。
一太は無駄足になることを予感しながらも、アイスの影を探し出そうと美園のフロアを歩き回った。アイスがよく利用するというゲストハウスフロアを見てみたかったこともあった。
やはりとは言いたくないが、尻尾すら見えなかった。無為に時間をすごす余裕はなく、撤収するしかない。
いったん一太は<ABP倉庫>に戻った。一般業務の社員がいなくなった夜の事務所で、事態が進展するまで正業のほうをこなしておく。そのつもりだったのに、貨物業者の調整よりも、探しきれなかったアイスのことばかりが頭にうかんだ。
監視に残っていた浅野たちも、ひとりで出てきた高須賀未央を公園で追い詰めながらカウンターを食らっていた。アイスまでもが出てきたのだ。正業など放っておいて、自分も残るべきだったか——
考え込むうちに浅野が駆け込んできた。
「動きがありました。確認と指示を」
公園から引き上げてきた浅野には、ディオゴのオフィスの電話盗聴に加わらせていた。広げていたファイルを鍵付きの引き出しに放り込み、慌ただしく立ち上がる。
「十二村を連れてこい」
「あの人は外した方がよくありませんか?」
「援護させるためじゃない」
尋問する気だった。
十二村も創立時からのメンバーで、アイスやディオゴとは古い付き合いになる。ずっとディオゴの直属で働いていたが、いまは一太についていた。
はっきりいって、使える部下ではない。常に人から距離をとり、一人仕事が多い十二村は、チームプレーには不向きで、扱いが限定された。
口さがないやつは陰でお荷物を押し付けられたと言っているが、一太はそうではないと思っている。おそらく、ディオゴが仕向けたお目付け役だ。
一太が境遇を恨んで手向かってくると恐れている、あるいは後継としての能力を密かに測ろうとしている……そういったことは考えなかった。お目付け役をつけられる程度には気にかけられているのだと思うだけである。
むしろ、一太のほうが十二村を観察していた。
アイスにだけは気を許している気配が十二村にある。笑みで本音をみせないアイスと実は通じているのではないか? だとしたら公園で一時的に姿をくらましたのは、アイスにコンタクトをとっていたのでは?
そう考えると、独断で動きだしたアイスの拠点も、十二村ならピンポイントで知っていることもあり得た。
「十二村を4番ガレージに連れていく」
「4番ですか?」
浅野が念押しするように指示を繰り返した。4番ガレージは車庫以外にも用途があるスペースだった。収納棚には車用品やタイヤにまぎれて尋問用の道具がおかれ、排気ガスやオイルを換気するための換気扇が、尋問者の不快度をさげる働きもする。
「獲物が逃げる時間を与えるわけにはいかない。急ぐぞ」
指示をたたみかけると浅野に薄い笑みが浮かんだ。
「十二村まで背く気配があれば、このまま……ですね」
一太は「処分する」とは返さない。私情を入れて期待する浅野が不快だった。
4番ガレージにいる時間は一〇分にも満たなかったかった。
十二村が答えなくても、ジャケットから出てきたポケットティッシュが答えだ。尋問に加わっていたメンバーを連れて、一太は4番ガレージから飛び出した。
「十二村を放っておくんですか⁉︎」
「居場所をつかむ情報を隠してたんだ。ベテランらしく、自分の身は自分で処分するさ。高須賀未央の対処より先にくる案件はない」
車の用意をさせ、浅野だけ連れて備品室へとむかう。
アイスが潜んでいたのは<ゲストハウス・ファースト>。怜佳と同じフロアにいた。
美園のフロアを一太が探っていたとき、それらしき部屋をすでに見つけていた。
怜佳が訪ずれた部屋だった。閉じられたドアの外で耳を澄ませたが、かすかに聞こえるのはクラシック音楽だけで確信がもてない。このときは、そのまま離れた。
音楽の趣味はともかく、アイスなら怜佳を部屋に呼ぶような不用心はしない。それに、怜佳の協力者はアイス一人とは限らない。そう判断した。
間違っていた。
アイスが不用意な接触を避けていても、一般人の怜佳が不意に近づいてしまう可能性だってあったのだ。怜佳が入っていった部屋を確かめるべきだった。
切り込みが足りなかった点を一通りさらうと、一太は頭を切りかえた。
人員は増やさずいくことにする。<美園マンション>内部の入り組んだ空間を考えると、大人数では連携がむずかしいし、一太が動かせる人数も少なかった。
サブリーダーになる浅野を連れてオフィスに入った。アイスのことを老骨と揶揄したが、年齢でみくびる愚行はおかさない。落ちていく体力に反比例して深めた奸智で生き延びている。銃の保管ケースをあけた。
「使っていいんですか?」
浅野がはずんだ声を出したが、銃は実用性とともにリスクもついてくる。発砲事件となれば、多忙な警察も揉み合いではすませてはくれない。
「保険だ。ただし必要な場面と判断したら躊躇しなくていい。後始末はおれがどうにかする」
見失っていたアイスの後ろ姿をやっと見つけた。退路と引き換えにしてでも、一太は目的の完遂をめざす。
しかしながら見ている先が、無意識のうちにずれてきていた。
父親たるディオゴではなく——
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

