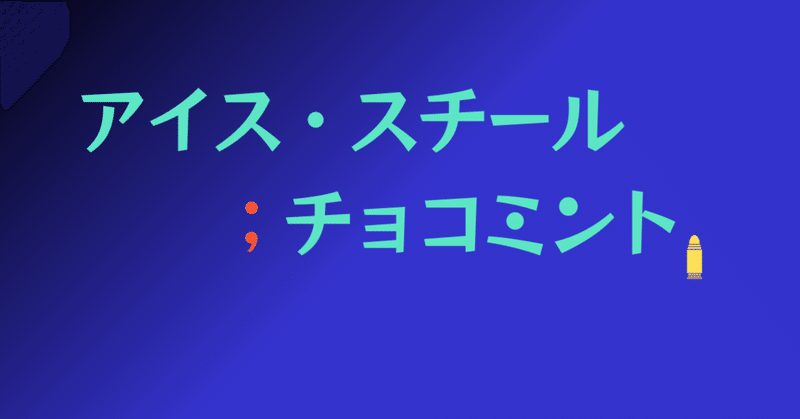
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 二章 3話 グウィンに憑いた幽霊
3話 グウィンに憑いた幽霊
「あとで手持ちの紙幣を折ってくれない? 札の額ごとに折り方を変えて区別してるんだ。手触りでも判別できるんだけど、支払いに時間が掛かっちゃうから」
「そんなことでいいの? いつだって手伝うよ」
グウィンに返す借りは、ミオにとっては簡単なことだった。というか、手触りで札が判別できるグウィンがすごい……。
こうして話している間もずっと、ジェラートパンをはさんだ店員と客の楽しげなやりとりが流れてくる。夕食の時間帯にあっても、店は忙しそうだった。
「こういう雰囲気の中にいると、幽霊話がしょっちゅう出てくるのが嘘みたい」
「ああ、定番の」
「アイスに言ったら、イメージに囚われてるだけっだって。グウィンはどう思う?」
「話には聞くけど、あたしはほとんど〝見えない〟からなあ」
「声とか音を聞いたことは? 霊が出るときにラップ音がするっていうけど」
「ラップ音がどんなのかはわからないけど、生身の人間の悲鳴なら聞いたことあるよ」
「え……」
ミオの背筋にアイスクリームのせいではない冷たさが走った。
「でも、人の目の死角で犯罪が起こるのは、どこだって同じでしょ? おかしな噂がたつ<美園マンション>にも、とっておきの場所だってあるし。一般客の立ち入りは禁止されてるんだけどね」
「じゃあ、入れないじゃない」
「だからこっそり入る。経路を警備の人が教えてくれたの」
「…………」それでいいのか警備員。
「ミオがどんな顔してるか想像できるよ」
「でも、<美園マンション>でとっておきの場所なんて……あ」
入る前に見上げた、美園の外観を思い出した。
「ひょっとして屋上?」
<美園マンション>は周囲の建物より高かった。ビルがひしめいている中に建っていても、屋上なら三六〇度、あけた空間になる。
「空が広く感じるなんて、この街中じゃ、ちょっとできない体験でしょ」
「あぶなくないなら、わたしもちょっとだけ……あれ、グウィンはなんで……その……」
「見えないのに行くかって?」
「う……うん」
「見えなくたって風を感じることはできる。地上で感じるのとは違う風が流れてる。そうだ——」
グウィンが思い出したように付け加える。
「パラペットが低いってアイスが言ってた。上がったら、屋上の縁には近づかないようにしてね。それさえ守れば大丈夫」
すでに屋上にいく話になっていた。
「アイスも上がってたんだ……って、そのまえにパラペットって何?」
「えっと……手すり? 端っこのほうに低い壁が立ち上がってる、あれ。美園はフェンスとか柵じゃなくてパラペットなの。立ち入り禁止になってるのはそのせい。高さがなくて、簡単に乗り越えられるから」
「だから飛び降りたとかの幽霊話が出るのかな」
「ミオのこと訊いてもいい?」
「え、あ……うん」
もう少し現実を忘れた、どうでもいい話をしていたかったが、訊く気満々のグウィンの顔を見たら断れなくなった。
「ミオはこれから、どんなことしたい?」
「えっと、それは高校卒業してってこと?」
「なんでも。学生のうちにチャレンジしたいことでも、卒業後にやってみたいことでも」
「それが……夢のない話になるけど、わからない」
「そっか、これからなんだね」
「どういう……?」
「『わからない』っていうのは、まだ見つけてないってこと。これから探すんだよ」
「すごいポジティブ思考」
感心して笑ってしまった。
「前向きで考えるのなら進学したい。それぐらいのお金を遺してもらえたし、知らないことを知っていたら、やりたいことや得意なことがわかるかもしれない。家の事情で、一年生のうちから進学をあきらめてるクラスメートもいるから、複雑な気分になるけど」
「だったらなおさら、ミオは進学のチャンスを大事にしてほしいな」
「こんな動機でもいいのかな?」
「きっかけは何だっていいんだよ。いい結果も悪い結果も、やってみてこそついてくる。学校いけるのなら、絶対いくべきだよ」
学校に思いれでもあるのか、ずいぶん勧めてくる。
「じゃ、グウィンが整体の勉強したきっかけ——!」
話に熱が入るまま思わず身を乗り出したとき、小さなテーブルに立てかけてあった白杖をうっかり蹴飛ばしてしまった。白状が床にはね、高い音が店内に響いた。
「ごめんなさい!」ミオは慌てて拾いあげつつ、
「ん?」
予想外の重さにとまどった。
「軽いほうが使いやすそうに思ってたけど、グウィンの白杖は違うんだね」
「アルミは曲がることがあるし、カーボンは横からの力に弱い。その点、スチールは丈夫で使い勝手がいい。自分仕様に変えたら、ますます頼れる〝バディ〟になったよ」
ボールペンでも軽い方が疲れないという人がいれば、重いほうが安定して書きやすいという人もいる。
グウィンの白杖は、見た目は基本的な直杖タイプだが、重さに個性があった。これなら、さっきみたいに、うっかり人間に蹴飛ばされても安心だ。
グウィンが白杖を手にとった。
「おなか落ち着いた? ミオの服探しをしたら、食事を買って戻ろう。アイスにも栄養とらせないと」
店員に挨拶して<エスクリム>をでた。吹き抜けのあるスペースから、路地みたいに狭い廊下へとグウィンが入っていく。
細い廊下の両端にも小さな店が連なっていた。飲食店や雑貨、チケット売買店といった店舗にまじって、ガラクタに見えなくもない金属部品ばかりを並べていたり、修理済みの札をはりつけた電化製品を扱っていたり。
それらのあいだをグウィンは迷うことなくずんずん進んでいく。隣を歩きながら、ミオはもう一度確かめたくなった。
「人間って目から入る情報に頼ってるじゃない? グウィンは……その、ぼんやりとしか見えなくて、不安にならない?」
「もう慣れたかなあ。最初はもちろん不安だったし、怖かったけど」
ひと呼吸おいて、グウィンの声が少し低くなる。
「この国にくる以前は、必要なものを銃弾でとりかえす前線にいたんだよ。自らすすんで入った世界だったけど、惨たらしい場面をたくさん見るうちに、勝手に絶望して、厭になって。いっそ見えない方がマシだとか考えるようになった。本当に視力が落ちるなんて露ほども考えてなかったから、そんな短絡的なこと思ってたんだろうね」
想像が追いつかないハードな答えが返ってきた。
「ごめんね、いきなり重い話して。思い返すうちに、つい……」
ミオも彩乃を思いうかべた。夫婦間でのことを話してくれなかったのは、大人になろうとするミオの背伸びを見抜いていたのかもしれなかった。
「視力が落ちた原因は、診てもらってもわからなかった。もっと悪くなるんじゃないかって不安もある。だけど見方をかえたら、ネガティブなことばっかりでもなかった。
説教じみた言い方しか思い浮かばないけど、ものの見方はひとつじゃないって気づけたのはよかったよ。いい歳になるまで気づかなかったのかよっていうツッコミはなしで」
一転、茶化して軽い話のように話す。
会ったばかりのグウィンの、これまでのことを思った。
グウィンに案内された店は、アパレルショップというより衣類問屋と呼ぶ方がふさわしかった。ワゴンに山盛りにされ、壁にも低い天井からも、びっしり吊り下げられた商品に、服の海にダイブしている気分になる。
「ここから探し出すの……?」
ミオはなかば呆然とした。楽しいはずの服選びが、目当ての服を掘りあてる肉体労働になりそうだった。
「店の人に手伝ってもらう?」
「ぜひ」
呼ばれてきた二〇代にみえる店員は、ミオの全身を見てから次々に取ってきた。ワゴンの服の山の傾斜にならべてみせる。
ゼブラ柄のジャケット、アニマルプリントのTシャツにカラフルなパンツ……
「ほかの人とかぶらへんのが大事なんですよ! 個性とインパクトで攻めな!」
誰に向けて攻めろというのか、やたら派手なデザインをぐいぐい勧めてくる。
ミオは負けなかった。ここでひるんだら、ホワイトタイガーの顔が大きくプリントされた、ド迫力Tシャツを着るはめになる。
「アースカラーもしくはナチュラルカラーで。あと、動きやすいデザインでお願いします!」
「そんなんで、ええんですか?」
「そんなんが、いいんです!」
要求をはっきり伝えると仕事は早かった。無尽蔵にみえた在庫の中から、サイズまでぴったりのものを出してきてくれた。
とはいえ、店員もあきらめたわけではなかった。
「おとなしい服着はるんやったら、小物でアクセントつけてみません?」
すかさずラメやスパンコールが入ったポーチやストールを繰り出してくるあたり、実に商魂たくましい。
上下二組だけ買って、ミオはグウィンとともに店を出た。アイスから預かったお金は結構な額が残っていて、ほっとする。
このお金は、怜佳から受けとった報酬のなかから出ている。本来受け取るべきの人のところにとどまらず、自分のために使われているのかと思うと、すっきりしない心持ちになる。おやつに使うより返したかった。
照明が頼りない廊下を歩きながら、服代をわたすときのアイスの顔を思い出した。
一瞬、笑みが大きくなったのは、受けとらせようとして表情をつくったのか、本心からの笑みだったのか……
「アイスっていつも笑ってるよね。最初はお気楽だって思ってたんだけど、爆発火災のときまで笑んでると、なんだか……」ミオは言葉を探した。
「大丈夫かなって。おかしいっていうんじゃなくて、危うい? みたいな。気持ちと違う表情を続けて、きつくないのかな……とか」
「ひとづてで聞いたんだけど、アイスが言うには、逃げられないなら楽しんでしまうほうが良い手なんだって。
でもあたしには、笑ってる空気が感じられない。笑ってるように見えてるんだとしたら、ストレスを減らすために自分を守ってるんじゃないかな」
グウィンの横顔は歩く先よりもっと奥の、ずっと遠くを見ているようだった。
「笑って他人事みたいにとらえる。そうやってヒトや事象から距離をとって、冷静に観察して、本質的能力を発揮できるようにする。最初はそうやってたのが、変わってきたんじゃないかっていうのが、あたしの勝手な憶測」
「いまの仕事、平気にみえたけど、ほんとはつらいのかな……」
「こればっかりは本人に訊かないとね。アイスとの付き合いは一〇年ぐらいになるけど、知ってることなんて、たかが知れてる。
けど、知らないまんまでもいいとも思ってる。全部を理解しようなんておこがましいし、あたしに悪いことしないはずっていう期待があるから。アイスの仕事のことは——」
グウィンの話は唐突に中断される。
ガラスが割れたような破裂音がおこった。
鋭く響いた音に、ミオは肩を跳ね上げて固まった。
まわりにいた人たちも似たような反応をみせた。音が続かないとわかると、原因を探して、あちこち首を巡らした。
そうだ、グウィンは⁉︎
はっとして振り返った隣、グウィンは床に這うように体勢を低くしていた。うかがえる横顔は強張り、じっとしている。
「グウィン……?」
「すまない! ウチの電球が原因だ、なんでもないから落ち着いてくれ!」
すぐに音の発生源から声が上がった。集まってきた人たちが、カレー屋のなかを覗き込んでいる。どうも店内に吊るしていた白熱電球が割れたらしかった。
ほっとして身体の力が抜けた。ひざまずいてグウィンの肩に手をおく。
「大丈夫だよ。電球が壊れただけみたい……グウィン⁉︎」
様子がおかしい。
ミオは姿勢をさらに低くした。伏せたままでいるグウィンの顔をのぞきこんだ。
呼吸が荒い。血の気をうしなって蒼白になった顔が汗で濡れていた。
「具合わるいの⁉︎ わたし、ど、どうしたらいい?」
慌てるミオのそばに初老の女性がきた。
「バウティスタさん、うちの店で休んでいきなさい」
そうしてミオに、
「お嬢さんはそっち側から支えてくれる? ふたりで——」
「……いい、ありがとう」
慌てるようにグウィンが上体を起こす。
「落ち着いてきたから、大丈夫」よろめきながら立ち上がった。
「ごめんね。耳が敏感だから、大きな音には過剰に反応しちゃうんだ。イダさんも、商売のじゃましてごめん」
問題ないアピールも、胸元をおさえながらでは説得力がない。それでも、
「食事を仕入れてアイスの部屋に戻ろう。そのほうが、あたしも落ち着けるから」
そそくさとイダに会釈し、振り切るように歩き出した。
あとを追おうとしたところで、イダに引きとめられた。
「本人が言うならしょうがないけど、お嬢さんからも一度診てもらうように言ってあげて。さっきみたいこと、前にもあったから」
「初めてじゃない……?」
気になることを言われたが、グウィンはどんどん足を進めている。イダに慌ただしく礼を言い、ミオはあとを追った。
「ねえ、グウィンは以前にも——」
「電球の破裂は時々あるんだよ。電力が不安定だからそれでショートしたり、間違ったワット数でうっかりつけてたりで。あ、そうだ。電球だけじゃなくて配管の下もなるべく歩かない方がいいよ。交換が追いつかないから……」
体調の急変から気を逸らさせるように、過去のハプニングをあれこれ話しはじめた。
破裂音に驚いただけとは思えない。けれど、言いたくない事かもしれないと思うと、それ以上訊けなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

