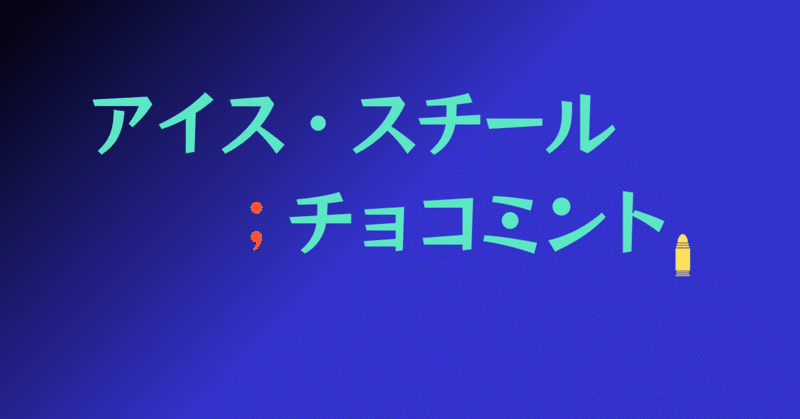
[連載小説]アイス・スチール;チョコミント 二章 2話 「大変」の基準
2話 「大変」の基準
稀有の出来事だ。
上りのエレベータに乗っていたグウィン・サントス・バウティスタは、胸中で驚いていた。
六階にとまると、ぎゅう詰めだった箱から人がどっと降りていった。残っているのはグウィンのほかに一人だけ。<美園マンション>にはよく来ているが、エレベーターを二人で使うなど初めてだった。
美園の三階より上階には、安いゲストハウスがひしめいている。格安のぶん、部屋は狭い。それだけ美園全体の宿泊人数も増え、二基しかないエレベーターは常に混雑を極めた。なのに今日のこの珍事は、良いことより悪いことがおこる前兆かと思ってしまう。
「降りるのは何階ですか?」
箱に残ったもうひとりが訊いてくれた。声からして若い男性。
グウィンが手にしている白杖を見ての配慮だ。礼とともにお願いした。
「九階です」
声をかけてくる人間には、いくつかのパターンがあった。優しい配慮、あるいはこの街の人間なら、お節介やきの下町気質。悪い場合は打算的思惑、ときに女なら抵抗が難しいという悪意から。
グウィンは白杖の石突を床につけたまま、ゆったりと持つ。この男性には警戒の必要がないように思われた。
初めて乗った人間なら不安を覚えるだろう賑やかな異音を立ててエレベーターがとまった。
「お先にどうぞ」
グウィンの視界に、エレベータのドアを押さえている、ぼんやりとしたシルエットが映った。
男性も同じ階で降りた。エレベーターを降りたグウィンの背後から、ペパーミントのシャープで爽やかな香りがついてきた。
甘い匂いも感じることから、ティーではなくアイスクリームを持っているのだろう。下の店舗フロアには、お茶やデザートまで含めた食べ物屋が集まっていた。
グウィンは歩を進めながら話しかけた。
「手伝っていただいて助かりました」
礼はいつも積極的にしていた。こうすればまた別の機会に、ほかの誰かを助けてくれるかもしれない。
「いえ、これぐらい。あの……こういうときは、おれの肘を持ってもらえばいいんでしょうか?」
「何度も来ている場所なので、誘導がなくても大丈夫です。お気遣い、ありがとう」
結局、ゲストハウスのフロントまで一緒にきた。
「じゃ、これで」
ミントの香りが廊下の奥へと遠のいていく。グウィンがこれから訪問する客と同じゲストハウスに宿をとっているらしかった。
「あ、グウィンさん」
姓のバウティスタが言いづらいからと、ファーストネームで呼ぶようになったフロント係によばれる。
「サトーさんから内線電話をあずかってるよ。部屋じゃなくて、診療所に来てくれってさ」
せっかく上がってきたのに。
このままここにいても大丈夫なのか……。
診療所の待合室で、ひとりぽつねんと座るミオは落ち着かなかった。
古臭くはあるものの所内はきれいだし、スタッフもカウンターの人も普通で丁寧だった。
けれどいま、アイスの傷の処置をしているのは看護師——。
診療所まで簡単にはたどり着けないつくりにして、看板すら出していないなんて、胡散くさいことこの上ない。
かといって、ここを出ても行くあてがなかった。ホテルに泊まるだけならまだしも、乱暴な連中が追いかけてくるかもしれないと思うと、ひとりになるのは怖い。消極的選択で待合室に残っていた。
一般的な診療所なら夜診療の時間だが、ほかの患者の気配はなかった。
静かだ。しばらくすると疲れと眠気が強くなってきた。両親の死から、普通の学生なら経験しないようなことが続いている。ずっと緊張したままで、気持ちが休まる暇がなかった。
ただ、座っているのは背もたれの低いロビーベンチだった。居眠りできるほどには、くつろげない。時間潰しにテレビでもと思ったときに、やっと思い出した。
怜佳の会社が爆発火災をおこしたあと、どうなったのか、わからないままだった。
眠気が吹き飛んだ。いっときでも忘れていたことに罪悪感を感じる。アイスの言うとおり、怜佳なら大丈夫と思い込みたかったせいなのか。
ニュースに出ているかもしれない。ブラウン管テレビのスイッチをいれた。
おしゃれなスーツを着た男性刑事が、いかにもな悪役と対峙しているドラマが映し出される。観たいのは、こんなのじゃない。チャンネルに手をかけた。
「あれ?」
つまんだチャンネルが回らなかった。少し力を加えてみる。やはり動かない。あまり力を加えると壊してしまいそうでもある。
ドラマのシーンは流れつづけ、刑事が悪役をパンチ一発で吹っ飛ばした。起き上がった悪役の顔はきれいだ。
本当の暴力はこんなのじゃなかった。
<オーシロ運送>の休憩室で、アイスがナイフ男たちとやりあった場面が、不意に脳内再生された。
肘を折られた男の悲鳴が耳の奥で聞こえる。
鉄臭いようなにおいが鼻をつく。
喉を押さえられているような違和感。
チャンネルに手をかけたまま、ミオの身体は動かなくなった。
「古いテレビだからね。回すのには、ちょっとコツがあるんだよ」
やわらかい女性の声で呪縛がとけた。手がチャンネルから離れる。
かわってミオの横からのびた手がチェンネルをつまんだ。
「少しだけ押し込んでから回してみて」
軽い音とともにチャンネルがかわった。画面が旅番組を映し出す。
「ね?」
「あ、ありがとうございます」
礼とともに振りむくと、三〇代後半ぐらいの女性に微笑み返された。
「いきなり声かけて、ごめんね。アイスから様子を見てくるよう頼まれてきたら、テレビの前で動かなくなっている人がいたから」
はたから見れば、おかしな子に見えただろう。ミオは顔に血が集まってくるのをごまかすように訊いた。
「診療所の方ですか?」
スタンドカラーで腰丈のケーシー白衣を着ている。しかしミオの視界に、休憩室にはなかったもの——おそらく彼女のものが目にはいり、疑問がうかんだ。
なぜ、テレビのまえで固まっていたのが見えたのだろうか。
「あたしは、ここのスタッフじゃない。診療所に呼ばれてくることもある整体師。アイスはお得意さんのひとりなの。で、まずはこれ」
ケーシー白衣の女性から、濡れタオルをわたされた。
「顔だけでも拭いて。気分がさっぱりするよ」
そうしてロビーベンチまで戻り、立てかけていた白杖を手にとった。
「温泉が好きなの?」
「え……」
白杖に気を取られていたミオは画面を振り返る。バスタオル姿の女性タレントが露天風呂に入っているシーンだった。
「いえ、ニュースがみたくて……っていうより」躊躇しながら訊いた。
「不躾な質問ですけど、あの……見えてるんですか?」
「うっすら、ぼんやり——というのは『見える』うちに入るのかな?」
「ごめんなさい。白杖を使っているのは、まったく見えない方ばかりだと思ってました」
「白杖があると確かめることができて、安全になるから持ってる。持つかどうかは見える範囲や、その人の考え方次第で変わってくるよ。画面が温泉だとわかったのは、タレントの台詞から。ほら、ニュースがみたいんでしょ?」
アドバイスに従って挑戦。軽い音をたててチャンネルが回った。歌謡番組、バラエティ、やっとニュース番組をみつけると、与党議員の賄賂疑惑を聞き流しながらタオルを使った。
「アイスから少しだけ聞いた。大変だったね。あなたに大きな怪我がなくてよかった」
「はい、まあ……」
女性がなめらかな動きでベンチシートにすわった。
「お腹すいてない? ニュースがおわったら一階にいこうよ。飲み物だけでも種類がいっぱいあって楽しいよ」
「……あ、はい」
返事がうわの空になってしまうは、白衣の女性の動きが、なめらかなせいだった。
イスにつまずくようなことはないし、腕時計もしている。こういったところだけを見ていると、視力に問題はないぐらいに思えた。
そうこうするあいだ、待ちかねたワードがテレビから聞こえてきた。
アナウンサーが爆発火災のニュースを読み上げる。身元不明の焼死体が四体発見された——。
怜佳と二谷が残っていた事務所に何人きたのかわからない。焼死体となっているのは誰なのか。火から逃れた人間はいるのか……
「グウィン、ちょっとお願いしていい?」
処置をおえたらしいアイスが入ってきた。ちょうどよかった。
「警察に聞きにいこうよ! 亡くなった人が誰なのか確かめなきゃ」
説明を端折って訴えた。それでも、すぐに察したらしい。見慣れてきたアイスの笑みが、すっと消えた。
「家族でなきゃ警察はおしえてくれない。確かめにいかなくたって、怜佳さんが生きていればここにくる。ミオが危険を承知で無意味な外出をする意味は? 遺産があれば殺されることはないから大丈夫だとか思わないで。殺さずに——」
「アイス!」
グウィンが鋭い声を発した。
「あなたはまず休んで。適切な言葉が使えてない」
「……そうだね。ごめん」
謝罪の表示か、力を抜いたのか。アイスは首をかくりと折った。顔を上げたとき、初対面から見ている、ゆるい笑みがうかんだ顔に戻っていた。
「ミオに食事をとらせたい。グウィンに頼んでいいかな?」
「さっき誘ってたとこ。あたしも買いにいくつもりだったから」
「このマンションから出なければいいんでしょ? ひとりで行ってくるよ」
ミオとしては気を遣ったつもりだったが、
「美園の店舗フロアにきたことある?」とアイス。
「はじめて」
「グウィン、お願い」
信用されていなかった。
フロアで迷ったとしても、建物内なら大丈夫だと思うのだが。それに、白杖を持っているグウィンに連れていってもらうというのも、なんだか違う感じがした。
「じゃ、ミオさん——でいいかな? あたしは、グウィン・サントス・バウティスタ。ファースト、ミドル、ラスト、どれでも呼びやすいネームで呼んで。さん付けとか面倒だから、ないほうが嬉しい」
「わたしの名前も呼び捨てにしてくれたら、グウィンって呼ぶよ」
年上相手にずうずうしかと思ったが、グウィンにはそれでよかったようだ。
「ところでミオは着替え持ってる?」
「ひと組もってきてたけど、もう使った。ごめんなさい、におう?」
汗もぬぐわないまま動き回っていた。
「汗じゃなくて……煤かな? このにおい」
火災現場の中にいたわけではなかったのに、嗅覚がずいぶん鋭い。
「女の子にニオイの話は失礼だけど、大変な目に遭ったときの服は、脱いじゃった方がリラックスできるから」
「じゃあ、服も買ってきたらいいよ」
アイスがポケットから謝礼の封筒をだした。
「ブランドメーカーを売りにしてる店は偽装品しかないから気をつけて。買うのは持ち運べる範囲でね」
怜佳から受けとった封筒のなかから、何枚かの札を抜き出す。
「いい。お金もってる」
「『ありがとう』の一言でもらっとけばいいんだよ。アイスに大人の見栄を張らせてあげて」
グウィンに言われて素直に従うことにする。
「あれ、お金はわたしが持つの?」
グウィンが預かるのだと思っていた。
「おつりも好きに使って構わない。当分は食べるぐらいしか気分転換の方法がないから、甘いものとか買ったらいいよ。ただし注意がふたつ。計画的に使うことと、ポケットでもバックでも、財布は身体の前で持っておくこと。でないと九割がたスられる」
「アイスの手当はもうすんだの?」
「スンさん、手際がいいからね」
脇腹の怪我のせいで少し猫背になっているアイスが背中をむけた。
「じゃあ、グウィンに甘えて、あたしは休ませてもらっとく」
「わかった。部屋はまだ変わってないよね?」
アイスが自室にしょっちゅう出入りさせている人がいるのは意外だった。いつも淡い笑みを受かべているアイスだが、相手と近しくなるための笑みではなかったから。
ミオとアイスの間で距離が縮まるような会話はまだない。会ってまだ時間がそれほど経っていないし、アイスにとってはただの契約対象だ。
当然のことと理解しつつ、少し寂しい気もする。
グウィンが腕時計の風防ガラスをあけ、針にふれた。
「八時をすぎたから混雑のピークは過ぎてる。ゆっくり店を見て回れるよ」
「針の傾きを指先で読むんだ……」
ミオは素直に驚いた。さわる腕時計があるなんて思いもしなかった。
「慣れたら特別でもなんでもないって。さ、行こっか」
グウィンが白杖を手に立ち上がった。慌ててドアへと走る。
「気を遣ってくれてありがと。でも身の回りのたいていのことはできるから、ミオがそんなに張り切らなくても問題ないよ。助けてほしいときは遠慮なく言わせてもらってる」
「正直いって、どうすればいいのかわかんないの。具体的におしえるって、わずらわしい?」
「確かに、めんどくさいなって思うことはある。でも、しょうがないってあきらめてるとこもある。いろんなことが健康な人の基準でできてるから、サポートが必要ない人が気づけなくてもしょうがないよね——って偉そうなこと言っても、あたしもこうなるまでは気づいてない人間だったんだけど」
あははと快活に笑った。
診療所をでて廊下へ。グウィンは白杖に頼ることなく歩いた。
「これも慣れ?」
「しょっちゅう来てると、身体が建物の大きさを覚えてくるから杖がなくても平気。ただ、こういうときは——」
階段の手前までくると、一段目の位置を白杖で確かめた。
「階段の踏み板が色違いだったら、白杖がなくてもいけるんだけどなあ」
そんなカラフルな階段、まずない。
「普段は歩いてる人でも病気や怪我で入院して、一時的に車椅子を使うことあるでしょ? 一〇割かゼロかだけじゃなくて、必要に応じて二割だけだったり、八割使ったり。あたしの杖もそんな感じ」
「よかったら教えて欲しいんだけど……」
「イヤなら答えない。言ってみて」
「グウィンは、どんなふうに見えてるの? 目の前が暗い感じ?」
「逆。白っぽい。濃い霧のなかにいるみたい。それで顔の前のごく狭い範囲でだけ、霧が薄い。ミオの顔まではわからないけど——」
グウィンの口元から小さな破裂音が数回聞こえたかと思うと、
「うん、やっぱり。歳のわりには背がスラリとしててカッコいいっていうのはわかる」
「カッコいいのかなあ……」
何が「やっぱり」だったのかより、カッコいいと言われたことが腑に落ちずに問い返した。
「あっ、気にしてたなら、ごめん」
「でも、わたしの身長の悩みより、グウィンの……」
「視力の問題のほうが大変そう、とか?」
「うん」
「まあ、そんなふうに思うよね」
「どうってことない」とでもいうようだった。
「大変さなんて見るところによって違ってくる。だから、身長の悩みのほうが小さい問題だなんて言い切れないかもよ? 見えないほうが楽なことだってあるかもしれない」
「えっ?」
振りむいた先にあった笑みは、苦笑といったものではなかった。悲しみもまじっているよう複雑な笑みで……
その先を訊きたいと思いながら、ミオは問う言葉を喉の奥に飲み込んだ。思わず口に出てしまっただけで、ふれてほしくないことかもしれない。
階段をのぼりきったグウィンが鍵をとりだした。
「地階から一階フロアには、ここのドアでしか出入りできない。いつも施錠されてるから、必要なときは診療所が貸してくれる合鍵を使って」
ドアを開けると、ざわめきが届いてきた。短い廊下を進んで店舗フロアに出る。
全身が活気に満ちたノイズに包まれた。
店員と客とのやりとりや、食器やイスがぶつかる音といった、それぞれでは大きくない音でも、広い空間のなかでまとめて聞くと圧倒的ボリュームになる。耳の中までもが混沌として、賑やかな喧噪に全身があらわれた。
「<美園マンション>のなかに〝世界〟がある——って言ったら誇大表現だけど、いろんな人や店が集まってる。水が合えば楽しい場所だと思うよ」
雑音に流されそうになるグウィンの声に耳を傾けていると、警備員が話しかけてきた。
グウィンが親しげに返す。と、警備員の視線がミオにもくる。慌てて会釈。彩乃に躾けられた習慣だ。いかつい顔にうかべた微笑をプレゼントしてもらって別れた。
「そこに人だかりができてるでしょ」
グウィンが的確に指をさした。四メートルぐらいの距離なら、おおよその様子がわかるようだ。
「エレベーターがすごく混むの。箱はそこそこ大きいんだけど、昇降スピードが遅いし、使う人も多いから。だからといって階段はダメだよ。昼間でもあぶない」
「さっきは階段つかったよ?」
「地階と一階のあいだは階段しかない。鍵を使っての限られた人の出入りしかないから、地上階よりは安全」
歩くペースを落としたグウィンが、先導してフロアをすすむ。
「美園には個人住宅もあるんだけど、三階からうえ十一階までのほとんどをゲストハウスが占めてる。数が三〇軒近くあるうえに小さい部屋が多いから、部屋の総数はわかんない。部屋を出るときは帰れるように工夫してね」
「慣れてないと、ややこしい?」
「慣れてても酔っ払って帰ってきたりすると迷子になるそうだよ」
「お酒飲めない歳でよかったと思ってる」
「アルコールはダメだけど、甘いものはどう? 先にデザート休憩しよう」
「食事がまだだよ?」
「大変だった日は特別。アイスクリームでいいかな?」
「好き! おすすめの店あるの?」
アイスクリームと聞くと、ミオの頭はひとつのビジュアルに占拠された。青みがかったグリーンに散った褐色のアクセント。疲れた身体が猛烈に欲した。
フロア中央、吹き抜けのあるスペースの一角に目指す店はあった。
小さな店舗には不釣り合いな大きな看板がかけられている。<エスクリム>の屋号の下は、各種アイスクリームの写真で壁が見えなくなっているほどで、周囲の店よりひときわ色鮮やかな店頭が目をひいた。
「二〇年以上続いてるんだって。フロアでいちばんの老舗かも」
「店長も古いよ。もう、トシ。腰イタイ、部屋で休んでる」
南方系の濃く四角い顔立ちをした店員が笑顔で迎えてくれた。
「明日なら様子をみにいける。電話しとくね」
「ありがとございます。店長出てこないと、わたし休めない」
店員がミオにも親しげな笑みをみせた。
「イラッシャイマセ。ドレニナサイマスカ?」
「チョコミントください」
ミオには、この一択しかなかった。
グウィンにはアイス棒みたいな平たい棒を複数、両手で広げて顔の前に出した。
「今日は、どれする?」
「じゃあ……これ」
グウィンが一本引き抜き、店員にわたす。
「おー、これは」
棒の先を見ておかしそうに笑う。きょとんとしているミオに向けて説明した。
「グウィンさん、アイスクリームでロシアンルーレットやる。棒にメニュー書いてある。なに当たるかグウィンさん、わからない」
そうしてオーダーを用意しながら念を押した。
「残す、ダメ。お金、倍とるよ」
「うわぁ……今日はついてない」
店員の反応から、どれが当たったのかわかったようだ。このリアクションは、好きではないメニュー。コーンに入ったアイスを手渡されて、眉を八の字にした。
「カレーアイス引いちゃったか」
「カレー、唐揚げ、ハンバーグの、あのカレー?」
「ミオのたとえはよくわからないけど、スパイスを調合してつくる、あのカレー」
「カレーをだす店が多いから人気メニューなんだと思うけど……」
アイスクリームにまで使わなくても——とまでは売っている店のなかで言えない。
「香辛料とアイスクリームの組み合わせはありなんだけど、カレーとなると微妙なんだよなあ」
「う、うん……あ、お金」
自分の分の代金を出そうとしてグウィンにとめられた。「ここは、あたしのオゴリ」
そうして財布から折りたたんだ札を定員にわたした。
ミオは、代金にあった少額紙幣を迷いなく出したグウィンが不思議だった。どうしてわかったのか。
グウィンを見ていると、わからないことだらけだ。もうひとつ、訊いてみた。
「苦手なものが当たるかもしれないのに、どうしてクジ引きスタイルなの?」
アイスクリーム片手に、狭い店内にあるミニサイズのテーブル席に身体をすべりこませる。
「ロシアンルーレットみたいなゲームにしたら面白いかなって。苦手なものが当たるかもしれないなかで、好きなものだったら余計に嬉しいじゃない?」
「そう……なの?」
見えないことは不便しかないと思っていた。けれど、逆にそこを利用して遊んでいる。たくましい。
「最初はジェラートパンを直感で指して注文してたんだけど、何度もきてるうちに、どの位置に何のアイスクリームがあるか覚えてきちゃって。そしたら店長が、さっきの棒をつくってきたの」
「親切な人ですね」
「ちょっと違うな。〝貸し〟をつくろうとするんだよ。強引なギブアンドテイク? 人に親切にしたら、そのうち自分の得になって返ってくるのを期待するっていう」
カレーアイスを不味そうに食べながら、楽しそうに話す。
「じゃあオゴってもらったわたしは、グウィンに貸しをつくったことになるんだ」
「わかってるんなら話がはやい。早速返してもらおっかな」
爽やかな笑みを添えられて、ミオは思わず頷いてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

