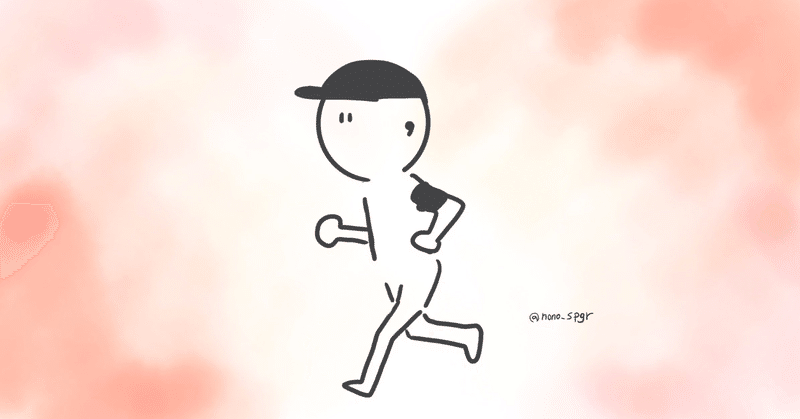
脳卒中後遺症者における身体の自己管理
対象者の方々から,どのような自主訓練がありますか?
どのように身体を管理すればいいですか?
これらの訴えは普段から治療場面でよく聞かれる内容です.
何をすればいいのか?
発症から数日の方では,もっと動かしたらいいのかと努力される方もいれば,
発症から数年経過した方では,歩くときに麻痺側の足が内側に曲がってくることが増え,歩くにくくなった,歩くときの見た目(歩容)が気になるからと自己身体の変化について話される方もいます.
それらの多様な訴えのなかで共通していることは,
自己身体への関心,
自己の身体に対して期待をこめているということです.
脳卒中の場合,急性発症となりますから,
つい先ほどまで動けていた身体,感じている世界がこれまでとは違う感覚世界に転換し,
心身ともに不安定な状態となることが想像できます.
先ほどまでに感じていた世界と目が覚めて感じている世界とのギャップ.
場合によっては,その狭間に自己が時間的に追いついていないこともありますので,発症前の自己イメージと運動による記憶が運動行動に影響も与えます.
対象者が後遺症の影響によって,
家庭での日常の営み,仕事や社会活動に向けた未来に対する不安,
なんでわたしがこのようなことにといった後悔しようのない過去,
そのような過去と未来に目を向けてしまうことも多く感じます.
臨床場面で自己管理を提示するときに難しいと感じることは,
今,現在の時間的空間的な知覚経験が思考のなかで省略されてしまうと,
自己身体の些細な変化を識別することに自ら制約をかけてしまうことに陥りやすいかもしれません.
前回,靴下の着脱をやりとりした症例さんでは,
麻痺している脚が持ち上げられないと自己身体を客観的に捉え,これからの生活行為に不安を抱えていました.
そのため,麻痺している身体が自己であることを前提にし,治療場面でも身体の変化を認めることに抵抗しているようにも感じられました.
わたしは作業療法士として,その多くの部分が対象者の知覚と運動の機能にかかわっています.
対象者が,たとえなんらかの障害は残していても,日々の日常をより不自由感なく,心身ともに落ち着いて過ごせるように援助することが主な役割です.
ここでいう知覚と運動の機能とは,生活行為の目的がいかに遂行,達成するために身体を適切に環境と相互交流しながら働かせられるかという能力のことを指します.
ですから,症例さんとは治療場面のなかでテーマとして掲げた靴下の着脱行為を実現し,
ご自身の身体管理の意味も含め,
日常の生活行為として再現できるように援助工夫を検討する必要があります.
この症例さんとは,些細なことからその変化に注意を向け,それを認めていくような自己の変化に気づくことからやりとりをしました.
今,現在の自己に対してです.
今,現在の自己には身体保持感と運動主体感というキーワードで研究がなされています.
身体保持感とは,自己身体が自身のものであるという意識であり,身体の感受性から生起する自己感を指します.
つまり,「今」といった身体化された自己です.
一方,運動主体感とは,自己の運動を実現しているのはまさに自身であるという意識であり,身体の運動性から生起される自己感を指します.
つまり,意志と目的を伴う運動によって私たちの知覚経験は変化し,
今実行している行為は他の誰でもない個人の視点で運動主体感が沸き上がります.
それが,自己の変化として自己意識が更新される大切な要素であると考えています.
自己の変化は,自己の身体や環境を通じて生成される相互依存関係に基づいています.
そのため,脳卒中により生活行為の遂行に困難性を抱えるということは,
自己身体を通じて,自己身体そのものや環境を知覚することに制限されている可能性を踏まえる必要があると考えます.
そのため,片麻痺者の身体の自己管理には,その生活行為において何を手がかりにその行為が生成されているのか,知覚情報の抽出を明確にしておくことが大切です.
例えば,麻痺によって傾いた姿勢をみたとき,
こちらが観念的に,身体イメージが崩れている,真っすぐという体軸が傾いている,もしくは麻痺した部分に力が入らないからといったネガティブな評価はしません.
そうなると,今抱えている傾いた姿勢に対して,問題解決の手がかりが見い出せないからです.
中枢神経系は,姿勢を保持するために重力を基準にして身体のなかで力のつりあいをとり,その対象者の姿勢緊張の状態から結果的に傾いていると考えます.
つまり,姿勢保持という課題を達成するために機能した結果として捉えます.
ですから,そのような場合のかかわりは,重量方向を知覚し,環境から受ける床反力や身体にかかる重力の感覚変化によって身体バランスを調整していくように援助します.
身体の自己管理で意図していることは,
知覚と運動の機能の改善,
できなかったことができるように,
困難で努力を伴うものをより円滑に変化させることです.
身体運動では,意志と目的に基づいて努力することに加え,運動の認識が必要と考えます.
これは,運動の形態を真似ることではありません.
視覚的なイメージをもって運動の形態を再現するのではなく,
自己の内的な運動感覚,環境から受ける抵抗感の変化に基づいて,なんらかの目的志向に運動が組み込まれるという配慮が必要と考えます.
例えば,立ち上がることが大変なら,何か必要なものをとるために立ち上がるといった目的課題のなかに立ち上がるという動作が組み込まれるということです.
ご本人が難しく感じたり,他者からみて難しそうに見える動きは適切な姿勢運動パターンではない可能性があります.
意志による意識的努力の必要性を極力少なく,
運動を知識に頼るのではなく,
自己内部と環境との関係で生じていることに注意を向け,
感じとる感覚的なやりとりを治療場面で実現し,
再現できたことを自己管理として提示する工夫が私たち療法士には求められるのではないかと考えています.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
