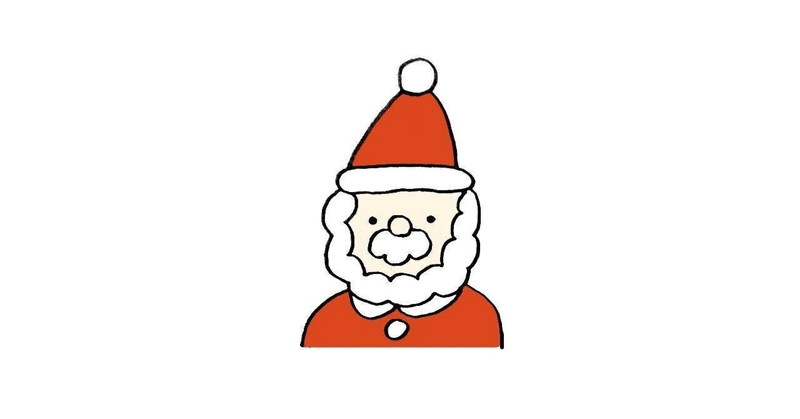
12月30日のクリスマス
12月28日に仕事を納め、昨日地元へ帰ってきた。
見慣れた、でも看板が変わっていたり新しいお店ができていたりする、風景に染み入る。あかい陽に照らされ撓んだ空、真ん中がもうすぐ海についてしまいそう。
各駅停車でも2時間で帰ってこられるくらいの距離だけど、やっぱり“地元”というのは特別だ。生まれてからずっと同じ町で育ててくれた両親に、感謝している。
うっかり東京の鍵をさしてしまい、ああ間違えたとさし直した。
「ただいまー」
「おかえり」
言うことも言われることもすっかり減った、今の生活にはないセリフが、このドアを開けばすっと出てくる。これが実家なんだと思う。
リビングにプレゼントが置かれていた。同じショッパーが2つに紙の包みが1つ。私と妹、弟のだ。意識的に声を弾ませ、母のほうを振り返る。
「えー今年も届いたの?」
「ね、いい子だったんだね」
友だちからは「小3の時、いないって言われた」とか「10歳からサンタさんじゃなくて親からのプレゼントになった」とか聞く。子を持つ同僚も「もう信じてないですよ」と言っていた。
やっぱりうちは変わっているんだろうと思う。母は今日までずっと「サンタさんはいる」を貫いているのだ。今年も例年通り、3人分用意してくれていた。
★
私が15歳の頃、父さんが亡くなった。貧しかったわけではないが、母はそれまで専業主婦、まだ中学生・小学生の私たち。家計も、10年以上ぶりに働き始めた母のことも心配だった。
それなのに母は、毎年変わらず「サンタさんに手紙書かないの?欲しいものないの?」と聞いてくる。そのたび私の中で、言葉にならないフラストレーションがふつふつ沸いた。のんきなのか無理しているのか、どっちにしろ嫌だった。
一度、ガールフレンドに話したことがある。彼女は一言「お母さんがかわいそう」と言った。「乗っかってあげるのが子どものやさしさだよ」と。
声が出なかった。ふんわり巻かれた毛先が、風にあおられ目にかかる。払う彼女の手を眺めながら、そんなこと考えたことなかったなと思った。早く大人になろうと背伸びしてばかりで、母と目線があっていなかったことに気づいた。
さみしくさせていたのかもしれない、私が父さんの代わりになろうとすることなんて、母は望んでいないのかもしれない。初めて立ち止まれた瞬間だった。
★
弟もはるばる帰省して、久しぶりに家族が揃った。誰ともなく言い出す「早く開けようよ」。
私は24、弟は22、末っ子も20歳だ。本当はみんなとっくにわかっているけれど、誰も「母さんでしょ」なんて言わない。
3人並んでワイワイ開封する。その時間がギフトだって、きっと弟も妹もわかっているから。
家族全員集まれた今日、12月30日こそが、わが家のクリスマス。
お読みいただきありがとうございます。 物書きになるべく上京し、編集者として働きながらnoteを執筆しています。ぜひまた読みに来てください。あなたの応援が励みになります。
