大聖堂
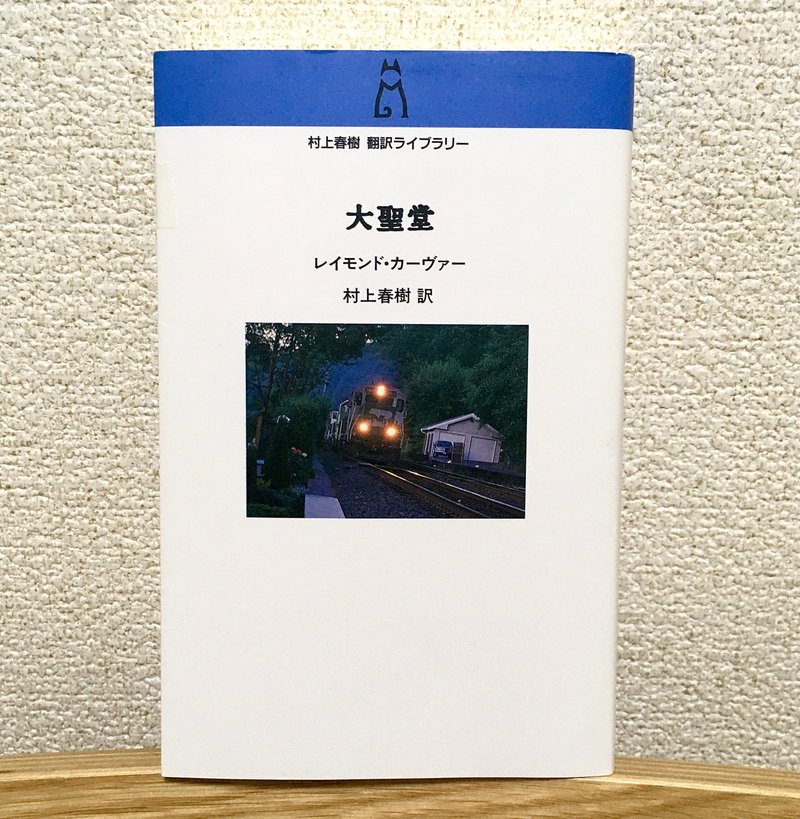
序文(著者の妻、テス・ギャラガーによる)が印象的。レイモンド・カーヴァーの『朗読』についてのこと、話は悲劇なのになぜか聴いて笑ってしまうとか、笑い声が大きすぎて途中で朗読が中断される、とかそういったエピソード。そこにある喪失のいたましさの表れ方がきわめて大胆かつ率直であったせいでそうなる、とある。
70年代、80年代にかけて色褪せたアメリカン・ドリームについて、訳者の言葉を借りれば「アメリカという幻想の共同体からのfailure(フェイリャ=失敗者)」についての短篇集。仕事にあぶれた人、再就職する気がない人、離婚した人、子どもをなくした人、アル中になった人、逃げるように居を転々とする人…、そういった人たちばかりの話。
僕(誠心)が好きな話には「フィジカルの変容」がある。落ちていくときも救われるときもメンタルの前にフィジカルがある。途中からそんな視点で自然と読むようになっていった。
僕の好きな短篇ベスト5は
①ささやかだけれど、役にたつこと
②熱
③ぼくが電話をかけている場所
④大聖堂
⑤ビタミン
やさしく見守る人が登場する話なのかな。
『熱』では、主人公の妻が同僚と駆け落ちして出ていき、2人の子どもを男手一つで育てる。ベビーシッター探しに苦労したり失敗したりするのだが、スーパー家政婦とめぐりあうことができた。この方、とてもすばらしい。
一方、ちょこちょことおせっかいのように電話をかけてくる妻(元妻?)がなんだかおもしろい。それなりのことをそれなりの論拠をもって説いてくる(笑)「熱が出たときは何かのメッセージなのよ。日誌つけなさいね」とか言ってくる。「こいつ(妻)狂ってやがる」、と言いながらもその電話を受け続けるまじめな主人公。子どもともしっかり接している。なかなかマトモな人。ちょっとかわいそうにも思えるがきちんとフィジカル変容していことには救われる。
『ぼくが電話をかけている場所』は、いわゆるアルコール中毒者の療養所の話。ここのフランク・マーティン所長がとてもやさしい。療養者であるJPの妻ロキシーも、いろいろあったとはいえ、面会の際にみせるカラっとした明るさが良い。こういうのってアメリカのお話って感じがする。
JPとロキシーは煙突掃除の仕事がきっかけで知り合うのだけれど、JPは幼少期に井戸に落っこちて閉じ込められる経験をしていて、このへんは訳者(村上春樹)の話を想像させる。あと、フランク・マーティンさんがジャック・ロンドンの話を持ち出すけれど、このへんはカーヴァーさんがロンドンさんの生命力みたいなものに自分を重ねていたのかな…と思う。ジャック・ロンドンが持ち出される話といえば「アイロンのある風景」ってのもありました。
『ビタミン』は、ビタミン・ビジネス(サプリメントの訪販みたいな)とその凋落が描かれていて、当時のセールス・トークや、なぜ売れなくなったんか、みたいなところが興味深かった。これはfailureだらけの話。ビタミン・ビジネスに燃える妻とその組織戦略。当時はどんなんだったのかな。
しかしなんといってもフィジカルの変容としては表題作の『大聖堂』でしょう。
レイモンド・カーヴァーをはじめて読む方に、この短篇集をおすすめします。
(『Carver's Dozen レイモンド・カーヴァー傑作選』もおすすめ)
*****
この短篇集、なんだか読み終えるのが寂しかった。
僕もカーヴァーさんの朗読会に参加してみたかった。
最後に、序文『夢の残骸』より引用します。
中期から晩年にかけてのカーヴァーの短篇に絶えず姿をのぞかせることになったもうひとつの要素は、そのユーモアである。最後に北西部で朗読会を行った時、彼が『象』を朗読したシアトルの小さな書店は聴衆でごったがえしていたのだが、笑い声があまりに大きかったので、彼は何度も朗読を中断しなくてはならなかった。時折シャイな微笑みを浮かべつつ目を上げ、自分も笑い出してしまいそうになるのを抑えて、先を読み進もうとしていた。でもそれと同時に、その頃の彼は息をするのもつらくなっていた。だから、彼はそのような人々の熱中ぶりからエネルギーを引き出してもいたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
