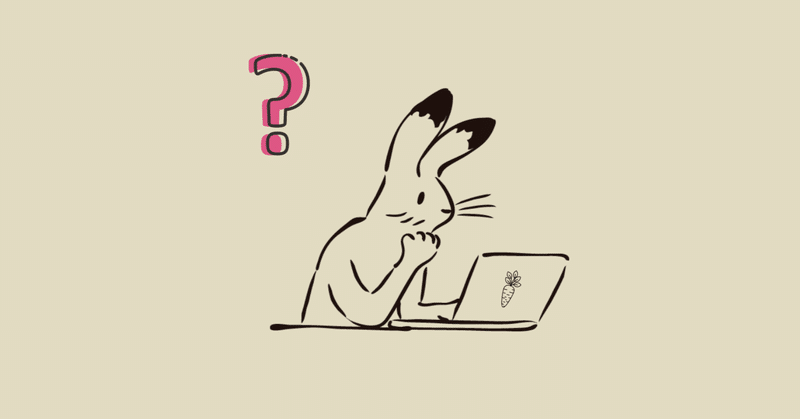
お寺のDX:書き起こし編
DXの意味が誤解されていることが多い昨今、仏教会でもDXを推進する動きが専門誌などや実際のお寺の声でも聞こえてくる。
ただ、「それはDXの定義から外れてるなぁ」ということも実際には横行しているけれど盛んにメディアや業者から「お寺もDXですよ」と言われると耳を傾けたくなる気持ちも分かる。
ではDXとはなにか?は別の話で書くとして、今回はDXを実施したい寺院が避けて通れない「現在帳・過去帳デジタル化のための書き起こし」について。
現在帳・過去帳の書き起こしは課題として感じつつもなかなか進まず、かといって業者に依頼するのも憚られる。といったお寺も多い。
当社も積極的に受けているわけではないが、支援しているお寺がDXを進めるにあたり必然的に遭遇する問題。
そんなわけで、過去帳のデジタル化のために書き起こしの依頼をいただくことがあり、今も絶賛対応中で来月まで依頼が埋まっている。
そんな中で、感じていることを書き留めたい。
この作業をしていて聞こえてくるのはお寺が過去帳の書き起こしを一般的な書き起こし業者に依頼すると漢字間違えや書き起こせない文字が膨大で惨憺たることになるらしい。
ということ。
実際に、当社も過去帳の書き起こしを受けるにあたって個人情報保護管理がしっかりしている企業に相談したこともあるが、シュミレーションの段階で先方の戸惑っている様子(過去帳とはなにか?戒名の漢字に読めないものが多いのはどうしたらいいか?現在帳名簿と過去帳名簿が噛み合わない点はどうしたらいいか?など)が伺えたし、価格も安くはなかった。
このことから当社は自社内で管理・統制できる範囲で現在帳と過去帳の書き起こし作業を請け負っているが、当社は過去そんなこともなくむしろ感謝していただいており、これはなんの違いだろう?と考えて思うのは、2つある。
1つは一般の会社は
常用漢字慣れ
デジタル慣れ
していることだろうと思う。
今の社会人のデスクワーカーの多くは多様な漢字に触れる経験が少なかったり、デジタル化に慣れてパソコンのデジタル文字ばかり見て、早い時間軸の中にいると漢字への意識が下がり、漢字の細部がデジタルだと潰れてしまうこともあるので文字の細部まで意識を向けるのが難しい風潮さえある。
もちろんこちらが特殊な業界なので追加で費用を払えば慎重に実施してくれる企業もあるが、そうなると本山や大きなお寺、会員が多いお寺ならいざしらず、町のお寺では手が出にくい0が一つ増える金額を提示されることも珍しくない。
例えば私の苗字の邊は取引先の一般企業やIT系の方はかなりの確率で邉に間違える方が多いけど、この業界の方にはほぼ間違えられたことがないのが良い例だなあと思う。
(間違えられても慣れっこなので私は不快に思わないというかむしろ申し訳なく思うけど、間違えない人にはなにやら感心してしまう。笑)
私の10代は文学にどっぷりで、しかも古典好きで古事記の研究をしたり、源氏物語の原本を草書体で書き写すという謎の経験をし、大学は古い論文を読んだり、自分も書いたりしていたバックボーンを下地にこの業界に21歳で入ったので戒名や俗名の旧漢字への識別能力がどうやら高いと気づいたのは最近のこと。
同僚たちも、戒名や俗名の一文字違いがご家族を不快にさせることを承知しているので法要受付や位牌受付を通して、文字への識別能力は高いものがあると思う。
このことから、現在帳と過去帳で同姓同名だけど漢字違いがあればどちらが正か確認したり、読めない漢字はお寺に確認するなどできるだけ丁寧に実施している。
また、文字の問題にとどまらずデータ自体をどのように書き起こしていけば将来的に価値あるデータになるのか?このタイミングでどんな情報も追加すればいいのか?などアドバイスしつつお寺と協力してデータ化していく。
そんなことをしていると、「本当にこの金額でいいの?」とお寺がびっくりしてくださることもあるが、当社としては書き起こしは支援の1つであって主力事業ではないので、赤字にはならないように利益がでるように計算したうえで、提供しているので問題はない。
ただ、このレベルになるまでのスタッフの教育も容易ではないので相変わらず対応できる数は限られるのは課題。
冒頭の
これはなんの違いだろう?
に話を戻すと、2つ目は
一文字をデータとして見るのか?そとれも言の葉のとして一つ一つに意味や命を感じられるか?
といった感性の問題は大きいなのかもしれない。ということ。
俗名は親や親類縁者が子に祈りを込めて与えた名前。
戒名は僧侶が仏様、当人、家族いろんな視点を含めて授ける生き様や祈りを込めた名前。
そんなことを念頭に、万葉集で「言霊の幸ふ国」と言われたこの国で言葉の多様さが失われてる弊害を感じつつ、一文字一文字と丁寧に向き合っていきたい。
また、
お寺にとってどのようにデータをまとめていけばいいのか?
といった視点も欠かせない。
依頼をうけた用紙をただ文字起こしするだけではなく、お寺が将来的にこの情報を生かしてどのように運営していくのか?といった視点を寺院の運営に理解をもってアドバイスできるかどうかはとても重要だと思う。
当社の場合、文字起こしをしたデータを開発している「クラウド管理 寺務台帳」に入れてその後の運用支援を行っているのでその視点は絶対に外さずに書き起こすのは当然でもある。
目をしょぼしょぼさせながら今日も書き起こしに励んでいる仲間に感謝しつつ、引き続き、地域や檀信徒から「ありがとう」と言われることが多いお寺を増やすために精進していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
