
【ニッポンの世界史】#31 学習参考書と世界史:なぜ世界史は「暗記地獄」化したのか?
これまで私たちは、「ニッポンの世界史」は、アカデミズムや学習指導要領のような“公式”世界史と、それらと対抗関係にある“非公式” 世界史の綱引きによって形成されてきた経緯をみてきました。
“公式”の語りを、“非公式”の語りが突き崩すといっても、両者の間に厚い壁があったわけではありません。
ときに、ひとりの書き手が、両者を行ったり来たりすることもみられました。
歴史学者の土井正興(1924〜1993)がそれにあたります。
土井正興: スパルタクスの研究者から教科書執筆者へ
土井は経歴法政二高教諭を経て、専修大学で古代ローマ史のスパルタクスの反乱の研究にたずさわった研究者(著書に『スパルタクス反乱論序説』『スパルタクスの蜂起』『古代奴隷制社会論』など)。
スパルタクスは当時はマルクス主義の理論において「階級闘争」を象徴する人物とされ、その反乱は「奴隷の階級闘争」とされており、土井もそのパラダイムのなかにありました(現在では反乱には自由人や農民も参加していることから、単純なマルクス主義的解釈は成り立たないという見方が主流です)。
そんな彼は1972年に三省堂の教科書執筆に携わっています。
検定に通った教科書というと“公式”的なものと思うかもしれませんが、土井の関わった『新世界史』(1972)当時としては意欲的な構成をとっていたことで知られます。

古い教科書の目次。
— みんなの世界史 (@minnanosekaishi) February 15, 2024
三省堂『新世界史』(土井正興、小倉芳彦、阪東宏、小島晋治著)昭和51(1976)年初版、翌年再版発行
1500年で世界史を前期後期に分ける山川とは異なり、三省堂の土井は19世紀までは文化圏別に一気に学ぶ構成をとった(この思想は78年度指導要領に採用されることに) pic.twitter.com/HifSDKvUvs
このように、土井らの『新世界史』には文化圏学習の範囲を18世紀まで引き下げ、19世紀に世界史が転換期を迎えたとの見方をとる点に特徴ありました。

なおその後、この『新講世界史』のとった、文化圏を18世紀まで延長させる構成は、その後1970年度版学習指導要領をマイナーチェンジさせた1978年度版学習指導要領にも採用されています。 ここでもまた”非公式”世界史のほうが、”公式”世界史に先んじていたのです。

しかし、土井の仕事は教科書執筆にとどまりません。
今度は媒体を変え、学習参考書の執筆にとりかかるのです。
学習参考書がつくった「ニッポンの世界史」
世界史の学習参考書は、科目世界史が設置された直後に多くの書籍が執筆され、教科書検定制度が整う以前は、それらが事実上教科書としての役割を担いました(「準教科書」と呼ばれます)。
その後、受験戦争の到来とともに、過去問、問題集、総整理、レファレンス用の辞書や資料集、年表、歴史地図など、さまざまな種類の「学習参考書」が刊行され続けます。
当時の受験参考書は、大学教授によって執筆されることが一般的でした。たとえば、東海大教授で世界史研究所所長でもあった吉岡力の『世界史の研究』(旺文社、1949)、有高巌『世界史精講』(池田書店、1956初版)は幾度も版をかさねるベストセラーとなりました。




これら参考書は版を重ねるなかで、その構成もアップデートされていきます。
たとえば吉岡力『世界史の研究』は、1967年の9訂版で4編16章に構成を改め、数年後の1970年度学習指導要領で採用された文化圏学習を先取りしています。

"非公式"世界史が、"公式"世界史に先行する。この事例をみるだけでも、学習参考書を「ニッポンの世界史」の検討から外してはならない理由は理解していただけるでしょう。
斬新だった『新講世界史』の構成
そんな中、1976年に発売された土井らの学習参考書『新講世界史』は、これら既存の参考書とは一線を画する斬新な構成によって大きな話題を集めます。
ページをめくると、これまで世界史とりあげられることの少なかったオセアニアがいきなり冒頭に掲載。
さらにアフリカの章においては、たとえばエジプト文明をオリエントから切り離して掲載する新しい試みが採用されました。

こうした”マイナー” 地域を詳細に記述しすぎると、教科書検定で「細かすぎる」と不許可の烙印をおされてしまう。教科書執筆にも関わった世界史教員鈴木亮の述懐によれば、教科書検定にあたって「西ヨーロッパについては、書かないともっと書くようにいわれる」のに対し、「朝鮮やベトナム、東南アジア、中東、中南米、アフリカ、太平洋などのこと」は「くわしすぎる。そんなに書く必要がない」とされたのだといいます。あえて媒体をうつしたのは、検定に縛られることのない自由な記述を学習参考書でなら実現できると考えたからでしょう。
一方、時代区分をよく見てみると、18世紀まで各地域縦割りの文化圏学習の方式をとった『新世界史』(1972)と異なる方式であることがわかります。
まず、世界史に2本の線を引き、3つのパートに分ける。
1つ目は「前近代における諸地域の動向とその歴史的展開」として、ヨーロッパ、西アジア、内陸アジア、インド・東南アジア、東アジア世界、太平洋、アフリカを学習する。
2つ目は 「大航海時代」に始まり「帝国主義の形成」にいたる、ヨーロッパの進出と諸地域の対応をみていく。
そして3つ目は、「ロシア革命」を境に、いかに「人民大衆」が民族解放・階級闘争をすすめているかをみていきます。
特に3つ目の考え方には、当時の世界の状況が反映されています。1973年の第4次中東戦争、1975年のサイゴン陥落など、世界では刻一刻と、ヨーロッパの支配をうけていた人びとが「闘争」を続けている。
しかし、日本の高校生の世界に対する関心は、上の世代にくらべ、格段に薄まっている。そこで、ヨーロッパによって世界の人びとが従属させられていくプロセスを学ぶ構成をとることが必要なのだと考えた。
そこで、19世紀を画期とする『新世界史』と異なり、「大航海時代」を世界史の画期ととらえる構成がとられました。
つまり、ヨーロッパが非ヨーロッパを支配する起点として大航海時代をとらえ、その支配の終焉の鐘の音が、ベトナム戦争(土井は「ベトナム革命」と呼びます)のアメリカの敗北とともに、高らかに鳴り響く。まさに今、1970年代半ばに、世界史の構成が刷新されつつあるのだという世界観です。
土井が構成を重視していたことは、参考書の序に「世界史の構成について」という1章を設けていることからもうかがえます。
ある意味、クライマックスに「ベトナム戦争」を位置付けるための構成であるといっても過言ではありません。

吉田悟郎による批判
マイナーであった地域をとりあげた大胆な構造は、受験生というよりは、当時の研究者や現場の教員によっておおいに注目されたようで、当時の教育雑誌には、編著者の寄稿や書評が踊りました。
一方で、アジア・アフリカ・ラテンアメリカの民族闘争を、社会主義の勝利という世界史の目的にの一環としてとらえる叙述方法には批判もみられました。
たとえば、上原専禄の流れを汲む吉田悟郎が、その急先鋒でした。
吉田の主張はこうです。
土井はいささか社会主義的な「公式」や「法則」に世界史を当てはめすぎているのではないか。
世界史を学ぶ日本の人々含めた多様な主体を「人民」や「階級」とくくることによって、多彩な生活実感や複雑な生活意識をとらえそこねてしまうのではないか。
以前みたように、世界史構成(=史像)を再構成していくことの必要性を早くから提起していた吉田は、世界史を構成する作業には(1)構造や内容の面と、(2)視点や立場、方法といった姿勢の面の2つがかかわると指摘。
土井には(1)はあるが、(2)が不十分だとします。
すなわち、吉田も参加した『日本国民の世界史』で、上原専禄がうちだしていた、日本人が自分の生活実感や切実な生活課題を通して、世界とのつながりを追うことで立ち上がってくるような世界史認識が欠けているのではないかといいます。
また吉田は、先史時代に世界史の起点を置くことにも疑義を呈しています。人類史の起点がすなわち世界史の起点ということにはならない。ある切実な問題について、その根となる起点を、世界史のなかに主体的に求めていくことこそが大切なのではないかというのです。当時、長い目で世界史をとらえる時代性が芽生えていたことについて第29回で述べましたが、こうした人類史的な世界史観に対する批判的な目は、上原専禄譲りのものでもあります。
「人類史」的世界史に釘を刺す上原専禄(『日本国民の世界史』1960年より)。 pic.twitter.com/HthL04RCuU
— みんなの世界史 (@minnanosekaishi) January 12, 2024
まとめると、吉田の主張は、世界の「人民大衆」に注目するだけで、自分たちの世界史認識を示したことになるという認識には不足がある、という点にあります(吉田「「世界史の深さ」—土井正興『世界史の認識と民衆』をめぐって」『世界史の方法』青木書店、1978、102−116頁)。「問題構造に則して歴史的現実があるのであって、「客観的な発展法則」というものに則して歴史的現実があるのではない」というわけです(同、112頁)。
この立場を吉田は、端的に次のように言い表しています。
自国史と世界史が関連しあっているのだということをお互いに感じ合う、目を開き合う、論じ合うということが大事です。結びつくのだということを急がないことです。(80頁)
歴史批評・歴史対話・歴史創造
1970年代に土井と吉田のあいだに起きたこの論争にこれ以上立ち入ることはやめにしますが、この論争には「世界史がわかる」とは何か、「世界史の構成」はどうあるべきかをめぐる対立点を浮かび上がらせたことに意義があるとともに、研究者・世界史教育者の中での出来事ではあるものの、参考書や教科書をまたいで、互いの世界史の構成を批評しあう文化が息づいていたことを、ここにみることができます。
土井にとっての世界史は、現代の世界にのこる不公正が、いかに歴史的につくられたものであるのか、そしてその路線は、人々が願えば修正することができるのだと、気づかせるためのものでありました。
だからこそ、従来の世界史では陰に隠れがちであったマイノリティに注目していったわけですし、近代批判という点では、これまでみてきた1970年代の時代精神とも合致するものでした。
すでにフランスではミシェル・フーコーが、権力関係の網の目の複雑さについて指摘し、無意識レベルで主体の振る舞いを規定し社会を形成している不可視の構造への注目もはじまっていました(構造主義)。
それに比べると土井の構想は、抑圧し、搾取する側としての権力者と、虐げられ抵抗する側の被支配者という二元論的なもので、吉田がいうようにどうしても図式的な次元にとどまるものといわざるをえません。
他方でもちろん、物質的な豊かさが国民的に広く享受されるように、ポストモダニズムに足をつっこみつつある時代性の中で、歴史を認識する確固たる「主体」を確立させよという吉田の主張も、次第に説得力が失われつつある状況であったことはいなめません。
とはいえ、ここに観察できるのは、土井の立てた世界史の「構成」に対し、それをそのまま受け入れるのではなく、その「構成」がどのような「世界史認識の動機・発想(理由)」に基づいているのか吟味し、互いに確認し合おうとする姿勢です。
2010年代以降の世界史教育に大きな影響を与えている世界史教員・小川幸司の提唱する「世界史実践」の6層構造の、第4層から第6層と、深く交わるものではないか。小川の世界史実践のなかに、吉田の世界史実践が脈々と流れ込んでいるのではないか、と感じるゆえんであります。
1【歴史実証】
問題設定に基づき、諸種の史料の記述を検討(史料批判・復元・解釈)することにより、問題設定に関わる「事実の探究」(確認・復元・推測を行う。
2【歴史解釈】
事実間の原因と結果のありよう(因果関係)やつながり(連関性・構造性)、そして比較した時に浮かび上がること(類似性・相違性)について問題設定に関わる仮説を構築することにより、「連関・構造の探究」を行う。
3【歴史批評】
その歴史解釈について、より長い時間軸やより広い空間軸においてみたときの意義や、現代の世界に対する意義について、「意味の探究」を行う。
4【歴史叙述】
歴史解釈や歴史批評を論理的・効果的に表現する「叙述の探究」を行う。
5【歴史対話】
以上の営みについて事実立脚性と論理整合性に基づいて検証を重ね、特に歴史実証の矛盾や歴史解釈の矛盾のうえに歴史批評や歴史叙述が行われていないか、歴史批評や歴史叙述のありかたが歴史実証・歴史解釈を歪めていないかなどを、他者との共同によって考察することにより、「検証の探究」を行う。
6【歴史創造】
歴史を参照しながら、自分の生きている位置を見定め、自分の進むべき道を選択肢、自らが歴史主体として生きることにより、「行為の探究」を行う。
アファーマティブアクションの招いた暗記地獄?
最後に、土井のようにマイノリティに着目することが、かえって「覚えるべき受験単語」を増やすという思わぬ結果を招いたのではないかという点についても指摘しておきましょう。
『新講世界史』冒頭の扉には、次のように述べられています。
現在の学校教育であたえられている世界史の知識は決して十全なものではない。未来を展望して、現在を生きるために、必要な重要な問題が欠落している場合が少なくない。本書では、そうした点を補うための努力を、執筆者の力量の許すかぎりにおいてしたつもりである。
要するに、アジア・アフリカ・ラテンアメリカの時代となる来るべき世界を生きていく上で、それらの知識を増やすことが必要だ。
にもかかわらず学校では追いついていない。
知識を拡充すべきだ、ということを言っている。
アフリカ、オセアニア、アメリカの執筆を分担した共著者の吉村徳蔵も「私にとって、私自身の世界史からすっぽり抜けおちていた空間が、いささか埋められた感じです」と述べています(『歴史教育研究』60、1977、34頁)。
ただ、それを崩すために、それまで手薄だったアフリカ、東南アジア、オセアニアが加わったとしても、西洋史や中国史分野の詳細さが放置されたとすれば、全体としての用語数は増えるばかりです。
そして実際にそうなってしまった。では、西ヨーロッパに関する記述量を減らせるかというと、そうはいかない。地域バランスをとろうとしても、結果的にアフリカやアジア、太平洋の用語を増加させて終わってしまう。もちろん、批判者の意識は「用語をおぼえさせる」ことにはなかったわけですが、結果的に非西洋地域の「アファーマティブ・アクション」が、かえって受験生を苦しめる結果となってしまう難しさが、ここにありました。
これはひとえに、用語の数を規制する「世界史」の理論がいまだに不在であったからです。
そもそも日本の科目世界史は、「世界史学」が不在であるという指摘(『世界史の可能性』)からスタートしました。プロパーあって、学問なし。いったいどのような構成を描けば、世界史という枠組みを仕立てることができるのか、国内外の構想に影響されながら再定義を続けてきたわけです。
用語をどう精選するか?
この状況、とくにヨーロッパ中心主義的な世界史をなんとかしなければならないということは、土井も考えていたことでした。
『歴史地理教育』275号(1978年3月)の「世界史像をめぐって」という論文の中では、世界史に関する「基礎学力」「基礎事項」をとりあげることが大切だとして、用語の見直しの方向性について次のように議論しています。
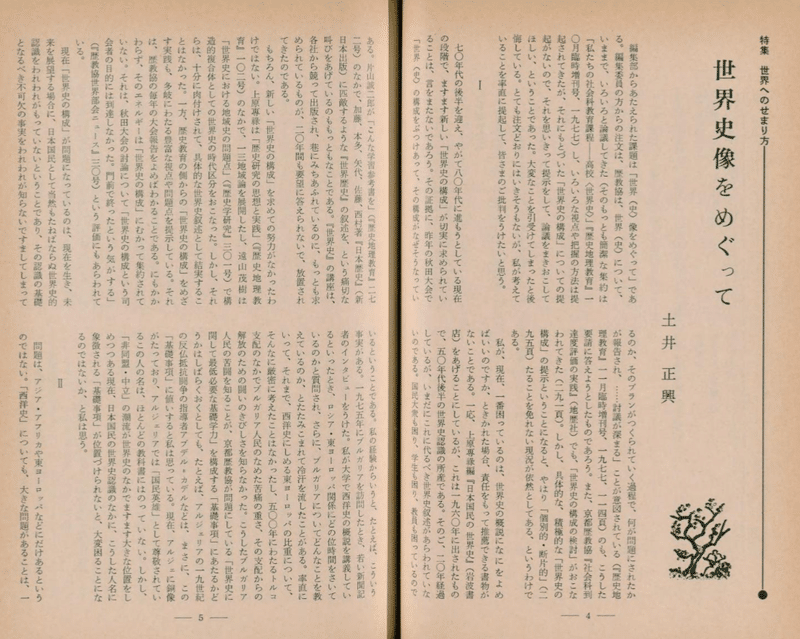
それは、歴教協の現在までの実践のなかで、世界史の描く時代、各地域の諸歴史的事象について、どの部分について『世界史の構成』の不可欠の構成部分となるべき見なおしや点検がおこなわれたのかを、個々の事実についてリスト・アップし、各時代、各地域にかきわけ集積して一覧表にしていく作業である。
土井にとって不可欠の構成部分とは、「非同盟-中立」の潮流を体現する人物や事象にほかなりません。
たとえばアルジェリアの抵抗運動を指導した「アブデル・カデル」、ベトナムの「ファン・ボイ・チャウ」などは重要と判定されるわけです。
しかし、これに対して吉田は、そのように基礎事項をあらかじめ立ててしまうのは、日本国民の世界史認識を主体的に立てていくことにはならず、それでは「客観的な発展法則」というものに則して歴史的現実があることになってしまうと批判します。
吉田は「問題構造に則して歴史的現実がある」、生徒が自分自身の置かれた生活実感から問いを立て、その答えを世界史に投げかけ、そこから形成されていったものを構造的・段階的に分解したときにはじめて、基礎事項は見えてくるととらえるからです。
「ニッポンの世界史」にとって何が重要用語であるか、未だに見定まらない状況は続いています(有体にいえば、大学受験でよく出題される語句が重要だという尺度のみが存在する)。
2017年には、教科書執筆者も参加する民間団体(高大連携歴史教育研究会)によって新指導要領の教科書における用語精選が提起されたことがあります(精選案(第1次)、Q&A)。概念的な用語と事実用語の交通整理が若干ながらおこなわれるようになったほかは、実際にはあまり変わっていないというのが現状でしょう。
用語の見直しには「どんな観点から見直すか」という姿勢がなければならないと看破する吉田の指摘は、いまだに重く響き続けていると言わざるをえません(吉田、上掲、113頁)。
***
さて、これまで見てきたとおり1970年代には、西洋中心主義を突き崩し世界史をトータルに語ろうとする動きは、“公式”のみならず“非公式”のフィールドにおいて進んでいきました。しかしそれは、まだまだ途上にありました。
そんな中、加熱する受験戦争が、「マイナー」な地域への注目とあいまって、受験に必要とされる知識量を増やしていく。その状況に高校教員や受験産業、出版社、大学の出題者が適応し、さらに量が増えていく——。
こうして「暗記地獄」としての世界史イメージはさらに増幅され、1979年に始まる共通一次試験では、世界史の選択が多くの受験生に敬遠される事態を生み出すことになります。

では、「ニッポンの世界史」にこびりついたマイナス・イメージは、これからどう変わっていくのか?
いきおい1980年代に足を踏み入れる前に、わたしたちは1970年代の新しい潮流を、もう少しだけ一緒に確認しておくことにしましょう。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
