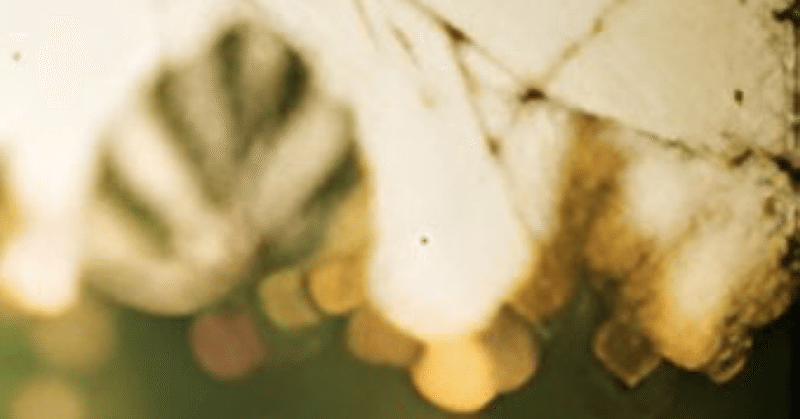
フランス処刑人一族サンソン家の歴史
今回は表題の通り、フランス処刑人一族サンソン家について紹介していく。サンソン家はフランスのパリで、死刑執行の職務を務めた一族である。サンソン家の歴史については、サンソン家第6代当主アンリ=クレマン・サンソンが著した『サンソン回想録(原題:Mémoires des Sanson)』から垣間見ることができる。アンリ=クレマン・サンソンは不祥事で処刑人の仕事を罷免される運命を辿るが、その後は家賃収入で実母と共に暮らした。その隠居生活の中で綴られたのが『サンソン回想録』である。彼は歴代当主たちの手記をもとにサンソン家の歴史を書き上げた。当時としては異例の8万部を記録するベストセラー作品となった。
パリの処刑人一族として知られるサンソン家。その初代となるシャルル・サンソン・ド・ロンヴァルは砲兵隊に所属する軍人だったが、処刑人の娘マルグリット・ジュアンヌと恋に落ち、娘婿として処刑人の仕事を引き継いだ。ロンヴァルが落馬して怪我を負ったところ、ピエール・ジュアンヌという男に助けられたことがきっかけだった。ロンヴァルは、ピエール・ジュアンヌが新約聖書の善きサマリア人の如く親切に自分を介抱してくれた述べている。ロンヴァルはピエール・ジュアンヌ宅で療養する中、その娘マルグリットの美しさに魅せられていた。快復してジュアンヌ宅を離れると、彼は惚れていたマルグリットのことを考えないよう自分に強いた。だが、日に日に想いは募るばかりだった。ある日、ロンヴァルはマルグリット宅周辺に訪れ、彼女を待ち伏せすることにした。だが、マルグリットの父からは娘に近づくなと拒絶され、無念にも追い返されてしまう。それでも諦めきれなかったロンヴァルは、マリグリットの父がいないタイミングを狙って、彼女に度々会いに行った。そして、幾度もマルグリットに自身の想い告げる。だが、マルグリットは「私と一緒にいることで、あなたに不幸が降りかかる」と答えた。というのも、マルグリットは当時のフランスで忌まわしき存在として忌み嫌われていた処刑人の娘だったのだ。それでもロンヴァルは受け入れると告げ、彼女の父に結婚の許しを申し出た。そして、それは同時に娘婿として処刑人の仕事を引き継ぐことを意味していた。処刑人の娘と結婚すれば、その激しい差別から他の仕事に就くことは叶わなくなる。それでもロンヴァルはマルグリットへの愛を貫き、彼女と結婚して処刑人の道を歩む道を選んだ。だが、悲惨なことに結婚して間もなく、マルグリットは出産時に子どもを残して死亡した。最愛の妻を早くに亡くしたロンヴァルは、陰鬱な性格になっていた。これが処刑人サンソン家の始まりである。
以下、歴代のサンソン家当主を列挙する。サンソンは6代目当主まで続いた。
初代当主
シャルル・サンソン・ド・ロンヴァル
砲兵隊に所属する軍人だったが、処刑人の娘マルグリットと恋に落ち、処刑人の仕事を引き継いだ。やっとのことで一緒になった最愛の妻を早くに失う不幸に遭った。
第2代当主
シャルル・サンソン
ロンヴァルとマルグリットの長男。母は彼の出産時に他界。また、彼の代に処刑人が徴税する権利が失われ、代わりに年間16,000ルーヴルが支給される年俸制に変更された。
第3代当主
シャルル=ジャン・バティスト・サンソン
7歳にして処刑人となった歴史上最年少の処刑人。父の急死を機に幼くして職務を引き継がなければならなかった。2度結婚しており、8男2女をもうけた。晩年は脳卒中で半身不随になり、息子に職務を継承した。
第4代当主
シャルル=アンリ・サンソン
ルイ16世、マリー=アントワネット、ロベスピエール、ダントン、デムーラン、サン=ジュスト、シャルロット・コルデーなどの著名人の処刑を担当した最も著名なサンソン。ルイ16世に忠誠を誓っていたため、国王の処刑は彼の精神をひどく蝕み、後に引退の道を選ぶ。
第5代当主
アンリ・サンソン
国民防衛軍の砲兵隊員としてフランス革命に参加した。ルイ15世の公式寵妃デュ・バリー夫人の処刑を担当。デュ・バリー夫人は処刑時に慈悲を乞い、それが叶わないと分かると暴れ回って処刑に難航した。また、マリー=アントワネットの処刑時に断頭台で彼女に足を踏まれてしまったサンソンは、このアンリ・サンソンである。
第6代当主
アンリ=クレマン・サンソン
『サンソン回想録』の筆者。金遣いが荒く、借金をしてギロチンを質屋に入れる不祥事で信用を失い、処刑人を罷免。その後は家賃収入で生計を立て、実母と共に細々と暮らした。
ちなみに、フランス語でサン(音)、ソン(ない)という意味からサンソン家の紋章は、音が鳴らない割れた鐘がモティーフとされた。割れた鐘を2匹の犬が見つめているデザインは、印象的である。
先に述べたように『サンソン回想録』は、サンソン家の第6代当主アンリ=クレマン・サンソンによって出版された。彼は放蕩息子で、サンソン家の財産一代にして使い果たしてしまった。それどころか、金に困った彼は、なんと処刑道具のギロチンを質屋に入れてしまう。この不祥事が公になり、彼は免職となった。そうした人物ではあったものの、彼が出版した『サンソン回想録』はサンソン家と当時のフランスの様子を現在に伝える一級の文献となっている。歴代のサンソン当主の経歴を紹介すると共に、国王ルイ16世を処刑した第4代当主シャルル=アンリ・サンソンの日記も収録されている。この日記からは、フランス革命の生の声を聞くことができる。
貨幣好きの私が個人的に興味を持ったシャルル=アンリ・サンソンの日記の箇所は、アッシニア紙幣についての記録である。処刑人シャルル=アンリ・サンソンの日記から、当時のフランスでは貨幣の偽造が死刑に値したことが分かる。1793年11月17日に書かれた彼の日記では、アッシニア紙幣の偽造者たちが逮捕されたことが述べられている。そしてサンソンは、彼らを処刑したと記している。反革命勢力はフランス政府が発行するアッシニア紙幣を偽造し、これを自分たちの活動資金に当てていた。アッシニア紙幣の偽造品を掴まされた市民は、その負債を他人に押し付けることに走り、これは経済に大打撃を与えた。この経済打撃も反革命勢力の狙いのひとつだった。シャルル=アンリ・サンソンの日記によれば、偽造されたアッシニア紙幣は精巧な造りで、本物との見分けが難しいと言及されている。
また、1794年6月15日に記されたシャルル=アンリ・サンソンとロベスピエールの出会いのエピソードも印象的である。サンソンは姪たちを連れて散歩している時にセーヌ川沿いでロベスピエールと偶然にも出会った。革命政府の独裁者ロベスピエールは、いつも複数の護衛官を引き連れていたと噂されていたが、実際にサンソンが彼に出会った時は白黒のまだら模様の大型犬を連れて散歩する、ごく普通の紳士だった。彼は白い胴着の上に青い礼服を羽織り、黄色の半ズボンを履いていた。髪は髪粉かけて整え、帽子を引っ掛けた杖を肩に担いでいた。ロベスピエールは、愛想良くサンソンが連れる姪たちに挨拶した。姪たちも挨拶を返すと、ロベスピエールは気さくに話しかけ、姪たちの名前を訊ねた。だが、姪たちはサンソンという苗字まで悪気なく答えてしまった。その瞬間、ロベスピエールの顔つきが急激に変わった。先ほどまでの親しげな表情は、もうそこになかった。驚きから青ざめた表情は土色に変わり、笑顔は消えていた。ロベスピエールは軽蔑の目でサンソンたちを見やると、沈黙の後に「キミは......」と言いかけ、その場を去っていった。断頭台に人々を次々に送り込んでいる張本人との出会いは、サンソンにとっても印象的な出来事だったようで、日記にもそのことが詳しく記されている。
処刑人というその職業柄、シャルル=アンリ・サンソンは人々から忌み嫌われていたが、不動産ビジネスと医療事業で成功しており、豊かな生活を送っていた。処刑人と聞くと残忍な人間そのものと思われるかもしれないが、サンソンは心優しい人物だった上、ルイ16世のことを慕っていた。それゆえ、彼にとって王の処刑を執行することは極めて苦痛となるものだった。サンソンは王党派による介入で、処刑が邪魔されることさえ期待していた。実際、父を誤って殺害してしまった青年の処刑に民衆が暴動を起こし、邪魔して解放するという前例があったからである。だが、王党派は誰も助けには来なかった。サンソンはルイ16世の処刑後、隠れて元国王のためにミサを行った。償い切れない罪を犯してしまったという自責の念に駆られたからである。これが革命政府に知られれば、今度は彼が反逆罪として断頭台送られる危険性もある。だが、そのリスクを冒してまでも懺悔のミサを執り行ったという。国王の処刑を機に精神を病んだ彼は、しばらくして引退し、その仕事を息子アンリ・サンソンに託した。処刑人は忌み嫌われる仕事であり、成り手がいないことから世襲されるのが一般的だった。
ルイ16世の最期は、シャルル=アンリ・サンソンの日記などの同時代の文献によって比較的詳細に記録されている。ルイ16世の最期は、以下のような内容である。ルイ16世は断頭台に上がると、処刑人サンソンにまず上着を脱ぐように指示された。だが、ルイ16世はそれを断った。王がいつまでも上着を脱ごうとしなかったので、サンソンが涙目で懇願すると、とうとう上着を脱いだ。サンソンも顔面蒼白だった。代々国王の代理として処刑を執行してきただけに、その国王を処刑するなど彼にとってはあり得ないことだった。次に、サンソンは手を縛るので、後ろに回すように指示した。だが、これにルイ16世は猛烈に反発した。これは国王のルイ16世にとっては許せない恥辱だった。サンソンがいくら言ってもルイ16世が言うことを利かなかったため、サンソンはお付きの神父に「これでは刑が執行できない」と説得を仰いだ。神父はルイ16世に「これが国王としての最後の試練あり、これを乗り越えれば神に近づく」と諭した。ルイ16世は諦めの表情を浮かべ、神父が持つイエスの神像に口付けしながら両手を紐で結ばせた。そして、斬首の際に邪魔にるという理由から、ルイ16世はサンソンによって髪を短く削ぎ落とされた。そうして、とうとう腹這いの状態で断頭台に固定され、刃が振り下ろされた。不幸にも刃の位置がずれており、断頭台の刃はルイ16世の後頭部と下顎を切り裂く悲惨なものになっていた。サンソンは切り落とした首の髪の毛を持ち、民衆にその首を見せた。処刑人が罪人の首を持って民衆の見せるのは恨みからではなく、習わしである。
受刑者を楽に死なせる人道的な思想から生まれた断頭台が、簡単に処刑を行う道具として多くの人間の命を奪うことになってしまったのは何とも皮肉である。斬首を人が行う場合、凄まじい集中力が必要とされた。また、失敗も多く、何度もやり直して死刑囚を苦しめることも多かった。特に体調が悪かったり、気に迷いがあると斬首は失敗した。また、相手側の協力も必要で、喚かれたり、動かれたりすると、失敗してしまう高度な技だった。剣の消耗も激しく、一人切った後はよく研ぎ直す手間もあった。こうした難しさが処刑される人数を自然と抑えていた。だが、それが断頭台の登場によってほぼ無制限となった。サンソン自身、処刑の数が多過ぎて手に負えないので負担を減らして欲しいとの要請を出してもいる。それほど、人力での処刑は難しいものだった。
最後に『サンソン回想録』を著者アンリ=クレマン・サンソンについて話していこう。サンソン家第6代当主アンリ=クレマン・サンソンには、回想録の中でTというイニシャルで示される親しい学友がいた。Tとはいつも共に下校し、Tの家の前で別れるのが彼らの日課だった。ある日、Tはサンソンの家に行ってみたいと言った。サンソンはこれを歓迎し、友人を自宅に招いた。だが、サンソンの父はTを素っ気なく扱った。次の日からTはサンソンを避けるようになった。父親が素っ気なく扱ったことが気に障っただろうか。避けられる理由が分からないサンソンは、しばらくしてから勇気を出してTを問い詰めた。すると、Tは紙にペンで何かを描き始めた。それは、ギロチンの絵だった。「キミは処刑人の子だろう」この時、サンソンは初めて自分の父が人々に忌み嫌われる処刑人であることを知った。家族ではなく、友人から自分の出生にまつわる衝撃の事実を伝えられた体験は生涯、彼を苦しめることになった。サンソンは自宅に帰ると、泣きながら母の膝に崩れ落ちた。サンソンの父は、学校に猛抗議した。校長はTを叱咤したが、サンソンは学校に戻るつもりはなかった。父もそれを了承し、サンソンは15歳で学校を辞めた。これがアンリ=クレマン・サンソンの悲しき少年時代である。
その後、彼はヨーロッパを遊学する。裕福なサンソン家には、息子を遊学させるだけの資産があった。旅から帰ってしばらくすると、アンリ=クレマン・サンソンは近所の乙女と恋に落ち、10代で結婚に至った。アンリ=クレマン・サンソンには、息子と二人の娘がいた。だが、息子は若くして事故死した。娘は二人とも、医師の家庭に嫁いだ。日頃から遺骸に触れることが多い処刑人は、医師を兼ねることもあった。歴代のサンソンたちも医師を兼任したが、アンリ=クレマン・サンソンの時代には、医療行為には医師の資格がいるため、処刑人が医師として副業を行うことはできなくなっていた。
アンリ=クレマン・サンソンは、息子が他界したことで、サンソン家はここで途絶えると回想録の中で綴っている。だが、それは同時にサンソン家が忌々しい処刑人の呪縛から解放される救いとも皮肉げに述べている。第二次世界大戦が終わると、バーバラ・レヴィという人物がアンリ=クレマン・サンソンの娘たちから繋がる末裔を探した。だが、誰も名乗りを上げず、結局サンソン家の子孫は見つからずに終わった。
以上、今回はフランスの処刑人一族サンソンの歴史について紹介した。サンソン家を知れば、悪役が相応しい処刑人のイメージが一転することだろう。その仕事から忌み嫌われ、激しい差別を受けてきた一族の強く気高い人生に少しでも興味を持ってもらえれば幸いである。そこから私たちは、差別や生き方の本質を必ず見出せることだろう。
【主要参考文献】
*以下、サンソン家に関する情報を得た今回の記事の主な文献
バーバラ・レヴィ著、喜多迅鷹・喜多元子訳『パリの断頭台』法政大学出版局、1987
安達正勝『死刑執行人サンソン』集英社新書、2003
オノレ・ド・バルザック著、安達正勝訳『サンソン回想録:フランス革命を生きた死刑執行人の物語』国書刊行会、2020
アンリ=クレマン・サンソン著、西川秀和訳『増補版サンソン家回顧録上巻』2021
アンリ=クレマン・サンソン著、西川秀和訳『増補版サンソン家回顧録下巻』2021
ロジェ・グラール著、西川秀和訳『重罪判決執行人サンソン家の系譜』2023
*以下、サンソンたちが生きたフランス革命期及びその前後の時代背景・文化把握のために使用した文献
池田理代子『フランス革命の女たち』新潮社、1985
飯塚信雄『デュバリー伯爵夫人と王妃マリ・アントワネット』文化出版局、1985
柴田三千雄『パリのフランス革命』東京大学出版会、1988
芝生瑞和『図説 フランス革命』河出書房新社、1989
安達正勝『マラーを殺した女』中央文庫、1996
遅塚忠躬『フランス革命 歴史における劇薬』岩波ジュニア新書、1997
松浦義弘『フランス革命の社社会史』山川出版、1997
藤本ひとみ『マリー・アントワネットの生涯』中央公論社、1998
ロバート・ダーントン著、近藤朱蔵訳『革命前のフランス人は何を読んでいたのか 禁じられたベストセラー』新曜社、2005
五十嵐武士・福井憲彦『アメリカとフランスの革命』中央公論社、1998
エヴリーヌ・ルヴェ著、遠藤ゆかり訳『王妃マリー・アントワネット』創元社、2001
T.C.W.ブラニング著、天野知恵子訳『フランス革命』岩波書店、2005
柴田三千雄『フランス史10講』岩波書店、2006
柴田三千雄『フランス革命』岩波書店、2007
安達正勝『物語 フランス革命』中公新書、2008
アンタール・セルプ著、リンツビヒラ裕美訳『マリー・アントワネットの首飾り事件』彩流社、2008
中野京子『名画で読み解くブルボン王朝 12の物語』光文社新書、2010
新人物往来社編『王妃マリー・アントワネット』新人物往来社、2010
佐藤賢一『フランス革命の肖像』集英社新書、2010
ウィリアム・リッチー・ニュートン著、北浦春香訳『ヴェルサイユ宮殿に暮らす』白水社、2010
佐々木真『図説 フランスの歴史』河出書房新社、2011
エドマンド・バーク著、佐藤健志訳『新訳 フランス革命の省察』PHP、2011
中野京子『マリー・アントワネット 運命の24時間』朝日新聞出版、2012
安達正勝『フランス革命の志士たち』筑摩書房、2012
竹中幸史『図説 フランス革命史』河出書房新社、2013
石井美樹子『マリー・アントワネット ファッションで世界を変えた女』河出書房新社、2014
安達正勝『マリー・アントワネット』中公新書、2014
長谷川輝夫『図説 ブルボン王朝』河出書房新社、2014
パウル・クリストフ著、藤川芳郎訳『マリー・アントワネットとマリア・テレジア 秘密の往復書簡』岩波書店、2015
神野正史『世界史劇場 フランス革命の激流』ベレ出版、2015
イネス・ド・ケルタンギ著、ダコスタ吉村花子訳『カンパン夫人』白水社、2016
惚領冬美・塚田有那『マリー・アントワネットの嘘』講談社、2016
エレーヌ・ドラレクス著、ダコスタ吉村花子訳『麗しのマリー・アントワネット』グラフィック社、2016
ウィル・バショア著、阿部寿美代訳『マリー・アントワネットの髪結い』原書房、2017
ピーター・マクフィー著、高橋暁生訳『ロベスピエール』白水社、2017
山崎耕一『フランス革命』刀水書房、2018
ジュール・ミシュレ著、瓜生純久訳『抄訳 フランス革命史』本の泉社、2018
エマニュエル・ド・ヴァレスキエル著、土居佳代子訳『マリー・アントワネットの最後の日々 上』原書房、2018
エマニュエル・ド・ヴァレスキエル著、土居佳代子訳『マリー・アントワネットの最後の日々 下』原書房、2018
松浦義弘『ロベスピエール』山川出版、2018
エヴリン・ファー著、ダコスタ吉村花子訳『マリー・アントワネットの暗号』河出書房新社、2018
ジャック・ルヴロン著、ダコスタ吉村花子訳『ヴェルサイ宮殿 影の主役たち』河出書房新社、2019
福井憲彦『教養としてのフランス史の読み方』PHP、2019
佐藤賢一『ブルボン朝 フランス王朝史3』講談社現代新書、2019
ピエール=イヴ・ボルペール『マリー・アントワネットは何を食べていたか』原書房、2019
エマニュエル・ド・ヴァリクール著、ダコスタ吉村花子訳『マリー・アントワネットと5人の男 上』原書房、2020
エマニュエル・ド・ヴァリクール著、ダコスタ吉村花子訳『マリー・アントワネットと5人の男 下』原書房、2020
鈴木杜幾子『画家たちのフランス革命』角川選書、2020
ジャン=クリスティアン・プティフィス著、土居佳代子訳『12の場所からたどるマリー・アントワネット 上』原書房、2020
ジャン=クリスティアン・プティフィス著、土居佳代子訳『12の場所からたどるマリー・アントワネット 下』原書房、2020
クリスティーヌ・ル・ボゼック著、藤原翔太訳『女性たちのフランス革命』慶應義塾大学出版会、2022
岩井淳・山崎耕一編『比較革命史の新地平』山川出版社、2022
ピーター・マクフィー著、永見瑞木・安藤裕介訳『フランス革命史 自由か死か』白水社、2022
ダニエル・ステルン著、志賀亮一・杉村和子訳『女がみた一八四八年革命 上』2022
ダニエル・ステルン著、志賀亮一・杉村和子訳『女がみた一八四八年革命 下』2023
ルネ・セディヨ著、山崎耕一訳『フランス革命の代償』草思社文庫、2023
ミシェル・ビアール著、小井髙志訳『自決と粛清』藤原書店、2023
Shelk 🦋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
