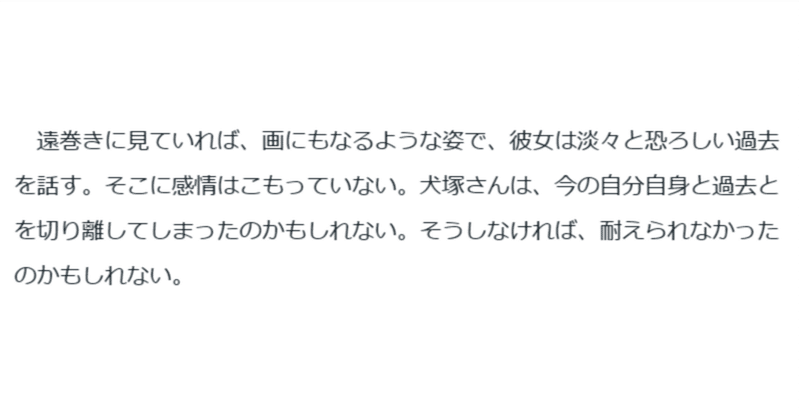
(19)あの頃わたしは確かにそこにいた
犬塚さんとまた会ったのは、秋になってすぐだった。診察時間を昼手前に戻し、案の定何時間も待たされ、外のベンチで昼食を摂っていると彼女は現れた。
「あ、あの時の人だ?」
私は、お久しぶりです、と、覚えています、の二つの意味を込めて小さく頭を下げる。
「あれ以来見かけないから、転院したのかと思ってた。また会えてわたしは嬉しいよ」
犬塚さんはベンチに座り、やはりこちらを見ずにそう言った。
「今年の夏は暑かったね。焼け死ぬかと思ったよ。なんとか終わってよかった」
「そうですね」
ウインナーを摘まみながら返事をする。
「秋になって、やっとまたこうやってベンチにこられる。夏の間は暑くて無理だった。でもあの室内にこもっていると、落ち着かないんだ。じっとしていられなくなりそうで、怖くてさ。ああ、やっと口を開ける。今はあなたが聞いてくれているかもしれないけれど、わたしは誰が聞いていなくてもずっと喋ってしまうから」
犬塚さんの病を考える。大人しくしている、ということに苦痛を覚える病、そういったものが存在するのかもしれない。犬塚さんはそれなのかもしれない。私は自分の患っている病も含めて、あまり知識がない。教師を辞めてから、学ぶ、ということに恐怖を覚えるようになってしまった。今の私は偶然知り得た知識しか増えない。
「隣町の大きな公園では、コスモスが満開に近いらしい。コスモスって香りあるのかな。あまりイメージはないけれど、コスモスの香水、っていうとなんとなくありそうな気がしてくるのはなんでなんだろうね。小物なんかのモチーフにはよく用いられているよね。アクセサリーとかさ。わたしみたいな、黒づくめの女には不似合いなんだろうけれど」
そんなことないですよ、きっとあなたのような美しい人にはコスモスだってよく似合う。そんなことを考えるが、口には出さない。
「あんまりこうやって、話しかけていると、看護師に叱られるんだけどね。辞められないんだ。医者も言う。あなたのその癖を治すのは難しいって」
犬塚さんが言う。言い始める。
「一方的に話しかけられることを迷惑がる人がいる、そういう人が世の中の大半を占める、っていうのは、ちゃんと理解しているつもりなんだ。だから、できればしたくない。わたしだって、嫌われるのは嫌だ。でも、止まらないんだ。衝動が止められないんだ。話しかけやすそうな人を見かけると、そしてその人が一人きりだったりすると、もう駄目なんだ。一声かけて、相手がなんだろうって顔を返してきて、でももうその瞬間から言葉が止まらずに口からぼろぼろと零れて、溢れてきて、まるで嘔吐みたいに、もう自分じゃコントロールできないんだ。相手がどんどん迷惑そうな顔をして、はあ、みたいな短い返事もしなくなって、こちらに背を向けて、それでもわたしは話し続けて、最終的には相手がその場から立ち去って、それでもわたしは話し続けているんだ。虚空に向かって、ずっと、ずっと、話し続けてしまうんだ」
きょうの犬塚さんはきっと調子が悪いんだろうな、と思う。私もそうだからわかる。
調子が悪いときは、症状が強く出る。部屋の掃除をいつまで経っても止められない。馬鹿みたいに凝った料理を明け方までかけて作ってしまう。生徒の親から責められ続けたあの日を思い出して息がうまく吸えなくなって、死にたくない、死にたくない、とぐちゃぐちゃの息継ぎの透き間に呟き続ける。
そういう日が、私たちのような人間には存在して、犬塚さんはきっとそれがきょうで、でも犬塚さんは必死の思いでこのメンタルクリニックまでたどり着いたんだろう。彼女は診察まであとどのくらいあるのだろう。どのみちあと少しだ、それまで何とかなってほしい。私のパーソナルスペースの周りに言葉を置き並べるくらいのことなら私だって拒絶しない。見ていて辛いから。あなたは今、そのまま喋り続けていい。犬塚さんに思う。私はできるだけゆっくりとお弁当を食べる。
「もう一度、もう一度舞台に立ちたいんだ。わたし、売れてなんてなかったけど東京で舞台女優やってたんだ。ファンも、それなりにはいたんだ。公演で主役もらったときは嬉しかったな。ああ、頑張ってきてよかったって思った。ファンの人たちがこっそり裏で手を組んでさ、花輪を贈ってくれて。あれには泣いたな。努力が認められたって思った。頑張れば報われるんだって思った。舞台はちゃんと成功して、舞台雑誌にも小さくだけど講演内容が載った」
美しい横顔で、犬塚さんが過去を語り出す。その独白を、舞台の上だと考えてみようとする。うまくいかない。
「けど、その頃からかな、初期から応援してくれてた男のファンの人がちょっとおかしくなっちゃって。人気出たって言っていいのかな、公演数も増えて、演じる機会が増えて、だからSNSとかでファンときちんと触れ合う時間が取れなくなって。そしたらその男の人、出待ちとかじゃなくて、わたしが私生活で通う服屋とか、本屋とか、レコード屋とか、そういうところにも現れるようになって。あれ偶然ですね、なんて言ってわたしのことを芸名で呼ぶんだけど、ああこれストーカーされてるなあってのはすぐにわかった。事務所に言って、注意してもらって、次があったら出禁ですよって言ってもらって。その人も、はいすみませんでした、って、わたしにもつけ回してすみませんでしたって素直に謝ってくれて。ああこれでまた演技に専念できるって思って、その日は電車で帰って。家に着いたら、玄関の前にその男がしゃがんでてさ。わたしのことを、本名で呼んで、『×××、好きだよ』って、笑顔で言ったんだよ。三徳包丁を持ちながら。そのあとは、もうただ必死だったな。その場から走って逃げて、スマホで警察呼んで、事情説明して、警官二人と家に戻ったらまだその男がさっきの姿そのままに、三徳包丁持ったまま言うんだよ。『×××、好きだよ。結婚しようね』って。警官が優しい声で、包丁をこちらに渡してくださいって言ったら、ストーカーが、結婚してくれるなら渡しますって言うんだよ。その時の男の目がさ、真っ黒で。黒い絵の具のチューブを絞った時みたいに、本当に、本当に真っ黒くて、それ以来わたし、他人の目がうまく見られない」
弁当に目を落とす。もう空っぽだ。気づかれないように、一切動かないでいる。秋口、気持ちのいい風が吹いて、私たちの髪を揺らす。
遠巻きに見ていれば、画にもなるような姿で、彼女は淡々と恐ろしい過去を話す。そこに感情はこもっていない。犬塚さんは、今の自分自身と過去とを切り離してしまったのかもしれない。そうしなければ、耐えられなかったのかもしれない。
「女優は辞めるしかなかった。必要なシーンで、相手の役者の目が見られないんだ。バイトをしようったって似たようなもので、客や同僚と目を合わせなきゃならない場面なんていくらでもある。ああ、もうおしまいだって思って、こうして田舎に戻ってきて、今、頭を治してる」
犬塚さんの足元を見る。彼女はまだサンダルを履いていて、マニキュアはところどころ剥げていた。
「あとで人づてに、あのストーカーが自殺したって聞いた。元々あの人も心を病んでて、でも舞台が好きで観に通ってて、そこでわたしのことを見つけたんだって。わたしの中に、自分と似たような影を感じたって、ファン同士の会話でよく言ってたらしくてさ。昔の、舞台の上のわたしだったらわたしはいつでも本気だから暗いこと考えてる暇なんかないよって即答できたけど、今は違う。あのストーカーは、わたしの本質をどこかで見抜いていたのかもしれないな。だから狂うほどにわたしのことを好きになってしまって、実際に狂ってしまって、おかしくなって、だからわたしが目の前からいなくなって、病んだ心がもうどうしようもなくなって、死んじゃったのかなって。わたし、あの男が死んだことに責任は感じてないんだ。わたしのせいじゃないでしょって。だってわたしは演じていただけでしょって。でも、それでもなんか、わたしも、おかしくなってしまった。早く治して舞台に立ちたい。そういう気持ちがある。それと同時に、また舞台に立ったら、またいつか狂っちゃうんじゃないかって、そういう恐怖もある。それをどうにかしない限り、わたしはただの地面にしか立てない」
犬塚さんがガリ、と地面をサンダルの先で抉る。難しいね、と、私を見ずに笑う。
看護師がやってきて、名城さーん、と私の名前を呼んで、
「次の診察ですので、中にきてくださーい」
と言う。私は看護師に頷いて見せ、弁当包みで弁当を包む。鞄にしまい、立ち上がると、犬塚さんは、私の胸の辺りを見ながら、
「行ってらっしゃい」
とまた綺麗な顔を綺麗なままに変化させて、そっと笑ってみせた。最後まで一度も目は合わなかった。
(続)
ここから先は
¥ 110
頂戴したお金は本やCD、食べ物など、私の心に優しいものを購入する資金にさせていただいています。皆さんありがとうございます。
