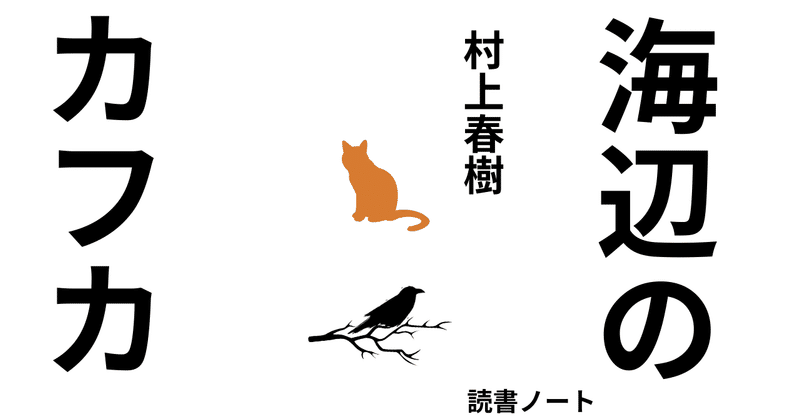
「海辺のカフカ」(村上春樹)【読書ノート】
村上春樹さんの小説を初めて読んだ。
まず、構成に驚いた。
「カラスと呼ばれる少年」という挿入からはじまり、そのあとに「僕」を主人公とした物語がスタートしたかと思えば、突然「アメリカ国防省の極秘資料」が挿し込まれる。また「僕」の物語に戻ったかと思えば、再びアメリカ陸軍情報部(MIS)報告書というものが挿し込まれる。「一体何事か?」と思うと今度は、猫と喋れる老人が主人公の物語が始まる・・・。
とても戸惑うのだが、この戸惑わせ方じたいが、既に物語の本質の一部だと感じた。
物語はまさに戸惑いの連続で構成されている。
カラスと呼ばれる少年という謎の声や、猫と話せる老人、ジョニーウォーカーと名乗る猟奇的な男、カーネル・サンダーズと名乗る謎のおじさん・・・。
戸惑いの連続だった。
大島さんがこんなことを言っている。
「この僕らの住んでいる世界には、いつもとなり合わせに別の世界がある。君はある程度までそこに足を踏み入れることができる。そこから無事に戻ってくることもできる。注意さえすればね。でもある地点を超えてしまうと、そこから二度と出れなくなる。帰り道が分からなくなってしまう。迷宮だ。(後略)
まさに迷宮に入っていくようだった。
こういう迷宮的な構成が、村上春樹さん特有の文体で綴られていく。
村上春樹さんは、とても平易な言葉を用いるのに、複雑な世界を描き切るからすごいと思った。
また、作中に古今東西の芸術、音楽、文学、哲学、歴史等々からの引用がとても多いことも特徴の一つだ。
シューベルト、漱石、イェーツ、ベートーヴェン、源氏物語、雨月物語、ヘーゲル、チェーホフ、ルソー、プリンス・・・。
何故こんなに引用が多いのか?
私は、これらの引用によって「時間と場所の超越」を果たしているのかなと思った。「今、ここ」を相対化しているんじゃないかなと。
また、主語をカフカにしたり、ナカタさんにしたり、あるいは客観的な出来事にしたり(三人称に)することで、「今、ここ」の超越だけではなく、主体と客体の境も無くしている気がする。
終盤、カフカに「カラスの少年」の声がボイスオーバーしていき、カフカの自己意識が消えていくような描写もある。
カーネル・サンダーズが紹介してくれた女の子の下記のセリフは、このような自己意識と客体(世界)の境目が曖昧になっている状態を示唆している気がする。
「『<私>は関連の内容であると同時に、関連することそのものでもある』」
「ふうん」
「ヘーゲルは<自己意識>というものを規定し、人間はただ単に自己と客体を離ればなれに認識するだけではなく、媒介としての客体に自己を投影することによって、行為的に、自己をより深く理解することができると考えたの。それが自己意識」
次々と起こる不思議な出来事の中で、カフカは戸惑ってしまう。
「僕はどうすればいいのか、まったくわからなくなっている。自分がどっちを向いているのかもわからない。なにが正しく、なにがまちがっているのか。前に進めばいいのか、うしろに戻ればいいのか。(中略)僕はいったいどうすればいいのだろ?」
それに対する大島さんの言葉が良かった。
「なにもしなければいい」(中略)
「風の音を聞いていればいい」(中略)
「いろんなことは君のせいじゃない。僕のせいでもない。予言のせいでもないし、呪いのせいでもない。DNAのせいでもないし、不条理のせいでもない。構造主義のせいでもないし、第三次産業革命のせいでもない。僕らがみんな滅び、失われていくのは、世界の仕組みそのものが滅びと喪失の上に成り立っているからだ。僕らの存在はその原理の影絵のようなものに過ぎない。風は吹く。荒れ狂う強い風があり、心地よいそよ風がある。でもすべての風はいつか失われて消えていく。風は物体ではない。それは空気の移動の総称に過ぎない。君は耳を澄ます。君はそのメタファーを理解する。
生きていくと、戸惑うことが「起こってしまう」ものだ。
「なんでこんなことに・・・。」
「どうすればよかったのだろうか・・・。」
と絶望したり、悲しんだり、悔いたりすることばかりだ。
だけど、それは大島さんがいう通りそれは、「世界の仕組みそのものが滅びと喪失の上に成り立っているから」かもしれない。
風は吹くのだ。
作品冒頭で言われている通り、運命は砂嵐のようにやってくるのだ。
最後に登場する、サーファーの大島さんのお兄さんも同じようなことを言っていた。
「俺たちはサーフィンを通して、自然の力に逆らわないことを覚える。たとえそれがどんなに荒っぽいものであってもだ。(中略)あわててじたばたしたところでなんともならない。かえって体力を消耗するだけだ。(中略)でもそういう恐怖をいったん乗り越えてみないことには、一人前のサーファーにはなれない。
ハワイにはトイレット・ボウルという海の中の砂嵐のようなスポットがあるそうだ。
「風」と「波」というふうに、メタファーが潜む対象は異なるが、
大島兄弟の言っていることは共通していると思う。
カラスと呼ばれる少年のセリフも良かった。
「いいかい、それはもうすでに起こってしまったことなんだ(中略)今さらとりかえしのつかないことだ。(中略)でも起こってしまったことというのは、粉々に割れてしまったお皿と同じだ。どんなに手を尽くしても、それはもとどおりにはならない。」
このセリフの通り、
起こってしまったことは、起こってしまったことと捉えるということも必要なんじゃないかと思った。
そして、風の音を聞いたり、波のなかでじっとしていたりする。
そういう過ごし方もあるんじゃないかと思った。
あるいは、ナカタさんやホシノ青年のような生き方にもとても惹かれた。
ナカタさんは幼いころの事故の影響で、字が読めなくなるなど、知性が失われてしまった老人である。
ちょうど、黒澤明監督の「白痴」の主人公の亀田を彷彿とさせられた。
(というかソックリだと思った。)
ナカタさんは頭で考えて分からないことは分からないままにしておく。
そして、分かることに対して精一杯取り組む。
ホシノさんはホシノさんで、ナカタさんが得体の知れないオジサンなのに、彼の言う事を信じてついていく。
二人とも、あまりにもピュアだ。
二人のことを見ていて、「ああ、こういうふうに生きたらいいのかもしれないな」と率直に思わされた。
「なんでこうなってしまったのだろう」とか、
「どうやって生きて行けばいいのだろう」みたいに考えるのではなくて・・・。
「分からないことは分からない」、
「この世界には分からないこともある」。
そして、「分かることを精一杯やる。」
こういう生き方でいいんじゃないかなと・・・。
「海辺のカフカ」全体を通して言えることだが、「なんで?」とか「どういうこと?」が解決されていないことがとても多い。
なんでナカタさんは猫と喋れるのかとか、
なんでナカタさんは空からイワシを降らせることができるのか?とか、
ジョニーウォーカーはなんで猫を殺して笛を作るのか?というか笛ってなんなんだ?とか、入口の石ってなんなんだ?とか・・・。
挙げ出したらキリが無い。
だけど、大島さんが言っている通り、私たちが住んでいる世界には別の世界が隣にあるのかもしれない。人智を超えたものがあるのかもしれない。この世界には分からないことがあるのだろう。
人間は科学ですべて分かったような気になっているけど、実際のところこの世界のほとんどのことが分かっていないのだろう。
例えば、作中で出てくるような、無意識のこと、暗示のこと、夢のこと、時間のこと、生霊のこと、記憶のこと・・・。
私たちはいろいろと分からないんだけど、分からない中で生きている。
ナカタさんはたしかに字が読めなかったりと、社会生活上の不便はあるかもしれないけれど、それは誤差の範囲であって、みんな「分からない」中で生きているんじゃないかなと思う。
これから生きていく中で、(というかきっと今も)たくさん嵐だったり、風だったり、いろんなことが起きてそれに巻き込まれていくのだろうと思う。
そういう時は甲村図書館に行き、大島さんに会いに行こうと思う。
もちろん、これも一種のメタファーなのだが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

