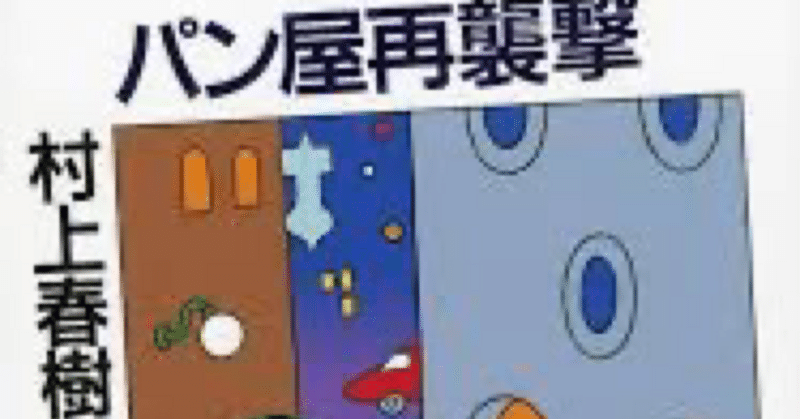
『パン屋再襲撃』(『ねじまき鳥クロニクル』)村上春樹
僕は十八歳で、そのとき下宿先の煎餅布団に寝転び本を読んでいた。その六畳一間はすぐ外を走る電車の小さな駅の光を窓から取り込み、中途半端な明るさを保ちながら夜半を迎えようとしているところだった。
六月の気だるい蒸し暑さが夜を包み、若者ばかりが押し込められた、縦に五列横に十二列のその古い学生アパートを、枡に区切られた陰気な標本箱のように見せていた。やれやれ、まだ零時前か、と僕は思った。
もしも村上春樹が好きかと問われたら、自信を持ってそうであると答えることが僕にはいまだできないように思う。そこで僕がいつから春樹を読んでいるのかを思い出してみようとすると、それは確かにニ〇〇九年六月のことだった。
ここまで考えて、僕は頭を上げて暗い天井を眺め、自分がこれまでの人生の過程で失ってきた多くのもののことを考えた。失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い。
旧帝国大学の一つである西日本の大学の文学部に入学した僕は、下宿先への引っ越しやら近所の探索やら履修登録やらを終え大学生活にも慣れ始めると、それまでの習慣に従い図書館に通い始めた。そこで驚いたのは、大学の図書館というのはひどく広大で地方の図書館数個分も思われるほどの蔵書があるにもかかわらず、専門書や論文がそのほとんどを占めており、現代小説は全くといっていいほどその姿が見えないことだった。
僕は戸惑い、煌々と灯が灯りPCを抱えた学生たちが歩き回る開架から、薄暗く黴臭い書棚が等間隔に立ち並ぶ閉架までを彷徨い歩いた。閉架は何階層にも渡って続き、人の気配がまるでなく古い書籍の息遣いだけに満ちているようで、恐怖に息が詰まった。文学部の生徒向けと思われる区域には、しかし紫式部の解釈や崩字の読解方法、連歌の歴史といった研究に必要な書籍のみが整然と納められていた。
ひどく落胆し、慣れ親しんだ母校の図書室を懐かしく思い出す僕は、そこで初めてのホームシックを感じた。その時書棚の最上段で目を留めたのが、『ねじまき鳥クロニクルだった』

____
※本文章は村上春樹『ノルウェイの森』冒頭のオマージュです。
肝心の『パン屋再襲撃』の感想まで辿り着かなかった、、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
