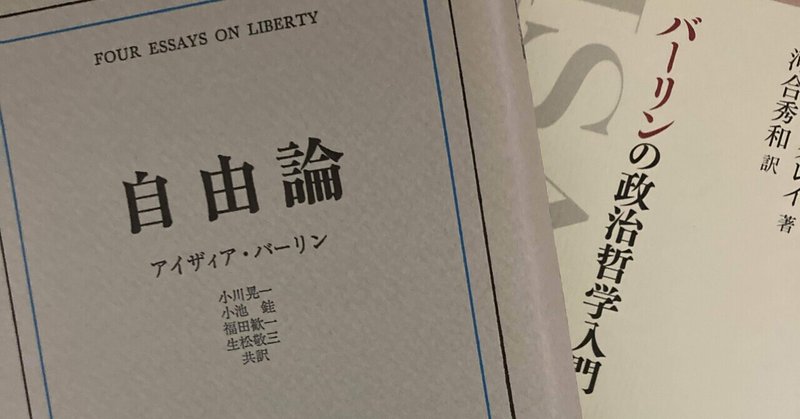
書評:アイザィア・バーリン『自由論』
20世紀の知の巨匠が展開する「真理」概念を巡る知的伝統への挑戦
今回ご紹介するのは、アイザィア・バーリン『自由論』という著作(およびバーリンの直系の弟子ジョン・グレイの『バーリンの政治哲学入門』という著作)。
20世紀は、政治・社会哲学領域において自由を巡る考察と議論が深く行われた時代であった。
代表的には、エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』で展開した、自由という概念を「〜からの自由」と「〜への自由」に分ける考察(過去に投稿済)。
また、ロールズやマイケル・サンデルらにより争われた「リベラル・コミュニタリアン論争」も、正義の本質を考察した際の自由の位置付けを巡るものであったと言い換えることができよう。
そして、バーリンも「消極的自由」と「積極的自由」という表現を用いて、自由を2つの側面から捉える「2つ自由概念」論を主張した。彼の自由論はフロムのそれと軌を一にする部分は確かにあり、「自由を巡る考察と論争」という文脈ではその位置付けは概ね正しい。
しかし、バーリンの政治哲学の核心は自由論そのものにあるのではなく、古代以来の西洋の知的伝統に脈々と確認される「真理」という概念そのものへの挑戦であり、彼の自由論はあくまでその論旨の中に位置取ってこそ本来の意義を認めることができるのである。
彼の「真理」に対する認識は、
◯共通的な真理なるものは本質的に存在しない
→例えばプラトンのイデア論のような、本質的には存在するのだが肉体を持つ人間には認識し得ないとするような立場とは根本的に異なる。
◯複数の価値を相互に比較するための「共通の尺度」はなく、故に価値の結合や調和は不可能
→本質的には全ての価値は1つの至上価値へと繋がっているとする立場、同じ認識ながら何らかの現実的制約のために実現が困難とする立場を否定するのみならず、そうした哲学を基盤とした歴史認識等派生社会科学の基本認識をも否定する。
◯「共通の尺度」がない中で人間は選択をせねばならいが故に「選択の自由」こそが自由の体系の中で最も尊重されるべき
とまとめることができるだろうか。
通常私は哲人の著作を読む時、まずは一旦その主張を受け入れながらその内容を記憶の中にストックし、それまであるいはそれからの読書や私自身の考察との比較の中で非同期で検証を行う。なので、普段なら少々目新しい主張に出会っても正しく理解することを前提にそのまま読み進めてしまう。
しかしバーリンという哲人の主張は彼が活躍する学術領域においてはかなり抜本的でメタ次元を巡る議論を形成しているため、同様の読み進め方が通用しない面がある。
そのため読み進めるにあたりバーリンの主張を逐一自力で検証し、反証は見つからないかを都度確認し、何度も同じ箇所を読み返しながら読み進めることとなる。
当然力不足なので、途中何度も「読了はできないかも」と投げ出しそうになったが、幸いジョン・グレイ『バーリンの政治哲学入門』の邦訳が2009年に発刊されており、それを補助として大いに活用できたことで、普段しない検証的読み方で納得のいく読了を迎えることができた。
私自身は、バーリンの論理展開には高度な説得力があるものと考えている。
しかし、「選択の自由」に収斂させる(「選択の自由」を選択する)という彼の判断については、同じく大いに説得力を感じながらも、完全に同意することはできなかった。
「自由」が人間にとって重要な要素であることは認めながらも、やはり人間には「自由」では包摂し切れない価値はあるはず。私はそのように思う。人間にとっての価値を自由以上に包摂し得る価値概念を巡り、考察と議論の営みは継続していかなければならないだろうというのが、私が本著と丹念に向き合った感想だ。
もちろんバーリンの思想の本質は「価値の間には本質的に共通の尺度がないこと」という主張にあるため、こうした至上価値を何と考えるかを巡る議論は成立不可能であり、であるが故に個人に「選択の自由」がなければならないことになるのはその通りで、「選択の自由」の価値の高さを些かも否定するつもりはない。
ただ「選択」のような、人間の「意思」によって行われる行為を過度に重視すると、事実上「意思」の行使能力を失った人(例えば植物人間状態になった人)の人権・生存権を巡る価値判断を行わねばならない際に、非常に危険な判断に傾くリスクを恐れる。
バーリンの主張については、「真理」という概念に対する知的伝統批判の部分をしかと受け止めたいと思う。
読了難易度:★★★★☆
西洋的知的伝統に対する抜本度:★★★★★
自由を巡る議論の明瞭度:★★★☆☆
トータルオススメ度:★★★★★
#KING王 #読書#読書感想#読書記録#レビュー#書評#社会科学#政治哲学#アイザィア・バーリン#バーリン#自由論#消極的自由#積極的自由
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
