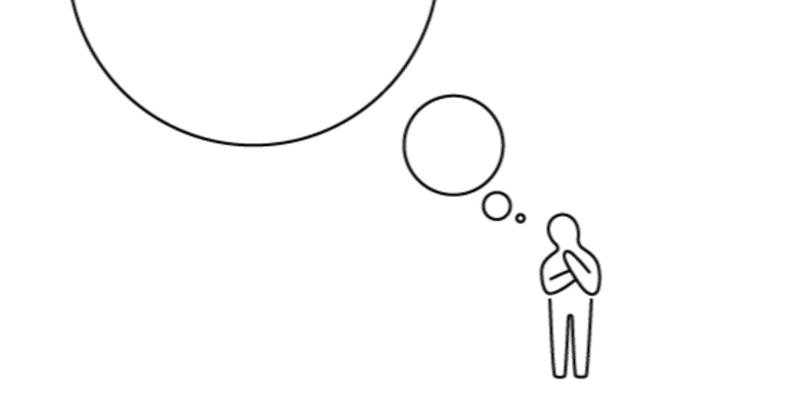
定数を扱えないデザイン業務の難しさ
今回は少し課題の多い話。
クリエイティブ業務は定数を扱えない。
もちろん、受注件数や利益率・加工高等、数値で表現できるものはあるかもしれないが、
一つの業務に対してどれだけの時間掛かるか、費用として掛かるか専門知識がなければ正確に答えることはできない。
ましてや費用についてはどれだけ経験値の高い方でもそれが費用として説得のある裏付けは難しいように思う。
実際にデザイン価格の目安はだいぶ古いがJAGDA(日本グラフィックデザイン協会)が指標を出していた気がする。
今までの先人が色々な議論がなされてきたと考えたうえで、
何故、クライアントとの工数や確認に掛かる時間まで算出して計算しないのかといつも思う。
よく上がってくるスケジュールはどちらか一方の都合のみを記載したものが殆どで、クライアントが受け取ったデザインや制作物を協議する時間を設けていなかったり、そのデザインの確認がどのようにクライアントの社内の工程で為されるのかを知らない人が多い。
クライアントからすると作成にかかる時間や、依頼している会社の業務量の把握をしていないのと同じだと思う。
なので、結局毎回スケジュールがオンスケに変わり仕事全体が逼迫する羽目になる。それは生産性の低下にもつながるし、関係者すべてに波及する事態にもなってしまう。
一度先輩に言われて驚いたのが、
「誰も異論を言わないようなクオリティのクリエイティブをすればいい」
といったニュアンスの話をしていたが、
あまりにも理想論で現実的ではないと思った。

この理想を実現するためには、それこそヒアリングや
クライアント課題の抽出に時間をかけて正確に情報を判断する必要がある。
実際に営業主幹が聞いてきた情報はいつも不足が多く、
必ず再度確認を依頼していた。
社内での打ち合わせは、オリエン情報の横流しは当たり前で
それをするのであれば、クライアントとのやり取りを
変わってほしいとさえ感じていた。

クリエイティブは属人化が顕著で、
社内でも互いの業務の内容を知らないことが多い。
データの作りも個人差があり、管理しにくいのが現実だ。
例えば業務フローのルール化、データ作成のフォーマット化、
必ず複数人のチームで制作を行うなど
取り組み方法はいくらでもあるが、忙しいことを理由にしない人が多い。
こういった風通しの悪い環境が、評価にも少なからず影響する。
現代に根付いた制作現場の環境はなかなか改善しないだろうと思う。。。
もしこれから制作関係の事務所や組織を作ろうとしている人は、
まずは制作やデータの管理などルールを定めることに力を入れた方が、
将来多数の人を管理するときに非常に役に立つと断言したい。
生産量の効率を数値で出すうえでよく言われる
経営の考え方の一つの方法として人事生産性と労働生産性というものがある。
人時生産性

人時生産性 = 粗利益 ÷ 総労働時間
労働生産性

労働生産性 = 産出量 ÷ 労働投入量
この指標を知らない人が意外と多い。こういう知識があるだけで、
普段自分が関わる仕事の売り上げがどの程度なのか、
その売り上げに見合った作業時間はどのくらいなのか、
逆算して考えると今までよくわからなかった
自身の貢献度も可視化しやすい。
それだけでなく、ノルマを抱えている人もこういった目線を持つことで、
業務の取捨選択が可能となり効率よくこなすことができるのと思う。
デザイン業務は定数化できない。
だけど分析方法はいくらでもあるだろうし、
やり方もいかようにもあるだろう。
こういった課題を解決するために、
引き続き様々な知見を得て、模索していきたい。
良ければ《スキ》をお願いします!
同じ活動者や、友人、
将来デザインの仕事をしてみたいと思った方も大歓迎!
興味をもって一緒に制作の仕事してみたいと思ってもらえたら
いつでもお問い合わせください。
s.zakinori.design@gmail.com ← お仕事の依頼・相談はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
