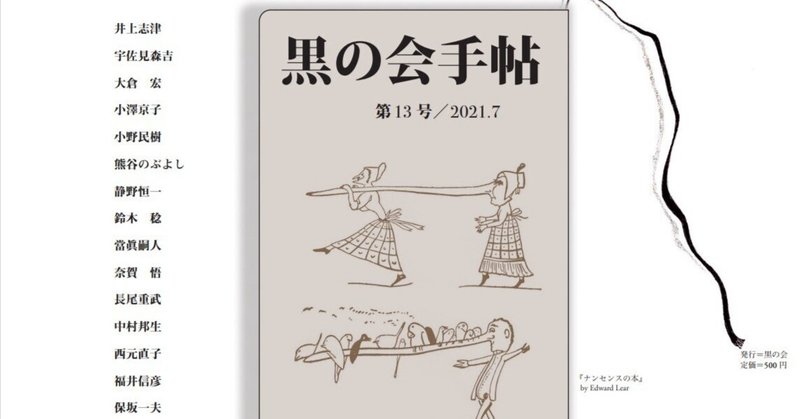
「ディア・ハンター」と父
美容院などで雑談していると、「これまで見た映画の中で一番好きな作品は何ですか」と聞かれることがある。適当に答えればいいのだろうが、真剣に考えて、たいてい「『ディア・ハンター』です」と答える。
「ディア・ハンター」は一九七八年のアメリカ映画。一九七九年のアカデミー賞に九部門ノミネートされ、作品賞、監督賞(マイケル・チミノ)、助演男優賞(クリストファー・ウォーケン)など五部門を受賞した。
私が見たのは高校生だった一九八三年ごろ、東京・三鷹の名画座「三鷹オスカー」でのリバイバル上映だった。見終わって、場内が明るくなっても、しばらく座席から動けなかった。あれほどの衝撃を受けた映画はなかった。
一九六〇年代末期、ペンシルべニア州の田舎町クレアトンで暮らしていたロシア系移民の若者たちがベトナム戦争に出征したことで人生が狂わされる過程を描いた物語。序盤はクレアトンでの暮らしが描かれる。大型トレーラーが轟音を響かせて走り抜ける夜明けの街並み。煙を噴き上げる製鉄所。そこで働くマイケル(ロバート・デ・ニーロ)、ニック(クリストファー・ウォーケン)、スティーブン(ジョン・サヴェージ)の三人は出征を控えている。仲間のスタン(ジョン・カザール)、アクセル(チャック・アスペグレン)と、たまり場になっているジョン(ジョージ・ズンザ)の店で「君の瞳に恋してる」を歌いながらビールを飲み、ビリヤードに興じる姿が魅力的だ。
スティーブンの結婚式が行われた夜、ニックはマイケルに「ベトナムで俺に万一のことがあったら、必ずここへ連れて帰ってくれ」と頼む。翌朝、マイケルたちは鹿狩りに出かける。マイケルはいつものように信条通り、鹿を一発で仕留める。鹿狩りを終えて再び店に集まると、ジョンがピアノでショパンを弾き始める。ニックの微笑み。ヘリコプターの音が入り込み、場面は一挙にベトナムの戦場に変わる。
それからは地獄の光景が容赦なく展開される。戦場で偶然再会したマイケル、ニック、スティーブンはベトナム人民軍の捕虜になってしまう。閉じ込められた水小屋では、北ベトナム兵たちが捕虜にロシアンルーレットを強要し、賭けをして楽しんでいる。死の恐怖に、ニックとスティーブンの精神が壊れていく。
マイケルはクレアトンに帰還するが、ニックは行方不明になっている。スティーブンは両足と片腕を失い、復員軍事病院にいた。見舞いに来たマイケルに、スティーブンはサイゴンから毎月届く差出人不明の紙幣を見せる。マイケルは送金しているのはニックだと直感し、陥落寸前のサイゴンへ向かう。
ニックは記憶を失い、賭博場でロシアンルーレットのプレイヤーになっていた。マイケルはニックの記憶を取り戻し、クレアトンへ連れて帰ろうと、命を賭けてニックに対峙する。躊躇なく銃を取るニックの手を、マイケルは必死で押しとどめ、話しかける。故郷の山のこと、ニックの好きな木のこと……。そのとき、ニックの表情がかすかに変わる。ニックは微笑んで「一発か」と言う。しかし……。
映画は、ニックを失った仲間たちがジョンの店で食事の準備をする場面で終わる。ニックの婚約者だったリンダ(メリル・ストリープ)を気遣うマイケル。スティーブンの妻が「暗い日ね」とつぶやく。ジョンは厨房でスクランブルエッグを作ろうとするが、うまくいかず、泣きながらアメリカの愛国歌「ゴッド・ブレス・アメリカ」を歌う。ため息のような声で、リンダも歌い始める。全員で合唱し、マイケルが「ニックに」とグラスを上げ、みんなで乾杯したところでストップモーション。エンディングのギター曲が流れる……。
余りにも重苦しく、やり切れない映画だった。高校生の私は、愛国歌をうたって、これほど悲しいシーンがあるのかと思った。ニックの微笑みとマイケルの慟哭が頭から離れなくなり、その日から二週間ぐらいは泣きながら過ごした。
私はニックを演じたクリストファー・ウォーケンのファンになった。その翌年か、テレビ放送されたとき、家にはビデオデッキがなかったため、父のカメラを固定してテレビ画面を連写した。賭博場でプレイヤーになり、赤い鉢巻を巻いて出てきたニックの写真がよく撮れたので、硬質クリアファイルに入れ、下敷きとして学校の授業で大切に使った。事情を知らない級友は、虚ろな目をした青年の写真が入った下敷きを少し気味悪く見ていたに違いない。
さて、この映画を、今は亡き私の両親は一九七九年の公開時に見ていた。その日の出来事が、昨年亡くなった母が遺した日記に綴られているのを見て、私は父がとても懐かしくなった。
その日曜日、小学六年生だった私は、両親が映画を見ている間、都心にある祖母の家に預けられていた。両親は映画が終わった後に私を迎えに来て、夕飯をご馳走になって帰ることになっていた。けれども、母は「ディア・ハンター」を見終わって劇場を出たとき、ある「悪い予感」がしたという。
「ディア・ハンター」は当時三十八歳だった母にとっても、四十三歳だった父にとっても衝撃的で、気分が落ち込んだようだ。母は「このまま、あの幸せそうな家に行きたくないなあ」と思ったという。祖母は、母より十七歳上の兄(私の伯父)の一家と暮らしていた。伯父は官僚として、事務次官まで務め上げた後、どこかの財団法人に天下りしていた。
父は出版社で英語の辞典をつくる編集者だった。真面目で、几帳面で、静かで、子どもや女性やお年寄りに優しい人だった。祖母にも優しかったので、祖母はいつも、都下にある私の家に泊まりに来るのを楽しみにしていた。その父がその日、祖母の家で、伯父と大ゲンカをした。母の予感は的中したのである。
ケンカのきっかけはくだらなかった。その日は東京都知事選の日だった。三期務めた革新系知事の美濃部亮吉が高齢を理由に出馬を見送り、自民・民社・公明などが推薦した元官僚の鈴木俊一と元総評議長の太田薫との戦いになっていた。
父は共産党員でも社会党員でもなかったが、自民党支持者ではなかった。伯父はもちろん自民党支持者だったが、そんなことは自明なので、二人が政治や社会問題について話したことなどなかったという。しかし、母の日記によると、その日は夕飯までの酒を飲む間、伯父が社会人になったばかりの娘(私の従姉)に「鈴木俊一に投票したか?」と聞き、従姉が「したよ」と答えたことから不穏なムードが漂い始めたらしい。
母は日記にこう書いていた。
「兄貴が『大衆は底辺だ』とか『マスコミが大衆操作をしている』とか恥ずかしいことを言い出して、彼が反論を始めた。しかし、ちっとも議論はかみ合わず、二人とも激高し始めた。途中から入って来たマキオが『あなたは何だ!』と彼に怒鳴り、兄貴とマキオと彼の三人で『うるさい!』『黙れ!』『帰れ!』『帰る!』『二度と来るな!』と低レベルに怒鳴りあって、彼がバタン! と荒々しく出て行ってしまった」
マキオというのは伯父の長男で、そのときは二十九歳。伯父が五十六歳、私の父が四十三歳という年齢構成だった。居間から怒鳴り声が聞こえてきたとき、私は祖母の部屋で犬と遊んでいた。廊下に出てみると、祖母が心配そうな顔で居間から出てきて、私に「お部屋に入っときなさい」と言ったのを覚えている。結局、父が帰ってしまったので、私と母も急いで後を追ったが、もう父の姿はどこにもなかった。
その後の詳細は不明だ。後日、父と伯父は手打ちをしたようだが、親戚の間では、ムードが険悪になったとき、伯父が「もうやめよう」と何度も言ったのに父がしつこくやめなかったので、父が悪いことになったらしい。板挟みになって、一番居たたまれない思いをしたのは祖母だっただろう。祖母は母に「パパはどうしたんやろうね。仕事に疲れているんやろか」と心配していたという。
祖母の言う通り、父は会社でいやなことが溜まっていたのかもしれないと思う。そこに「ディア・ハンター」を見て、沈鬱な気分になったところに大衆は底辺だと言われたから、何だかニックたちを侮辱されたような気持ちになって、我慢ができなくなったのかもしれない。「ディア・ハンター」にはそれぐらい、見た人の感情を激しく揺さぶるパワーがあった。とはいっても、妻の肉親だからと、それまでせっかく友好的に振る舞ってきたのに、映画に感化されて、築いてきたものを一瞬でぶち壊した父を考えると、バカだなあとおかしく、愛おしくなる。
父は母が死ぬ二年前、八十二歳で死んだ。現役時代は多忙を理由にほとんど家にいなかった。私は父が好きだったが、死なれてみると、実は父のことを何も知らないなと感じている。もっと仕事の話や若かったときのことなど、いろんな話を聞けばよかった。私が高校生時代にリバイバル上映の「ディア・ハンター」を見て感動していたときも、父と感想を話し合った記憶はない。
あの騒動から十年後に祖母は亡くなり、途中からケンカに参入した従兄も、伯父よりも先に六十一の若さで死んだ。息子に先立たれ、元気をなくしていた伯父も、その二年後に亡くなった。母の日記を読んだら、私はその場にいなかったのに、みんなが本気でケンカをしている顔がドラマのシーンのように浮かんできて涙がこぼれた。
母の日記を読んだ後、「ディア・ハンター」を久しぶりに見た。ベトナムの戦場でマイケルとニックとスティーブンが偶然会って捕虜になるなんて、結構、雑な作り方だなとか、やっぱりアジア人を一方的に醜く描きすぎだなとか、そもそも北ベトナム兵は捕虜にロシアンルーレットをさせたのかなと思ったが(ベトナム戦争の取材でピューリッツァー賞を受賞したジャーナリストは捕虜にロシアンルーレットをさせた事実はないと指摘したそうだ)、それでもこの映画の素晴らしさとエネルギーは少しも変わっていなかった。引き出しにしまってある私の下敷きの中のニックの写真も、さすがに色あせてはいるが、今も特別な輝きを放っている。
(黒の会手帖第13号 2021・7)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
