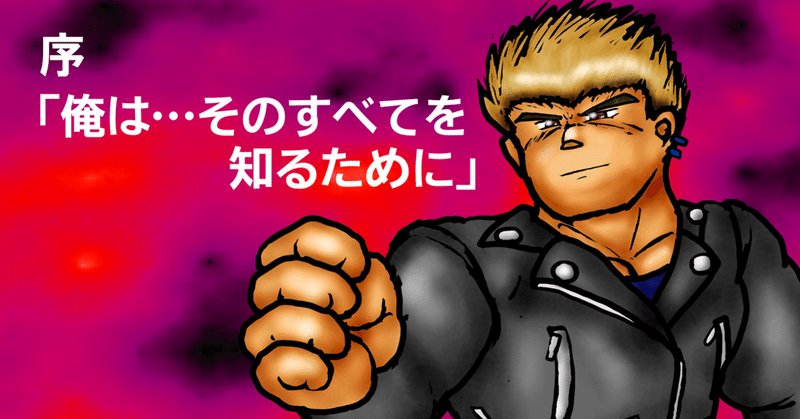
序 「俺は…そのすべてを知るために」
バビロンという街は、もともとエピックヒーロー、ダン・スタージェムの開いた街である。ダン・スタージェム…大脱出を敢行して人々を世界の破滅から救い出した大英雄だが…かれが大脱出以後の生き残るのが難しかった時代に、ふるさとであるこの街を守ってすんでいたといわれている。事実この街の郊外にはダンが育った実家が残っていて、今でもダンの剣術を伝える「星空の戦士達」の聖地として知られている。
「女神」を崇める謎の国家「帝国」がサクロニアに侵攻を開始し、唯一サクロニア側で対抗していた大国イックスが滅亡した「銀竜戦役」以降、このバビロンという街はサクロニア側の対帝国の最前線の都市となった。そのため、すっかり街の雰囲気も昔と違ったものになってしまったのは仕方がない。
第一まず、人口が難民のため数倍に膨れ上がったということがある。帝国に占領された地域から逃げ出してきた難民は百万人以上の数であり、彼らを食わせるだけでもバビロンはピンチになってしまう。それも一時のことならば何とか…援助とかそういうやつで何とでもなるのであろうが、今の状態を見ている限りは全く状況が改善するめどはない。となると、難民じゃなくて新しい市民をどう食わせてゆくのかという深刻な問題に直面してしまうのである。
ともかく、昔は石灰岩作りの由緒ある美しい町並みの豊かな街だったこのバビロンだが、今やかなりの面積の難民キャンプというか、スラム街が広がる…雑然とした街になってしまったのである。
帝国…サクロニアと隣り合う異世界であるカナンで最大の国家…がサクロニア側に進出してから120年、サクロニア最大の強国イックスが滅亡してから5年の月日が流れた。サクロニア内で帝国領となった地域は既にかなりの面積になる。シリーン亜大陸の全域、サクロニア大陸西部の主要地帯全土…厳しい身分制度と奴隷社会を持つ帝国に連れ去られ、奴隷として働かされているサクロニア人も少なくない。いや、それ以上にサクロニアと帝国の間でどうしようもなかったのは、サクロニアに住む非人間種族のことだった。
サクロニアにおいては人間族は人口のわずか4割弱であり、それ以外の人口は他の諸種族…エルフやドワーフ、オークなどの非人間種族である。これらのさまざまな種族が混在して(しばしば喧嘩も起きたのだが)今の独特のサクロニア文明を築き上げた。しかし帝国においては…全くといっていいほど人間以外の種族はすんでいなかったし、仮にいたとしてもそれはどこかの貴族の「ペット」だった。要するに人間以外の種族は動物として扱われていたのである。当然帝国が占領する地域では大規模な非人間種族の虐殺が行われていたし、逆に非人間種族は帝国に対して全く妥協の余地がないほど激しい怒りを燃やしていた。
といっても…今や軍事バランスは圧倒的なまでに帝国側に傾いており、面と向かって帝国軍と事を構える能力のある国家はもはやサクロニアには存在しない。圧倒的な魔法力、軍事力、そして数々の謎めいた超兵器の前にはどうすることもできないというのが実状だった。事実周辺諸国の中には属国状態にならざるをえなかった国も少なくなかった。ヌミディア王国、アーモンド伯国など旧イックスの近くの諸国においては、帝国の守護女神「帝国女神」の教会を作り、多額の貢納品を毎年差し出すことによって、何とか国家としての形態を維持してる状態だった。それ以外の国でも…サクロニアの産業の中心だったイックス、そしてハートランド連合の崩壊によって取り返しのつかないほどの痛手を受けていたのである。難民急増による食糧難、それ以外のすべての工業製品の入手難、交通、通信の混乱、軍事費の増大による財政難 …
いや、それよりももっとひどかったのは、恐らく先の戦争で使われたさまざまな超兵器による後遺症と思われる…気象の異常だっただろう。サクロニア全土で飢饉や干ばつが続発していた。精霊バランスが決定的に狂ってしまったのかもしれない。異常気象だけではない…サラマンダーの大発生、謎の奇病の流行などの明らかに精霊バランスの異常から来る異変がサクロニア全域でしばしば発生している。このために人々の暮らしは今までにない危機に直面していた。
サクロニアは…暗い時代を迎えていたのである。
* * *
そんなバビロン市のスラム街の町角…食うや食わずやの人々がなんとか細々と生計を立てている街の片隅を、一人の少しばかり変わった青年が歩いていた。身の丈は180cm程度とこの付近ではそれほど目立つ背の高さではない。金髪の髪はかなり固いらしく、それをさらに逆立てて油で固めている。
身なりはそれほど貧乏ではないようだった。背中に竜の派手なプリントのある革のジャケットとパンツという、非常に勇ましい服装である。だいたい考えて見れば最近はこういった革のジャケットなどなかなか購入できるものではない。もちろんもっと南方の…まだ無傷の諸国に行けば生産していないわけではないのだが、このバビロンではあまり着ている人はいない。というのはこんないい服よりもまず食料をなんとかしなければならない、というわけでこういったものはどうしても二の次になってしまうのである。
といっても別に…誰もこういう服がほしくない、というわけではない。格好いいし、何よりも暖かい。革の服は風をしっかり防ぐので、ここバビロンのような砂埃の多い風の吹く街では重宝である。逆に言えば、こんないい服を着てふらふらスラム街を歩いていれば、どこからか追い剥ぎに遭ったとしても仕方がない。
ところがこの変わった身なりの青年はまるでそんな危険も全く気がついていないかのようである。いや…彼にはそんな危険などないのかもしれない。なぜなら …
この青年、実際に近くに寄ってみると遠めで見たときよりもずっと迫力があったからである。腕も足も丸太のように太く、筋肉質だった。革のジャケットに隠れていてもはっきりと判るくらいに筋骨たくましい。恐らく…これほどまでに鍛えられた身体を持っているということは、間違いなく相当の熟練の戦士か拳法家だろう。武器をほとんど持っていないところを見ると拳法家と考えるのが自然である。 言ってしまえばこんな厄介な相手に喧嘩を売るというのは自殺行為であるということなのだ。
それに加えて…どうも彼の顔立ちを見ていると(あまりじろじろ見ていると殴られそうなのだが)…どこかこの辺の住民と違うところがあった。このバビロンという街には元々の住民に加えて、イックスから逃げてきた避難民や東の草原地方から来た騎馬民族、南方の商人たちなど、さまざまな人種が入り乱れている。さらにいろいろな種族…エルフやドワーフ、オークや精霊種族である鋼鉄精霊やサンドマンまで混住しているのだから、少々顔立ちが違っていても誰も気に留めないのだが…それにしても彼の顔立ちはどこか雰囲気が違っている。一番近いのはミトラ系の顔立ちだったが、それと比べてもどこか…そう、異世界風の雰囲気が漂っているのである。
青年はしばらく街をさまようように歩くと、町角に座っていた年老いた乞食の前に立ち止まった。乞食は彼の…あまりに威圧感のある姿にさすがにおびえているようである。青年は懐から革の小さな袋を出すと、そこから丸い金の小粒を取り出した。そう…彼が出したのは「貨幣」ではない。金の粒だったのである。
青年は金を老乞食に投げると、なまりの強い西方語で言った。
「…灰色の予言者はどこにいる?」
乞食は金の小粒を拾ってじっと見ると、それをそそくさとどこかに隠してうなずいた。そして東の方にある小さなテントを指差した。
青年はそれだけ聞くと十分だという風にうなずいて、そのテントの方へ歩いていった。
* * *
そのテントは古ぼけた、かなり痛んだものだった。恐らくイックスの陥落のときに市外に持ち出されたものなのだろう。屋根にあたるところに何か擦り切れたような字が書いてある。合成繊維のようなものでできているらしく、古ぼけているが穴などはあいていないようである。
といっても青年はそういうことにはあまり興味はないらしく、無頓着にテントに押し入った。中はあまり明るくなく、簡単な身の回りの品が多少おかれているだけの雑風景なものだった。中央に一人の全身を古ぼけた黒っぽいローブに包み、頭からも布をかぶっている人物がじっと座っている。どうも瞑想にふけっているようで彼が入ってきたことに何も気がついていないように見える。
ただ、鍛えられた拳法家である青年には、この変わった予言者が…どうも老人とかそういうわけではないということがすぐに判った。いや、むしろローブの中の男は…からだの大きさから考えるとかなりの熟練の戦士風に感じるほどだった。
青年はとりあえず…この奇妙な男に声をかけてみた。
「あんたが、灰色の予言者なのか?」
青年が声をかけると、ローブの男は静かに目を開けて一言答えた。
「ああ…そうだ。ジャッキー。」
「ジャッキー」と呼ばれた青年はさすがにぎょっとした表情を隠せなかった。まだ彼は名乗っていないのにも関わらず、このローブの男は彼の名を知っていたのである。男はローブの中に光る漆黒の瞳でジャッキーの方をじっと見ていた。
漆黒の瞳…ジャッキーはその吸い込まれるような瞳の暗さに息を呑んだ。そう… まるで夜の闇そのもののように印象的な黒い瞳だった。
わずかの間気おされたジャッキーだったが、すぐに気を取り直して再びこの予言者に…話し掛けることにした。相手は「予言者」なのだから自分の名前を知っていたとしてもなにも驚くことはない…と、無理に自分を納得させてのことである。
「黄帝の剣のことについて聞きたい。」
ジャッキーはその…「黄帝の剣」という名を、少しばかり強く、正確な「中原語」で言った。それを聞いて予言者はうなずいた。
そう…ジャッキーははるか遠い中原から来たのである。普段はきれいに染めた金髪のおかげでわかりにくいが、実は本当は真っ黒な髪の毛である。もちろん本名はジャッキーではない。サクロニアの人々には発音しにくい中原の名前の代わりにニックネームで名乗るようになったということもあるし、それ以上にできれば …本名を隠していたかったのである。ただ…相手が予言者ということだから、こんな偽名がどこまで通用するのかわからないのも真実だった。あくまで本物だとしたら、だが …
とにかくこの予言者が本物なのかどうかはわからない。ましてや遠い中原地方の至宝である「黄帝の剣」の手がかりをこの予言者が言い当てることができるのかどうかわかったものではない。ただ…噂ではいくつもの奇跡を起こしたという本物の予言者…ということだった。それなら…彼の求める、そして彼のふるさとである「中原」の運命を握るあの剣のありかを「当ててみろ!」という、挑戦的な気持ちがなかったわけではない。
ジャッキーは懐から金の入った袋を取り出すと、今度は袋ごと予言者の前に置いた。しかし予言者はそれをジャッキーの手に押し返した。
「俺は…こんなものはいらない。」
「?」
「もし、おまえが…本当にあの…『黄帝の剣』を…そして、その狂った運命すら…探しているのなら、教えてやる。」
「俺は」と自称する老予言者というのはさすがに聞いたことはない。ジャッキーにはこの予言者の年齢がうすうす想像ついた。恐らく…30歳程度なのだろう… 老人とは思えない太く力強い腕が、はっきりとこの予言者の年齢を語っている。どういうわけで彼が予言者となって、こんなところにじっとしているのか…ジャッキーは首をかしげざるをえなかった。
それよりも驚いたのは予言者の男が、いとも簡単に「黄帝の剣のありかを教えてやる」と言い切ったことだった。「狂った運命」と言ってのけるということは …この予言者はなにかを…黄帝の剣のありかだけでなく、その能力や秘密まではっきりと知っているのだ。そして…それを探そうとしているジャッキーに警告しているのである。
しかし、ジャッキーはわずかに考えた後、まるで何も不安がないかのようにうなずいた。そのあまりの決断の明快さは、あたかも簡単なパズルがとけたかのようだった。灰色の予言者…そのローブの男はわずかにフードをずらして再びジャッキーの姿を見つめた。
「ああ。それでいい。俺は…そのすべてを知るために来たんだ。」
予言者はうなずいた。そして静かに語りはじめた。
「黄帝の剣を …そして進化のルーンの真実を知りたいなら…まずジャッキー、俺は帝国について話さなければならないのだ…」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
