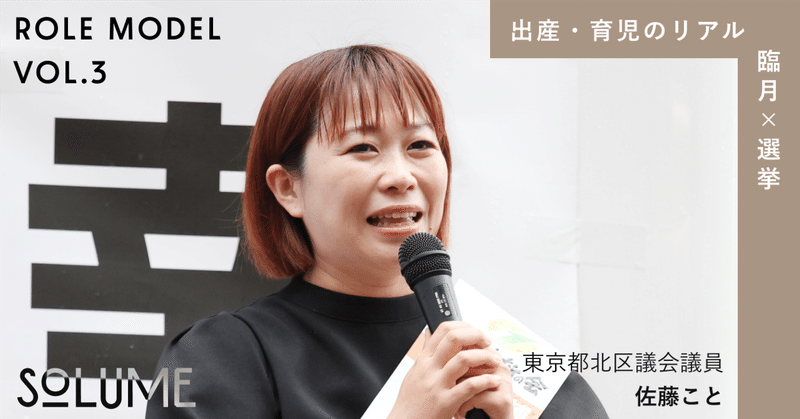
「妊娠は計画どおりにいかない。選挙とかぶっちゃうのも、その状況で頑張るしかないのも、私たち世代のリアル」北区議会議員・佐藤ことさん
広告代理店や障害者就労ベンチャーに勤めながら、2020年より政治活動をはじめた佐藤ことさん。二度の落選を経て、今春チャレンジした北区議会議員選挙では、告示日の翌日に第二子の出産を迎えました。選挙期間の大半を産院で過ごしている姿は、メディアでも大きく取り上げられています。
最終的には、2位の候補に2000票以上の大差をつけての、トップ当選。「臨月選挙」にチャレンジしたのは「出産とかぶっちゃったら、仕方ない。それが私たちの世代のリアルだから」と語ります。佐藤さんにお話を聞きました。
佐藤こと
東京都北区議会議員。
1988年生まれ。東京都北区神谷在住、二児の母(小1、0歳)
ダブリン大学トリニティカレッジ心理学部卒業後、広告代理店を経て、障害者就労支援ベンチャーへ。 日本維新の会北区議員団幹事長。
趣味は銭湯、手話勉強中。
佐藤こと 公式サイト (http://satokoto.com)
私たち世代の「当事者」が、議会にいる必要がある
佐藤ことさんは、もともと議員になろうと思っていたわけではない。障害者就労支援の仕事をするなかで、制度や法律が壁になることが多く、政治の力でなんとかしてほしいと考えるようになった。そこで、人脈を広げてロビイング(※)ができるようにと政治塾に通いはじめたのが、政治の世界に足を踏み入れたきっかけだ。自身が選挙に出るなんて、考えてもいなかった。
転機になったのは、2016年に第一子を出産したこと。

「それまでの人生では、幸いにも男女の差を感じたことがなかったんです。学校でも仕事でも、頑張れば成果が出たし認めてもらえた。でも、妊娠したとたんに周りから突然“ママ”として扱われ、家事をしたり家族をサポートしたりというような『女性のロール』を求められるようになりました。そのうえ、妊婦健診や出産の費用は保険適用じゃないし、補助があっても足りず、結局は持ち出しになってしまう。働きながら子育てをしていきたいのに、保育園に入れるのもものすごく大変でした。
私の無知や準備不足もあったと思うけれど、こんなに大変になるんじゃそりゃみんな産みたくないでしょ、と思ったんです。たとえ個人の準備が行き届いていなくたって、産み育て、当たり前に働いていける社会になってほしいと強く感じました」
そうした違和感や憤りは、いまの社会で子どもを産み育てていれば、多かれ少なかれ抱くものだろう。とはいえ、ふつうはモヤモヤするだけで、出馬までは至らない。選挙にはたくさんの時間とお金がかかるし、家族の理解を得るのも大変だ。
「だから、実際に選挙に出られる人って本当に少ないんですよね。一方で、政治好きの男性が、当選する前から議員のような顔をして名刺を配っていたりして……でも、そういう議員さんばかりでは、私たちの課題はおそらく解決していきません。自分と同じような局面にいる“当事者”の議員が、どうしても必要だと思いました」
選挙は、働きながら両立するのがまず難しい。佐藤さんは最初の立候補のときに勤務先から「選挙の結果がわかるまで、活動期間は休職でいい」と言ってもらえたのが幸いだった。もともと「女性は子どもを産んだら育児に専念するだろう」とさえ思っていた夫にも、理解してもらえた。
「話し合いはたくさんしましたね。『もう決まったから』『この日は選挙運動でいないのでよろしく』などと、強引に家を空けるようなときもありました(笑)。ただ、平日の昼間は私が子どもを見ていたし、休日や夜くらい見てもらわないと平等じゃないという想いもあったんです。いまでは本当にたくさんの協力をしてくれて、心から感謝しています」

ただし、選挙自体の滑り出しは決して順調ではなかった。2020年の都議会議員補欠選挙や2021年の都議会議員選挙では、二度続けて落選。辞めたいと思うことも、何度もあったという。
「でも、毎回落選しているとはいえ、私に票を投じてくださっている方がいるんですよね。子育て世代の方から『3年前からずっと応援しています』と言われることも多いし、その方々の期待や願いを思うと、もっと頑張らなくちゃいけないと感じるんです」
※企業が自社の活動を有利に展開したり、社会課題の解決を促したりするよう、政府に対してルールの策定を働きかけること
妊娠が選挙とかぶったらかぶったで、最善を尽くすしかない
そして、2023年4月。北区議会議員選挙に出馬した佐藤さんのお腹には、第二子となる赤ちゃんがいた。臨月で選挙戦を迎えた様子は、メディアでもたびたび取り上げられている。「区議選は地元とのつながりや握手の数で決まる」と言われるくらい、地道な日々の活動が響く選挙だ。そんななか、告示翌日の出産で本人は不在。しかし、佐藤さんは史上最多得票でトップ当選を果たした。
「今回の選挙では、そもそも世の中の流れが大きく変わったのを感じました。どこの自治体でも、活動量が比較的少ない女性議員の当選が増えたんです。それはたぶん、コロナ禍によって従来議員の岩盤組織が崩れたから。以前は町内の新年会を一日20件もハシゴしたり、いろんなお祭りや餅つきなどのイベントに顔を出したりして強めてきた結束が、集まる機会を失って弱まったのだと思います。浮動票をいかに獲得するかという勝負になったとき、女性候補のほうが共感を呼びやすかったのではないでしょうか。これは時代の変化です。24時間選挙のことを考える時間がなくても、同じ土俵で闘えるようになりました」
最終的にすばらしい結果が得られたとはいえ、臨月で選挙に出ることに不安はなかったのだろうか? 佐藤さんは「かぶっちゃったからしょうがない」とやさしく微笑む。
「2020年の選挙を終えたあと、また出馬することは決めていたので、どのタイミングで第二子を産むかは悩みました。でも、任期中に出産育児をしている区議に相談すると、みなさん『タイミングなんて考えないほうがいい』と応援してくださって。2021年に二回目の選挙を終えてから妊活をはじめたものの、なかなか授からなくて不妊治療をすることになりました。できればもう少し早めに産んで、産後半年くらいで今回の選挙を迎えたかったけれど、そればかりはどうにも調整できず……子育てとは絶対に重なると覚悟していましたが、まさかここまでまるかぶりするとは思っていませんでしたね」
そう笑う佐藤さんを見ていると、これはこれでアリなんだよな、と思えてくる。仕事でもしょっちゅうあることだ。このヤマを越えたら旅行に行こうと考えていたって、一生ヤマは越えられない。先に旅行のスケジュールと航空券を押さえた者だけが、ヤマの向こう側まで行ける。あるあるだ。
「ただ、有権者からは『計画性がない』と批判もされたし、支持者にも『次の選挙を待てばいいんじゃないか』と言われました。でも、次の選挙は4年後。そんなの待てません。それに私は3人目もほしいと思っているので、4年後には3人目を身ごもっている可能性だってあります。だったら、いつのタイミングで出馬しても同じ。妊娠は計画どおりにいかないし、その状況で最善を尽くすしかない……すごい覚悟があったわけじゃないけれど、結果的にそうなっちゃった。それが私たちの世代のリアルなんですよね」
同時期に妊娠をしている有権者からは「妊娠中にバリバリ活動をしている人がいると、何もできない私の肩身が狭くなる」といった意見が届いたこともあったという。もちろん、妊娠中は母体と胎児の健康が最優先だし、誰しもが精力的に活動する必要はまったくない。
「でも、そうした配慮をしていると、妊娠・出産の真っただ中にいる当事者や小さな子どもがいる女性は、いつまでたっても議会に行けなくなるんです。私たちの視点がまったくないまま、政治が動いていくのはとても怖い。だからどんなことを言われても、当事者が議会にいる状況を作るために活動を続けたい、という強い意志があります」

日々の暮らしで感じる課題感を活かして
そりゃあ、選挙と妊娠は絶対にかぶっていないほうがいいですよ、と佐藤さん。たとえば街頭を回るにしたって、チラシにスピーカー、のぼりなど、候補者はとにかく荷物が多い。佐藤さんの支援者は仕事や子育てをしている人が多いから、政治活動は休日が中心になる。これまでの選挙では、平日の街頭は佐藤さんが一人で荷物をかついで回っていたが、妊娠中は重いものを持つのも難しく、平日はほとんど動けなかった。もちろん、つわりの時期は日常生活だってままならないのに、政治活動はほぼ無理だ。
とはいえ、授かったからにはこの状態でやるしかない。チラシのポスティングを業者に委託したり、政治課題を話し合うオンラインプラットフォームを活用したり、これまでしてこなかった工夫も試した。
「選挙期間の途中で出産を迎えることはわかっていたから、私がいなくてもどうにかできる仕組みづくりをがんばりました。体調を優先して午前中と夜は休み、昼間に3ヶ所だけ遊説するとか、夫やスタッフさんだけで活動してもらうとか……リモートでの演説もやりましたね。告示後の数日間は活動するつもりだったのが、陣痛が来て離脱がちょっと早まっちゃったんですけど(笑)。でも、無痛分娩だったから分娩台のうえでその日のスケジュールを組み、周りに託す連絡もできました」
出産費用の手出しは、出産一時金を差し引いても70万円。無痛分娩の費用が上乗せになったためだ。第一子のときの普通分娩に比べ、無痛分娩があまりにも快適で、これが追加料金なく用意されるような社会を願った。
「しかも妊娠中は、長女の保育園の卒園準備もあって。卒園式後の謝恩会のセッティングをしたり、そこで流すムービーを作ったり、いろいろとタスクがあったんですね。だから2月3月は選挙準備と卒園準備が重なり、あわせて入学準備や学童の説明会をこなしながら、確定申告もして……本当に大変でした(笑)。でも、そういう日々の暮らしのなかで『何回同じことを書かせるんだ!』『なんでこんなに時間がかかるの!?』と憤る場面がたくさんあるからこそ、議員になって仕組みを変えていきたいというモチベーションにつながったように思います」
多くの保護者が感じている苦しみや不便を、同じように感じている議員がいる――その事実が心強い。

「困っている人に対して、簡単に支援が届く世の中にしていきたいんです。いまは煩雑な手続きが必要で、申請しないと助けてもらえないことも多いから、その手順を簡素化していけたらいいですよね。そのためにも、自分が直面した課題感は活きると思っています。子育てと仕事の問題もそうだし、直近の小1の壁もそう。不妊治療も、そこまでステップが進んでいない自分でさえ本当に大変でした。ただ、保険適用が始まったとたんに会計がぐっと安くなり、政治の力で暮らしが変わることを実感できたから、私も力を入れて取り組んでいきたいと思っています」
ただ、街頭に立ち、地域の有権者とふれあうこと自体はとても好きだったと、佐藤さんは言う。それができなかった今回の選挙は、不安だけでなく、さみしさもあった。一方で、出産や育児、病気や介護などと選挙を両立できる可能性を示せたことには、大きな価値を感じている。
「選挙活動だけに時間を使えない人もどんどん議会に入っていくべきだから、臨月選挙という大きな縛りはあったけれど、試行錯誤できてよかった。多様性のある議会を実現していくために、これからもがんばります」
取材・文:菅原さくら
写真提供:武藤裕也、佐藤ことさん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
