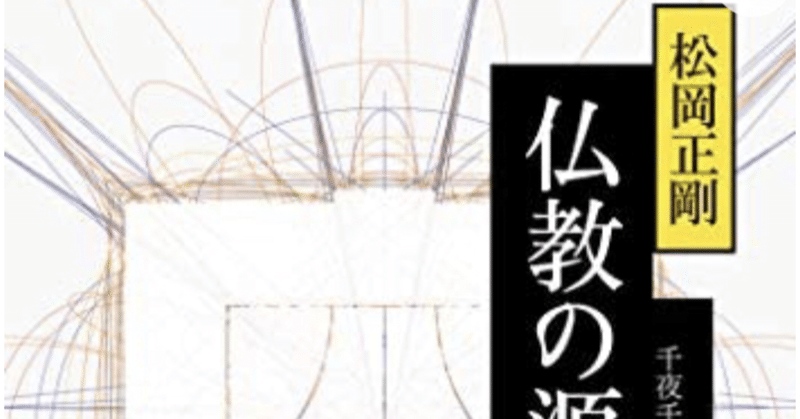
松岡正剛『千夜千冊エディション 仏教の源流』
仏教の誕生から中国に伝播して発展するまでの流れに焦点をあてた骨太な一冊です。
仏教に関するものは身近にあふれていますが、いざ仏教とはなんだろうかと考えると漠然としてしまうのですが、原因のひとつとして中心となる経典が分かりにくいということがあります。
どれだけ理解できるかはともかく、キリスト教なら聖書、イスラム教ならコーランが確固とした中心としてあり、それに触れなくては始まらないというところがありますが、はて仏教でそれにあたる経典とはなんでしょう。般若心経?法華経?いやいや、ブッダ自身の言葉に直接あたるのが大事ならスッタニパータ?どれも重要な経典であることは間違いありませんが、これ一つをもってして仏教の中心と言い切ることは(法華経を奉じる方は別として)難しいのではないでしょうか。他にも多数の経典がひしめいているのはご存じのとおりです。
かように仏教には多数の経典があり、さらに仏教のあり方もインドから中国、そして日本に拡がっていく過程において変容を遂げていっているのですが、こうした仏教のありようは、時空と地域を越えた壮大な「編集プロジェクト」とみなすことも可能でしょう。とすれば仏教を捉える試みは「編集工学」を確立した松岡正剛の腕のみせどころです。実際、本書には仏教が達成してきた編集手腕に正剛さんが舌を巻く場面がしばしばあるのです。
本書の構成は他のエディションと同様4章仕立て。さらに本書の特色として4本の大きい柱がずんと据えられているところにあります。
まず第1章は「古代インドの哲学」。仏教誕生以前のインド哲学の高度な達成が4冊の「千夜千冊」を通して述べられていて、ここに最初の柱である『パガヴァッド・ギーター』があります。肉親との闘いに迷いをみせる王子アルジュナにクリシュナ神が「闘いなさい、そのほうが心も知も平静になれる」と説いた不思議な書ですが、「非暴力、不服従」と唱えたガンジーをはじめ、ソロー、ユング、ヘッセ、シモーヌ・ヴェイユといった知性が愛読した奥深い書物です。正剛さんは『ギーター』の基となっている長大な叙事詩『マハーバーラタ』を要約しながら、『ギータ―』の勘所を指摘してくれています。仏教は「神なき宗教」ですが、古代インドの「神ある宗教」の達成をギータ―に読み取っているのです。
第2章は「ブッダの目覚め」。ここではブッダの生涯や思想についてスポットがあてられ、ブッダが古代インド哲学から何を受け取り、何を加えたかが語られています。後半ではブッダが到達した「空」についての考察が、立川武蔵『空の思想史』を通して展開されています。
そして本書の中核をなすのが第3章「仏典の編集的世界像」。先に述べた本書の4本柱のうちの3本はここに収録されています。すなわち『法華経』・『華厳経』・『維摩経』。どれも読み応え充分ですが、とりわけ個人的に「正剛さん、ノッてるな」と感じたのは『華厳経』と『維摩経』を語っているところ。内容はお世辞にも易しいとは言えませんが、前者はそのめくるめく編集的世界観に、後者では維摩のパーソナリティに正剛さんが心底惚れ込んでいることが文章を通して伝わってくるので、読んでいてもっとも楽しかった箇所でした。華厳経の世界観については、『鏡のテオーリア』の多田智満子さんや、明恵上人をユングと並ぶ師と仰いだ河合隼雄さん、『レンマ学』を提唱し華厳的世界観を現代に再生せんと試みている中沢新一さんなど、私が関心をもって読んできた方たちともつながっているので、もっと学ばねば・・・と改めて思った次第。
そして第4章「中国仏教の冒険」では、いよいよ仏教がインドを越え中国で発展し、逆にインドでは亡んでしまった過程が描かれます。とりわけ興味深く読んだのは仏教のみならず、マニ教やキリスト教ネストリウス派(景教)がシルクロードを通して中国に伝わってきた動向を解説した『シルクロードの宗教』でした。日本についてもここではちらほら見えかくれしていて、道教はなぜ日本では発展しなかったのか?などの興味深い考察もありました。
日本仏教についてのエディションは後日のお楽しみ、となりますが空海、法然についての著書がある正剛さんはどんな風に日本仏教を“千夜千冊”するのか、楽しみに待ちたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
