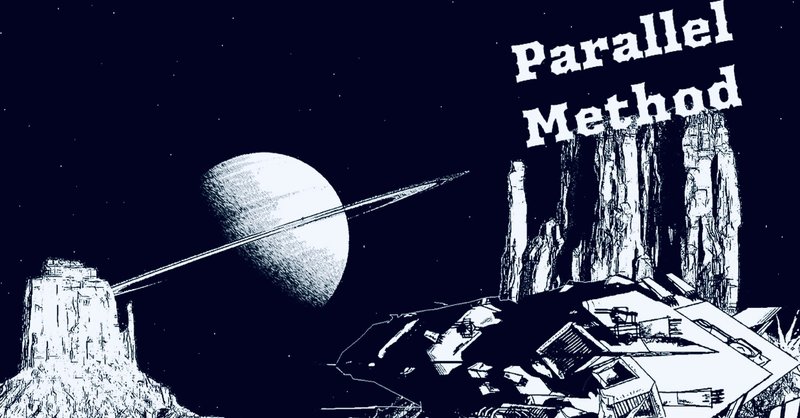
『Parallel Method』プロトタイプ本編①(ネタバレ注意)
『Parallel Method』第1部〈Forest of Mind〉編の一部始終の完全なネタバレです。あらすじ・会話文に肉付け、推敲を施して「本編」に仕上げます。別作品『亞莫』にも登場するキャラクターが多いため、設定の矛盾などが生じないよう備忘録としても書いています。随時加筆修正。
●差別的・猥褻(性的で下品)な発言や表現があります。非人道的な行為を肯定・助長するためのものではありません。
●具体的にグロテスクな表現はありませんが、幼い子どもが死ぬなど残酷な事実を示唆する表現があります。
───────────────
主な登場人物
⚫︎シティ・フォレスター 今作の一人目の中心人物
⚫︎レリーフ(Imaginary Brother/架空の兄)
⚫︎鶴見林太郎(Man Machine/機械の男)
⚫︎スター・フォレスター
⚫︎ナイル
⚫︎〈教護院〉の友人たち
⚫︎ 肖珠(シァオ・ジュ/通称パール)
⚫︎〈旅団〉の仲間たち
⚫︎〈時渡り〉トイ・メイカー
⚫︎オフィーリア 今作の二人目の中心人物
⚫︎望月(ワンユエ/本名オルフェウス)
⚫︎ユリディス
⚫︎ブライト兄弟(兄トーラス、弟アニュラス)
⚫︎ゼッド
⚫︎ギイ
⚫︎アナスタシア
⚫︎ウェイン/〈達成感〉
※ギイの職業「骨格言語翻訳家」原案は館長仮名(Twitter @storyyakata)さまよりご考案頂きました。
───────────────
〈Forest of Mind〉編
第1章 〈心の森〉
病んだ心の化身、病気の黒犬であるシティ・フォレスターは夜毎訪ねてくる不思議な存在・レリーフ(Imaginary Brother)から“外”の世界についてさまざまな話を聴き、己の力で強く生きていくことに憧れを抱くようになる。
「みて。ちょうちょがいるよ、レリーフ」
「レリーフ?」
「えほんでべんきょうしたの。レリーフということばがあったよ。きれいなうきぼりの絵、レリーフというんだって。どこからともなく現れるあなたみたいだった……あなたのこと、そう呼んでもいい?」
「今夜は何を読むんだい。シティ」
「戦乙女の伝説だよ。一緒に読もう」
〈心の森〉に迷い込んだ青年・鶴見林太郎(Man Machine)と一度だけ出会う。シティは鶴見林太郎の存在が異質なものだと感じ、恐れと敵愾心を向ける。
「あなたは、兄さんとようお話しとるっちゅう、シティさんやね? 話だけは聞いとったけど、〈心の森〉はほんまに存在するんですね」
「……あなた、あなた、なんかおかしい。レリーフとも違う変な感じがする。こわい、ちかづかないで! かむよ!」
「そんな、私は何もしません。ただお話しようと」
言葉を遮り、いやだいやだと喚いて、鶴見林太郎とまともに対話しなかった。
「ツルミに会ったそうだね」
「……追い返しちゃった。お友だちなの? おこる?」
「怒らないよ。ただ、もし次に会った時には、できれば優しくしてやってくれるかい。ここは、心に迷いや傷を負った者の魂が訪れる場所。大丈夫、安心して。ツルミは私の大切な友だちだから、シティともきっと仲良くなれる」
「ツ……ツ、ル、ミ。なんだか呼びにくいなあ」
「この世には、いろいろな言葉があるからね」
「ぱんくずを落としていく子は、かしこくない。石ころを落としていく子は、ちょっとおりこうさん。いちばんおりこうさんはね、自分の血を落としていくんだよ。においですぐ帰り道がわかるでしょ!」
「血は流しすぎると死んでしまうし、シティのように鼻が効くひとはそう多くないんだよ」
絵本のなかのまほう使いが話す、知らない国のことば。いってみたいな、外のせかい。
遠くに街あかり。本当に遠くに。幻みたいに。あそこにたどり着けるかな。
お友だちと名前で呼び合えば、もっとなかよくなれるんだよ。
「ダンスの練習、たのしくて好き。でもレリーフは、踊り方よりまず歩き方だって言う。またダンスの練習で足を踏みつけちゃったこと、怒っているのかな……?」
お友だちがほしい。わたしを不気味な黒犬だって分かっても、嫌わずにいてくれる、髪の毛をリボンで結び合ったりできるお友だち。
うわん! って鳴いたら声が響いた。うわお。オオカミになった気分だね。
昔のわたし。もっと小さかった頃のわたし。「わたしが姿をみせるとみんなこわがる。わたしは怪物だ。わたしはみにくくて、やっかいもの。あいつがまたくる。優しいことばをかけにくる。また〈安心〉とやらを押しつけにきたの?」 そんなことばかり言ってた。
「〈心の森〉のカラスは嫌い。つつくし、うるさいし、ずるがしこいから。わたしに嫌なことばかり言うよ」
「シティ。私はね、〈概念体〉という種族で、外の世界のあるひとには、カラスと呼ばれている。真っ黒なスーツで時空を航るからね。カラスは美しい鳥だと、私は思うよ」
「……そうなの?」
「ものの見方はたくさんある」
「わかんない」
「考えるんだ。考えることは貴いことだよ」
「シティ。私の言葉は、私の態度は、私の背中は、キミの世界が花開くための踏み台。存分に、私の上に乗りなさい。そして、どうか私などよりずっと彩りある生を」
レリーフはヒトじゃないけど男の人? わたしは黒犬だけど女の子? 姿に心が引っ張られている。だいじなのはそこじゃない。
ごめんねを言ってきます。〈心の森〉をぐるぐる回って、今まで、わたしがかみついたり、ひっかいたり、ひどいことを言ってしまったひとたちに、ごめんなさいを。カラスにも、石を投げてごめんって言うの。分かってほしいとか、許してほしいとかじゃない。謝るのがけじめなんだよ。
「レリーフ。ツルミにも、ごめんねって伝えて」
心のきれいなひとってどういうこと? お皿を舐めたり、四つん這いで走らないこと? ちがうんだよ、きっとちがうんだ。考えろ、シティ! 「考えることは貴いこと」だ!
《シティ・フォレスター。よくお聴き。姿勢正しく、前を向き、誇りをもって、視線はまっすぐ。他人をじろじろ見たり、睨んではいけません。お話する時は優しく。元気な挨拶は得意ですね? そう、シティ・フォレスター。その笑顔を絶やさないで。》
〈心の森〉の泉の精は、清らかな心の状態なら〈心の森〉を出られると言った。
泉の精から〈変化(へんげ)〉の魔法を授かり、ヒトに姿を変えられるようになる。
レリーフの姿は、むかしのお友だちの身体なんだって。とてもなかよしだったんだって。お友だちは、どこにいるの。レリーフは、ただ帽子を目深に被って微笑んだだけ。
レリーフのことをずっと考えてる。「シティ、恋をしているの?」 おしゃべりな小鳥たちが喚いては去ってゆくけれど。いいえ、恋でもなんでもいいの。レリーフはわたしの宝もの。
虹、朝やけ、夕やけ、あおぞら、よぞら。かみなり、たつまき。みずうみ、さばく。みんなきれい。
「えー! お金って食べものがもらえるの! ご本も! すごい! わたし、お金たくさんほしいな!」
「シティ。大きな声でお金がほしいと言うことを、良いと思うひとも居るし、悪いと思うひとも居る」
「どうして?」
「外に出て、街へ行ってみれば分かるかもしれないね」
かしこいふりはだめ。おりこうさんは、分からないってすなおに言える。
何冊も何冊も本を読んでいたら、とうとう熱が出ちゃった。
「よく来てくれるね、レリーフ。わたしが、可愛い女の子の姿になれたからかな?」
「いいや、シティ・フォレスター。あなたがもう誰かに噛み付いたり、言葉で傷つけたりしないからだ」
「……うれしい。ありがとう」
レリーフとともに丸太小屋を建て、そこに住み、生活と暮らしについて知識を得る。
クッションと灯り、ベッドにテーブルも要るよね。また丸太を運んでこなくちゃ。生活ってこんなふうに汗をかくことなのかな。お腹がすいて、食べて、眠って、また明日汗をかくためにやってゆくことなのかなあ。
レリーフも丸太を運んでくれる。でもあなたって背は高いけどこんなに細いのに……びっくり。あなたって力持ち? 魔法のちから?
小さな小屋。わたしにぴったり。
夜、燭台のもとで本を読む。ふと本棚を眺めて気が付く。
「この本も、こっちもそうだ……お伽話や少し不思議な物語は、全部ギイっていうひとが翻訳してる。こんなたくさんの本を、たったひとりで? 文体も時代もぜんぜん違うのに。ひとりのひとじゃないのかな……?」
小屋には小さなキッチンもある。レリーフがジャムを作ってくれる。ブラックベリーのジャム、さいこう。ジャムを瓶に詰めながら、レリーフは言う。甘いジャムが好きなひとも居れば、苦手なひとも居るだろうねって。
「喧嘩になっちゃわないかな?」
「考えかたや感じかたはそれぞれあっていいんだよ。それぞれ考えていることを言い合って、分かり合えたら、人びとにとって好いことではないかな。私はそのなかに混ざれないけれども……そう思うよ」
生活をするって大変だ。お金が要るんだよね。自分で木の実やキノコを採ったりしているけれど、レリーフがくれるお野菜やお肉、歯ブラシやふわふわのタオル、たくさんの本。レリーフは、いったいどこから持ってくるんだろう。
「レリーフってお仕事はなに?」
「私は、人間のように働いてお金をもらい生活しているわけではないよ」
「そうなの? じゃあ、わたしにくれる食べものやご本のお金はどうしたの? ……ぬすんだ?」
「私がそんなことをすると思うかい」
「ううん。だけど、むつかしいご本に、タダでランチを食べさせてくれるお店なんてないって書いてあったから」
「そうだね。私たち〈概念体〉は、感情を司るんだ。それぞれ任されている感情は違っていて、たまたま私はひとに〈安心〉を与えるのが仕事だけれど、そうしているとお礼にお金を差し出してくれるひとも居る。私は世界中の銀行にお金を預けておいて、いざ必要な時に使う。シティ、あなたが元気になるための食べものや本を贈る時とかのためにね」
「お金を手に入れる方法はたくさんある。ものを売ったり、人を助けたり、物やひとを運んだり、楽しませたり、きれいなものや、おいしいものを作ったり。シティ、もう理解できると思う。この世は今のところ、そういうお金のやりとりで多くのひとが生活しているんだ。もちろんそうじゃないひとたちも居る。でも、あなたが旅立ってゆく街ではきっと、それが世の理とされているだろう」
「わたしひとりでもできることって、何があるかなあ」
「お金を貯めて、ほしいものがあるのかい」
「うん。やりたいことのために、まずお金が要るんだって分かった」
「何がほしいのか、聞いてもいいかい」
「友だちがほしい」
「友だちか」
「そう。お金で買えないお友だちがほしい。たくさんの場所を行ったり来たりするために、そのお友だちに出会うために、くやしいけど、お金が要るんだ」
「ねえ、レリーフ。わたしは一人前になるまで、もうあなたと逢わないことに決めた。あなたに誇れるわたしになるまで。遠くからわたしを見ていて。一人前になったら、その時は……もう一度、一緒にダンスを踊って」
鞄に詰めたのは簡素な着替えと二冊の本。一冊はいちばん好きな物語。もう一冊は日記帳。インク壺と羽ペン。小型の燭台、蝋燭、マッチ箱。ちょっとした貨幣。非常食のクッキー缶。レリーフがくれた、小さな鳥の形をした木彫りのお守り。
鳥。レリーフたち〈概念体〉は時を航るカラス……。
ばさばさと頭上で羽ばたきの音。
「安心しな、泣き虫シティ・フォレスター。おまえがいつ逃げ帰ってきてもいいように、丸太小屋はオレが見張っててやるよ。カラスは綺麗好きなんだぜ」
「……ありがとう」
レリーフと約束を交わし、カラスの言葉に涙を堪え、シティは〈心の森〉から外界へと足を踏み出す。
第2章 〈スラム街〉
長いこと歩き、ある街に辿り着く。レリーフが出発前に持たせてくれたお金で下宿先を探す。噴水前の広場で歌をうたい、下宿先の一階に併設されている大衆酒場で皿洗いをして働き、小銭を稼ぐ日々。その間二か月ほど。
なけなしの貯金をはたき、街の服屋で一着だけ服を仕立ててもらう。真っ黒なワンピースだ。ささやかなレースが施されているが、太く厳ついベルトと、鋭利な鉄の刺や鋲が打たれている。
鞄に下宿先の酒場のステッカーを貼っていたため、店主は知り合いのよしみと言って多少の値引きをしてくれた。人と人との繋がりが思わぬところで活きることを知る。
シティは自分を体現する服装のために、必死で金を貯めたのだった。この服は、“特別な時”に着るために、畳んで鞄へ仕舞っておくことにする。
ある日、〈スラム街〉への入り口近くで馬車に轢き逃げされた老人を助けようと駆け寄った瞬間、馬車から降りてきた男たちに取り囲まれ、馬車に強引に連れ込まれる。轢き逃げされたふりをした老人もグルだった。
ショックを受けている間に、両手を縄で縛られてしまう。
一人の男の元に誘拐される。
屋根も半分崩落しているような、荒れ果てた掘立て小屋だ。馬車の男たちはシティを放り出すとすぐさま去っていった。追跡を免れるために誘拐した子どもを転々とさせるものらしい。
拘束を解こうと必死になりながら、男と対話をし、窮地を脱しようとする。
「おじさんが犯人?」
「いんや。悪いがどうしても人間の小娘を拐ってこいって命令でよ。オレはターゲットを決めて馬車の奴らに持ってこさせる、そんでご主人サマへの受け渡し係ってところだ。見たとこ12歳くれえか? それとも14はいってるか? 路上の歌うたいで日銭稼ぐような貧しいガキは大抵チビだからな。まあ見た目幼いほうが喜ぶ下衆が多いからよ、たぶん値切られることはねえ」
(考えろ、考えろシティ。戦乙女の伝説を思い出すんだ、シティ。こういう時、自分だけが一方的に危ない時は、話をするんだ。すこしでもこのひとから話を聞き出すんだ!)
「どうしてわたしを選んだの?」
「はっ、そりゃ迷子みてえに人気のねえところをふらふら歩いてりゃ……あと、まあ、赤毛じゃなかったからだ」
「赤毛じゃだめなの?」
後ろ手で変化させた黒犬の爪がとうとう縄をほつれさせ、拘束から脱する。そして、全身漆黒の〈心の森のシティ〉の姿へと変身する。
「ニンゲンの子がほしいって言ったよね。おじさん、わたしニンゲンじゃないよ!」
「魔獣か!? こんな人間もどきを連れてこいなんて言われてねぇ。くそ、もう奴に連絡をしちまった!」
「わたし、ずっとこの黒犬の姿でいようか。ワンワン鳴くだけにしようか。そうしたら、その商人さんはニンゲンの子がほしいんだから、わたしを連れていかないよね」
「頼む。奴は冷血で残酷なんだ、オレの首が飛んじまう。人間の姿に戻って大人しく売られてくれ。頼む……」
「首が飛ぶって、どういうこと?」
「文字通りだ。殺されちまう。それか奴隷に逆戻りだ。オレは奴からすりゃ下っ端の下っ端だ」
シティは荒い呼吸を整えながら、男を観察した。男は魂の抜けたような目をしていた。充分に距離を取ってから、静かに告げる。
「おじさんのことを聴かせて」
「……。元々は奴隷だった。元ご主人のお嬢さんが、そう、赤毛のお嬢さんがおめでたいほどお人好しの博識でよ。こっそりオレに読み書きや計算を教えてくれたんだ。それで館に来た商人に取り入って、タダ働きだった奴隷から一転、雇ってもらうことができた」
「ひとを売り買いする商人さんだって分かっていたのに?」
「知らなかった! 奴は表向きはただの道具屋や骨董商を装ってる。外国の珍しい壺やら貴重な絵やらを取り扱う。そういう品の荷に人を隠し入れて売り買いするのさ」
「商人は確かに仕事をこなせば金とある程度の自由をくれる。でも……」
「失敗したら、殺されてしまうの?」
「代えはいくらでもいる、元奴隷の使えない駒は要らねえとよく言ってる」
「……良い案があるよ、おじさん」
「人間の姿になってくれるか?」
「そうじゃない。おじさんも、わたしと逃げるんだよ!」
「おじさんは、本当はわるいひとじゃない。赤毛のお嬢さんにご恩を感じているんだよね。だから赤毛の子は狙わなかった」
「無茶だ。逃げられるわけがねえ。街は奴の情報網が張り巡らされてる。どこかに逃げ込むなんざ……」
「街の外、別の国へだよ!」
「……それこそ無茶だ」
自身を一時的に巨大化させ、男に背に乗るよう促した。逡巡する暇や余裕など男にもなく、シティは彼を乗せると、国境を目指して全速力で疾り出す。
「なあ、あんた……名前は?」
「シティ・フォレスター。おじさんは?」
「……ナイルだ」
やがて、ある大河を越えたところで、シティは満身創痍になる。ナイルも河越えで体力を消耗している。
「ナイルおじさん……大丈夫? ごめんね、わたし、もう、動けないや……」
「いや、もういい。もう、充分だ。動けるようになったらオレを置いていけ。悪かった……ありがとよ」
第3章 〈教護院〉
その後、ナイルと別れ力尽きて倒れていたところを〈教護院〉に“保護”され、五年間を過ごすことになる。
最初に受けたのは“選別”。
集められた子どもたちは種族に関わらず、魔法の使えぬ者と魔法使いの素質のある者とに分けられ、それぞれの教育を受けた。シティは出自柄、魔力をその身に具え、精霊から〈変化〉の魔法を伝授されていたため、魔法使いとして扱われた。
魔法使いは、基本的にヒトの姿をしていても魔力のおかげで数百年は生きながらえる長命な種族である、と初めて知る。
魔法という学問の基礎を学ぶ。魔法史、魔法食、魔法薬学、降霊術、変身術、攻性魔法、守護魔法、治癒魔法、そして、呪いと解放の〈黒魔術〉。ただし、移動術や飛行術は施設からの逃亡を阻止するため教わることはなかった。
〈教護院〉での生活が始まると、まずシティは誘拐される前に身を寄せていた下宿先へ手紙を書いた。
『親愛なるおばさん、おじさん。シティ・フォレスターです。数日間、留守にしていてご心配をおかけしました。ある事情で、隣国の教護院にお世話になっています。どうか安心してください。
でも、そちらにはもう戻れそうにありません。短い間でしたが、優しくしてくれて有難うございました。お家賃は最初にまとめて三か月分お支払いしたけれど、荷物がそのままでごめんなさい。いつかその荷物が必要になるかもしれません。大事なものが入っているんです。どうか、わたしの鞄を捨てずに保管していてもらえませんか。勝手なお願いでごめんなさい。どうかお願いします。 感謝を込めて シティ・フォレスター』
手紙は、施設の外へ奉仕作業に向かう際に、こっそりと投函した。〈教護院〉から外部への公式な手紙であれば、差出人を証明する院の紋章を象った印璽が施されているはずだ。しかし、その手紙は粗末な紙を封筒型にし、樹液を練ってこしらえた糊で封をされているだけだった。
孤児ばかりが集まるはずの〈教護院〉から手紙の送り先がある子どもが居ることに郵便屋は驚いたが、故あってのことだろうと〈教護院〉には連絡せず、そのまま配達をした。
院内は表面的には慈善的で平和だが、“先生”から子どもへの慢性化した圧力やえこひいきがあり、子どもの「身元引き受け人」が望むような非人道的な教育を施される面もあった。
そのフラストレーションによって、子どもたちのなかでも派閥やカーストが生まれ、陰湿な暴力や蛮行がまかり通っていた。
子どもたちは全員純白の、〈聖服〉と呼ばれるローブを身につけることになっていたが、ボロボロに汚れている子どもはよく目立った。そういう子どもは自信をなくし、与えられる「仕事」もうまくこなせないことが多かった。“先生”は、皆の面前で、たとえば廊下で、たとえば食堂で、そんな子どもに唾を飛ばし罵る。
「使いものにならないボロ雑巾め!」
子ども同士での一方的な暴力も、見て見ぬふりをしてしまった。助けを求めるように見つめる子どもから目を逸らした。
「しょうがないよ……止めたらあたしたちだって目をつけられる。あいつら魔法使いの上に、〈スラム街〉育ちで腕っぷしも強い」
「そう、いけないことなのは分かる。でも怖いんだ。誰も守ってくれないんだもの」
シティはそのたびに、〈心の森〉に居た頃、自己卑下していた自分を思い出し、自身から滲み出てくる暗黒の感情に支配されそうになる。
〈心の森〉という特異な出身であるからこそ重宝され、手酷い仕打ちを受けないだけなのだ、と恐怖する。同室の友人や、暴力に屈しない仲間の存在だけがシティの支えとなった。
そんな劣悪な環境のなか、シティが入院した年に院内で男の子・ユニヴァースが生まれた。出産したのは年端もゆかぬ少女だった。むろん、“父親”が誰かは不明だった。〈教護院〉に引き取られた捨て子として扱われるほかなかった。
それでも多くの者がユニヴァースを可愛がった。シティも、ユニヴァースの小さな手に指を握られ、無邪気な笑みを向けられた時、花が咲くような想いがした。
それゆえに、愛情を注がれるがゆえに、ユニヴァースを憎悪する者が居たということだ。
まだたった五歳だった。彼の遺体が見つかったとき、あまりの惨さに、“先生”たちさえ母である少女には見せられず、死因の詳細は伏せられた。
当時院内最年少だったユニヴァースの死に直面し、シティはこれまでにない強大なショックを受ける。
いっそ、ここから逃げ出してしまいたいと。
渡り廊下を同室の友人と歩きながら、ひそひそと話す。
「……シティ。“先生”たちの話を聞いてしまったの。ユニヴァースの生育歴が消えたんだって。あの子が存在した証が消えちゃったんだって」
「そんな……そんなひどい。証拠隠滅? 誰が……でもお墓は残ったままだよ」
「そう、それが不思議なの。あの子のお墓に、あとでお参りにいこう」
ある日、シティはたまたま〈教護院〉にやってきた〈旅団〉についていきたいと勢いよく願い出て、旅団に引き取られる形で卒院する。
「旅団長の肖珠(シァオ・ジュ)です。我らに同行したいという少女は、一体どういう人となりですか」
「ええ、年齢はおそらく16歳ほどの魔法使い。特筆すべきはあの不可知の土地〈心の森〉出身のヘルハウンドである点です。犬としても少女としても使えます。健康で、仕事は集中すればまあまあできます。物覚えも数をこなせば問題ありません。臆病で少々間の抜けたところはありますが素直で言うことはよく聞きます。あとは……」
「いえ、そういったことではなく。例えば、困っている者を見過ごさず助けますか。汚い金を餌に悪事へ唆された時、毅然と断りますか」
「……私どもは、そういった視点から子どもたちを観たことがありません。直接、お会いになられたほうがよいでしょう」
「よく分かりました。シティ・フォレスターさんの身元をお引き受けいたしましょう」
「こ、こんなにも頂いてよろしいのですか?」
「ええ、安いものです。彼女に申し訳なくなるほど。あなたがたは、彼女を“高く売れた”とお思いでしょうが、きっといつか、彼女を手放したことを惜しむ日が来るでしょう」
応接室から出てきたシティにさっそく付き纏い、からかう声が飛ぶ。
「シティ、シティ! 売られたの、買われたの、どっち?」
「どっちでもない」
「あのでけえ旅団って見世物サーカスだろ? 黒犬の立ちションべん見せてやれよ、見世物シティ! ぎゃははは!」
「うるさい」
共同の個室へ戻ると、友人が静かに微笑んだ。
「行っちゃうのね」
「うん、行くよ。みんなの幸せを願ってる」
「あたしも、シティの幸せを願ってる」
出発の日。
シティは純白のローブではなく、自分で選んだ服装をしている。全身真っ黒で、可憐なレースがついているが、鋭い刺や鋲が打たれた装飾に、何本もの太いベルト。そして頭部には白黒ストライプのリボン。
隣の国の、元下宿先のおばさんとおじさん宛てに手紙を書いたのだった。必要な時が来ました、わたしの荷物を〈教護院〉に送ってくださいと。ここを去る者の私物を取り上げる意味はなく、“先生”も素直に鞄を渡してくれた。
「その格好、よく似合うわ」
「有難う。……おばさんたち、この服、五年の間ずっと手入れしてくれてたんだ。ぜんぜん傷んでない」
〈旅団〉の巨大なカボチャ型の馬車が外で待っていた。
「見送りに来てくれて有難う。また逢いにくるね」
「ええ、待ってる」
第4章 〈旅団〉
その後、青年・肖珠(パール)をはじめとした〈旅団ヴァン・デリア〉の仲間たちと二年間の旅路を過ごすことになる。
世界図の西側の大砂漠を越える旅だった。
〈旅団〉の馬車の一番奥。暗がりでとぐろを巻く巨体の四つの目が開く。二頭竜のシー・テム・ヴァン・デリアだ。右の首がシー、左の首がテム。
「歓迎」「しましょう」「シティ」「フォレスター」「ようこそ」「旅団」「ヴァン・デリアへ」
〈教護院〉を出た次の日には、隣街に着く。ここを過ぎたら砂漠は目前、荒寥とした乾燥地帯が広がっているという。
その始めの日に、シティはパールを呼びとめる。
「訊きたいことがあります。改めて、あなたの名前を聴かせて」
「肖珠、と申します」
「う、うまく聞き取れなかったみたい。もういっかい」
「シァオ、ジュ、です」
「ショー、じゅうー……? ……ご、ごめんなさい」
「ですから、パールと御呼びください。呼びにくいのは分かっております。でも、一度は本当の名前を名乗らないといけません。その後で、呼びやすい通称を名乗るのが筋というものです」
「……パール?」
「はい」
「あなたにそっくりなひとを知ってる。本当にそっくり。ツ、ル、ミ。ツルミっていうの、知らない?」
「私は、さっき言った通り、この国のひとたちが名を呼びやすいよう、パールと名乗っています。色々な国を旅しますから、そのたびに違った名を名乗ることも多い。ですが、ツルミと名乗ったことはありませんね。あなたはその人に実際会ったのでしょう? 私には黒犬の姿のあなたにも会った記憶がありません」
「そうだよね……」
「世界は広いですから、一人や二人、瓜二つの他人が居てもおかしくないでしょう」
街の広場で、車を引く馬を駱駝へと交換し、いよいよ砂漠が目前だ、とパールが皆へ告げる。新しい仲間を歓迎する夜であることも。
広場に車を停めさせてもらい、広い車内で街の迷惑にならぬようささやかな宴が催された。ぽこぽこと泡立つような鼓と、優しい微風のような笛の音色。
夜更け。
長い銀髪を頭の後ろでひとつにたばねた女性。腰にはサーベル。昼間のパールの時よりも緊張しながら、ついに声をかける。
「こんばんは……」
「こんばんは。シティ・フォレスターさん。話しかけてくれるのを待ってたよ」
低く力強い声が、名を呼んだ。深い皺だらけの、それでも頑とした掌に握手する。
「パールの友達だってね」
「へ?」
「ありゃ、違うの。そう聞いたんだけど。まあいいか。あたしの名はクリスタル。年寄りだけど一応剣士で用心棒。よろしくね」
シティはさっきからまともに話ができずにいる。体がかちこちだ。広場をひとまわり一緒に歩きながら、クリスタルが話をしてくれる。
「わたしみたいなのを受け入れてくれて有難うございます。ここは、いろんなひとたちの寄る辺みたい」
「そう。あなたの言うとおり、〈旅団〉は傷ついた渡り鳥が羽を休めるような集まりだよ。それぞれがどんな事情を持っているのか、一度に知ることはできないだろうけど」
目を輝かせるシティにクリスタルは目を細める。
「……他人に興味があるんだね」
「そうなんです! わたし、〈心の森〉のシティだから」
「〈心の森〉……話には聞いたことあるなあ。この〈旅団ヴァン・デリア〉はね、千年近い歴史があるんだ。初代団長はこの世のありとあらゆる場所を旅してきたというよ」
「初代団長さんって……あの車の二頭竜の、シー・テム・ヴァン・デリアさんたち?」
「そうだよ。せっかくだから他にも気になる人がいたら教えてあげる」
「……あの、男の子がひとり居ますよね。わたしよりすこし、年上くらいの」
「あー、ベックかな? 根性悪のクソガキ。生まれたばっかり。まだ十八歳くらいよ、確か」
「……生まれたばっかり?」
シティの問いには答えずクリスタルは車を指差した。
「宴の時に話す機会がなかったり、寝てた連中もいるだろ? これから一緒に旅をする仲間だから伝えとこう。音楽を演奏してた〈太陽〉の踊り子イルリメと〈月〉の歌姫ラリプナは姉妹みたいなもんね。大型犬とヒトの混合種族、ワンダステイ。あなたと似てるね。詩人で繊細なうえにもうお爺さんだからよければ話し相手になってやって。樹木の精霊一族のお嬢さま、コンスタンスはまだたったの九歳。あの子も大概素直じゃないな」
「元ゴロツキも捨て子も種族は問わずなんでもござれ。料理人や医者も居る。なにか困ったことがあったら彼に訊いたらいい、現団長で曲芸師のパール。彼の本名はあたしも発音できないや!」
からからと笑うクリスタル。
「……あっと、忘れてた。そういえば、最近仲間になった男がひとり。変な男だよ。何もない空間から突然現れてぶっ倒れて、過労らしいから団長の判断で元気になるまで一緒に居ることになったんだけどさ。鞄抱えて、コート着て、〈達成感〉を与えるために世界中走り回ってるとか何とか言ってたけどよくわかんないや。今も馬車の中でぐうぐう寝てるし。まあうちは懐が深いのが取り柄だからさ、ワケ有りの奴なんて珍しくもないけどね」
クリスタルが呆れたようにに息をつく。
クリスタルは変だというが、シティはすこしひっかかるところがあった。何だか似たようなひとを知っている気がするから。
「そのひとに、お名前はある?」
「ああ。ウェインっていうらしいよ」
あれ。名前があるんだ。じゃあ、ちがうのかな。レリーフと同じようなひとかも、って思ったんだけどな。
「その真っ黒でベルトだらけの格好、暑くない? これから砂漠を越えて、さらに南へ向かうよ」
「大丈夫、わたし暑さも寒さもへっちゃらな黒犬だから。それに好きで着てるの」
「ああ、そんならいいや。心配しただけ」
「うん、有難う」
突然、髪を掠めて投げつけられたのは針金。
「……あなたは、ベック!? なにをするの、危な……」
「クリスタルからおれの名を聞いたな。おまえなんかに気安く呼ばれたくない」
「いいか。おまえやあの変な男みたいな新入りどもが、うちで悪さをしないか見張るのがおれの役目だ。シー婆とテム爺が与えてくれた仕事だ。絶対に手は抜かない」
「悪さなんてしない! 今のあなたのほうがよっぽどひどいよ。怪我をするところだった!」
「どうだかな。そう言って盗っ人は〈旅団〉に忍び込むんだ」
「こらこら、あんたたち。夜遅いんだから早く寝な。街のひとたちに迷惑だろ」
旅の途中、竜の子ベックとは何度か衝突をし、よく喧嘩になる。そのたび、とらえどころのない不思議な男ウェインやクリスタルが場をとりなすことが多かった。
ある時、一行は物資の取引のため、あるオアシス付近の町に立ち寄る。ワンダステイとシティが運んでいた、皆の食糧と物々交換するはずの大切な織物などを賊に強奪されてしまう。
「盗られただあ!? シー婆とテム爺が蒐めてきた東の貴重な調度品も! ラリプナとイルリメの髪の毛で編んだ〈月と太陽の紗〉も! 皆のこれからの生活はどうなる!?」
ごめんなさい、とシティの震える口元から謝罪の言葉が漏れる。激昂するベックをワンダステイがなだめようとする。
「お待ちなさい。フォレスターのお嬢さんのせいではない。私が重量に耐えきれず背から荷を下ろしたところを狙われたのだ。責めるならこの老躯を責めるがよい」
「ワンダー爺さんは黙っててくれ」
「いいの、ワンダステイ。すこし休んだらって言ったのはわたし、悪いのはわたし。本当に……とんだ厄介者だわ」
「大丈夫よ。あたしらお得意のサーカス芸があるじゃない。投げ銭をもらえば幾らか足しになる」
からっとした声の持ち主、イルリメが車の中から現れた。
「他に行商人たちもこの町に来てる。〈旅団ヴァン・デリア〉と言えば千年の歴史。顔が広い初代団長の口利きで何かしら恵んでもらえるかもしれない」
「この〈ヴァン・デリア〉が物乞いをするだって……!」
「分かち合えば喜びは倍に、悲しみは半分に。旅は道連れ、世は情け。ベック、あんたも初代からこういう言葉、聴いたことあるでしょ。つまらない恥だの見栄だのは見苦しいだけ」
〈月〉の子であり陽の下に出られないラリプナが日影に留まって状況を見守りながら、イルリメの言葉を継いだ。
「そうそう。冷静に考えましょう。あたしたちの髪ならすぐ伸びるしね。砂漠で怒り狂ったら頭の中が沸騰して脳みそが干からびてしまうわ」
「ふたりの言う通りだ。フォレスターのお嬢さん、気に病むことはない。無償の飯屋などないが、我々には舞踏と曲芸の興行と、千年、世界のあらゆるひとたちと紡いできた関係がある」
それでも顔を上げられないシティを見て、嫌悪を隠そうともせずベックが吐き捨てる。
「〈病んだ心の化身〉! まさにその通りだな。皆が前向きに励ましてくれたのに、いつまでもグズグズいじけて、見てると腹が立つ! おまえなんか、外にしゃしゃり出てこないで〈心の森〉で引きこもってりゃよかったんだ!」
「……いつもいつも、おまえなんかって言わないで! それならわたしだって言わせてもらうけど……ベックなんか竜のなり損ないのくせに!」
「何だと……!!」
「両者ともそこまで」
その途端。パールの静かだがよく通る声とともに、今にも互いに飛びかからんばかりのシティとベックは取り押さえられていた。
クリスタルとワンダステイが、半身黒犬の姿になり唸り声を上げるシティを。ウェインとイルリメが、荒々しく真紅の呼気を吐き出す半竜のベックを。
ふたりは引き離され、重たい空気のまま陽が落ちる。
満月の夜。
カボチャ型の車の屋根であぐらをかくベックの後ろに、パールが佇む。
「なんだよ。説教でもしにきたのかよ」
「ベック。私も魔法使いのなり損ないです。たったひとつの魔法しか使えません」
「……! あんた」
「皆は私を人間だと思っているでしょう。打ち明けたのは、初代団長と、たった今、あなたにだけ。世代が変わるごとに他者の姿を借りながら、ずっとこの〈旅団〉と共に過ごしてきました。変身術ではなく、魂と精神の器の容れ替えです。この姿も、〈賢哲の蒼き岩場〉で見つけた誰かの〈記憶〉の拾いもの。シティさんが出逢った、ツルミというひとのものかもしれませんね」
「そうだ、シティ・フォレスター……あいつ、おれのことを……!」
「“なり損ない”だけれど、時にそれも役に立つ」
ベックがいきおい振り返ると、パールは月光の下、微笑んでいた。
「この身には、〈終焉の黒魔術〉が封印されているのです。その行使のみが、私にできることのすべて」
〈終焉の黒魔術〉。表裏一体の〈呪い〉と〈解放〉を司るすべての黒魔術を、この世から消し去る最後の黒魔術。
いつだったかも思い出せない遠い昔、この世を創造したと伝承される者から与えられたのだという。
「……あんたみたいな若造が、なんで団長なのかずっと不思議だった」
「はは、キミも若造ではないですか」
「今はだけどな。竜は千年生きる」
「そう。竜は千年、と言われていますね。……この先。初代が亡くなったら、今のままでは、かれらを頼りにしている皆は混乱するでしょう。その時のために、じきに皆に正体を明かさねばならないとは思っていました。今、キミに話せて良かったのかもしれません」
「……シー婆と、テム爺が、永くねえ、ってことは分かってる」
「そう、キミには酷な事実ですが、この先どんなに保ってもあと百年かすこし……。時代が巡って、キミが団長になる時もくるでしょう」
「……なり損ないは、何にもなれないに決まってる」
「決まっている? なぜ。キミは千年を生きるのでしょう。千年もの月日を、なにひとつ変わりばえしないまま生きて死ぬのですか。自分は変わらないというその思い込み。ベック、それはいっそ世界に対して傲慢ですよ」
「傲慢。なにが傲慢だ」
「なぜなら現にキミは、変わっているからです。変わり続けているからです。シーとテムに拾われる前後で、キミの心は少しも変わらなかったのか。救われなかったとでもいうのか」
「あ……」
「キミはその恩義と忠誠感から、出会ったその日にシティ・フォレスターに釘を刺した。感情を表に出すことの少なかったキミが、彼女と喧嘩を繰り返して、これまでにないほど激昂した。十八年という短い時のなかでさえ、こんなに変化に富んでいるではありませんか」
ベックは無言のままだった。だが、パールは彼の内から音や感触のように伝わってくるものを確信する。
「そしてまた、今、キミの心のなかできっと何かが変わった。……初代亡き後、我ら行くあてのない者たちの寄る辺〈旅団ヴァン・デリア〉は存続するか、それとも結束を失い散り散りになり、その旅路に幕を下ろすか」
「終わらせたくない。“ここ”は消えちゃダメだ」
「なればどうすべきか。現団長である私から告げる。未来の団長はキミです、ベック。誇り高き竜族よ、あなた自身に問いかけてください」
同時刻。
魔鉱石が水底に埋まっている影響で、エメラルドグリーンに発光する泉の側。座り込むシティの横に、クリスタルが黙ったまま腰を下ろす。
クリスタルは素焼きのマグカップにコーヒーを淹れたものを片方シティに差し出した。優しい土の手触りのマグカップを両手で受け取る。
砂漠の夜は寒い。熱いコーヒーが、涙を流しきって冷えたシティの心と身体を慰める。
「クリスタル。ひとを侮辱したり、されてしまったこと、ある……?」
「……あるよ。聴きたい?」
「あなたが話せるなら……」
「いいよ。ちょいと血生臭い話だけど。あたしは剣(つるぎ)の国出身でね。剣の腕前がすべてに勝る、そんな価値観の環境で育った。早熟ってやつかな、己の剣術に慢心して、師匠さえ見下してた。どいつもこいつも弱くて手応えがない、ってね。同じ門下生が必死で修行してる姿を鼻で嗤ったりもした。そんなことをして一人前のつもりで旅してたら、異国で出逢った剣士におまえの剣は脆い、と一刀両断された。一瞬でね。じつにあっけなく、完敗だった。肩から腹まで一閃の刃で裂かれて、殺されかけたよ」
シティは息を飲むも、無言で先を促す。
「その剣士が、この〈旅団〉の先代・用心棒。情けをかけられて旅に同行するようになったけど、あたしの悪名はそこそこ広まっててね。そのせいで皆には随分迷惑を……迷惑どころじゃないね。かつてあたしに侮辱され、蔑まれたことを恨んで復讐するために追ってきた剣士たちの奇襲を受けて、先代は亡くなった。あたしを庇ったんだ」
クリスタルの低い声は始めから最後まで静かだった。
息を飲んだまま呼吸を忘れているシティの背を、クリスタルがとんとんと柔らかく叩いた。
「それからいろいろあって三十年ばかし、〈旅団〉に忠誠を誓って仕えてるってわけ。昔話はこれでおしまい」
深い息を吐き、シティは言葉に迷いながら首を振った。
「……気高いあなたに限って、そんなことないと思ってた」
「光栄な言葉だね。でも、あたしもこんなふうに汚れてるんだよ。清廉潔白な奴なんて、この世のどこにも居ないんじゃないかねえ。居たとしても、そいつは過去にきっと泥にまみれた経験がある奴さ」
数ヶ月が過ぎた頃、あるオアシスにたどり着いた時、ウェインは告げる。
「さて。俺はそろそろ、ここらで気ままな一人旅に戻るよ」
「ウェイン、あなたが居なくなるのは寂しいよ」
「そうさ、それに砂漠をひとりで越えるなんて危険すぎる」
「ここが嫌になった?」
「いやいや。居心地が良すぎるくらいだね。だからよくないんだ。カラスは飛び回ってなきゃな。一応、“仕事”もしなきゃならないんでね」
「カラス……。ウェイン、教えて。あなた、〈概念体〉って知ってる?」
虚を衝かれたウェインが、ややあって笑みを浮かべる。
言葉はなかった。だが、シティはそれで理解した。
「有難う、ウェイン。……あの、もしも〈安心〉を届けて世界を駆け巡る“カラス”に逢ったら、シティ・フォレスターは元気でやっています、と伝えて」
「うーん。その必要はないと思うがねえ」
「……え?」
「シティ・フォレスター、あなたのなかに〈安心感〉が在れば、“そいつ”はたとえ今ここに居なくたって、存在する。あいつにはきっと分かるはずだぜ」
シティは、この機を逃すまいと、ずっと考え続けていたひとつの問いをウェインに投げる。
種族が同じでも、能力が違っても、関係なく優遇される者、蔑まれる者。他者と自分の違い。あらゆる他者の違い。
「ウェイン。人間って、他者(ひと)って、どう思う。人間って、なんだと思う。何が人間の証で、どこからが人間じゃないと思う?」
「良い質問だ。答えの代わりにひとつ教えよう。俺たち〈概念体〉は、この惑星で〈感情〉を所有・循環・増幅させ、幻質……魔力を持たない者を〈トゥア・ロー〉と呼ぶ。すなわちヒト(Homo sapiens)だな。でも、かれらが〈人間〉と自称するから、俺はかれらを人間と呼ぶ」
「〈トゥア・ロー〉……」
「どこかの少数民族の言葉で、“こんにちは”って意味らしい。最初に〈人間〉に出逢った〈概念体〉が、初めて声を掛けられた時に聞いた言葉が由来だとさ」
不思議な男ウェインは去った。
去る者があれば、現れる者がある。
砂漠を越え、シティが〈旅団〉で過ごし始めて二年が経った頃。
「〈時渡り〉の魔法……」
「そう。私は一度だけその魔法によって現れた人物と出逢いました。トイ。その名はトイ・メイカー。次の街で、会う約束をしています」
パールから〈時渡り〉の情報を得て、世界を創った伝説の存在といわれるトイ・メイカーに出会う。
《亞莫よ。投企計よ。創意よ。今しばらく待たれよ……。》
《物語を編まなくてはならない。物語を消し去ってはならない。物語を喰い尽くされてはならない。》
《この視界に開ける物語を観ていたい。シティ・フォレスター。時を航り、現実を超え、物語を生きる者。ゆくべき者よ。》
トイから〈時渡り〉の魔法を伝授される。
〈時渡り〉は過去にも未来にも行ける。ただし、時空駆動体・精神生命体と呼ばれる者にしか行使できず、過去や未来自分自身、および自分が生まれるより以前の時象に干渉することはできない。時象の改編を行ったとしても、過去にとっても未来にとってもそれは“必然”であり、事実は変えられない可能性が高い。
トイから、五百年先の未来では竜族が迫害され、存続の危機にまで追い詰められていることを聴く。
二頭竜のシー・テム・ヴァン・デリアや竜の子ベックとの交流を通し、竜族の未来を案じたシティは、〈時渡り〉を行使することを決意する。
「未来は変えられない、と言われていますよ」
「それでも、巡ってきた可能性を逃したくない。わたしにできることをしたいよ。……ううん、建前なのかもしれない。わたしはいろんな世界を見たい。いろんなひとに逢いたい。トイさんが言うように、わたしは“行かなきゃいけない”気がしているの……」
竜の子ベックが相変わらずの仏頂面で進み出て、シティに小さな小袋を投げつける。小銭を入れるような、赤紫色の紐で綴じられた小袋。
「その袋! 今は絶対開けるなよ」
「なあに? 何が入ってるの?」
「……お守り」
思ってもみなかった言葉に目を丸くするシティにさっさと背を向け、竜の子ベックはその赤い尻尾を振った。シティは小袋を鞄の中にそっと仕舞う。
再び、持ちものは自分の身と鞄ひとつ。
「パール。わたしを連れ出してくれて有難う。みんなも、短い間だったけれど有難う。いつかまた、どこかできっと」
「こちらこそ今まで有難う、シティ・フォレスターさん。良い旅を」
第5章 〈自由〉
そこは北方の地。
ある国の軍施設内に幽閉されている水竜の生体兵器・オフィーリアと、その世話係の軍人・望月(ワンユエ)。
オフィーリアは上半身がヒトに近く、下半身がマーメイドのように竜の様相をなしている。
初めての〈時渡り〉を行使したシティは、五百年後の世界へと転送される。
到着地点は、オフィーリアが幽閉されている檻のなかだった。そこでシティはふたりに出会う。
突如、牢のなかに黒い円のゲートが開く。飛ばされてきたシティは、しばらく石の床の上に叩きつけられて気絶していた。
目が覚めると、シティは敷き物の上に寝かされており、オフィーリアと望月がこちらを見つめていた。オフィーリアは小さな食卓でフライドポテトをかじっている。
どうやら時刻は夕食時らしい。冷たい石の牢獄に、薄明かりが灯っている。
「あら、お目覚めみたい。はじめまして。わたし、ちょうど食事中でごめんなさいね」
「あなたたちは……?」
「こちらが聞きたい。あなたの名は?」
「シティ・フォレスター。ええと……」
シティが何と説明して良いか迷っていると、ふたりは気にせずそれぞれ名乗り、勝手に話し始めた。
「そーいえば飼育員さん、軍内に侵入者だけど報告しなくていいの?」
「いやあ驚いた! いったい何の魔法だろうか! 初めて目の当たりにしてあまりのショックで記憶が飛んでしまったようだ!」
「生体反応センサーがあるって言ってなかった?」
「ああ、それは報告した。誤作動だって」
シティが状況を掴めず困惑するなか、オフィーリアが食事を終え、望月が食器を下膳する。
「それじゃ、俺はこれで失礼するよ。オフィーリア、明日は……耐えられそうか」
「いつもどおりよ。大丈夫」
「……そうか。終わったら無理をするなよ。おやすみ」
重たい鉄扉が閉ざされる。
「見逃してくれるの? 望月さんは、軍人さんなのにそれでいいの……?」
「さあ。なぜか分からないけど、あのひとだけ、他の軍人とは違う。わたしを唯一、実験体とか兵器扱いしない」
「実験、体? 兵器……?」
「さ、今夜は歯を磨いてもう寝なくちゃ。悪いけど、わたし、明日の朝からちょっとひと仕事あるの」
次の朝。
オフィーリアは檻からどこかへ連れ出されていった。シティはその直前、オフィーリアから姿を隠すよう囁かれ、とっさに小鼠に変身して牢の隅でそれを見送った。
再びオフィーリアが牢に戻ってきたのは、日が暮れる頃だった。全身に傷を負った彼女を見てシティは動転し、治癒魔法を試みようとするが、オフィーリアに制止される。
「あいつらはわたし自身の、兵器としての回復力を観察するためにこういうことをしている。下手に魔法で治癒された痕跡を見つけられると、あなたの存在が知られてしまう」
「でも、でもこんな……」
「狼狽えないで、シティ・フォレスター。問題ない。損傷を受けてもこの程度では壊れぬように造られている。あなたのその気持ちだけでいいわ」
「よ、よくないよ。だって、たとえば体格が良くて頑丈な身体のひとを、それだからって、それだけの理由で殴ってもいい理屈なんてある?」
「……あなた、すごくまともなことを言う。どこから来たの? 昨日は全然話ができなかったから、気になっていたの。お互い自己紹介しましょう」
ふたりはそれぞれの来し方を語り合う。
オフィーリアは、生体兵器として生まれて十八年間、ずっと牢に閉じ込められ、身体的・精神的な苦痛を伴う実験台にされてきたことを話す。
「耐久性試験とかいって、大火炎を放出する部屋に閉じ込められたりした。あれは死ぬかと思ったわね。傷を癒して強度を高める施術を受けたらもう一回火の海へ。その繰り返し。だけどわたし、水中で暮らす竜の素体を元に造られてるらしいから、どうしても乾燥には弱くって。そしたらなんて言われたと思う? “せっかく造ってやったのに使えんやつめ!” 」
シティの脳裏をフラッシュバックする光景。
〈教護院〉の“先生”の言葉──「使いものにならないボロ雑巾め!」
「うっ……」
「……ごめん。もうこの話やめとく?」
「……大丈夫、わたしは、大丈夫じゃないけど大丈夫、そうじゃなくて、オフィーリアさんがそのことを話すの、つらくないかなって……」
「……そんなこと言われたの初めて」
「路上で生活しているようなひとたちを連れてきて、こいつらを殺せと言われたわ。嫌だと言ったら無理矢理に力を発動させられた。どうしても嫌で全力で抵抗したら、今度は死刑囚ならば殺せるか、とそのひとたちが連れてこられた。見たらすぐ分かった、無実の罪を着せられた竜族も中には居たのよ! 無垢で絶望に満ちたあの目……わたしを見るあの目……!」
シティはオフィーリアの頬を伝う涙を拭き、黙って彼女の傷だらけの身体の、傷のない肩の一部に手を添えた。
「竜は気高く誇り高い。けれど、今の時代では暗黒種族とか邪悪の化身だとか言われているわ。そうだ、シティ。侮辱された時はね、親指を下げるか、中指を立てて“ファッキュー”よ」
「でも、他者(ひと)を侮辱はしてはいけないでしょう? それじゃわたしも相手を侮辱することになってしまう……こう……ぐるぐると、終わりなく続いてしまうよ」
「うん。言いたいことは分かる。負の連鎖ね。わたしは方法(メソッド)を教えただけ。するかしないかは、シティ、あなたが決めること。……ふふ、わたしって、悪い友だちね」
「オフィーリアさんは、強いんだね」
「さんは要らない。それに、わたしひとりだったら、とても正気を保っていられなかったでしょうね。飼育員さんと、もうひとり……」
「ほかにも、誰か優しい軍人さんがいるの?」
「ううん。なんていうか、わたしもあのひとのことがよくわからないの。姿も知らないし、分かるのは声だけ。でも、なんてことないくだらない話をしたり、つらい時には慰めてくれる。もしかしたら、わたしが頭のなかで勝手に作り上げた誰かなのかも」
不当に拘束され実験体にされているオフィーリアと交流を重ねていくうち、彼女と同じ世界で、ともに「自由」に生きていくことを決意する。
あることをきっかけに、軍人・望月の正体が、オフィーリアを解放するために姿を変えて軍部に潜伏している翼竜・オルフェウスであることを知る。
「この国は現状、表向きは軍と政治は切り離され独立したものとされている。立場上はね。しかし、政府はもはや骨抜き状態だ。事実上、軍の独裁体制になりつつある」
「この姿は旧友の身体でね。もう数百年前になるか……旅好きで料理好きな、良い奴だったよ。彼から教わった料理法が今に活きているというわけさ」
シティはオルフェウスに協力することを約束する。
「望……オルフェウスさん。あなたが、突然現れたわたしを捕らえたりしなかったのは、オフィーリアのために仲間が必要だったから?」
「捕らえる必要などなかった。現れた場所が牢のなかだっただろう? ……というのは冗談で、最初はもちろん驚いたとも。だが、あなたから微かに同胞の……竜族の気配がした」
「あ……! これ……」
鞄の中身を思い出す。別れ際、竜の子ベックから投げつけられた赤紫色の小さな袋を開ける。中には、ベックの鱗が一枚入っていた。
「懐かしい気配だった。竜が己の一部、角や爪や鱗を渡すのは、厚誼の証だ。だから、あなたは竜族を害さないと判断した」
「ベック……」
「あなたにも、よい友だちが居るんだな」
牢の外から差し込む光。
純白の毛並みに蜂蜜色の瞳をした猫が狭い窓枠に器用に立って見下ろしていた。
望月が敬礼のポーズをとる。
「軍の施設なのに、猫が居る……」
「エリーゼ将軍。特別に大将の地位を与えられしお方だ。撫でる際は大将直々の許可が必要になる」
「そ、そうなんだ……」
「厳つく空気のぴりつく軍内において、癒しと力を与えてくださる大変貴重なお方だ」
オルフェウスは、竜族の故郷の誰にも告げず単身で潜伏している。これまで自身が竜族であることは、迂闊に誰かに打ち明けるわけにはいかなかった。
「今のところ、この国で俺の正体を知っているのは、“養父母”だけだ」
「偶然、夫婦が人気のない夜道で通り魔に遭ったところに俺が居合わせてね。竜族への差別や迫害の煽りを受けて、社会生活が困難になった蜥蜴や鰐、蛇族の者たちだった……多勢に無勢、止むを得ず元の姿になってそいつらを追い払った。その後、どうか家に来て礼をさせてほしいと夫婦に強く引き留められた。どうやら話を聞くと、その昔、彼らの先祖も竜族に命を救われたことがあるそうだ。流浪の旅をする竜で、名も教えてくれなかったらしいが」
「そうなんだ……不思議なご縁だね」
「うん。ふたりには子どもがいなかった。俺を遠縁の養子ということにして、それからずっと俺に協力し続けてくれている。先祖のことや通り魔の件の借りもあるんだろうが、純粋にかれらは差別や偏見を許さない、魂の清らかなひとたちなんだ」
人間の姿を借り、この国へ移住して、身分を匿ってくれる協力者を探し、国民として認可をもらい、十年以上この国の人間であることを演じ続け、地域の人びとに馴染み、軍に入隊して、ようやくオフィーリアに接触できるようになった。
“望月”を養子として迎え入れ匿ってくれている夫婦以外に、もっと外部の協力者が必要だという。
シティは街に出て、自分の他にも協力者を探してみる、と申し出た。
「オフィーリア。絶対にまた逢おう、次はこの檻の外で」
「シティ。無茶をしてはだめよ」
「さあ、こっちだ。魔法使いの侵入者対策で、透明魔法を行使するとセキュリティが反応する。見回りのロボットや監視の目が少ない鉱山側の北門から送り出そう」
オルフェウスによって軍施設から逃がしてもらったシティは、五百年後の世界を興味深く観て回る。
一方、オフィーリアは、ふとした時に己の内から語りかけてくる存在と対話を重ねていた。
「火傷に苦しむ夜も、懺悔に泣く夜も、あなたはわたしに話しかけて、支えてくれた。でも、あなたが誰なのか、ずっと教えてはくれなかった」
長らく正体不明だったが、彼女は軍部がオフィーリアを生み出す際に利用された、オルフェウスの伴侶・ユリディスという水竜の魂であることが判明する。
ふたりは母娘というよりも友人のように魂を共有しており、牢の中から脱出するという決意を交わす。
「私と魂を一体にする限り、あなたの身が滅んでも、あなたは蘇ります。それは私でないあなたが生まれたのと同様に、今と同じあなたではないかもしれないけれど」
「魂って不思議ね。ユリディス……あなたが居るからわたしが居るのね。わたしが居るから、あなたも居る。わたし、それが嬉しいの。昔は自分なんて生まれてこなければと思ってた……今は、嬉しい」
「有難う、オフィーリア。あなたのなかに私が居れば、私はたとえもう存在しなくとも、ここに居ます」
第6章 〈脱出〉
軍施設は演習などを行うため、牧草地や野原が多く家々から距離の離れた田舎に存在する。
軍施設付近のある田舎町で、シティはブライト兄弟に出会う。道端で車椅子の老人の姿と、寄り添う青年の姿を見かける。なにか様子がおかしい。近寄って車椅子の人物に目線を合わせるよう腰をかがめ、声をかける。
「お困りですか?」
「有難うございます。弟の具合が急に悪くなったようで、常備薬と魔法とで対応しているところなのですが」
「わたしも一応魔法使いです、お手伝いします。緊急時なのでお聞きしますが弟さんの病名は?」
「〈呪縛病〉です」
「……聴いたことがあります。それなら治療法は〈黒魔術〉ですね。ただわたしも対処療法しか知らないので」
「……〈黒魔術〉?」
「お兄さま、弟さんのお名前は?」
「アニュラス・ブライトです」
「分かりました。……アニュラス・ブライトさん、失礼します」
〈黒魔術〉は、行使者が持つ対象者に関する情報が多ければ多いほど、術の効力が増す。“名前”は最もシンプルにして重要な情報だ。
シティがアニュラスの“発作”を鎮静化させたことで、その後かれらは互いの出自を語り、魔法使い同士、意気投合する。
兄・トーラスは魔法薬学の研究者でもあり医者だった。弟・アニュラスは不治と呼ばれる難病〈呪縛病〉で急速に老いてゆき、寝たきりの状態が続いていた。
シティが〈教護院〉や〈旅団〉時代に学んだ魔法は、トーラスの知らないもの、すなわち〈黒魔術〉であった。対象に呪いをかけ、また呪いを解く魔法。
「フォレスターさん、あなたの知る〈黒魔術〉を魔法薬に応用できれば、アニュラスの〈解呪(ゆるし)薬〉が開発できるかもしれない……!」
シティはトーラスへの協力を快諾するが、ひとつの願いがあることをトーラスに告げる。指定された言葉を口にした瞬間舌が裂ける〈禁句の呪い〉を提示して、これから話す秘密を守れるか、と問う。
「見返り、と言ったらその通りなのだけど、迫害やひどい扱いを受けて自由を奪われたひと、助けたいひとたちがいる。力を貸してくれますか?」
オフィーリアと望月の件を話すと、トーラスはその〈禁句の呪い〉を受け入れ、重々しく頷く。
「秘密は守る。約束しよう。困った時はお互いさまだ」
シティの一案は、オフィーリアの「脱獄」のため、トーラスに軍医希望者として軍に侵入し、望月(オルフェウス)と接触して、軍内部に警報機の誤作動を誘発する細工をしてほしい、というものだった。
「わたしが黒犬に姿を変えても意味がない。敷地内には侵入できても厳重に警備されてる建物には入る術がないし、何より軍人たちにとっては、犬イコール軍用犬。何者かのスパイ犬だと真っ先に想起するはず。猫のエリーゼ大将ならいざ知らずね」
「……成程、だが……」
トーラスは、自分にもしものことがあればアニュラスを一人残すことになってしまう、と逡巡する。
そこで、シティは専門外ではあるものの習得していた〈変身術〉を行使してトーラスとは外見的特徴の異なる大人の男性に変身し、トーラスの医師免許だけを借り、代わりに潜入することにした。
トーラス(シティ)の身元を偽るため、シティは〈時渡り〉を行使する。かつて過ごした〈教護院〉内に忍び込み、院内で亡くなった少年・ユニヴァースの生育歴書類を入手する。確かに存在したがもう居ない存在の情報。
これに、五百年後の世界のトーラスの情報を上書きする。これで、トーラスであってトーラスではない架空の魔法薬学医師が“存在”する。
五百年前は魔法法整備が行き届いておらず、公的書類の魔法による改竄が可能だった。
「ああ……」
シティはその少年の墓前で跪き、首を垂れて謝罪をする。
「ひどいをことをしたのはわたしだったのね。ごめんなさい、ユニヴァース。力を貸してほしいなんて綺麗事は言わない。あなたのこと、利用します。あなたの安らかな眠りを、あなたの人生の真実を、あなたに無関係なことのために変えてしまいます。あなたの眠れる魂がこの冒涜に怒るならば、わたしはどんな報いも受けます」
回廊から子どもたちの足音と小さな話し声。
おっと、あぶない。過去の自分に出会ってしまうと異常時象の一種、タイム・パラドックスが発動して、シティ・フォレスターという存在はそのまま動けなくなり、永久に〈時の化石〉となってしまうのだ。急いでその場を立ち去る。
再び五百年後へと向かう。
オフィーリア脱出作戦のため、夜中、シティは密かにブライト家を訪ねる。
私用の立体映像通信デバイスによって、望月ことオルフェウスと、発信源が傍受・特定されないよう秘密裏に開発された通信機を以て、オフィーリアもその場の作戦会議に同席する。ただ、軍内でいつ通信に気付かれるか分からないため、作戦を概ね練り上げたところでオフィーリアは早めに回線を切る。
シティが提案する作戦概要、それぞれが成すべきことを、オフィーリア、オルフェウス、トーラス、アニュラスとで検討し、作戦実行日時を決めた。
その後、まずオルフェウスは“望月”としてやっておかねばならないことに着手し始めた。正体を明かし、オフィーリア脱出に踏み切るするということは、今まで匿ってくれた夫婦にも軍による“粛清”が及ぶに違いない。
オルフェウスは夫婦に事情を話し、これまでの感謝とこの先のかれらの身の振り方について相談した。
「あなたの目的を知り、迎え入れた時から分かっていたことです。時が来たということでしょう」
また、シティは、改竄したユニヴァースの生育歴とトーラスから借りた医師免許の情報を整合させ、偽の身分証明書を作成し、軍医を希望する通達を送った。この時、住所はオルフェウスが身を寄せている夫婦ら所有の、小さな貸し部屋を使わせてもらった。
旅人や生活に困った者などが一時的に滞在する部屋だが、軍の身内である望月の関係者名義ならば怪しまれることはないだろうとの判断だ。軍医を目指してこの街にやってきたばかり、ということにすればよい。
作戦決行日。
軍施設に侵入を果たした「トーラス・ブライト」(シティ)は、元の姿に戻りかけてしまい、怪しまれるも、オルフェウスの機転で細工を完了。警報機の施設内各地での誤作動で軍内は混乱する。
オルフェウスが翼竜化し、軍内の一部を爆破してオフィーリアの脱出に成功する。翼竜・オルフェウスの背に乗り全員が軍施設から逃れた。
オフィーリアは、この時初めてオルフェウスの真の姿を目にする。
エリーゼはどこへ。
エリーゼはどこへ。
一同は、オフィーリアを捜索しこちらを抹消しようとするであろう軍の動きに備え、「協力して竜族への迫害や軍事利用、兵器開発をする軍部を変えよう」と結託する。
そのためには、一大勢力を作り上げ、軍と交渉をする必要がある。
本物のトーラスは、この間ずっとアニュラスの日常的な介護のため自宅とその隣の職場で過ごしていた。
軍靴の音を聞き、トーラスはアニュラスが横たわるベッドサイドの椅子から静かに立ち上がる。
「……ああ、来たようだ。すまない。少しばかりうるさくなるよ」
「に、い、さ、ん。いっ、しょ、に、た、た、か、お、う」
「ああ。有難う、アニュラス」
軍人たちが「トーラス・ブライト医師が生体兵器奪取の主犯の一人」であるとしてブライト家に押し入ろうとするが、防犯用の魔法陣の前で、トーラスが立ちはだかる。
「軍人さんたち、うちで騒がれては困ります。病気の弟が寝ているんですよ。私はその生体なんとかってやつも知りませんし、その日もずっと弟の傍と職場に居ました。証人ならたくさん居ますよ」
「だが間違いなく貴様の名だ! 免許も同様!」
「名前と免許だけ? 犯人の外見は? 生育歴は? 私のと比べてみてください。ほら、あなたがたがお探しのトーラス・ブライトは一人っ子で、身寄りのない子を保護する〈教護院〉出身ではありませんか。同姓同名で、同じ医師免許を持っているだけの別人です。私たち兄弟は父母に育てられ、ずっとこの家で暮らしてきました。成程、外見だけなら魔法で変えられましょう。だが、現に私は関わっていない。改竄防止魔法が施されているはずの正式な書面の情報と合致しない。あなたがたは私を連行することはできない」
「それでもこのブライト兄弟に蛮行を働くというのなら、私たちは不当な暴力に対して徹底的に抗戦する。知っていますか? 弟は喜怒哀楽の感情を私と共鳴する時、私の魔力を大きく増幅させてくれる。あなたがた一兵卒の数十人程度、私たち兄弟の前では無力に等しい。覚悟してかかってきて頂きたい。あなたがたのような輩を、この家に一歩たりとも踏み入れさせはしない」
オルフェウスとオフィーリアは軍の管轄から離れた北方の鉱山へと身を潜める。
「あなたからしたら、わたしは娘になる? それとも伴侶の生まれ変わり?」
「竜族は姓をもたない。愛し合うことはあるが、家族はつくらない。それは、竜族たることそのものが、互いを繋ぐ、一個の誇りあるアイデンティティだからだ」
「アイデンティティ? 初めて聞く言葉ね」
「……魂、みたいなものかな」
オフィーリアのなかで声が聴こえる。
魂を共有する者。存在を相補する者。互いの存在を確信できる者。
「魂。それなら理解できる。飼育員さん……じゃない。望月、でもない。オルフェウス。助けてくれて、本当に有難う」
「オフィーリア。キミの内なる声が俺を呼んでいるのが分かるよ。ユリディス……話したいことはたくさんあるが、のんびりしてはいられない。始まりはここからだ。キミたちはもう、檻のなかでも冷蔵庫のなかでもない。一緒になって、助けてほしい者たちが居る」
第7章 〈再会〉
シティは内なる意識世界の道を辿って〈心の森〉へ戻り、そこに棲む精霊たちに「迫害され、軍事利用されている友だちを、竜族を助けてくれ」と助力を請う。
「シティ。オレもついてくぜ」
「カラス!?」
「へへっ、〈心の森〉の丸太小屋はずっとあの頃のままさ。このオレにも清らかな心とやらが宿ったらしいんでな、本物の広々とした星空や青空を飛んでみたいのよ」
「……あなたの名前……」
「スター。スター・フォレスターだぜ、キョウダイ」
フォレスター。森のひと。その名を冠するカラスが、黒い中折れ帽とサスペンダーに黒いスラックス姿の少女へと姿を変える。シティの肩へ腕を回し、にやりと笑う。
「ヘイ、キョウダイ! 感動で泣くんじゃないぜ?」
「だれが泣くもんか!」
その帰り際、意識と現実の入り混じった世界に謎の別れ道があり、片方の道にぼんやりと佇む鶴見林太郎に再会する。シティは、鶴見林太郎が五百年経ったはずの時流に居ることに驚愕する。
「ツルミ……!?」
「おや。数百年経ったのに、よう憶えてくれてはりますね。シティさん。いや、違う道から来たっちゅうことは、あなたが五百年生きたわけやないんですね。兄さんのようやる、パラレル・ジャンプってやつかな?」
「……初めて会った時から、あなたの正体が分からなかった。今も分からない。分かるのは、あなたにもまだ行くべき道があるってこと……」
「かもしれません。ここで一瞬、道が交わったのもなにかのご縁。どうか、お達者で」
道の分岐点を振り返ることなく歩き始めると、スターが困惑して後を追いかけてくる。
「お、おい、なあ。今、誰と喋ってたんだ?」
「え?」
意識世界から戻り、今度は〈旅団〉の仲間たちにも協力を求めるため動く。戻ってきた時間軸は、およそシティが〈時渡り〉を初めて行使してから数ヶ月経った時点だった。
〈旅団〉は各地を転々としているが、南へ向かったという情報と、スターがカラスの姿になって長距離飛行で捜索することで、〈旅団〉の居場所を突き止めた。
以後、スターはカラスの姿のまま、気ままにシティの頭上を飛び回ったり木の枝に留まったりして、彼女の行動を見守る。
旅団長パールは、五百年後の世界で竜族が迫害され、軍事利用されている詳細を知り、皆との協議の結果、軍と交渉する勢力として加勢することに同意する。
「五百年後、我らが〈旅団〉はあなたがたの助けに馳せ参じましょう。その頃には、竜であるベックも立派な青年になっていることでしょう」
「ただし、シティ・フォレスター。これからあちらへ〈時渡り〉をし、ことがすべて片付いたら、あなたはもう、こちらの世界に戻ってきてはなりません。おそらく、戻ってはこられない。あなたは、五百年後の未来びとに等しいのだから。〈黒魔術〉は、戦いのために存在するのではないのだから。それゆえに、未来の世界では〈黒魔術〉が封印されているのでしょう」
「〈黒魔術〉、呪いの魔法は、憎しみや悪事のために行使されることもあります。しかし、呪いの本質は、その対象に強い強い〈意味〉を与えるということです。それは束縛にもなれば、強力な信念にもなります。どうか、〈黒魔術〉を未来の世で再び解き放つからには、使いかたを誤らないで。誤った使いかたを広めないで」
「……分かった。約束します」
シティとパールは「約束」の握手を交わす。
その時、パールはこの「約束」が破られた時、すべての〈黒魔術〉が再び無効化し、封印されるよう〈終焉の黒魔術〉をその身からシティへと送り込む。パールにとって、最初で最後の魔法の行使。
「……これはきっと、必然なのでしょうね」
「パール、いえ、肖珠。今まで有難う」
「おや、私の名の発音を練習してくれたのですね。さようなら、シティ・フォレスターさん。良い旅を」
そっと歩み寄る剣士の姿を見た途端に、シティは悲しくなり、突然涙が溢れて止まらなくなった。
「クリスタル……」
「この〈旅団〉のなかで、ヒトなのはあたしだけなんだ。ここで、本当にさよならってわけね」
「クリスタル……!」
「あはは。五百年後の世界なんて想像もつかないわ。楽しんで……ばかりはいられないんだろうけど、元気でね。あんたのこと、見えなくてもずっと見守ってるから」
思わずクリスタルの肩に顔を埋め泣き咽ぶシティ。深い皺が刻まれたクリスタルのまなじりに優しくきらめく一粒の光。
〈旅団〉に別れを告げると、今度は正式に〈教護院〉を訪れ、友人たちにも最後の挨拶をする。
シティがかつて誘拐犯とともに逃亡した時のように、スターが巨大なカラスへと変化し、シティを背に乗せて飛んだ。シティは飛行術が使えず、〈時渡り〉先でさらに〈時渡り〉をすることは禁じられている。灼熱の大砂漠から〈教護院〉のある街までの最短ルートをパールたちから教えてもらったものの、その行程には数日かかった。
「スター……大丈夫? ごめんね、わたし飛行術は勉強中でまだ飛べなくて」
「なんのこれしき、よ。キョウダイ、それより目印のポイントを見逃さないよう頼むぜ」
〈教護院〉では同室だった友人がその知性を認められ、“先生”として抜擢され教鞭をとるようになっていた。それは彼女自身が選んだ道でもあるという。
「そっか、あなたはここの先生なんだ」
「まだまだよ、助手や見習いってところ。でも、暴力を受けたり苦しんでいる子たちの相談役になれたら、って思うの。少しずつ環境を変えていかなくちゃ」
「そっか。すばらしいことだね。わたし、あなたを誇りに思う」
「そんな、照れちゃうな……、……シティ、なにかあったの? 挨拶って、そんなかしこまって、どこか遠いところへ行くつもり?」
「もう逢えない、わけじゃないでしょ? シティ、またどこかで逢えるよね?」
「……ううん。たぶん、二度と逢えない」
「シティ!」
後方から友人の涙まじりの呼び声。振り返ると、友人はシティを強く抱擁した。シティも彼女の背に腕を回した。
〈教護院〉からの帰り道、痩せた浮浪者たちがうずくまる薄暗い路地の入り口をじっと見つめるシティ。
ある露天商の前で立ち止まる。その顔に見覚えがあった。
かつての誘拐犯・ナイルと再会する。
「ナイルおじさん?」
「……あんたみたいな真っ当そうな身なりの知り合い、オレにはいな……待ってくれ。あんた、もしかして」
「シティ・フォレスター。憶えているかな」
「……忘れるわけがねえ、本当にあんたか!? なんてえこった、こんなことがあるのかよ……」
「生きていてよかった、ナイルおじさん」
「呼び捨てでいい、フォレスターさんよ。そうだ、あの時の詫びと恩返しをまだしてねえんだっけな」
「わたしのほうこそ呼び捨てでいいよ。まあ、誘拐されかけたんだからそのお詫びはともかく、お礼なんていらないよ。あの時、有難うって言ってくれたじゃない」
「いいや、借りは返す。必ずだ」
その声に偽りはないと感じられた。シティは片膝をついて露店の品定めをするふりをしながら、ナイルと目線を合わせて密かに囁く。
「ナイル。もしお礼に何かしてくれるのならば……手伝ってほしいことがある」
「……。真剣だな。危ない橋か?」
「あなた、人間のまま生を全うして死にたい?」
「……具体的に言ってくれ」
「信じられないかもしれないけど、五百年後の世界のお話。あなたに、もし大切な人やこの時代でやらなくちゃいけないことがあるなら、この話は聞かなかったことにして。わたしの〈時渡り〉の魔法で、あちらの世界に一緒に行って、力を貸してほしい」
思わず声を上げそうになったナイルを静かに制して、声を潜める。
「ひとつは貧しいひとや奴隷同然の扱いを受けているひとたちの結束のため。もうひとつは、あなたの商人としての知識。〈黒魔術〉で、ある病気のひとたちの“呪いを解く”ため。商人さんのお雇われだった頃も、わたしの知らないいろんな品々を見ているはずだよね」
「知識ったって……専門家ほどじゃねえぞ」
「黒トカゲの尻尾を食べる〈盗人花〉の生息地と、その主な用途は?」
「あ、ああ、暗黒の夜が続く〈黒い樹海〉の水辺。口唇である花弁が〈禁句の呪い〉を解く煎じ薬の主な材料になる。闇取引でよく扱った品だ」
「充分だよ。そういう、お行儀の良い基礎黒魔術の教科書には書かれていない、生身のヒトしか知らない知識がほしい。わたしは旅するなかでいろんな魔法使いに会ってたまたま知ったけど、それをさらりと答えられるあなたが居れば心強い」
「知識なら貸すが、どうやってその〈時渡り〉とやらをする?」
「あなたの身体と精神を切り離して、わたしの核である黒犬みたいな存在……精神生命体になる必要がある」
「……あんたが持ちかけてくる話は、いつも突拍子もねえな」
「クレイジーだよね」
「ああ、あん時以上にクレイジーだ。頭がおかしいとしか思えねえ」
引きつった笑みを浮かべながらも、ナイルのその眼には意志の光が灯っていた。酒瓶から注いだアルコールで布巾を濡らし、その煤まみれの手を拭いて、差し出す。シティは応じ、ふたりは握手を交わした。
バサバサとスターが舞い降りてきてシティの肩に留まる。
「さあて、これで挨拶回りは終わりか、キョウダイ?」
「な、なんだあ、このカラス……」
スターは抗議するように鳴き声をひとつ上げると、男装の少女へと姿を変え、腕を組み胸を張って宣言する。
「〈心の森〉のスター・フォレスターさまだぜ、おっさん! あんたもこれからオレらみたいな精神生命体になるんだろ?」
「お、おお……なんていうか、神に祈りたいってのはこういう気持ちなのかね」
「確かに、あなたにとっては命がけ、ってことにはなる」
ナイルの精神生命体化について、話を詰めてゆく。元々生粋のヒトであるナイルの〈生体変換魔法〉には高度な技術を要する。
ナイルは自らの露店を見渡し、ひとつの陶器の壺に目を留めた。人間が片手で抱えて持てるくらいの小さな壺だ。これを精神生命の器とすれば、ヒトの姿に変化(へんげ)する時は壺のなかから出てくればよいし、もしもの時も、壺に姿を変えれていれば誰かに怪しまれることはないだろう。
ナイルの提案にシティはしばらく目を閉じて思案し、やがて何度か頷いた。
「うん、うん、イメージできた。壺の姿の時は自分で動けないのがネックだけど、いいんだね?」
「誰にだってハンディはあるだろ。今までの人生だって似たようなもんさ、奴隷の頃は身動きできねえくらい当たり前だった。これで別天地に行けるんなら安いもんだ」
「オレは腹を括った。シティ、あんた自身はどうなんだ」
「……〈教護院〉で五年、〈旅団〉で各地を旅しながら二年。修行期間はたったそれだけ。こんな未熟な魔法使いに、出来るかと言われれば、賭けになる。正直怖いよ。失敗したらわたしもナイルもどうなるか分からない」
「でも話を持ちかけたのはわたし。ナイル、魔法の行使中、あなたの身になにかあったら全力であなたの命は守る」
「……命を守るなんて言われたのは初めてだな。それだけで充分だ」
こうして、ナイルへの〈生体変換魔法〉が行使される。
小さな壺となったナイルを、シティが掲げる。
「気分はどう?」
「身体が在るような無えような、変わった気分だ。悪くねえ」
「そう、よかった。わたし自身が精神生命体で、〈変化〉の魔法でヒトの姿になっているから、同じ魔術が効きやすかったのかも」
「そういや、シティ。〈心の森〉出身の魔法使いってこたぁ、人間よかだいぶ長生きだろ? 五百年後の世界のどっかで、未来のあんた自身に会うってことはねえのか?」
「〈心の森〉は、意志の無い〈病んだ心の化身〉にとってははほとんど時間の流れがない、永遠の悲嘆の場所なんだけど、“外”に出ればもちろん時間に従って生きることになる。魔法使いの平均寿命はだいたい三百年、永くても五百年とされてるよ。たぶん〈時渡り〉をしなくても、五百年後ではもうわたしは死んでる。そもそも、あの時代に“五百歳のわたし”は存在しないんだ。今この時代から消えて、五百年後に往くんだから。シティ・フォレスターは、ただ一人なんだから」
「ああ……成程、理屈はよくわからんが意味は理解できた」
この時代にはもう戻ってこない。
〈時渡り〉の直前、シティはふたりに告げる。
「スター。ナイル。ついてきてくれて有難う」
「ただのお節介さ」
「ただの恩返しだ」
第8章 〈変化〉
トーラスの研究者仲間で、魔法使いでもあるゼッドの屋敷に身を寄せる一行。トーラスがゼッドを紹介し、信頼できる仲間であることを告げる。
「幼馴染みだ。魔法使いも竜ほどじゃないが長命だからね。俺もゼッドも百年以上は生きている」
「幼馴染み?」
オフィーリアが、見たところ年齢のかけ離れているふたりの姿に目を丸くする。
「私はトーラスと違って外見固定魔法を使っていないから、緩やかにではあるが老いてゆく」
「自分の身体をどうするかはそれぞれ個人の自由だものね」
「そういうこと」
一方、シティは大きく様変わりした〈旅団〉の面々を見渡す。五百年の月日をまざまざと思い知らされる。知った顔は、何一つ変わらない姿の〈太陽〉の子イルリメと〈月〉の子ラリプナ、幼かった樹木の精霊コンスタンスと思しき女性身体の姿。彼女らはあの頃と同じように笑って再会を喜んでくれた。
現在〈旅団〉には、ベックがこの時のために時間をかけて仲間に加えてきた竜族の者たちや、ほかにも機械の身体だというアンドロイド、他の星からやってきた者たちも居るのだという。
〈旅団〉の団長となった、ベック。歩み寄ると、五百年を経て成長した彼からは壮年期の色濃い活力と豪胆さが感じ取れた。
「久しぶりだね、ベック。立派な団長さん」
「あんたはあの頃のままの青二才だな。おれが五百と二つ年上だぞ。気安く話しかけてくれるな」
「はは、口が悪いのは変わらないんだ。そういえば、パールは?」
「……もう居ない」
「……そう。あの……シーさんとテムさんや、クリスタル、ワンダステイは……」
「老衰だ。皆、苦しまずに逝った」
「うん、そうか……よかった」
「で、そっちのあんたが、話に聞いた囚われの竜族オフィーリアさんか」
「ええ。初めまして。ご協力に感謝します。竜族といっても、生まれたての“なり損ない”だけどね」
シティがハッとして思わずベックを見つめるが、彼は落ち着いた表情のままオフィーリアに尋ねる。
「生まれてどれくらいだ」
「十七か八くらいかな。あなたからしたら、赤ん坊みたいなものね」
「誰だって赤ん坊だった頃はある。それに、たとえ“なり損ない”でも、時にはそれが役に立つ」
「ベック。変わったね」
「五百年も経てばそれなりにな」
「そうだ、あの時、別れ際にくれた鱗。本当に有難う。そのおかげで、こうしてオルフェウスやオフィーリアと知り合うことができた」
「やめろよ、気色悪い。それより、本題に入ったらどうだ。これからどう動く?」
オルフェウスとオフィーリア。五百年前の約束通りやってきてくれた〈旅団〉の仲間たち。〈心の森〉の精霊たちと、スター・フォレスター。魔法使いブライト兄弟。元奴隷で〈黒魔術〉に用いる材料の知識を持ち、貧民層に訴えかける話術を持つナイル。
ただしブライト兄弟は、アニュラスの〈呪縛病〉の病状次第では二人とも行動不能になる可能性があるため、前線には出ない。あくまで自宅からの後方支援だ。
オルフェウスはシティに問い掛ける。
「仲間は揃った。どう思う」
「どうだろう。オフィーリアがこちら側に居るから、下手に探し出して攻撃してこないだけだよね。果たしてこれで交渉を持ちかけて、軍が動いてくれるかな。そもそも交渉の席にすらついてくれないかも。もっと強力な誘因(インセンティブ)がないと、権力者を動かすことはできないかもしれない」
「と言うと……あのお方の出番か」
オルフェウスが屋敷の窓際を示す。
「力が必要かね?」
いつの間に居たのか。
そこには、純白の毛並みに蜂蜜色の瞳を持つ猫が佇んでいた。
「我が名はエリーゼ。偽名だがね。我が国政の参謀長・主席補佐より遣わされし者である。故あって、政府と敵対し独断暴走する軍部に諜報のため潜入していた」
「オルフェウスは、エリーゼさんのことを知っていたの!?」
「言っただろう? 癒しと力を与えてくださる大変貴重なお方だ、と」
「これで、政府要人との繋がりができた」
「失礼は承知の上で申し上げる……“政府は腰抜け”。軍はおろか、市民さえそう囁いています。信用していいのですね?」
「全員が腰抜けではない。歯車を噛み合わせる必要がある。そう、壊れた時計を直して時を進めるようにな」
やや躊躇いがちに、スター・フォレスターが口を尖らせて発言する。
「ていうかよお、素人考えだけど、すべての根源はユリディスさんが軍に拐われたところから始まってんだろ? 過去に行ってそれを食い止めりゃあー……」
「ス、スター!」
シティが慌てて発言を遮ろうとするも、オフィーリアが笑い飛ばす。
「あはは! そしたらわたしは今ここに存在しなくなるわね!」
「あ……そっか、悪い」
「それにね、スター。〈時渡り〉の魔法は万能じゃないんだ。過去の時象に干渉しても、未来は変えられないんだよ。過去と未来は繋がってる。わたしは、これまでのことでそれがよく分かった。それでも、ひとや世界は変わってゆくんだ。変えようとしてゆく。その力を信じて進むしかない」
「へえー。〈心の森〉のシティも変わったもんだ」
スターは嬉しそうにニヤリと笑った。
何事か思案していた様子のベックが、研究者ゼッドやオルフェウスに向かって静かに発言する。
「過去といえば……そもそも、なぜこの地方では竜族が迫害されるようになった? この北の地も、おれの生きた五百年前はこんなふうではなかった。あるところでは崇められてさえいたし、少なくとも竜族であることを理由に差別を受けたことはない」
「あなたは先日この地方を訪れて、どのように感じた?」
「あからさまな侮蔑の空気が漂っている。同胞に近しい種族の蛇や蜥蜴族まで煽りをくらって、仕事にありつけず浮浪の身になっている有り様だ。なぜこんなことになった」
その問いには、その場に居る者のなかで最も過去を知る、齢およそ六百余のオルフェウスが応えた。
「始まりは四百年ほど前だ。世界を巡ってきたあなたがたは、この数百年でヒトの科学がとてつもない発展を遂げたのはよくご存知だろう」
「ああ。おれたち〈旅団〉はあくまで牛や駱駝、馬、象たちの力を借りて旅を続けてきたが、頭上が電線で張り巡らされたり、飛行機なんてのが空をビュンビュン飛び交った時代は驚きの連続だった。あれが魔法じゃないってんだからな」
「そう。科学を〈現実〉と認識したヒトは、次第に魔法使いや異種族の存在を否定し、架空の存在として忘れていった」
「確かに、あの頃から、おれたちはひっそりと旅をするようになった。〈旅団〉だけじゃない、精霊も魔獣も魔法使いも、姿を見せるのを避けて秘境の山奥や絶海の孤島に身を潜めた。ヒト同士の殺し合いになんざ巻き込まれたくなかったからな」
「賢明な判断だ」
「武器が前とは比べ物にならないほど強力になって、ひどい戦争や虐殺が何度も起きて……戦争自体はいつの時代もなくならないものだが、あれは悲惨だった。その場に居なくとも遠い地の情報が巡ってくる時代だ」
「核爆弾だな。戦後復興後、二百年以上かけて通信技術や人体工学などが目覚ましく進歩した。自立型アンドロイドが生まれたのもこの頃だ。宇宙開発と時空間研究によって、ヒトは、今までかれらが認知できなかった知的生命体……精神生命体〈概念体〉との接触を果たした」
訳がわからないといったふうに話を聞いていたシティが、ひとつの単語を聞いて思わず声を上げた。
「〈概念体〉……!?」
「知っているのか」
「……その、ふたりくらい、知り合いっていうか、友だちかも」
「すごいな。かれらは多くの者の前に〈幻質〉をまとって現れるが、なかなか自らの正体を明かさないと聞く。それに、ヒトとも一定の距離をとり、数多の国々がどんな交渉を持ちかけても、応じることはほとんど無かったという」
オルフェウスが感嘆の声を上げる。
「話を戻そう。ヒトはそこから〈現実〉の認知を改めて、再び異種族との交流を再開した。精霊も魔獣も魔法使いもこの時代を見て分かる通り、正体を隠さず、ごく平凡に世界に馴染んでいる」
「そのなかでも、ヒトは〈概念体〉に興味を示した?」
「ああ。〈概念体〉は、ヒトの感情を司る種族だという。そして、かれらは独自の世界を介して時空間転移をする。〈幻子〉という未知の粒子のようなものが支配する世界だ」
「〈幻子〉研究は、時空物理学などの正式な学問へと発展し、ヒトはヒトなりに精神生命体について理解をしはじめる。そして、〈幻子〉を自分たちのために利用できないかと考えついた。お約束のパターンだな」
「先陣を切るように、この北国が〈アトミック・タイム・ボム〉(原子時爆弾)の開発に乗り出した。それが百五十年前のこと」
「兵器開発……また戦争か」
「いいや。その兵器は、〈時空間〉を破壊するために計画された。確定した情報ではないが、この国の上層部と何者かが結託して、この世の時空間破壊を企てているらしい」
時空間の破壊。
なぜ、とベックが問う。
「原子時に支配された〈現実〉を破壊し、新たな〈幻子時〉の世界を創造すれば、ヒトの身であっても〈時渡り〉ができる、とでも考えたのだろう」
「竜はその身ひとつで多次元間の干渉壁を突破できる。そこに着目され、竜狩り、竜の軍事利用が進められた。そのことを合法的、倫理的に是だと錯覚させるため、一般市民には竜は邪悪だとか不吉だとか、恐るべき存在だとかいう否定的な固定観念を植えつけていった」
「そうして実験体にされて完成した時空間破壊兵器が、このわたしってわけ」
あっけらかんとした口調のオフィーリアが話を結ぶ。
降参するようにナイルが両手を上げた。スターも目が点になっている。
「悪い、五百年前から急にこっちに来た〈時渡り〉組には、さっぱり話が分からねえ……」
「オレも……」
「わたしも分からないと言えば分からないわ。時空間を破壊するために、火炙りにされたり人殺しを強要されたり。耐久性の実験だとか、時空間破壊イコール虐殺だということはわかるんだけど、そこまでして創りたい〈新世界〉なんて結局のところ今の世界の下位互換にしかならないだろう、って」
「……目の前に餌を吊るされた状態では、欲求や感情が先行してまともな判断ができないんだと思うよ」
オフィーリアの発言に応えながら、シティは自らの発言にふと引っかかりを覚える。
「感情。感情のコントロール……?」
「どうしたの、シティ」
「いや、なんでもない」
「国家政府。軍部。そして我々、民間の第三勢力。市民を巻き込む戦闘を避けながら、“非好戦的”に戦っていく必要がある。我々は長い歴史のなかで、流すべきでない血が河となるほど流されるのを何度も見てきたはずだ」
血。暴力。
〈教護院〉の虐げられた子どもたち。オフィーリアの傷だらけの身体。
蘇る光景に、シティ・フォレスターは決意を固くする。
皆が一様に沈黙によって同意した時、トーラスが挙手して一歩進み出る。
「トーラスさん?」
「……あなたがたが、多くのひとを動かそう、国を変えようというのなら、憶えていてほしいことがある。田舎で動けない家族をケアしながら、地道に暮らしている者も居るんだということを。忘れないでほしい。都会に出れば色々と便利で、魔法薬の研究も進むかもしれないが、我が弟アニュラスにとっては亡き両親と暮らした家こそが、安心できる場所なんだということを。これこそ偏見かもしれないが、都会の富裕層は、時々、田舎者や貧困者のことなど認識さえしていないような節があると感じるよ」
「……わたしやナイルも、〈教護院〉や〈スラム街〉の出身だし、〈旅団〉はゆくあてのないひとたちの寄る辺だから、よく分かる。見捨てないよ。どんなひとも見捨てない。そういう国になるように訴えていく。魂にかけて、誓うよ」
「有難う。……弟の食事の時間だ。俺は一旦抜けるよ。動く時はまた連絡をしてくれ。力になる。それと、フォレスターさん……」
「アニュラスさんの、解呪薬の件だね。元商人のナイルがいろいろな薬草や鉱石や生き物についての知識を持ってる。今の時代に失われた、〈黒魔術〉に関するものだよ。ゼッドさんの力も借りて、一緒に研究を進めよう」
「恩に着る。本当に有難う」
第9章 〈破戒〉
「変化も不変も定められたものかもしれない。未来は変えられないのかもしれない。だけど、起こったことがすべて必然ならば、これから起こり得ることにも必ず対処してゆける。わたしたちは、可能性さえ見つけられたなら、立ち止まらずに進んでゆける。それが、この世に生けるもの皆が持っている魔法だ。わたしはそう思う」
〈旅団〉のメンバーのなかで、異彩を放つ者が居た。その者は、〈骨格言語翻訳家〉と名乗った。
「ギイです。独話のギイだ。〈骨格〉から読み取れる言語を中心として翻訳家業をしながら世界を旅している、います」
「〈外世界〉から来たっていうのは本当の話なのか?」
「いいえ。僕は、私は、〈外世界〉よりもたらされし骨格言語をこの世に広めているだけ、それだけよ」
「あなたが翻訳した本をたくさん読んだ。時代も筆記方法も文体も内容もばらばらだった。本当にあなたひとりで? あなたが〈外世界〉からやってきたひと?」
「〈外世界〉の出自ではないと思うな、思うよ。翻訳を太古から繰り返しているのは覚えてるんだ、覚えてるんです。あたしの、俺の、知りうる限りの言語を翻訳しただけだからね、ですから、おそらく〈外世界〉からやってきたのは、トイ・メイカー。〈外世界〉の物語が滅びを迎えて、一部の物語を持って“こちら側”に亡命してきた、不死のひと」
政府要人を筆頭に、いよいよ一同は軍に対して交渉を持ちかける。
民間を代表して、シティ・フォレスター、ベックを中心とした〈旅団〉、交渉における最も重要な存在、オフィーリア。望月ではなく翼竜としてのオルフェウス。
軍の堅牢な建造物の屋上。そこに向かい無人の回廊をゆくふたつの影。
「イヤイヤイヤ。怖い怖い怖い。人前に出るのがすさまじく怖い。存在しない心臓が止まりそう。在るはずのない胃から戻しそう!」
「わがまま言うなよなあ」
「ああ、またこれだ。またボクから搾取するがいいさ。悲しき道化は笑って泣くさ!」
「そのくねくねした動き、器用だよな」
「くねくね動いていると気分良くてね」
「ああ、それがおまえさんの駆動(テクノ)だっけな。……ほれ、行くぞ。〈万能感〉」
建物の屋上を誰かが指差して、皆が注目した。
シティに衝撃が走る。
「もしかしてって思ってた。予感してた。そんな気がする。でも、そんなわけないって思いたかった」
「なんだ、あいつらは……?」
「……〈概念体〉、だよ」
「何だって!? 軍にかれらが加担していると!?」
軍部の者たちとは明らかに異様なふたりの姿。
ぼろぼろのコートを羽織った男と、素性の知れないシルクハットにマント姿の、道化めいた言動の何者か。
「よう、シティ・フォレスター。けっこう早い再会だな」
「ウェイン……! どうして、どうしてあなたが“そっち”に居るの!」
「言ったろ? 一応、“仕事”もしなきゃならないんでね、って」
「〈達成感〉殿、〈万能感〉殿! どうか表に出るのはお控えになってくださいと申し上げたはず……!」
「いえね、俺たちはあなたがたに従っている部下じゃない。〈この世の摂理〉から下された責務をこなしてるだけだ」
「〈概念体〉は呼び声に応え、各自司る感情を与える。〈達成感〉と〈万能感〉は責務を全うしているだけさ」
「本当に仕事をするのがいやだ! とにかく早く終わらせたい! そして無心のスキャットとパントマイムの駆動(テクノ)に耽りたい!!」
関節が存在しないとしか思えないひょろ長い手足と胴体をくねらせながら、〈万能感〉は見えない顔に苦渋を滲ませているようであった。
二体の概念体は口を揃えて言う。
「それじゃ、“仕事”なのでね」
なにかが、大気中を疾った。
波のような。風のような。何かが。
にわかに軍人たちに湧き上がる歓声。
「……お、おお! 我々ならやれるぞ! “悲願”を〈達成〉できる!」
「わ、私だ! 私が成功させたんだ! 私がオフィーリアを造った!」
「〈幻子時〉を掌握できればまさに〈万能〉だ!」
「我々が世界を創り変える!!」
オフィーリアを造った。そう高らかに笑った白衣の研究者の姿に、翼竜が耐えきれず咆吼を上げる。
オルフェウスが激昂し、皆がそれを制するので手一杯となってしまう。交渉になど持っていける状況ではない、とオフィーリアが叫ぶ。
「退こう! これじゃ話し合いなんてできない!!」
交渉は決裂に終わる。
「……復讐か」
〈旅団〉の団長、半竜のベックがぽつりと呟く。彼が、シティ・フォレスターに告げられなかった真実。
剣士・クリスタルの死について。
ベックは、皆老衰で逝ったとシティに告げた。だが、実際には、クリスタルは老いて剣の腕が鈍り背も曲がり始めた頃、自らの故郷、剣の国へと帰ったのだ。
剣の国は侮辱を最大の罪とする。
半ば国を追われるように出て行った彼女は、自ら裁きを受けるために戻った。裁きの場で、クリスタルは皆に詫びの言葉を述べた。彼女には、終身刑が言い渡された。
裁きの場を去るその時、どこからか一本の復讐の剣が、クリスタルの胸を貫いた。
それが真実だった。
オルフェウスは交渉時に、伴侶・ユリディスに直接手を下したという軍研究者を目にし、復讐を誓う。
そのため、“非好戦的”に戦う仲間たちとは道を違えることになる。途中から皆とは交流を絶ち、独断でその軍人を殺すためだけに動き始める。
〈我々は強くあるが故に他のものを徒に害さず。害されても報復するべからず〉
この竜族の掟を破ることは最も重い禁忌にあたる。
「オルフェウスに人殺しはさせない。ユリディス。わたしをわたし足らしめるもうひとつの魂よ。彼を止めましょう。そして、彼がもし禁忌を犯してしまったなら、わたしたちの身をもって、“彼”を消し去りましょう。〈原子時破壊〉の初実戦行使がこんな形になるとは思わなかったけれど……そうしなければ、復讐はさらなる報復を呼んで、やがて誰も止められぬ負の連鎖になる」
第10章 〈破壊〉
状況は停滞していた。
「わたし、今まで生きてきて……初めて、本当に、もう進めない、って思ってる」
「竜族は街中を堂々と歩けないほど迫害されて差別意識が広まっている。それも問題だけれど、その煽りを受けて生活が困難になっている蜥蜴族や蛇族のひとたちの支援もしたい」
トーラス・ブライトが一計を案じる。
「うちの庭は家一軒分建てられるくらいの広さがある。私有地だから、行き場のない者たちが雨風をしのぎ、くつろいで過ごせるような場所を作ることはできそうだ。手洗いなども我が家の設備を使ってくれてかまわない。弟のアニュラスに危害を加えない、それにアニュラスの病状の急変に気付いたらすぐ知らせてくれると、約束と協力をしてくれるなら、どんな者も受け容れよう」
「トーラス・ブライトさんよ。あんた、自分がいかにこの社会で生きやすい存在か、考えたことあるかい?」
「自覚はしているつもりです」
ブライト家の〈安息の広場〉には、噂を聞きつけてそろそろと竜族や蜥蜴族などの浮浪者たちが身を寄せはじめていた。
中には、やはり差別や偏見を受けたために憎悪を抱えている者たちも居た。
シティが〈黒魔術〉の使い手であることを知ると、彼らから懇願される。
「この世が呪わしい。この世が恨めしい! 〈黒魔術〉ならこの世の“悪”を呪うことができる!」
「〈黒魔術〉の、正しい使い方……」
シティが苦悩する一方。
オルフェウスの目の前にオフィーリアと、その魂を一体にするユリディスが立ち塞がる。
オフィーリア、ユリディス……とオルフェウスが枯れた声を絞り出す。
「〈我々は強くあるが故に他のものを徒に害さず。また害されても報復するべからず〉。忘れたの、オルフェウス」
「あなたの復讐は争いの火種になる。必ずなる。そうしたら、竜族や近縁の種族はますます迫害を受け、絶滅に追い込まれるかもしれない。たくさんの無関係な生命が奪われるかもしれない。あなたのその行いのために」
「では、俺のこの内に燃え盛る憎しみはどうすればいい。奴は笑っていた。ユリディスはもう戻らない。あの頃にはもう戻らないのに!!」
「あなたの復讐の火を、水竜たるわたしたちが鎮めましょう。あなたが抗うなら、あなたの〈時間〉ごと消し去りましょう」
「いえ、〈原子時破壊〉が可能なら、この身を破壊することもできるはず」
「ユリディス……オフィーリア……駄目だ、そんなことをしてはいけない」
「軍内のラボにわたしたちの開発データが残っているでしょう。あれも存在の記憶ごと破壊します。この魂は不滅のものに変えられたゆえ、滅んでも蘇ってしまいます。ユリディスでも、オフィーリアでもない何者かとして」
「オルフェウス。禁忌に触れたあなたを、もはや竜族として認めることはできない。〈原子時破壊〉によって、この身もろとも、あなたの〈竜族としての時間〉を消し去る。あなたができることはただひとつ。蘇ったわたしたちでない何者かを、兵器としてではなく、ただの竜族として生を全うさせること」
《すべては、壊し、また創るため。〈パラレル・メソッド〉の再構築のため。この世を支配するのは〈摂理〉ではない。すべては〈創意〉の下にある。》
《この世は〈外世界〉の模造品なのだ。》
《〈投企計〉に抗うため。〈バグ〉を滅するため。》
夜中。
軍との交渉が失敗した以上、戦いは避けられない形となった。ゼッドの屋敷に身を寄せて、〈傷つけない黒魔術〉、そして〈解呪薬〉の研究に没頭するシティ。
二階の書斎の窓が、外側からコンコンと叩かれる。
ウェインこと〈達成感〉が、笑みを浮かべていた。
「入れてくれるか? いや、窓越しでもいい。今の俺の姿や言動はあんたにしか認識できない。そのまま、ちっと聴いてくれや」
「ウェイン……!」
「シティ・フォレスター。ドライヴ・レコーダーは分かるか?」
「……この時代に来てから、なんとなく。クルマの内部の映像や音声を記録する技術……主に車内で、事故や事件があった時の事実を証明するために」
「その通り。一個の駆動体の活動記録。この世もそうなんだよ。この世に生きる者すべて。誰のどんな行動も、記録されている。“予定通り”になったかを証明するためにな。筋書きは変えられない」
「……その筋書き通りに、なんのご用?」
「話が早くていいね。そう、“予定通り”に伝えに来た。これから、この世は〈破壊〉される。何をどうしても、この世は終了する。俺たち〈概念体〉が、もうじきすべての〈感情〉を“回収”するからだ」
「すべてって……」
「すべてだ。〈原子時〉の歴史の始まりから終わりまで。回収した膨大な〈感情〉のリキュイドは、〈幻子時〉によって構成される多次元書物型世界〈パラレル・メソッド〉に送られる」
「……ついていけない。〈幻子時〉世界が存在するのは分かる。〈パラレル・メソッド〉とは何?」
「入れ子だよ。マトリョシカ人形さ。シティ・フォレスター。物語が好きだろ? 現実というこの世の内に、物語の世界があるよな。同じ認識だ。この世は物語で、それを編んで、読んでいる“目”がある。その“目”は、この物語に区切りをつけて、さらにその奥の物語の世界を読みたがっている」
「わたしたちはお話なんかじゃない。勝手に終わりにされるなんて、納得できるわけがない」
「そうだよな。これだから、あんたたちは面白いんだよなあ。もっと観ていたい。もっともっと観てみたい。ああ、排情孔(オリフィス)さえなけりゃあなあ」
「そうやって観察して面白がられるの、あまり良い気分でもないし、良い趣味とは思えないけど」
「失礼。話に戻るよ」
「この世のあらゆる感情、喜怒哀楽、安らぎ、苦しみ、寂しさ、憎しみ、虚しさ、すべての者が感情を失い、骨抜きになって、空っぽになる。〈感情〉のリキュイドは、次の世界に生きる者たちへ注入される。俺たち〈概念体〉の役割も終わり。たぶん次の世界で似たようなものに創り変えられるんだろう」
「……なぜ、わたしに話したの。この筋書きになんの意味があるといえる?」
「“上”の考えは俺もよくわからねえなあ。ただ、ひとりくらい世界の真実を知っている存在が居ても面白い、くらいの認識じゃないかねえ」
「馬鹿にするな……」
「そうだな。同意見だ」
ウェインこと〈達成感〉がぼろぼろのコートをはためかせて窓枠から宙へ上昇した。
「研究中、夜分遅くにどーも。それじゃあ俺はこれで」
「ウェイン!」
シティが窓を開けて呼び止める。
「その“上”のひとたちにあなたが会えるなら、“くたばりやがれ”って言っといて。あと、秘密を教えてくれて有難う。それが変えられない未来だとしても。それまで、その瞬間まで、後悔のないように生きることができるよ。本当に、有難う」
「応、シティ・フォレスター。たった今、なぜあなたに伝えたかが俺には分かった。もし会えたらな。確かに伝えるよ」
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
