
小説『水蜜桃の涙』
「第7章 哀しき想い」
この章の登場人物:
成沢清之助・・・・高等師範学校の最終学年に通う都会育ちの青年
谷口 倖造・・・・高等師範学校の教授
伊ケ谷 治平・・・村の名主
伊ケ谷宗一郎・・・伊ケ谷氏の長男で隣町の学校に在籍する中学生(17歳)
輝子・・・・・・・宗一郎の幼馴染で美しい村の少女(12歳)
再び時はさかのぼり、清之助たちが訪れた夏の村。
谷口教授と清之助は、その日のうちに東京へ帰り着かないとならないので、教授の実家へ寄ったあと昼には村を発った。
慌ただしい里帰りだったようだが、伊ケ谷宗一郎には全く関係ないし、わざわざ休日に呼び戻された自分はいったい何だったのだと腹を立てていた。
父親が自慢したいことのひとつに加えたいだけの学校設立という一大事業。
何の教育理念も本人の信念もありはしない。
元々そういう父親が嫌いであったから、家を離れて勉学に勤しむ環境は有難かった。
しかし今回の父の縁談には絶対に賛成できないでいたのだ。
輝子がまさか自分の継母になるなどという馬鹿らしい話は、誰が何と言おうと制止するつもりだった。
初恋だった。
もっと小さい頃から、近所中の子どもらといっしょに遊ぶ中にも小さな輝子はいた。
男の子も女の子もいっしょに里山じゅうを走り回って、お互いぶつかり合いそうになった時も、輝子が気圧されないように手をつないで走ってあげたり、もし輝子が転んだりしたのを見かけようものなら、急いで駆けつけて助け起こしてあげたり、怪我をしたひざこぞうを手当してあげたりと、そのかいがいしい姿は仲のいい男友達にからかわれても全く気にならなかった。
そして年を重ねるごとにどんどん美しくなっていく輝子が眩しく見え、好きだという感情はますます募り、息が苦しくなるほどであった。
自分が輝子のことを近くでずっと守っていくのだと固く誓っていた宗一郎は、父親が勝手に隣町の中学校へ入学の手続きをしたとき、最初は反発した。
輝子と離れたくなかったのである。
しかし説得されるうちによくよく考えてみると、この父親と比べられて優位に立てるのは学歴である。
いつしか父を負かしたいと思うようになった宗一郎は、尋常高等小学校までしか出ていない父よりも知識を深められるのだと思いなおした。そして視野を広めて、世間のことがわかる大人になったあかつきには輝子の前に立派になって現れて彼女を一生守ることができると考えたのだ。
この期間に頑張っておくべき目標を見つけて宗一郎は幾分満足した気分になった。
今回の帰郷も父の勝手は腹が立ったが、輝子と会えるかもしれないと思えば少しは許せる気がした。
夜の宴はそっと自分の部屋から見ていたが、酒が入り、話題が学校のことから我が家の事情に移り、宗一郎は嫌な予感がした。
案の定父の縁談の話が出たのを、聞き耳を立てている宗一郎にも十分聞こえてきたから面白くない。教授といっしょにくっついてきた書生も、酒が弱いのかすっかり横になって眠ってしまっているから、話も出来ずじまいでよけいに腹が立つ。
つまらないから自分もさっさと寝てしまおうと布団に入ったのだった。
翌朝いつもより早く目が覚めてしまった宗一郎は、彼よりも早くに目覚めた書生が出ていくのを見かけた。
いつかは自分も目指すかもしれない東京の学校について何かしら聞けるかもしれないと、宗一郎は遅れて後を追った。
少し行くと茂みの方から何やら誰ぞの話し声がする。
ふと輝子らしき声がしたような気がした。つい嬉しくなって、輝子をおどろかそうと声のした方へこっそり忍び寄ったが、まさかのあの書生がいるではないか。
ふたり奥の方で何やら楽しそうに話しているが、何を話しているかまではわからなかった。
なぜだか、無性に苛立ってきた宗一郎は声をかけることなくそのまま踵を返して帰っていった。
ふたりでいったい何を話していたのか。
水蜜桃を美味しそうに齧る輝子が見えたが、あの書生は何と言って話しかけたのか。
昨日突然やってきてそのままひっくり返っていた書生の姿は、取り立てて英明な人物には見えないのに、もうこのような朝早くから輝子と逢引きしているのか?
苛立ちとともに宗一郎の妄想は、嫉妬にまみれ始め、奇妙な怒りに転じていた。
東京の二人が帰ったと同時に、父のいる家に長居は無用と出ていく宗一郎だったが、やはりどうしても輝子と会ってからでないと心が落ち着かない。
彼女の顔を一目見れば、難しい授業も辛い勉学も我慢ができるというものだ。
おまけに今朝のあの様子のことをじっくりと聞き出さないと気になって仕方がなかった。
輝子の家に行くと彼女を呼び出した宗一郎は、すぐ近くの裏山の方へ連れて行き、誰にも話を聞かれないところを選んだ。
「宗一郎兄ちゃん、どうしたん?こんなところまで来て」
輝子は見知った宗一郎の顔が変に強張っているのと、緊張している様子を敏感に感じ取った。
「あいつと、あの東京の奴とどうやって知り合った!?」
宗一郎はなんだか自分でもわからない、抑えようがない怒りが沸々と湧き出てくるのを抑えることができずにいた。
「知り合ったって…。どうやっても何も、ただばったりと会っただけ」
「俺は見たんだ!今朝、あの書生と親し気に話している所を。あんな茂みに隠れて何を話していたんだ!」
宗一郎は、納得できるような返事を輝子がしてくれると思っていた。
自分が安心して帰ることができる内容の返事がどうしても欲しかったのだ。
「だって、私、水蜜桃を採って食べちゃったの見られたから、怖くなって。でも誰にも言わないって約束してくれたから」
輝子は宗一郎がなぜそんなことを聞いてくるのかわからなかったし、まさか水蜜桃を採ったことをなじるとも思えなかったので、ありのままを答えようとした。
「だから心を許したというのか?あんな、誰ともわからない奴に。お前はそんなに簡単に男になびくようになってしまったのか!?」
水蜜桃が何なのだ!と、ますます訳が分からなくなってきた宗一郎は、輝子にじりじりと詰め寄っていった。
輝子はなぜ宗一郎が怒っているのか、自分の何がいけないのかがよくわからないままでいたので、臆せずにただただ呆気にとられた面持ちで宗一郎を見つめていたのだった。
宗一郎は輝子にとって、小さい頃からとても優しい近所のおにいちゃんだったから、何の警戒もするはずがないのだ。
そんなまだ子どものような輝子が、宗一郎を見つめる顔は美しい女性なのだ。
それなのに彼女は自分のことをきっと男として見ていないのだろうと、宗一郎はこの時悟った。
「お前…うちの親父との縁談があるんだろう!?あの若い男とこっそり会っていたって、親父に俺が言ってもいいのか!?嫁入り前の娘が、許嫁がいる身でよその男と…」
宗一郎は言いながら、父親の問題に話をすり替えている卑怯さをわかっていながらも怒りが勝手に自分の中で暴発し、自分で制御できないまでになってしまっていた。
じりじりと輝子に近寄っていき、彼の手は輝子の襟元をつかんでいた。
驚いた顔の輝子を自分に近づけても逃げる風ではないのを、馬鹿にされている気がして、宗一郎は輝子を押し倒してしまった。その体の上に乗っかり、そこで初めて輝子は恐怖の表情を浮かべたが、宗一郎は「今頃遅いよ」とばかりに、あろうことか女性としての輝子のことを蹂躙してしまった。
一番やってはいけないことをしてしまった。
こうなるべきではなかった。こんなこと、そもそも自分は望んでいない。
理性を失い感情のままに、一番守るべきものを自分が犯してしまったのだ。
後悔しても悔やみきれない。あんなに大切にしていた輝子の心も体も、まさか守ってあげるべき立場の自分が傷つけてしまったのだ。
まともに輝子のことを見ることも出来ずに、宗一郎は卑怯な男としてその場を走り去ってしまった。
残された輝子は、恐怖と失望と痛みとで何が何だかわからずとも、あの優しかった宗一郎から裏切られたのは確かだと思い、悲しくて泣きながら家に帰った。
恥ずかしくて、でも辛いけれど現実を受け入れることが果たして自分はできるだろうかと苦悩した。
しかし家族にはとてもじゃないけれど言えない。言えるはずもない。
言えば父親からはきっと叱られるに違いない。
輝子自身が悪いと言われるに決まっている。
そもそも宗一郎がなぜあのようなことをしたのかもよくわからないのだ。
輝子はそこまでまだまだ幼い子どもだったのだ。
当分自分はひっそりと暮らしていこうと思っていた輝子だったが、いつのまにか月のものが来なくなり、夕餉の支度をしている時に、突然むかむかと気持ちが悪くなり、それに気づいた母親が問い詰めた。
輝子から聞いたことを驚きをもって聞いた母親は、このことは誰にも言うなと口を閉ざすことを輝子に諭した。しかしこのことをたまたま聞いていた幼い妹がつい近所の友に言ってしまったことから、あっという間に村じゅうに噂が広まってしまったのだ。
それは当然のごとく伊ケ谷氏の耳にも自然と入り、まさかの事実に憤怒の気色を帯びたまま彼は、輝子を一人邸に来させて、離れにある部屋に閉じ込め、誰にやられたのかを問い詰めた。
しかし輝子は、はじめはなかなかその名前を言おうとしなかった。
いつもは優しい宗一郎のことを、やはり庇いたい一心だったが、実家の家族のことを苦労の淵に立たせてもいいのかと脅された時には、やはりまだ子どもの輝子には家族を困らせることはできなかった。
悩んだ末にやっと宗一郎のことを口にした。
伊ケ谷氏はすぐにでも宗一郎に帰ってくるよう連絡をした。
もしかしてあの事が知れたのかと嫌な予感がした宗一郎だったが、そのままにしても恐らく父は学校まで押しかけて来るかもしれない、そこまでする人間なのだとわかっているから、ここは素直に応じ家へと帰ってきた。
だが帰ってくるなり、わかってはいたことだが怒りに震えていた父親はこれまで見たこともないような形相で、宗一郎のことを叱り飛ばした。
子を宿した輝子のことをこの時初めて聞いた宗一郎は驚きはしたものの、それをどうしたらいいとか咄嗟のことでは何も頭の中で解決できようもなかった。ただ戸惑うだけであった。
しかし、一応は宗一郎の言い分も聞こうとした伊ケ谷氏だったが、息子の口からまず出てきたのは父を愚弄する言葉だった。
「父さんなんか、輝子と結婚する資格はないよ!そもそも、なんだよ!あんな子どもと結婚だなんて、恥ずかしくないのか!?あんたなんか、俺の父親だとはとてもじゃないが言いたくないよ。
村の学校の話だって自分のことしか考えてないくせに、偉そうなことを村長たちに言っていたけど、結局自分の名前を残したいだけじゃないか!
父さんのことは嫌いなんだよ!輝子を父さんになんか取られてたまるもんか!」
このような言葉をこれまで宗一郎から聞いたこともなかった伊ケ谷氏は、衝撃と恥辱と憤りで我を忘れ、怒りのままに宗一郎のことを殴り倒した。何度も殴りつけた父が少し気が済んだかに見えたすきに、宗一郎は暴力の手から逃げ出した。
そのままの足で、輝子を閉じ込めたとされる離れの部屋のかんぬきを外し、中へ入ると、食事だけはきちんと与えられている状況は確認できた。夕餉を食べた後であろうことがわかる。
突然入ってきた宗一郎に驚いた輝子は、
「宗一郎にいちゃん、どうしたん?なぜ顔を怪我してるん?」
数か月前に乱暴をはたらき、そのまま自分を残して去ってしまった宗一郎を、輝子は非難するではなしに心配の言葉を口にしたのだが。
「輝子!お前、俺のことを父さんに言いつけたな!?そもそもお前が悪いんだ!俺の気持ちなんか全然気づいてくれないお前が!東京の男と仲良くしやがって!お前が悪い!!お前が俺の名前を出さなければ…!お前なんか一生口をつぐんでいろ!」
これも父親に似たのか、感情のままに手が出てしまうような理性のない性格が悲劇を招く。
大好きであるはずの輝子を今度は自分が思い切り平手打ちし、そのまま倒れ掛かった輝子はその先の箪笥にぶつかり、その反動でちゃぶ台に腹から崩れ落ちた拍子に相当腹をぶつけたらしい。
「輝子!!」
と、はっと我に返った宗一郎が見たのは、輝子の倒れた体の下から流れ出てきた赤いものだった。
「痛い…。宗一郎にいちゃん、お腹が痛いよ」
そこに追いかけてきた伊ケ谷氏は、悲惨な状況に何があったのかを瞬時に悟った。
「おい!誰かいないか!大変だ、誰か早く来てくれーー!」
伊ケ谷氏の叫び声が夕時に悲しく響く。宗一郎はなすすべもなくそこに立ちすくんだままだった。
しかし悲劇はそこで終ることはなく、この状況を恥じた伊ケ谷氏は輝子のことをを女中に世話をさせて、離れの部屋に再び閉じ込めてしまったのだった。
これがこの村で起こった悲劇の顛末である。
第8章へ続く
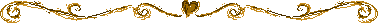
第1章から第6章まではマイマガジン「マサカノベル」に入れました。
まだお読みでない方はそちらへどうぞ。
今回もお読みくださりありがとうございました。
次回もまたご訪問いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

