
セイジ・オザワの思い出
日本のみならず、現在世界で最も有名な存命中の指揮者だった小澤征爾さんが八十八歳で亡くなられました。
二十世紀メディアが称賛した二大指揮者のヘルベルト・カラヤン、レナードバーンスタインの両巨匠の薫陶を受けられたと言う事実からも知られるように、やはり小澤征爾は古い世代の音楽家。
なのですが、二十一世紀の2002年には、かのグスタフ・マーラーも務めていた、欧州一のウィーン歌劇場の音楽監督にさえも就任して、やりたいことをやり尽くして全てを成し遂げた人だったと私は思います。
非西欧人の日本人である自分が、どれだけ欧州の音楽の場で活躍できるか、自分はそういう前人未到の領域におけるモルモットである
とも語っておられました。
音楽を人生の糧として生きてゆくというよりも、音楽世界の覇権のために生きていたという印象さえも私に抱かせるほどの八面六臂ぶりでしたが、ぶれない人生を最後まで送られたことはやはり人間としてすごいこと。
晩年にはアルツハイマー病を患われていることを公表され、半身不随のような姿でも指揮をされている姿に感銘を受けられた方も少なくないことでしょう。
わたしは毎日ピアノを弾いて、クラシック音楽を聴くこと音源を収集すること三十年という筋金入りのクラシック音楽愛好家ですが、どちらかといえばアンチ小澤征爾でしたね。
私は千枚を超える数のクラシック音楽のCDを所有していますが、私のコレクションには小澤のCDは一枚も含まれてはいません。
小澤を聴いたのは、図書館から借りてきたCDか、テレビ放送か、最近のYouTubeなのでした。
だから小澤の録音の多くを聴いては来ませんでしたが、少し聞けば自分の好きな指揮者とそうでない指揮者なのかはすぐにわかります。
アンチというのは相手を知り尽くした上で、この人とは相性が合わない、実力や業績は認めるけど、自分は好きじゃない、という部類の人間です。
だからわたしの書いた以下の文章は小澤先生を崇拝されている方には不快な投稿かもしれません。悪しからず。
小澤征爾の著書
若き日のヨーロッパ時代の青春の日々を痛快に語ったエッセイは昔読んだことがありました。
当時の日本ではほとんど知られていなかった、知る人ぞ知る玄人受け指揮者のカール・シューリヒトについての言及のある本です。小澤とシューリヒトは全く別の芸風を持つ指揮者なので、若き小澤征爾が憧れたのでした。
わたしはオケの響きはしばしば雑だけど、瀟洒で独特の軽やかな音楽を聴かせてくれたシューリヒトが大好き。小澤と本当に対極にあるような指揮者。
また最近では、小説家の村上春樹と対談した次の本も読みました。
一番印象だったのは、指揮者でいるということは一年中試験の期末テストを受けているようなものと語った一節。
常に次の演奏するプログラムの予習に追われていて、心休まる暇もないと。ドイツでのブラームスの次にボストンでベルリオーズをして日本でマーラーを、パリでオネゲルを指揮する、みたいにひたすら言われるかままに仕事を引き受けてこなしているのだと。
でもこれができてしまったという事実だけでもほんとにすごい。
この曲は嫌いだからやりたくない(例えば往年の超個性派指揮者クナッパーツブッシュや、生きた伝説となった名指揮者カルロス・クライバー)なんてゴネはこねずになんでもやってしまうし、見事にこなしてしまう。
でもどういう精神構造なのだろう。
複雑な悲劇的オラトリオを完璧な響きにまとめ上げて観客に涙を流させて、翌日には飛行機に乗って地球の反対側で人生の喜びに溢れてるモーツァルトの弦楽ディヴェルティメントに嬉々として取り組む。
小澤征爾にとって、音楽ってなんだったのだろう。
万能の音楽家って、自分には不可思議以上のなにものでもない。
内科も外科も婦人科でも何でもこなせる万能医師ならぬ、万能指揮者?
音楽界のブラックジャック?
これからメディアは数々の小澤征爾賛美の情報を発信続けるので、小澤征爾の音楽は嫌いだなんてことを書くと四面楚歌になってしまうのだろうけど、もう偉人として、晩年の優れた音楽普及活動などから人格者としての評価の固まっている小澤征爾なのだから、やっぱり小澤征爾の音楽は嫌いだったという言葉を書き残せる自由はあって欲しい。
小澤征爾の音楽が優れていても何が他の人の音楽と違うのか、どうしてコアなクラシック音楽ファンほど小澤征爾の作る音楽を好きではないとか、語ってもよい空気が少しでも残っているといいのだけど。
まあわたしがネットで何を語ろうと小澤征爾の業績になんら傷もつかない。
だからクラシック音楽初心者に、小澤征爾の音楽が業績世界一だからすごいなんて思うのは間違いだっていうことくらいの苦言はここにかいておいてもいいと思う。
ノーベル賞作家の川端康成や大江健三郎の作品が嫌いでも、彼らの偉大さはあなたが嫌いだと語ったところで揺らぐこともない。
というわけで、少しばかり小澤征爾の音楽的特徴について書いてみて、私が聞いた録音を少しばかり紹介してみたいと思います。
小澤征爾の音楽的特徴
日本内外の多くの識者がこれまで語られているように、小澤征爾の作る音楽的特徴は精緻で緻密な音楽。
弦楽演奏とシステマティックな指揮法教育に生涯を捧げた恩師の斎藤秀夫の意思を引き継いでか、とにかく小沢の音楽は精密画のように細部まで徹底的に磨き抜かれていました。
マクロよりもミクロ(マイクロ)な音楽。それが小澤征爾の音楽なのだと思います。
マクロな演奏は細部は乱れていて探せばいくらでも粗が見つかるけれども、全体としてとても感動的な演奏という印象を聞き手に与える演奏。
マイクロはその反対。
そういうわけだから細部まで磨き抜かれることで見事になる音楽をやらせると小澤の指揮する音楽は音楽的に本当に素晴らしかった。
でも芸術音楽とはエラーのない精緻な音響だけでできているわけではないので、小澤征爾の音楽が世界一と呼ばれるようになっても、決してロシアのゲルギエフのように豪快な音楽だとは言われなかったし、サイモン・ラトルやデヴィッド・ジンマンのようにユニークで面白い音楽という感じを与えてはくれなかった。
音楽ってそういうもので、指揮者の数だけ別の解釈があり、解釈の優劣は以下に伝統に根差しているとか音楽性が高いとかいろんな要素において評価される。
ある意味、聞き手次第だけれども、聞き手にも玄人からずぶの素人までいくらでもいるわけで、どれだけの音楽的教養を持ち得ているかでそれぞれが受ける音楽的感銘も変わってくる。
この事実を十二分に理解している小澤征爾は、自分はドイツ人ではないので、ドイツ的なベートーヴェンやブラームスは演奏できないしと自覚して、またそんなを演奏しようともしなかった。
だからドイツ的なベートーヴェンを期待する人には小澤の音楽は物足りないけれども、小澤にはドイツ的な伝統を重んじる指揮者が思いもつかないような「日本的な精緻さ」を生かした演奏を通じて、ベートーヴェンに別の光を当てた。
これは間違いないことで、だから欧米人は小澤にしかできない非欧米的な解釈を新鮮なものと感じたのでした。
行き過ぎては独りよがりで誰にも共感してくれないものになるのだけれども、楽譜という無味乾燥な記号を即物的に読み込んで、世界中の大指揮者と出会い、師事する機会を得た小澤は、新しい日本人としてのクラシック音楽を世界中で演奏してみせた。
努力の人だから、前述のように、試験勉強をひたすらやり遂げて及第してきた秀才は、誰よりも音楽を勉強した最も博学な音楽家の一人になれたのでしょう。
この意味でほんとにすごい人でした。
でも出てくる音楽は、そういう事情もあって、コアな音楽愛好家の自分には物足りないことも多かった。
まあ好き嫌いの世界です。
クラシック音楽を仕事にしていない自分には趣味なので、これでいいのです。
音楽には即物的な音以上の何かがある、ってクラシックオタクはよくつぶやく。
小澤さんは、音楽は音楽以上の何かではなく、音を受け取る人次第で音楽には意味が生まれるのだといわれるのだろうけれども。
だから概して、音楽には意味がある、哲学以上に深い思想なのだ、なんてのたまわったベートーヴェン先生をはじめとするドイツ音楽などは小澤征爾の演奏では物足りない。
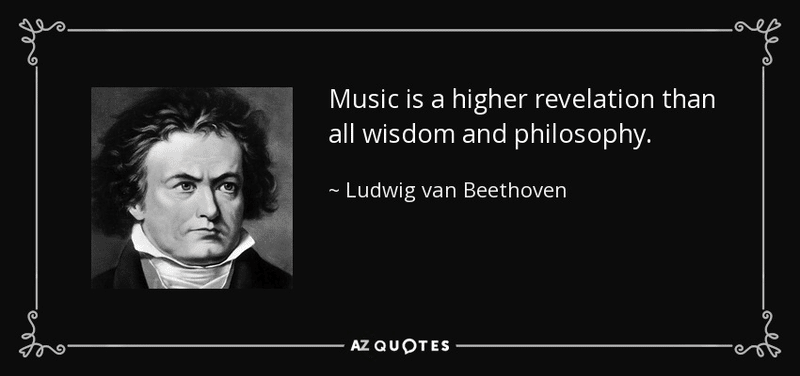
(音楽には神様の言葉みたいに理屈じゃわからない、
人間の浅知恵を超えた何かがある)
とても美しいのだけれども、美しいだけじゃない音楽もあるのだと思う。
例えば小澤が指揮したサイトウキネンオーケストラのブラームス。
すこぶる美しい。特に弦楽器合奏。
でもブラームスってこんな音楽を求めていたのかな?
わたしはそう思わざるを得ない。
こんな演奏の形も音楽の限りない可能性の一つで、こんな解釈も可能なのだということは間違いなくて、素晴らしい歴史的な名演奏として今後も語り継がれてゆくことでしょう。
私が以前聴いて感銘を受けた第4番のCDの映像がありますが、この演奏だったでしょうか。今では詳細は思い出せません。
でもこれもやはり素晴らしく、弦楽器の一体感はサイトウキネンオーケストラならではですね。
この動画のコメント欄には英語で小澤の解釈の悪口が書かれていますが、何をこの演奏から期待するかで、この演奏が感動的になるか、退屈極まりない駄演となるのが決まるのです。
私自身も、あの場面でぐっとテンポを落とせばもっとドラマチックになるし、個々の管楽器が弱く響けばより感動的なのに、なんてことも今回映像で聴いていて思わず思ってしまいました。
音程がずれていないとか、楽器間の縦の線が揃っているとか、音楽的には模範的だと思いますが、音楽のフレーズの間のタメとか節回しとか、この曲を聞きなれた耳には無個性なものに聞こえてしまう。
無個性という表現が悪ければ、平凡な表現。というか、楽譜そのままの音楽。そして伝統ある音楽の意味は楽譜の中には書かれていない!
だから伝統がクラシック音楽においては大事!
伝統は先輩や先人から学ぶものだけど、カラヤンなどを代表とする伝統を無視して新鮮な音楽を作ろうとした即物的アプローチが小澤征爾の音楽の基本なので、伝統的な解釈から無縁な音楽になったのは当然のことですね。
ですが逆に、ドイツやオーストリアの伝統がどうのといった世界から離れた世界の音楽では、小澤征爾のフランス音楽や二十世紀音楽はとみに評価されてきた。
きっと本人の感性にもこれらの音楽の方があっていたのでしょうね。
フォーレやビゼーやベルリオーズなんて、もう一人の恩師のシャルル・ミュンシュの鍛えたボストンフィルの演奏で聞くと、本当に素晴らしい(と私は思うけれども、悪口をいう人もたくさんいる)。
澄み切った、純度の高い、いわば蒸留水のような音楽だと、褒め言葉とも貶し言葉とも取れる評価をかつて見たことがありました。
間違っていないし、また言い過ぎでもない、と私は思います。
でもこれが小澤サウンドなのでしょう。
自分の音を作って、我が道を行くってかっこいい。
小澤征爾は小澤サウンドを世界に広めて、クラシック音楽に生涯を捧げた日本人として死んでいった。
やはりすごい人生でした。
日本では、今もクラシック音楽はもてはやされている。
でも音楽の伝統ってなんでしょうね。
クラシックの音楽の本場の欧米ではどこも補助金カットで存続の危ぶまれる団体がほとんど。
22世紀には、クラシック音楽はクラシック音楽後進国だったアジア諸国かアジア人が運営する海外の団体からでしかクラシック音楽は聴くことができなくなっているのかも。
最近のオーケストラにはアジア人演奏者が溢れている。伝統を受け継ぐべき欧米人はクラシックになんて、もはやあまり関心ないのです。
だから小澤サウンドは年寄りたちの好きな古臭い音楽とは違って、とても新鮮で美しいものだった。
これが私の思うところの小澤征爾です。
。。。。
最後に私が気に入っている、ある動画でおしまいにします。
私が大好きなアメリカのバーンスタインが監修していた有名なテレビプログラム Young People's Concert に登場した際の若き日の小澤征爾の映像。
マイクを持った壇上のバーンスタインは子どもたちでいっぱいの観客席に向けて、ニューヨークフィルの若い助手を紹介しますと、これまでで最も若いアシスタント、26歳の小澤を壇上にあげるのでした。
「フィガロの結婚」序曲。1962年四月の放送。
ほんとに若い小澤征爾。
もしかしたらテレビ初登場だったかも。
アメリカでの全国放送。
わたしはバーンスタインのこの教育番組が大好きで、YouTubeでもう十年以上も前に見つけて、何度も繰り返し見たほどでした。
本当に音楽の勉強になりました。
こんなに質の高い音楽教育番組は他にはありません。
このような教育者バーンスタインのもとでアシスタントできたからこそ、小澤は「世界のオザワ」になれたのかな、なんて当時は思っていました。

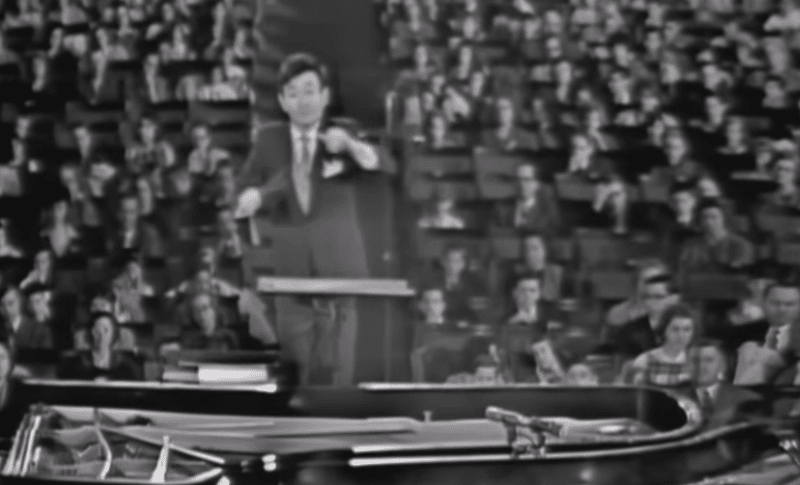

繰り返しますが、私は好んで小澤の音楽は聴かないのですが(他に小澤以外に聴きたい指揮者が多すぎるので)著書から知られるように、N響からボイコットされたり、波乱万丈だった小澤の音楽的人生のすごさには深い感銘を受けてきましたし、前人未到の道を歩まれた彼に心からの敬意を表することにやぶさかではありません。
だから小澤の指揮するようなブラームスが日本文化の中から生まれたのだと思うと感無量です。
日本人にしか演奏できない研ぎ澄まされた弦楽合奏によるブラームス。
やはりすごい人でしたね。これまでお疲れさまでした。そしてありがとうございました。
ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。
