
新刊サンプル「午前2時のアンダンテ」@11/11文学フリマ東京
※本記事内の文章・画像の転載はご遠慮ください。ご協力ありがとうございます。
来る2023年11月11日(土)に開催されます、「文学フリマ東京37」にサークル参加します。
【出店告知】文学フリマ東京37 「喫茶あわい」
「喫茶あわい」という個人サークルで出店します。今回は友人の茶菓嶋さんと合同ブースです。
場所は第二展示場(き-51)に配置されました。ジャンルは恋愛です。
Webカタログも公開中ですので是非ご覧ください!「気になる」ボタンを押下してくださいますと徒然が泣いて喜びます!
白と黒では折り合いのつかない感情、「きみ」と「ぼく」「あなた」と「わたし」の不確かで愛おしい距離感。唯一無二の『あわい(間)』を紡ぎだします。
そして本日!ようやく新刊入稿いたしました~!泣
長い長い闘いの末に……何とか……形になりそうで良かった……のですが!
フォントサイズを間違えました。。。
9pt(13Q)で作っていたつもりが、約8.5pt(12Q)になっておりました…
文庫サイズで作ったのにちょっと小さめになってしまいました…ぴえん
未だ実物届いていないけど、読みにくかったら本当にすみません!
試し読みと合わせて組版サンプルを公開しますので、イメージをつかみ取っていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
内容は「やさしい愛のおはなし」、ラブストーリーです。
自分でも大切な一篇となりましたので、一人でも多くの方にお手に取っていただけたら嬉しいです。
【新刊告知】「午前2時のアンダンテ」
A6判/84p/¥500 11/11文学フリマ東京37にて初頒布
(後日BOOTH通販を予定)
あらすじ
「昏い水底から私を連れ出してくれた玲くんは、魔法使いで王子様だね」
嬉しそうに笑う真唯ちゃんに、僕は救われる思いがした。僕は君にとっての魔法使いで、王子様。せめて、今夜━━君の前だけは、君の望む姿で演じ切らせてほしい。
最愛の恋人・真唯(まい)ちゃんが心の風邪をひいてしまった。眠れない彼女のために、玲(れい)は皆が寝静まった夜にデートを提案するが……。大切な人と夜を乗りこなす、やさしい愛のお話です。

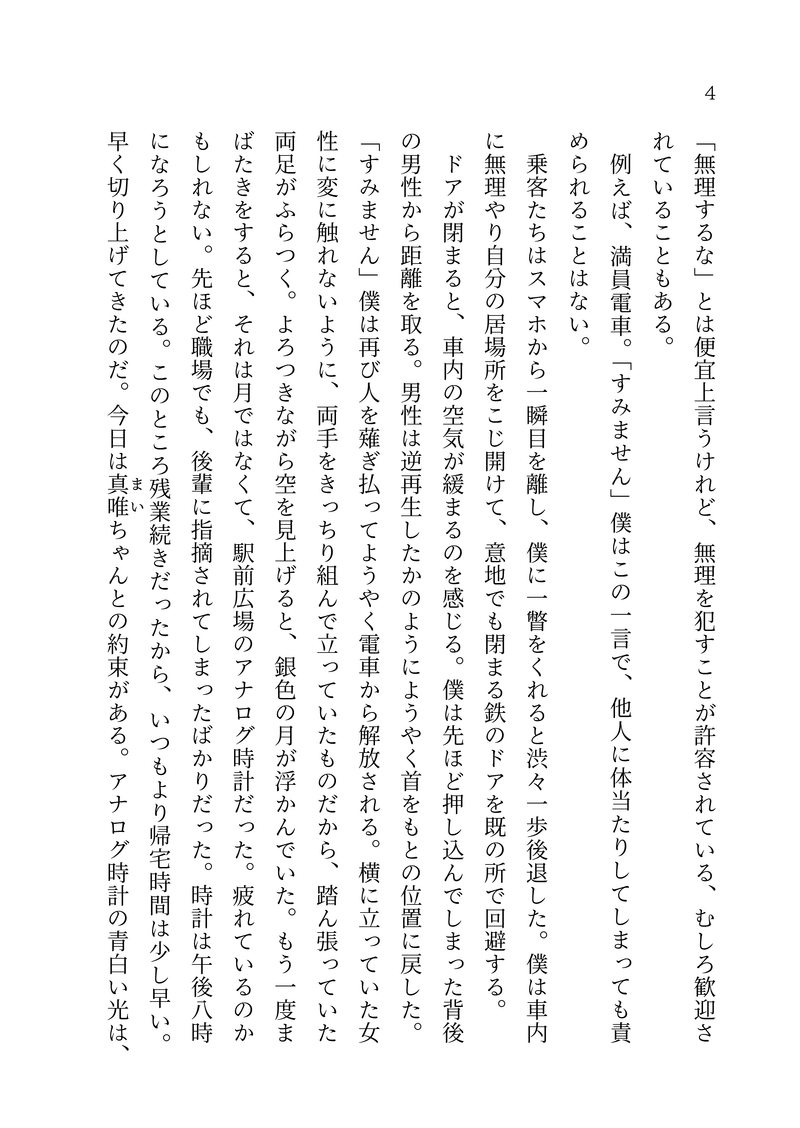
試し読み(PDFデータ)
試し読み(本文より抜粋)のPDFデータはこちらよりダウンロードできます。
実際のレイアウトのイメージも掴んでいただけるかと思います。
以下、試し読みです。(約12,000字/本文約28,000字)
試し読み
午前2時のアンダンテ 徒然みぞれ
「無理するな」とは便宜上言うけれど、無理を犯すことが許容されている、むしろ歓迎されていることもある。
例えば、満員電車。「すみません」僕はこの一言で、他人に体当たりしてしまっても責められることはない。
乗客たちはスマホから一瞬目を離し、僕に一瞥をくれると渋々一歩後退した。僕は車内に無理やり自分の居場所をこじ開けて、意地でも閉まる鉄のドアを既の所で回避する。
ドアが閉まると、車内の空気が緩まるのを感じる。僕は先ほど押し込んでしまった背後の男性から距離を取る。男性は逆再生したかのようにようやく首をもとの位置に戻した。
「すみません」僕は再び人を薙ぎ払ってようやく電車から解放される。横に立っていた女性に変に触れないように、両手をきっちり組んで立っていたものだから、踏ん張っていた両足がふらつく。よろつきながら空を見上げると、銀色の月が浮かんでいた。もう一度まばたきをすると、それは月ではなくて、駅前広場のアナログ時計だった。疲れているのかもしれない。先ほど職場でも、後輩に指摘されてしまったばかりだった。時計は午後八時になろうとしている。このところ残業続きだったから、いつもより帰宅時間は少し早い。早く切り上げてきたのだ。今日は真唯(まい)ちゃんとの約束がある。アナログ時計の青白い光は、僕を見送ってくれた彼女の肌を想起させた。
「いってらっしゃい」
「朝なんだからもう少し寝ていたっていいのに」
「いつも以上に眠れなくて」
確かに目の下はわずかに暗かったが、声は明るかった。
「今日は夜のお散歩だから、早く帰ってきてね」
「もちろん」
真唯ちゃんの弾んだ声に、僕は今日絶対に定時で上がることを誓った。
「『夜のピクニック』、学生の時に読んだよね。覚えてる?」
「恩田陸だ」
僕が答えると、真唯ちゃんはとても嬉しそうに笑った。
「でも夜通しは歩けないな。さすがに明日も仕事だ」
真唯ちゃんの笑顔が曇る。
「わかってる。玲くんにはお仕事があるもんね」
膨んだ頬がだんだんしぼんでゆき、顔の細い輪郭が明らかになった。
「ごめんね」
僕は真唯ちゃんを抱き寄せ、額にキスを落とした。
「お散歩、僕も行きたいな」
「お散歩じゃなくて、ピクニック」
「サンドイッチでも作ろうか」
僕が宥めるように言うと、真唯ちゃんの頬に再び赤みが差した。
「んー……、どちらかというとおにぎりが良いな!」
それはお散歩というより遠足なのでは、と僕は思ったが、黙っていた。
どのみち僕らは遠くへは行かれない。少なくとも真唯ちゃんは今、遠くへ足をのばすことはできない。
「それじゃあ、行ってくるね」
「いってらっしゃい」
少し寂しそうに手を振る真唯ちゃんを部屋に残して、玄関ドアが僕を外へと追い出した。
真唯ちゃんと最後に遠くに行ったのは、彼女の仕事のお祝いで行った都内のレストランだったかもしれない。その光景は今でも鮮明に思い出せるのだが、スケジュールアプリでカレンダーをなぞると、もう半年も前の出来事だった。
「おめでとう」
ピンクの泡の先に映る真唯ちゃんは伏し目がちに笑んだ。いつも明るい笑顔を見せてくれる真唯ちゃんだが、褒められることには慣れてないらしく、そこがとても可愛らしかった。
「ありがとう」
「夢の一歩だね」
「まだまだだけどね」
そう言いながらも、真唯ちゃんはスパークリングワインを一気に煽った。彼女のペースは少し心配ではあるけれど、これも照れ隠しの一つなのだと思うと僕は注意するのを忘れてしまう。
「こうしてお祝い出来て嬉しいよ」
「私も玲くんがお祝いしてくれて嬉しい」
真唯ちゃんがあまりにも幸せそうに笑うから、僕は自分が編集者という夢をかなえたような気持ちになった。夢見たことなど一度もないのに、真唯ちゃんが笑うとそう思えてくるから不思議だ。
その日、真唯ちゃんはお酒がそんなに強くもないのにワインの瓶を空にしてしまい(もちろん僕も加担したけれど)、とても親御さんのもとに帰せる状況ではなくなった。
「帰らないとご両親が心配するよ」
思えばここでタクシーを呼んでしまえばよかったのだ。つい、真唯ちゃんのへの字のくちびるに押し負けてしまった。
「私だけタクシーに押し込む方が心配じゃない?」
「それなら僕もタクシーに乗るから」
僕がそう言うと、真唯ちゃんは子どもみたいに頬を膨らませた。酔いが回って紅潮した頬が熟れた桃のようで、思わず僕の喉がうなった。
「もう、鈍いなあ!帰りたくないって言ってるの」
そう言って真唯ちゃんは僕の唇に自身を押し付けた。ぬるりとした熱い舌が絡む。普段と異なる真唯ちゃんの積極性に、僕は全身が硬く柔らかくなっていくのを感じた。
「っは、……確かに、これでは帰れないね」
僕は手の甲で唇を拭う。真唯ちゃんは蠱惑的な笑顔を巧みに使う。
「ね、心配でしょ。私のことが」
「すごく心配」
じゃあさあ。上機嫌だった真唯ちゃんの瞳がすっと透明になる。
「玲くんは、私を一人にしていいのかな?」
しん、と響く真唯ちゃんの濡れた声が、僕の深部の孤独に共鳴する。
そんなこと、できるわけない。僕は夜道に細く光る真唯ちゃんの身体を強く抱きしめた。
「……一人になんて、しないさ」
もたれかかるように倒れ込んだ彼女の身体を抱き留めて、僕は彼女の腰に手をまわし、求める彼女に応えた。
真唯ちゃんを連れて帰った僕は、まだ祝杯を求める彼女に水を飲ませ、軽くキスをして、ベッドに寝かせた。
「シングル・ベッドなの?」
「僕は床で寝るからいいよ」
「一人にしないって言ったじゃん」
真唯ちゃんは甘えた声を奏でて、僕を困らせる。
「……抱かないよ?」
「なんで?」
酔いが回って蕩けた瞳が、またも魅惑的に瞬く。意地悪な真唯ちゃんに、僕は仕返しがしてみたくなった。
「酔いが回った君を抱いても、明日には覚えていないかもしれない。それはもったいないでしょう?」
僕はあくまで紳士的に笑んで見せた。真唯ちゃんはへの字にした唇をんの字に歪ませ、もどかしそうに顔を赤く染めた。
「……一理あるかも」
「ん、じゃあ今日はもう寝よう」
残念そうな真唯ちゃんに後ろ髪をひかれながら、僕は部屋の電気を落とした。
暗闇の中で、ロウソクのように真唯ちゃんの声がぽつりと灯る。
「お酒はやっぱり、苦手だな……」
「どうして?」
「変なところ見せちゃうし」
「確かにそれは心配だけど」
僕の前ならいいよと添えると、「また口説く!」と真唯ちゃんに叱られてしまった。
「それに、祝杯以外はただの薬だもの」
それは飲む人の発言だなと思ったが、真唯ちゃんの顔はやけに真剣だったので、僕は一旦ひっこめることにした。そういえば大学時代のサークルの飲み会の時も、真唯ちゃんはソフトドリンクだったっけ。
「薬は毒にもなり得るしね」
「さすが、玲ちゃんはわかってる」と嬉しそうな声が返ってきて、僕は安心する。真唯ちゃんはお酒を舌の上で転がすように、僕の言葉を反芻していた。
「お酒は薬、薬は毒……。祝杯を挙げる時だけ、飲んでいたいな……」
深い眠りにつく寸前の、真唯ちゃんの蕩けた声を覚えている。
一人にしないという誓いを僕が破ってしまったように、真唯ちゃんもその約束を守り抜いてはくれなかった。
*
僕は真唯ちゃんの恋人だというのに連絡を怠っていた。今思うと僕はとんでもない男で、真唯ちゃんを守れなかった最低の彼氏だ。それでも別れずにいてくれる真唯ちゃんに、僕は一生頭を下げて生きていくしかない。
言い訳をさせてもらうと、僕は真唯ちゃんの邪魔をしたくなかった。僕という恋人に現を抜かすくらいなら、真唯ちゃんは真唯ちゃんの人生を生きてほしかった。たまに僕のことを思い出してくれたらそれでいい。僕の存在が真唯ちゃんの邪魔になるのであれば、僕は真唯ちゃんの目の前から消える覚悟だ。それくらい、僕は彼女の夢を応援していた。
「作家さんの担当に就くことになったの」
夢をかなえた真唯ちゃんは日に日に仕事が忙しくなっていった。会う回数は十日に一度から二週間に一度、一か月に一度、そして再調整と減っていき、メッセージも僕の分量の方が多くなっていた。既読さえつかない日も増えていった。それでも僕は──振り返るとそれがいけないのだが──あまり気にしていなかった。返信が来ないということは、それだけ真唯ちゃんが頑張っているという証拠で、その事実だけで僕は今日を生きることが出来た。心配ではあったけれど、僕が変にでしゃばることは彼女の迷惑になるのだと思っていた。
「お前それ、おかしくね?」
そう言い放ったのは、大学時代からの友人・真生(まお)だった。
「……そうなんだ」
「自覚ないのがなあ」
真生は深い溜息を吐いた。
「お前が優しすぎるだけで、普通は心配で心配でたまらなくなって、終いには彼女の家に押し掛けるんだぞ」
普通、という言葉に僕は顔をしかめた。
「迷惑な男だな」
「そんなことも考えられなくなるくらいおかしくなるもんなんだよ」
「心配していないわけじゃないんだけど」
思ったより苛立ちの滲む声になってしまい、真生は「わかってる」と詫びた。流石に申し訳無くなった時、真生が再び口を開いた。
「でも、藤波さんは今独りなんだろ?」
僕は言葉に詰まった。
あの日、君を一人にしないと誓った僕自身の言葉がよみがえる。
真生は横目で僕の顔色を窺っている。
「王子様が迎えに来るのを待っているかも」
真生は時々詩的な表現を使う。恥ずかしくないのかと正直思うけれど、これも彼が持つユーモアなのも理解していた。
「で、お前はどうしたいの?」
「僕は……」
恋愛はおろか人付き合いさえ平均よりも経験の乏しい僕に、真生はありがたい存在だった。真生は性別年代問わず、人付き合いの経験が豊富だ。羨ましいと感じる隙もないくらい僕とはかけ離れているけれど、偶然思考と感情の波長が合った。その偶然性に感謝せざるを得ない。彼と友人になれたことが、大学進学を諦めないで良かった一番の理由になった。
「どうしたいのか」
それは僕にとっては難しい問いだった。自分のことになると答えが出ないのだ。
真生はじっとこちらを見ている。やがて組んでいた手を緩めて「難しいよな」と呟いた。
「ま、藤波さんもそれがわからないから連絡が来ないんだろうけど」
「……」
逃げとも思える回答に腹を立てそうになったが、答えの出ない僕をフォローしてくれたのがわかって、僕は真生に頭を下げた。
「先生みたいだな」
僕が褒めると、真生はきまりが悪そうに視線を逸らした。
「少し、考えてる……教師」
真生にしては珍しく、自信のない声だった。
「へえ、いいじゃん」
真生が驚いた表情でこちらを見る。僕は動じない。本当に真生なら教師になれると思ったのだ。
「いいと思う。教師」
「……お前は『今から?』とか言わないんだな」
「え、何で?」
「無責任だなあ!でも……ありがとう」
真生が呆れながらも照れくさそうに微笑んだ時、ようやく僕は真生の懸念を察した。そして同時に思い出した。真唯ちゃんとも、これからの未来の話をしたかったのだ。
「どうした?」
あの日の祝杯がよみがえる。
「……たい」
「え?」
「真唯ちゃんの話が聞きたい」
僕の絞り出した声を聞いて、真生は破顔した。そして、僕の頭をわしゃわしゃ撫でる。
「僕は犬じゃない」
「わかってるよ」
「わかってない」
「わかってないのはお前だよ」
なおも僕の頭をこねくり回しながら、真生が楽しそうな声を上げた。
「お前さあ、気づいてないかもしれないけど、世間ではそういうのをバカップルっていうんだぜ」
「お熱いことで」と真生はからかうように言う。不思議と不快な気持ちにはならなかった。それが真生の言う「熱さ」なのかもしれないと、僕は内心思う。
「そうだな、僕は馬鹿なのかもしれない」
僕は至って真面目な回答をしたのに、真生は今にも抱腹絶倒寸前といった様子だ。
「盲目野郎はそんなに自分を客観視できねえよ」
けたけたと笑う真生の姿に、いよいよ僕が眉を顰めそうになった時、「でもさあ」と真生は大きなあくびをした後、目尻を擦りながら言った。
「安心した」
「え?」
「玲にもちゃんとやりたいこと、あるじゃん」
「それは、……」
それは真生が、真唯ちゃんが僕に教えてくれたから、で。
何故だか気恥ずかしさを感じた僕は、言葉を飲み込んで、深呼吸する。
「……うん。そう、あった。ちゃんとあったね」
「良かったな。藤波さんもお前の話が聞きたいってよ」
真生のほうこそ無責任だと言ってやりたいけれど、僕の心に広がったのは安寧だった。
僕はようやく気付いた。真唯ちゃんに会いたいという思いに、誰かの承認を得られないと行動できなくなっていたことに。自分の意志に他人の承認が必要だと、思い込んでいた。真生は、その歪みを少しでも平らに近づけようとしてくれているのかもしれない――なんて思ってしまうのは自惚れか。
「面倒な奴だな、僕は」
「はあ?今更かよ」
真生から今日一番の苛立ちが漏れたので、僕は少なからず傷ついた。
「悪かったよ」
「まあ、面倒くさいけど嫌いじゃない」
真生は頭の後ろで腕を組みながら、呆れつつ破顔した。
「じゃなかったらこんなアドバイスしねえよ」
「ありがとう」
「ん」真生はひらひらと手を振った。
「感謝してるんだったら、今すぐ藤波さんに会って来い」
「そうする」
「良い笑顔をしてるよ」
真生がすかさずスマホを向けたのを、僕は回避できなかった。
「ちょっ、……真生!」
「うん、よく撮れた。ほら」
真生が見せてきた画面の中の僕は、真生が「お熱いことで」と評価するのも納得できるくらい呆けた顔をしていた。絶対に真生には言わないが、本当に僕なのか疑いたくなるほど、とても明るい顔をしていた。
「絶対真唯ちゃんには送るなよ」
「さて、どうしよっかな」
「……面倒くさい奴」
「今更だろ」
ニヤニヤ笑う真生に僕は何も返せず、観念して溜息を吐くほかなかった。
*
『忙しいのにごめん。今度、五分だけでも声が聴きたい』
勇気を出して送ったメッセージは、一週間後にようやく既読がついた。ついたまま、それからまた一週間が過ぎた。
会いたくないのかもしれないと考えるより先に、真唯ちゃんのスマホが壊れている可能性を考えた僕は、流石に盲目すぎだというほかない。
けれど一目で良いから真唯ちゃんに会いたい、一言で良いから言葉を交わしたいという僕の意志だけは、なんとしても貫き通したかった。
僕は自分でも信じがたい程図々しい男になっていた。
スマホが壊れているならと僕は、直接真唯ちゃんに会いに行くことにした。僕はこの行動力を後に真生から褒められることになった。
恋人の実家に行くなんて、そういう時だけだと思っていたのに。それに、アポイントメントを取ってから訪問するのが普通だろう。初対面から印象を悪くしてどうする。僕自身も思ったが、緊急事態だからやむを得ないと、自分自身を納得させていた。
真唯ちゃんの実家は都心から四〇分ほどの郊外にある一軒家だった。戸建て住宅が並び、一家に一台もれなく自家用車を所有しているような地域だった。肩身の狭さを感じながら、鏡で自分の姿を確認し、一呼吸を吐いてからインターフォンを押す。
『はい』
女性の声だ。真唯ちゃんは両親と三人暮らしだと聞いていたからおそらく母親だろう。モニターに僕の姿が映ったのか、息を呑む気配がした。僕はモニターの向こうのお母さんに頭を下げた。
「突然のご訪問、申し訳ありません。永井玲と申します。真唯さんとお付き合いをさせていただいている者です」
突然の来訪により、第一印象がマイナスに振り切っているのは承知だが、僕はせめて全身全霊誠実であろうと努めた。
『ああ、あなたが永井さんね……』
モニター越しに、真唯ちゃんのお母さんが僕の頭の上から足先まで眺めているのが伝わってくる。僕は平静を装いながら、真唯ちゃんが僕の存在をご家族に打ち明けているという事実に少なからず喜びを感じていた。僕には、僕の家族には到底できないことだ。
僕は「はい」とうなずき、一礼する。そして僕が無礼を働いてまでここに来た理由を打ち明けた。何て図々しく、白々しいのだろう。ここに来る理由なんて一つしかないのに。それは緊張の混じる空気から既に伝わっているはずだが、僕は背筋を伸ばす。
「お世話になります。真唯さんはいらっしゃいますか」
ややあって、真唯ちゃんのお母さんは重たい口を開いた。
「いますけど、……」
否定の先の言葉を把握できかねていた時、玄関のドアが開いた。
「……真唯ちゃん」
ドアの向こうから現れた真唯ちゃんは、僕が初めて恋をした頃と同じ屈託のない笑みを浮かべているが、その肌は青白く、生気がなかった。肌を隠すように覆ういちご柄の部屋着は疲れの滲む目尻と同じく、くたびれていた。
「久しぶりだね。……ごめんね、玲くん」
乾いた唇を動かす真唯ちゃんの姿が、何年も前に会ったきりの母親の姿と重なって──喉がうねりを起こした。
『ごめんね、玲』
艶のない髪、虚ろに濁る瞳。何年も前から──きっと僕が生まれる前から──空っぽだったそれを何とか見繕い、親の体裁を拵えている、母の姿。
「真唯、ちゃん……」
僕は目の前の現実を確かめるように呟いた。重く響く声に、目の前の女性が頷いたので、僕はようやく彼女が真唯ちゃんだと認知できた。
「会えてよかった。僕は──」
「驚いたでしょう?」
僕の言葉は第三者の声に遮られた。
「お母さん……」
真唯ちゃんを抱き留めるように後ろから現れたのは、先ほどインターフォン越しで話した真唯ちゃんのお母さんだった。張りのある黒いワンピースに対して、真唯ちゃんとそっくりの目元には深いしわが寄っていた。
「すみません。真唯は今、少し疲れていましてね」
何に対する詫びなのだろう、と僕は思った。疲れているから連絡が取れなかった、ということなのか。そもそも、連絡が取れていないことを知っていたのだろうか。まるで自分に責任があるかのようなお母さんの姿に、僕は見覚えがあった。母が病のせいで混乱をきたすたびに近所に頭を下げていた、父親の背広だった。
お母さんの横で真唯ちゃんは口を固く結んでいた。話したくないというより、話すことがないといった様子だった。とりあえず、真唯ちゃんが本調子ではないということと、それでも踏ん張っていることがわかって、僕は安心した。疲れてはいるけれど、生活はちゃんとしていることが見えたからだ。
お母さんの言葉には「お引き取りください」の意が含まれていることに、もちろん気づいている。気づいていながら僕は、どうしても目的を達成せざるを得なかった。真唯ちゃんの口から聞きたかった。
「真唯さんと少し話がしたいんです」
僕は真唯ちゃんを見た。どこか怯えを見せる彼女に、僕は努めて柔く話しかける。
「もちろん真唯ちゃんが嫌だったら、帰るよ。君に会えただけで今日はとても嬉しいんだ」
五秒間、返事が来なかった。時が止まったようだった。真唯ちゃんの躊躇う顔を見るのは僕にとって本意ではなかった。彼女の同意が無ければただの乱暴と同じだ。
失礼しました。踵を返そうとすると、「待って」と真唯ちゃんが引き留めた。
「……お母さん、玲くんを部屋に入れてもいい?」
お母さんは今日一番の困惑を見せた。真唯ちゃんはお母さんを宥めるように「わかってる」と言い、ゆっくりと僕を見た。縋るような、僕を試すような、怯えと覚悟が混じった色をしていた。
「今の私を見てほしい。ううん、玲くんには見てもらわないといけないね」
白のインテリアで統一されている部屋は、カーテンで閉め切られていてくすんだグレーのようになっていた。
脱ぎ捨てられた服とカバーのかけられた本が、部屋の隅に山積されている。通販で買ったのだろうか、中途半端に開けられた段ボールが幾つも床に置かれている。脱ぎ捨てられた服はどれもTシャツやジャージなどのカジュアル着で、ブラウスやスカートの類は見られなかった。
雑然という言葉が適した部屋の中心に、真唯ちゃんが膝を抱えて座っていたであろうへこんだクッションが目についた。
「これが、今の私」
真唯ちゃんがクッションに腰を下ろすと、部屋は完成したのか、冷たい息遣いが聞こえてくるようだった。僕は敢えて腰を下ろさなかった。歓迎されていないのはわかっていたし、本当は僕がここにいてほしくないと彼女が訴えているのは伝わっていたから。
「……驚かないんだね」
正直、実家の方が荒れていたのでさほど驚きはしなかった。それ以上に感じたのは罪悪感だった。見慣れた光景だったからこそ、繰り返してはいけなかったはずなのに。母のようにどうしようもなくなる前に、僕にできることがあったはずなのに。
「ごめん」
「何で玲くんが謝るの」
真唯ちゃんは泣き笑いの顔を浮かべながらも、優しい目で僕を見る。
「もっと早く会いにくればよかった」
「会いたくなかったのは私の方だもん。玲くんは悪くないよ」
真唯ちゃんは弱弱しくも柔らかく笑った。自虐交じりの笑顔が僕をさらに苦しめた。
がらん。
真唯ちゃんへ手を伸ばした僕のつま先に当たったのは、チューハイの缶だった。目をやるとベッドサイドには杏露酒の瓶と、半分まで注がれたガラスのグラスが見えた。
「……お酒」
苦手だと言っていたのに。
「眠れないんだ」
真唯ちゃんの瞳はこの部屋と同じ色をしていた。
「薬は毒にもなり得るよ」
「毒でも今の私にとっては薬なのかもしれないね」
真唯ちゃんは薄く笑った。その目尻にはたちまち涙の粒が浮かんだ。
「何が毒なのかわからないよ」
真唯ちゃんの涙が足元の本にこぼれた。降り落ちた部分が色濃くなり、文字が滲んでいく。
「好きなことをしていたはずなのになあ」
真唯ちゃんは吐き出すかのように嗚咽を繰り返した。僕は真唯ちゃんを抱きしめた。否、抱きしめることしかできなかった。真唯ちゃんのためにできることがわからなかった。「僕が君の薬になる」とでも言えたらよかった?僕はただ、毒を吐き出す彼女に「うん」「うん」と、無責任な相槌を打つのみだった。
「…なくて、いい……」
絞り出した声が僕のものだと気づいたのは、僕の胸元に顔を埋める彼女の荒い呼吸が一瞬、凪いだから。
「しなくていい」
僕はその時、ようやく自分がすべきことがわかった。
「君が苦しむことはしなくていい。たとえそれが好きだったことだとしても……」
僕は一旦言葉を切った。これから伝えることは真唯ちゃんにとっては一番聞きたくない言葉だったが、彼女を救うにはこれしかなかった。
「それはもう、君にとって毒なんだ」
僕の腕の中で真唯ちゃんは小さくうめいた。大きく身体を震わせているが、溜め込んでいた硬いものが融けているようだった。僕は真唯ちゃんが落ち着くように背中をさすった。父が母にそうしていたように──
「あと、さ」
これは真唯ちゃんのためというより、僕自身の願望だった。
「もう無理して笑わなくていいよ」
真唯ちゃんが顔を上げて僕を見る。こうして至近距離で見ると、目の下の紫色がはっきりと見えた。真唯ちゃんの表情は何も映していなかった。それはただ、笑顔の下に抑圧していた、素の感情──真唯ちゃんは時折それを不真面目と呼んでいた──が浮き上がっているのみだった。
「君がどんなふうに笑っていたのかは、僕がちゃんと覚えているから」
真唯ちゃんは今度こそ声をあげて泣いた。真唯ちゃんの感情の発露は不思議と僕を安心させた。ようやく真唯ちゃんに会えた──そう思うと、僕も何故だか泣きたくなった。彼女に心配をかけてしまうから泣かなかったけれど、僕は心底幸せだと思った。
「今日は突然押しかけてしまってすみませんでした」
「……いいえ」
真唯ちゃんのお母さんが僕の無礼よりも気掛かりなことについては、何となく僕にも分かる。
「その、真唯の部屋……」
真唯ちゃんと同じ反応だ。相当隠したかったのだろう。
「真唯さんはさぞお辛いのだと思います」
「ずっとあの部屋にいるのは良くないって、私たちも思うのだけど……」
「そうですね」
僕の声に張りが生まれたのを察知して、お母さんが僕を見た。不安と希望とわずかな嫌悪が滲む瞳に、僕は丁寧に語りかける。
「真唯さんはあの部屋を出たほうがいいと思います」
この家に縛られる前に。僕の脳裏を母親の姿がかすめた。
「出るって、どうやって?一人で暮らせと?……」
僕の言いたいことを察したのか、お母さんが今度こそ厳しいまなざしを向けた。僕はあくまで平静を保ったまま、提案する。
「同棲ではありません。真唯さんに『家出』をさせてもらえませんか。ああ、家出では言葉が悪いですね……、ショート・トリップのようなものです。環境を変えて療養してみるのはどうでしょう」
お母さんは絶句していた。当然だと僕は思う。なんて傲慢、なんて図々しい。紳士的な装いをしているのがいやらしさを増している。けれど僕にはふしだらな気持ちは一切なく、ただ真唯ちゃんが、真唯ちゃんの家族が元気を取り戻すための一つの方法だと本気で信じていた。
皆で朽ちる前に、今ならまだ戻れる。
「……随分大胆ね。貴女の娘を僕に預けて下さいって?」
お母さんの冷たい苦笑いが肌を刺す。その通りなので僕はうなずき、再びお母さんが溜息を吐く前に先手を打つ。
「このままでは良くないと、お母様もおっしゃっていたので」
「……」
お母さんは僕をじっと見た後、隣にいる真唯ちゃんに視線を移した。
「真唯はどうしたいの?」
「私は……」
僕の目を見据えて、真唯ちゃんは言った。
「ちょっと家出しようかな」
*
ご両親公認の家出は、ひとまず二週間の最大一か月だった。真唯ちゃんは心の風邪をひいてから一か月半が経過していた。一般的には三か月が目安と言われている病気だから、ご両親の条件は最大の譲歩だ。けれど、一般的な事実が真唯ちゃんに当てはまるとも限らない。
初めて僕の家にやってきた時、真唯ちゃんはココアを飲みながらぽつりぽつりと、会えなかった空白の時間の出来事を話してくれた。
あの日お祝いした仕事の案件で、萎れていってしまったこと。
憧れの作家さんはスランプに陥っていて、担当編集者の真唯ちゃんに当たりが強くなったこと。
純粋な作品ファンとして先生を労わる気持ちと、仕事としてなんとしても先生に書いてもらわなければならない使命。両方を大切にしたいという気持ちが、かえって足かせとなってしまい、結局すべてが中途半端な結果になってしまったこと。
とうとう先生は書けなくなり、その責任を真唯ちゃんの上司が取らされることになったこと。
上司は真唯ちゃんを責めるようなことはしなかったが、周囲から苦言という非難を浴びせられたこと。
もっと努力をしなければと誠意をもってやり遂げようとしても、やることなすことすべてが裏目に出てしまった真唯ちゃんは、ある日突然、燃え尽きた。
せっかく祝ってくれたのに、自分の夢が叶ったのにと、それが原因になってしまったことに、真唯ちゃんはひどく罪悪感を覚えていた。
「本当に身体が動かないことがあるんだって、逆に感動しちゃったよ」
真唯ちゃんからは無理して笑っているわけではなく、笑うほかなかったという意図が読み取れた。
「食い意地張ってた私が、ご飯が喉通らなくなっちゃったんだよ。すごいよね。それでも会社には行かなきゃって思っていたから、それこそ這いつくばってパンプス履こうとしたんだけど、お母さんが止めたんだ。『もういいよ』って。今まで学校休んでいいよとか一度も言ってくれたことがなかったのにね」
僕は止めてくれたお母さんに感謝した。絶対悪のような物言いで真唯ちゃんを連れだしてしまったけれど、真唯ちゃんのご両親はちゃんと心配してくれる人たちなのだ。
「その時鏡に映った自分を見て、驚いたの……。今もひどい顔だけど、最初はもっとひどくてね。ただでさえ顔色が良くないのに無理やり化粧を乗せるものだから、もっと悲惨なことになっちゃってて。それを見てやっと、『私やばいんだな』って気づいたの」
それからお母さんと病院に行き、診断書をもらい、会社を休職することになった。それがこの数か月の真唯ちゃんの人生だった。
僕は時折相槌を打ちながら、真唯ちゃんの手を握っていた。真唯ちゃんが安心して話せるように。僕の父が母にやっていたことが役に立つ日が来ると思わなかった。
話を聞きながら僕は納得していた。真唯ちゃんの人生を大きく左右した数か月の中で、僕の出る幕はどこにもなかったのだ。
滔滔と話し続けていた真唯ちゃんは、我に返ったようにぴたりと話すのをやめ、相槌を打つ僕の顔を覗き込み、申し訳なさそうに目を潤ませた。
「ごめん……、だからと言って玲くんをおざなりにしていい理由にはならないよね」
そう言ってはすぐに口をつぐんだ。真唯ちゃんの表情が再び曇る。
「いや、何を言っても言い訳にしかならないね。ごめん……」
ごめん、ごめん、ごめん。真唯ちゃんは繰り返す。まるでうなされているかのように。すべての矢印が自分に向いてしまう優しい真唯ちゃんの手を固く握りしめる。
「……そうだね、真唯ちゃんのスマホが壊れたんじゃないかと勝手に判断して、約束もなしに突然家に押し掛けるくらいには心配だった」
彼女が再び大粒の涙をためる前に、「責めてるわけじゃないよ」と添える。
「今のは笑うところだよ」
「あ、は、はは……?」
「真唯ちゃん、それは大根役者だ」
「っ!ひどい!これでも演劇サークルだったの、玲くんも知ってるでしょ」
「でも裏方だったよね」
「うーるーさーい」
「あはは、ごめんって」
真唯ちゃんに笑顔が戻ってきて、僕は安心する。真唯ちゃんは頬に触れ、口角が上がっていることに気づくと、「ありがとう」と照れくさそうに、少し申し訳なさそうに笑んだ。
「でも……、何だか王子様みたいで嬉しかった」
一瞬、なんの話かわからなくて僕は戸惑った。実家突撃のことだと悟るまで間が開いてしまったが、真唯ちゃんが自分の詩的な発言に赤面をしているところだったので、かえってその間がいい方向に働いた。
はにかむ真唯ちゃんがあまりにも可愛くて、僕は魔女から大切な姫君を救ったような気持ちになる──誰が悪いわけではないのに。そう、誰も悪くない。真唯ちゃんがこんなに苦しんでいるのも、本当は誰も悪くないのだ。
僕は正しいことをしたとは思っていない。けれど、君が正しいと思ってくれたのなら、僕にとってはそれが正解の道になる。
「もちろん、いつでも迎えに行くよ」
僕は君の王子様だから──なんて台詞はとてもじゃないけれど言えない。その代わりに僕は僕なりの誠実を貫くと誓うよ。
「だから一人で苦しまなくていいよ」
僕は真唯ちゃんを強く抱きしめ、その額に口づけた。
愚直な真唯ちゃんは魔術にかかったようにゆっくりと瞼を閉じた。
「久しぶりにいい夢が見られそうな気がする……」
「それは良かった。でも、眠れなくてもいいんだ。眠れないのなら、寝なければいい。僕も付き合うから」
「付き合うって?」
きょとんとした表情の真唯ちゃんに、僕は微笑みを投げかける。
「一緒に眠れない夜を乗りこなそう」
ここまでお読みいただきありがとうございました!
お手に取っていただけたら嬉しいです。
何かございましたら徒然みぞれのX(旧Twitter)までお願いいたします。@SsMizore
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
