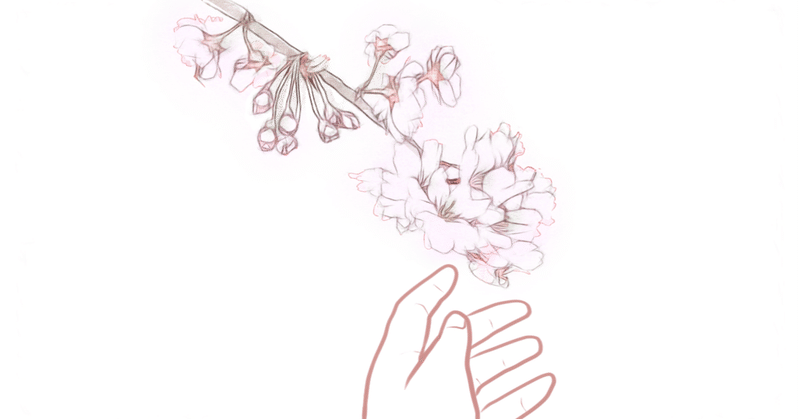
短編小説 「桜の思い出」
実家の庭先の樹齢二十八年、高さ四メートルほどの桜の木の下に立ち、私は見上げた。優しい風が吹き抜ける中、数少ない花びらはまるで時間を忘れさせるかのように、ゆっくりと、そして優雅に舞い降りる。その様子はまるで、ピンク色の雪のようで、何とも言えない美しさに左手のひらを桜の木に掲げた。
「安心して、すぐ終わるから」
私は目の前に置いたチェンソーに目を向けた。チェンソーのハンドルを左手で握り、プルコードを力強く引いた。エンジンは一瞬の静寂の後、轟音を立てて目を覚ます。その音は周囲の静けさを打ち破り、チェンソーの刃が回転を始める。
私はエンジンを少し吹かし、作業への準備が整ったことを周りに伝える。今はもう、桜の花びらが舞い落ちる静かな景色は騒々しい伐採作業へと変わる。
私は大きな声で叫んだ。
「お父ちゃん、兄ちゃん、準備いい?」周囲の桜の花びらが舞い落ちる中、チェンソーのエンジン音が響き渡る。
「大丈夫!」お父ちゃんが返事をした。兄ちゃんも「準備オーケー!」と力強く叫ぶ。二人は桜にくくりつけたロープをしっかりと握り、倒す方向へ引っ張る体勢に入っていた。
私は再びチェンソーのエンジンをふかし、刃を木にあてた。エンジンの唸りと共に、チェンソーの歯が木の幹に食い込んでいく。木の中からは、メリメリ割れるような音が次第に大きくなっていった。
お父ちゃんと兄ちゃんは、ロープをしっかりと引っ張り続けている。体重をかけた力強い引っ張りが、木の倒れる方向をコントロールしていた。
木が少しずつ傾き始めると、私はアクセルを戻し、二メートルほどの距離に下がった。そして、ゆっくりと、しかし確実に、桜の木は大地へと倒れていった。その倒れていく音は、周囲の静けさに響き渡り、一連の作業の終了を告げた。伐採作業は無事成功し、私たちは互いに顔を見合わせ、安堵の表情を浮かべた。
「もう一仕事だな」とお父ちゃんが言った。倒れた桜の木を見つめながら、私たちは次の作業に取り掛かる準備を始めた。これからは、冬に向けてその大きな木を小さく切り分けて、ストーブに使う薪に変える作業だ。
チェンソーを再び手に取り、お父ちゃんと兄ちゃんは大きな桜の幹を丁寧に切り始める。木の断面は美しいオレンジ色をしており、それぞれの切り口からは桜の木特有の甘い香りが立ち昇った。私は小枝を拾い集め、きれいに束ねて薪の山を作った。
作業をしながら、お父ちゃんは昔の話を始めた。「この桜を植えたのは、お前が生まれた年だ。小さな苗木だったのが、もうこんなに大きくなって……」アクセルを弱めては話を続ける。
「毎年、お前の成長と共にこの木も大きくなっていった。お前が初めて歩いた日も、この桜の木の下だったんだよ」
私はその話を聞きながら、桜の木と共に過ごした幼い日々を思い出していた。桜の木の下で遊んだ日々、花が満開の春に家族でお花見をしたこと……。それぞれの薪が、私の人生の一部のように感じる。
桜の木を薪に変える作業は、ただの作業以上のものだった。それは、過ぎ去った時間、家族の絆、そしてこれからの暖かい火を灯すための準備だった。私たちは黙々と作業を続け、倒れた桜の木から新しい生命と暖かさを引き出していた。
「思い出があるなら、残しておいてもよかったんじゃない?」私は花をつけた枝を見つめながら言った。
お父ちゃんは一瞬黙ってから、「いや、邪魔だからいいんだ。それに、薪にした方が母ちゃんも喜ぶ」と答えた。言葉には実用性と家族のための思いやりが込められていたが、それでも私の心は少し揺れ動いた。
黙々と作業を再開する。チェンソーの音が再び響き渡り、お父ちゃんは切り続けた。お父ちゃんの言葉には納得しているけれど、桜の木との思い出が心に残っている。その木がもたらした花々、家族で過ごした時間、そして今日この日までの変化。
薪の山が少しずつ大きくなる中、私は過去と現在、そして未来に思いを馳せる。
時間を割いてくれて、ありがとうございました。
月へ行きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
