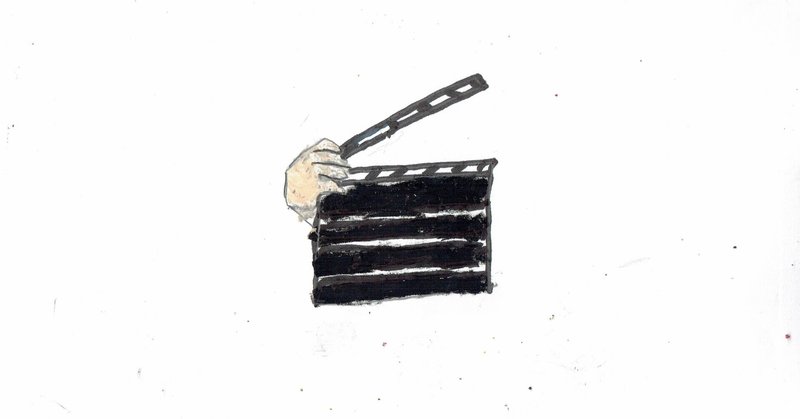
西川美和「映画にまつわるxについて」①〜映画作りへの矜持と恥じらい〜
「ゆれる」「ディア・ドクター」「夢売る二人」等で知られる映画監督の西川美和さんのエッセイがめちゃくちゃ面白かったので、noteに備忘録を書きたいと思います。(人気だったようで、2巻も出版されています)
言葉選びの細部に宿るこだわりとセンス
豊かな語彙力がありながらそれをひけらかすのではなく、軽妙で分かり易い文章でした。真に頭のいい人は小難しい文章ではなく、読み易い文章を書くのだなぁと思います。
めちゃくちゃ細かいのですが、西川さんのてにをはのチョイスが好きです。
例えば、朝青龍引退を惜しむ回の文章。
引退を惜しむ人たちもまた、「ヒールが居なくてはつまらない」と言ったりするが、私は彼のことを「ヒール」と感じたことはなかった。野生の世界が物語などで描かれる時、ハイエナやジャッカルやシャチなどを当たり前のように悪役に回すことへの違和感と似ている。ジャッカルを生きたこともない私たちに、一体何がわかるだろう?
「ジャッカルとして生きたこともない私たちに」ではなく、「ジャッカルを生きたこともない私たちに」とするところが好きです。なんでしょうね、その方がリズムがいいのは勿論、「ジャッカルとして」よりも「ジャッカルを」の方が読者の想像力を高く見積もられている気がするんです。
新作は概ね3年に1本という、寡作で知られる西川監督。このエッセイを読むと一作一作ほんとうに丁寧に魂込めて作り上げていることが伺えます。1年間365日、24時間(夢の中でも)次回作の脚本について考え、書いては消し、書いては直しを繰り返してようやっと完成稿が出来上がるそうです。
流石にエッセイはそこまで推敲せずにもっと気楽に執筆していると思いますが、それでも西川監督のことですから、エッセイと言えどちょっとした助詞にさえもある程度のこだわりをもって選択しているのではないかなと思います。
映画を生業に選んだきっかけ
女子高生の頃に「恐怖の24時間」というドラマを見たのが原体験らしいです。
実在の昭和の犯罪をモデルにしたシリーズの1作品で、5人を殺して全国を逃走した連続殺人犯の逮捕劇を描いた物語でした。
私の中には、何と言おうにも説明のつかないものがこみ上げてきて、夜も更けてすっかりぬるくなった風呂の湯の中に一人ちゃっぽりと身体を沈めると、まるで布団の中の役所広司が乗り移ったように泣けてきてしまった。(略)つまりは連続殺人犯にカタルシスを感じたということで、自分でも不気味に思ったが、そういう人物の中に巣くっていた「屈託」を炙り出してもらったことで、私の中にも眠る得体の知れないモノの存在を赦されたような気がした。人間の中に存在している、どこにも生きる場所の許されない、危険な廃棄物のようなモノをこうやって生かす方法があるんだ。
話は逸れますが、10年ほど前、友人から「演劇や映画には何某かのテーマがあるべきだと思うんだよね。例えば人を啓蒙する政治的メッセージとか。テーマの無い作品って、ある意味なくない?」と言われ、衝撃を受けたことがあります。
うまく言語化できないのですが、なんとなくショックだったのです。
今思えば、当時の私はテーマなるものをしっかりと意識して作品を作っていたわけではなかったので、そんな自身の創作行為を全否定された気持ちだったのでしょう。しかしそれ以降、「じゃあ、どんな作品なら作る意味があるのだろう」と考えるようになりました。
正直、テーマなんてものはコンパスみたいなもので、あれば制作という長い旅の中で迷子になる可能性が低くなるけれど、持ってなかったからと言ってダメなわけじゃないと思います。
テーマなんて凡そ見当たらない、ただただ人を楽しませるという目的のためだけに生み出されたエンタメ作品だって、そこから得る学びや気づきがなかったとしても、数時間浮世を忘れて楽しむことができるのであれば、それは間違いなく人の役に立っていると言えるでしょう。
楽しい気持ちにはならないけれど、感銘を受けたり、自分の半径5mの世界からは知り得ない情報を手にできるような作品もまた、人の役に立っていると言えるでしょう。
ではその一方で、人間の心の暗部にフォーカスを当てた作品はどうなのでしょう?見た後にイヤ〜な気分になったり、「人間って…最悪だな」なんて厭世的な気分になるような露悪的な作品は、果たして世のため人のためになっているか・・・
とはいえ、そういう毛色の作品が沢山生み出され続けているということは、求める人が沢山いるからに他なりません。
西川さんが感じた、私の中にも眠る得体の知れないモノの存在を赦されたような気がしたという気持ちは、多様な作品が生み出される理由を端的に言い表していると思います。
映画作りへの矜持と恥じらい
元々、西川監督の映画は好きだったのですが、このエッセイを読んでさらに好きになりました。西川作品に惚れたというよりも、西川監督に惚れたと言った方が正しいのですが。(それは西川監督の望むところではない気もするが)
以下、西川監督の作品への向き合い方が分かる箇所をピックアップしました↓
(視覚障害を持つ方向けの、字幕ガイダンスを自身の作品につけることになったエピソードより)
誤解を承知であえて言えば、映画の中の「聴いてもらうべき音」を「言葉」に直して字幕で観せる、「観てもらうべき風景」を「言葉」に直してアナウンスで聴かせる、という作品の披露の仕方というのは、本来自分の目指した表現としては不完全であることは否めない。「ストーリーが解ればいい」「大体でいい」のであれば、一切合切大体でいい、ということになる。そんな感覚ではワンカットも作っていない。(略)私は、言葉の威力というものが怖い。ガイダンスや字幕のように短いセンテンスになればなるほど、描写力のエッジは強くなり、ズバリと型にはめていく霊力に似たものを発揮する。それゆえに「言葉」に圧倒され、潰されていくのだ。映画の中の「得も言われぬもの」が。それこそが、私たちが死に物狂いで捉えている映画の真骨頂なのに。
(「ゆれる」の脚本執筆について)
直しても直しても、蟻地獄のように欠点が浮上する。私の手元には19稿ものデータが残っているが、直して直して直して、ここがおかしい、こうするべきだと思って変えていたら、第一稿に戻っちゃった、などということもしばしばだった。
旅は最後まで続いた。かつての「いいとき」は面影もなく、私と脚本の間には腐れ縁のような匂いが立っていたと思う。
最終稿である撮影稿にもなると、表紙を開くのも忌々しかった。美しい刷りたての記念すべき脚本を、プロデューサーが潤んだ目で感慨深げに手渡してくれたのに、私は離婚調停中の暴力夫にくれてやるような目つきで一瞥した。たまに「脚本がいいですよ」と言われることがあっても、何だか仇敵を褒められているようで面白くなく、「…どうだか」なんて奇妙な反応を返したりしたこともある。
もう、このくらいにしておこうじゃないか。
私と脚本は、徹底的にやり合ってきた。
決別の時がやってきた。
キャメラが回った時、その前にあるものは、私がホンを書くときにイメージしていた仔細とはどんなに近くても、同一ではない。映画が生まれる時、脚本は死ぬのだと思う。私の中にだけ生きていた風景と、生きていた人物たちとに別れを告げて、私は新しい仲間と映画を作る。
(略)
人が集い、映画は他社と共有され始める。それは奇跡が起きたような感覚だ。だって昨日まで、自分の中だけで育ててきた文字通りの秘蔵っ子たちのことを、今日初めて出会う俳優がすでに私よりもよく知り、空想していたりするのだから。
私は素晴らしい配役ができた場合は、彼らがオファーを引き受けてくれた時から、喜んで彼らにその養育権を譲る。そして現場に立った時には、私になどもはや操作させないぞ、と反旗を振るような面を見せてくれることをとても楽しみにしている。
長く長く、穴蔵の中で一人机に向かっている私にとっては、この、キャストたちそしてスタッフたちとの撮影期間が、セミにとっての地上の生のような、短いけれど賑々しい時間だ。
いやもう、痺れますね・・・!
西川監督の言葉への感受性の高さが伺える文章でした。
脚本を書くという孤独な作業は、まるでお腹を痛めて我が子を産むようなもので、どんなに誰かが手助けしてくれようと結局は個人的な営みなのです。
しかし一旦この世に産み落としたら、いつまでも後生大事に一人で抱き抱えていてはその子のためになりません。共に育ててくれる人を見つけた暁には、その人々を信頼し、託し、いつかはその手綱をプツリと切る潔さが必要なのです。
このエッセイからは、映画作りへの並々ならぬ情熱・映画への愛が感じられる一方で、とはいえ映画作りなんて虚業であるという冷静さも窺えました。
以下、西川監督がまだ助監督の頃、主人公の飼い猫が死んで横たわっているというカットを撮るために、動物プロダクションが用意した子猫に麻酔を投与してもらったエピソードからの抜粋です。
カメラや照明に囲まれ怯えて興奮した子猫は、麻酔を打っても一向に寝てはくれず、猫担当だった西川助監督は肩身の狭い思いをしながら撮影現場から少し離れたバンの中で「眠れ眠れ」と子猫を撫で続けていました。
がなり合うようなスタッフ同士のトランシーバーのやりとりが雑音混じりに聴こえていた。私は戦力外通告を受けた気分だった。けれど子猫はか弱く、抱きしめても足らぬほど愛らしく、ここでこの子を静か撫でていられるのなら、もう何がどうでもいいようにも思われた。あんな戦場に戻ることに、果たしてどれほどの意味があるのだろう。(略)何が映画だ、バカバカしい。所詮作りモノじゃねぇか。誰が見るともしれない得体の知れないワンカットのために、血眼になって、生きているものの息の根さえ止めようとして…
しかし私はおじさんが「これ以上打つと死ぬ」と言った瞬間、そんなこと知るか、と確かに思ったのであった。
瞬間的にでも「子猫が死ぬ?そんなこと知るか!」と思ってしまうことに作り手の業を感じさせはするのですが、このエピソードを振り返っているその眼差しが非常に冷静で、西川監督は自分を俯瞰で見ている人なんだなぁと思いました。
東日本大震災の頃、被災地で映画を上映するボランティアに行かないかと声をかけられ参加したエピソードもあるのですが、その時の逡巡も印象的でした。
体験・記憶・時間・体力など、自分の持ちうる全てのものを総動員して映画を作る情熱を持つ一方で、しかしそうして作った映画はこの世になくても誰も困りはしないものであるという冷静さを持っているところが、西川監督の魅力だと思いました。
長々書いてきましたが、まだまだ面白かった箇所があるので、続きは②に書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
