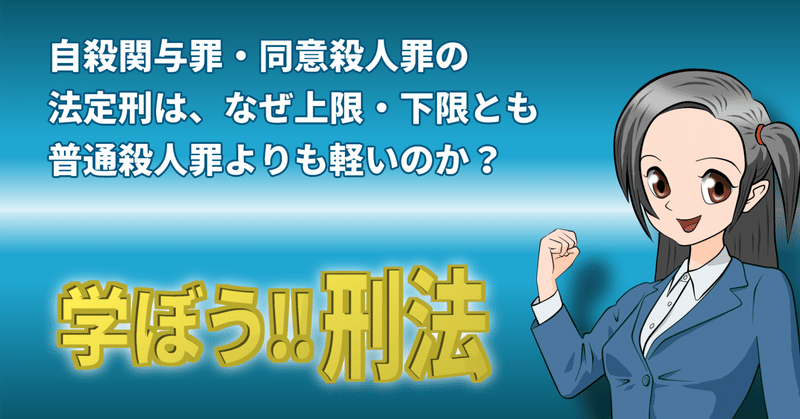
【学ぼう‼刑法】自殺関与罪・同意殺人罪の法定刑は、なぜ上限・下限とも普通殺人罪よりも軽いのか?
第1 自殺(未遂)が犯罪とされていない理由
1 現行法上自殺(未遂)を問うことの意味
自殺や自殺未遂は、現行法上、犯罪とはされていません。
では、自殺や自殺未遂が犯罪とされていない理由は何でしょうか?
こう問うと、現行法上、自殺や自殺未遂が犯罪とされていない(構成要件がない)以上、その理由を問うことは無意味ではないか、と感じる人もいるかもしれません。
しかし、現行法は、自殺や自殺未遂自体を処罰をしていないものの、これに関与する行為(自殺教唆・自殺幇助)は処罰の対象としています。そのため、なぜこれらの関与行為がなぜ処罰の対象とされているのか、更に言えばそれが妥当なのか、を考えるうえでは、自殺や自殺未遂が処罰されていない理由は何かという問題は、その前提となります。
刑法
(自殺関与及び同意殺人)
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
ですから、ここに、現行法上も、自殺や自殺未遂が処罰の対象とされていない理由を考えることの必要性が認められます。
2 自殺をめぐる学説
さて、自殺や自殺未遂が処罰の対象とされていない理由については、次のような見解が主張されています。
第1は、自殺は、違法ではないとする説。
第2は、自殺は、違法ではあるが、可罰的違法ではないとする説。
第3は、自殺は、可罰的違法ではあるが、有責ではないとする説。
第1の説は、自殺は、生命という権利の自己処分であるとか、自己決定権の行使であるから違法ではないと説明します。
第2の説は、権利の中にも権利主体が勝手に処分することができない権利があり、生命の権利はこれに当たるとしたうえで、しかし、生きる希望を失った者が自らの生命を絶つことに対して国家が刑罰をもって干渉することは個人の尊厳を侵害することになる、それゆえ、自殺は違法ではあるが、可罰的違法とはいえない、と説明します。
第3の説は、第2説と同様に、生命は自由に処分することができない権利であるとし、それが違法であることを前提としつつ、生きる希望を失って自殺をする者には「適法行為の期待可能性」がないから責任が阻却される、と説明します。
3 各説の違い
第1説と第2説との違いは、第1説では自殺行為が適法だが、第2説では(可罰的ではないにせよ)違法だとされる点です。この違いは、自殺をしようとしている者を制止した行為の評価に差が出てくると言われます。
つまり、第1説では、自殺が自己決定権の行使として適法な行為であるため、これを止めようとすることは「権利の行使を妨害」することになります。そこで、自殺者を制止した者がその手段として暴行や脅迫を用いた場合には、これらによって「権利の行使を妨害した」として、彼には強要罪(刑法223条)が成立することになります。そのため、第1説はこの点が不都合である、と第2説や第3説の論者からは批判されています。
これに対し、第2説や第3説では、自殺は違法行為なので、これを制止する行為が強要罪となることはありません。
もっとも、第2説や第3説の場合でも、自殺を制止しようとして被害者に怪我をさせてしまったような場合には、これをどのように正当化できるのかという問題は残ります。
第2 自殺関与罪の処罰根拠
1 制限責任説との親和性
以上のとおり、自殺や自殺未遂が処罰の対象とされていない理由としては、上記の3つの説があり、どの説も成り立ちます。しかし、自殺関与罪の前提としてこれを考える場合には、どの説を採用するかによって、その後の説明が変わってきます。
率直に言えば、自殺教唆・自殺幇助が処罰されることの前提としては、第3説を採用すると説明が容易です。現行法上、自殺が処罰されない一方で、自殺教唆・自殺幇助が処罰されていることを制限従属性説からストレートに基礎づけることができるからです。これに対して、第1説や第2説を採る場合には、説明にやや工夫(変化球的な説明)が必要となります。
少し解説しましょう。
現在、共犯の従属性の程度(要素従属性)をめぐっては、制限従属性説が通説です。そして、制限従属制説では、共犯は、正犯の構成要件該当性・違法性には連帯するが、責任については個別に判断されるとされます。そこで、第3説によれば、自殺者(正犯的立場の人)が処罰されないにもかかわらず、自殺教唆者・自殺幇助者だけが処罰される結論を、制限従属性説による「責任の個別化」によって論理的に導くことが可能です。

これに対して、自殺は違法ではないとする第1説や、自殺は可罰的違法ではないとする第2説によれば、自殺自体が違法(可罰的違法)でないならば、なぜ自殺を教唆することや幇助することが違法(可罰的)な行為となるのか、ということが問題となります。なぜなら、上述したように、制限従属性説によれば、共犯の違法性(可罰的違法性)は、正犯のそれに従属し連帯するはずだからです。そこで、制限従属性説からはイレギュラーなこの点をどう合理的に説明するかが問題となるワケです。
2 可罰的違法阻却の一身専属性
この点、まず、第2説からは、次のように説明されています。
自殺をすることは自由な権利の処分としては認められない。しかし、本人がする場合は、これを刑罰をもって禁止することは個人の尊厳を侵害することになる。そのため、本人自らが自殺する行為については可罰的違法性がない。しかし、本人以外の者が自殺者の自殺行為に関与することについては、このような理由が働かない。そこで、本人の自殺に関与した他人については可罰的違法性が認められる、と。
この第2説からの説明は、自殺が可罰的違法でない理由と個人の尊厳を絡めて、その不可罰の理由が自殺者本人にしか働かない理由として、一応成功していると言ってよいでしょうかね。
3 パターナリズムと違法の相対性
つぎに、第1説からは次のように説明されます。
自殺行為は、本人については自己決定権の行使として違法ではない。しかし、法は生命の価値を重く見て、これに対する保護の要請(パターナリズム)から、他人の関与を禁止した。そのため、自殺者自身の行為は適法ではあっても、関与者の行為は違法となる、と。
このような第1説からの説明は、どうでしょう?
みなさんは、この説明に「ああ、納得」という感じですか?
私は何となく腹落ちしない感じです。
また、この説明は自殺の違法性についての(人的な)相対性を肯定するものですが、この点については、これは可能なのかという疑問も呈されています。
主観的違法性論や行為反価値論(人的違法論)からは可能だとしても、結果反価値論(物的違法論)からは不可能であるとの批判があります。
しかし現実には、結果反価値論を採用する先生方もこのような説明をしていますので、実際のところ、どうなのでしょう? 結果反価値論からこのような説明が可能なのかどうか?
第3 同意殺人罪の可罰性と被害者の同意
1 被害者の同意と違法阻却
刑法202条は、自殺関与罪(自殺教唆・自殺幇助)とともに、同意殺人罪(嘱託殺人、承諾殺人)を規定しています。
そこで、今度はこちらに目を向けてみましょう。なぜ同意殺人を処罰することが可能なのかという点です。
「被害者の同意」は、「同意は不法を作らず」との法言により古くから違法性阻却事由の1つと考えられてきました。
もっとも、実際上は、被害者の同意のすべてが違法性阻却事由というわけではなく、被害者の同意によって、違法性以前に、構成要件該当性がなくなる場合(窃盗罪、住居侵入罪など)もあります。その一方で、被害者の同意があっても犯罪の成否にまったく影響しないという場合(16歳未満の者に対する不同意性交罪、不同意わいせつ罪など)もあります。
そこで、被害者の同意が、まさに違法性阻却事由として働くのは、傷害罪や器物損壊罪などの場合だとされます。これらの場合には、被害者が同意していても、構成要件該当性が失われません。つまり、被害者が同意していても「人の身体を傷害」したことには変わりはなく、また、自分の所有物を壊すことへの同意は、所有権の放棄ではないので、所有者の同意を得てその物を壊しても「他人の物を損壊した」という事実は変わりません。そこで、いずれの場合も、それぞれ傷害罪、器物損壊罪の構成要件には該当し、ただ、違法性が阻却されるため犯罪が成立しないと解されています。
2 なぜ殺人には被害者の同意が働かないのか?
では、被侵害法益が人の生命の場合、つまり、殺人の場合はどうでしょう。
この理屈で行けば、殺人の場合も、傷害罪の場合などと同様に、同意の上で被害者を殺したのであれば、違法性が阻却されて犯罪とはならない、ということになりそうですが、実際には、そうなっていません。すでに述べたように、現行法では(殺人罪とはならないものの)刑法202条という別の構成要件によって処罰の対象とされています。
つまり、同意殺人は「違法」ということです。
そこで、この場合に被害者が同意しているにもかかわらず行為者の行為が違法とされる理由は何かが問題となります。
そして、この点をめぐる議論は、基本的には、上述した自殺関与行為が違法とされる理由をめぐる議論と違いはありません。つまり……
第1説によれば、本人が自殺する行為は、自己決定権の行使として違法ではないが、法は生命の価値を重視し、生命保護の要請(パターナリズム)から、これに対する他人による関与を禁止した(他人の生命への不可侵)。そのため、この場合は、被害者もその同意によって自己に対する他人による殺害行為を正当化することはできない。そのため、同意殺人は違法である、と説明されます。
第2説によれば、自殺者といえども生命の権利を勝手に放棄することはできないが、自殺者本人が自殺をすることについては、国家がこれに刑罰をもって干渉することは個人の尊厳を害するがゆえにできず、可罰的違法性がないとされる。しかし、被害者自身にさえ自己の生命に対する処分権がない以上、被害者は第三者に対して有効な「被害者の同意」をすることができない。したがって、被害者が同意をしても無効である。そしてそうである以上、被害者の同意を得て殺す行為は可罰的に違法である、と説明されます。
第3説による説明も、第2説とほぼ同じです。被害者には生命に対する処分権はない。それゆえ、被害者は有効な「被害者の承諾」ができない。そのため、この場合は同意があってもその「被害者の同意」は無効である。そして、同意が無効である以上、被害者を殺害する行為は、同意のない場合と同様に違法である、と説明されます。
いずれにしても、構造的には、同意殺人の場合は「被害者の同意」があってもそれは無効であるから、違法性が阻却されず、処罰の対象されている、という説明になります。
第4 自殺関与罪・同意殺人罪の法定刑が殺人罪よりも軽い理由
1 自殺関与罪・同意殺人罪の法定刑
現行法上、自殺関与・同意殺人は、違法とされ、処罰の対象とされています。が、しかし、殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役であるのに対し、同意殺人罪・自殺関与罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮です。つまり、その法定刑は、殺人罪の法定刑よりもかなり低く設定されています。
では、その理由は何でしょうか?
普通殺人罪と同じく被害者の生命を失わせながら、同意殺人罪の法定刑が低くされている理由はどこに求められるのでしょうか?
2 自殺関与罪と殺人罪との対比
この点、自殺関与罪と殺人罪との比較であれば、行為者の結果(生命侵害)に対する関与の程度(距離)が違うという説明も可能でしょう。つまり、自殺関与罪の場合は、あくまで自殺者本人が最終的な決定権をもつ形で被害者の死亡が実現されますから、行為の結果に対する危険性・因果性という意味で、殺人の場合とは程度がかなり違うと考えられます。そこで、この点に法定刑の違いの根拠を見出すことも不可能ではないでしょう。
例えば、自殺をしたいというXに対して、Aが猟銃を貸してあげたという自殺幇助の事例では、あくまで引き金を引くのはXです。しかし、AがXを猟銃で撃ち殺したという殺人の事例では、引き金を引くのはAです。つまり、両者では、最終的な決断をするのがXかAか、実現行為をするのがXかAかという違いがあります。そこで、自殺関与罪と殺人罪とでは、行為者の行為の人の死に対する影響力の程度が違うので、行為の違法性の程度の違い、それが法定刑の違いに現れている、と説明することが可能です。
この場合の両者の違いは、被害者自身を通じた間接的な法益侵害か、直接的な法益侵害かの違いと表現してもよいでしょう。
3 同意殺人罪と殺人罪との対比
しかし、同意殺人では、このような説明はできません。同意殺人の場合は、行為態様や結果に対する危険性・因果性は、普通殺人の場合とまったく異ならないからです。Xに頼まれて、AがXを猟銃で撃ち殺した場合でも、頼まれもせずAがXを猟銃で撃ち殺した場合でも、最終的に決断をした者、そして実現行為をした者は、いずれもAであることに変わりません。それにもかかわらず、同意殺人罪の法定刑が普通殺人罪のそれよりも軽いのはなぜか。同意殺人罪の法定刑の軽さを語る際には、これが問題となるワケです。
もちろん、この点は、極めて素朴に考えれば「死に対するXの同意があるから」ということになります。そして、それ自体、まさに間違いないワケですが、問題なのは「Xの同意があると、なぜそれが法定刑を軽くする理由となるのか」という点です。
なぜなら、すでに確認したように、前述した第1説ないし第3説のいずれの立場に立つとしても、この場合の「Xの同意」は、違法性阻却事由たる「被害者の同意」としては無効と言わざるを得ないからです。「無効」であれば、そこには何らの法的効果もないハズです。それなのに、なぜその存在が法定刑を低くする理由となるのでしょうか? これこそが問題です。
4 各説による説明
そこで、この点についてどのような説明が可能かを考えてみましょう。まず、理論的には次の3つの説が成り立ち、実際にもこれら3つの説が主張されています。
【違法減少説】
同意殺人罪は、殺人罪よりも違法性が少ない。
【責任減少説】
同意殺人罪の違法性は殺人罪と同じだが、有責性が殺人罪よりも少ない。
【違法・責任減少説】
同意殺人罪は、違法・有責の双方が殺人罪よりも少ない。
そして、前述した第1説や第2説からは、違法減少説または違法・責任減少説が採られ、他方、第3説からは、責任減少説が採られるようです。
5 違法(・責任)減少説の問題点
しかし、前述したとおり、第2説のみならず、第1説も、この場合の「被害者の同意」は無効と解しています。そして「被害者の同意」が無効ならば、それによる法的効果は一切生じないと考えるのが論理的には素直な帰結のハズです。それなのに、なぜ違法性が(消滅しないものの)減少するのでしょうか?
一般に「被害者の同意」によって違法性が阻却されるのは、結果反価値論からは、法益侵害が失われるからという理由によるものです。他方、行為反価値論からは、倫理規範違反(社会的相当性からの逸脱)が無くなるからという説明になります。
では、各説の論者は、この点を実際にはどのように説明しているでしょうか?
まず、第1説に立つ山口先生は次のように説明しています。
このようなパターナリズムの見地から例外的に肯定される法益侵害は、生命主体の意思に反する死の惹起よりも、法益侵害性が明らかに軽微である。したがって、自殺関与罪・同意殺人罪の法定刑は、その理由から殺人罪におけるよりも軽くなっているのである。
また、同様に第1説に立つ西田先生は次のように説明しています。
この場合の減軽処罰の理由は、被害者の同意による法益性の減少に求められることになる。
いずれも、法益侵害性が減少していると言っています。しかし、有効な「被害者の同意」が認められないのであれば、法益が消滅しないだけでなく、法益が減少することもない、というべきではないでしょうか?
第2説を前提に違法・責任減少説に立つ団藤先生、大塚先生、大谷先生は、それぞれ次のように説明しています。
生命は本人の意思によって処分することのできるものではなく、したがって、自殺をはかって死に瀕している者であってもこれを殺せば殺人罪になることはいうまでもない。しかし、本人の意思にもとづいて本条に規定されたような態様の行為をすることは、通常の殺人罪よりも違法性が少なく、また、期待可能性も乏しいことが多い。
同意殺人、すなわち、被殺者の嘱託をうけ、またはその承諾を得てこれを殺す行為は、被殺者自身の生命に対する法益の放棄を前提としてなされるのであるから、被殺者の立場からすれば、自殺に準じて考えられるべきものがある。それゆえ、その違法性の程度は、通常の殺人罪に比して軽く、また、行為者の責任も減軽されうることが少なくない。
同意殺人罪は、法益の主体である被殺者本人が自由な意思決定に基づいて生命を放棄している場合であるから、法益侵害の程度が普通殺人罪よりも小さい。
確かに、これらの先生が行為反価値論に立っているということを前提に「違法性が少ない」と言われれば、行為反価値性が少なくなるという意味とも解されます。しかし「法益侵害の程度が普通殺人罪よりも小さい」と言われると、やはり「なんで?」という気持ちになってしまいませんか?
つまり、殺人に対する「被害者の同意」が違法であることにより無効ならば、その無効な同意によって、なぜ違法性の減少(とりわけ法益侵害性の減少)という効果が生じるのでしょうか? 上記の先生方の説明では、この点について何ら「論理的」に説明されてはいないように感じますが、いかがでしょうか?
それとも「全部有効」ではないが、「全部無効」というワケでもない、「半分だけ無効」とか「半分だけ有効」というものがあるのでしょうか?
6 責任減少説の問題点
以上に対し、第3説の立場から責任減少説を採る場合は、説明は遙かに容易です。
責任減少説は、自殺者や同意殺人罪の被殺者は、生きる希望を失って死にたいと思った人であるがゆえに「適法行為の期待可能性」がない、とされます。
これに対して、自殺関与や同意殺人の行為者は、仮に、自殺者・被殺者の心情に同情したうえでの行為であったとしても、「適用行為の期待可能性」がないとまでは言えません。それゆえ、その行為は処罰の対象とされています。しかし、このような自殺者・被殺者の心情に同情したという点において、普通殺人の行為者と比べて「適法行為の期待可能性」が乏しいので、責任が減少する。
責任減少説からは、このような説明がなされます。そして、このような説明は充分成り立つように思います。
しかし、この説明にまったく問題がないかといえば、そうでもないでしょう。
責任減少説は、自殺関与や同意殺人の行為者は「生きる希望を失った被害者に同情した」がゆえに、責任が減少すると言います。しかし、刑法202条の条文上は、その行為者が被害者に同情したことは要件とされていません。そして、実際の行為者の心情としても、被害者に同情して実行した場合もあるでしょうが、そうでない場合もあるでしょう。そうすると、責任減少説は、行為者が被害者に対する同情心からではなく、例えば、被害者が殺してくれたら謝礼を払うと言ったので、謝礼ほしさに被害者を殺した、というような場合には、同意殺人罪ではなく、普通殺人罪を適用するのでしょうか? それならば筋が通ります。しかし、おそらくそうではないでしょう。
例えば、ほとんど最近の同意殺人の典型例のように思われる老老介護の末の殺人のような場合だってそうでしょう。
【事例】Y女が長年、寝たきりで夫Bによる介護を受けて生活していたが、YがBを不憫に思って「殺してくれ」とBに頼み、Bがこれに応じてYを殺した。
この事例の場合、Yが「辛いので殺してくれ」と言い、BがこのYの心情に同情してYを殺したのであればBは嘱託殺人罪でしょうが、Yが長年の介護に疲れているBを同情して「殺してくれ」と言い、これに応じてBがYを殺したのであれば、Bは「死にたいという被害者の心情に同情」したワケではないので、普通殺人ということになるでしょう。責任減少説によれば、そうなるハズです。しかし、この結論は妥当だとは思われませんし、責任減少説だって、このような結論を是とはしないでしょう。
また、もし同意殺人罪の法定刑の低さの理由が、責任減少説が主張するように、行為者が被害者に同情したことによる「適法行為の期待可能性」の乏しさにあるのであれば、なぜ、法定刑の下限だけでなく、上限まで下げる必要があるのか、という点も疑問です。
確かに、被害者にいたく同情して行為に出たという行為者もいるでしょう。しかし、期待可能性の程度はいろいろです。非常に同情的な場合もあるでしょうし、それほどではないという場合もあるでしょう。そして、非常に同情的な動機による場合に対応するためというのが減軽の理由であるならば、下限のみを「6月以上」としておけば足りるハズです。それにもかかわらず、上限を「7年以下」と大幅に下げたのはなぜなのでしょうか? このような点からしても、現行法の規定ぶりは、責任減少ということだけでは合理的に説明し尽くせないものがあるように感じませんか?
第5 さらに一歩先へ
1 一応の中締め
以上が、自殺関与罪・同意殺人罪に関する現在までの議論です。
そして、刑法を勉強している理由が、例えば「司法試験合格のため」というようなものであれば、これより先に進む必要はありません。ここまでの議論をきちんと押さえて、試験に出たらどの説を採り、どう書くかということさえ決めておけば足ります。どうせ試験の答案上で「新しい説」などを展開することなどないからです。試験の答案上で新説など発表したら試験に落ちてしまいます。ですから、試験のために刑法を勉強しているのなら、これ以上先に進むことはオススメしません。試験ではそんなことは書かないと約束できる人だけがこの先に進んでください。
では、そう忠告したうえで、ここまでの議論から、もう少しこの論点を探求してみたいと感じた人は、一緒に少し先まで進んでみることにしましょう。
さて、これまでの議論を見ているだけだと、どれがよいのか迷路に入ってしまいそうではないですか? そこで、一度すべてを白紙に戻して1から考えてみることにしましょう。
2 まずは素直に考えてみる
まず、刑法による人の行動の制限は、憲法上は、憲法13条の「公共の福祉」による人権制限を根拠とします。
そして、ここにいう「公共の福祉」の意味については、人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理というもの(一元的内在的制約説)が、現在でも通説でしょうか?
もしこのように「公共の福祉」だけが人権の制約原理であると考え、かつ、それは「人権の矛盾・衝突」を調整する原理だと解するのであれば、簡単に言えば「人は他人に迷惑をかけない限り自由であり、その自由を制限される謂われはない」ということになるでしょう。
そうすると、自殺についても、それは自己の生命の処分であって「他人に迷惑をかけること」ではないため、「公共の福祉」によっても制限することができない、というのが素直な帰結です。
もちろん、現行刑法も「自殺」それ自体を制限してはいません。
しかし、自殺がその人の権利の行使であるなら、その実現に協力する行為も、だれに迷惑をかけるワケではありません。そうだとすれば、これについても同様に「公共の福祉」による制限はできないということになります。
そしてそうすると、そうした他人の自殺(死にたいという意思)に協力することを処罰する自殺関与罪や同意殺人罪は、憲法に反するということになりそうです。
まずはこれを確認しましょう。そのうえで、その理屈がどのように修正可能かを考えてみるワケです。
3 合理的人間像の限界とパターナリズム
さて、先に検討した第1説は、ここで突如として「パターナリズム」(保護主義)を持ち出すことで自殺関与罪・同意殺人罪の可罰性を基礎づけました。
しかし、このパターナリズムは、憲法上どのように位置づけられるのでしょうか? 憲法上、どのような正当性を持つのでしょうか?
このパターナリズムという考え方は、近代立憲主義の憲法が生まれた当時には、少なくとも成人に関しては存在しなかった考え方でしょう。というのも、18世紀当時の憲法は、啓蒙主義という時代的背景もあって「合理的人間像」を想定していたからです。
「合理的人間像」とは、人間は理性によって合理的に考え、合理的に行動することのできる存在であるという人間観です。このような人間観によれば、人間は合理的な存在なので、人間には自由を保障すれば、それぞれが自らの幸福を求め、合理的に考えて行動するので、それぞれの人は、自由によって自然と幸福になってゆくと考えられます。そこで、このような考え方の下では、個人に自由を保障することで、個人の尊厳は実現されるため「自由主義」と「個人の尊厳」とはほぼ同義となるでしょう。
ところが、このような「合理的人間像」は、近代立憲主義の憲法が生まれて100年もすると崩壊します。その間の資本主義の目覚ましい発展は、人々の間に大きな貧富の差をもたらし、その結果、富める者は生まれてから死ぬまで裕福な暮らしを約束される一方で、貧しい者は、社会の底辺から一生這い上がることができない、という社会矛盾を現出させました。貧しい者にとって「自由とは、空腹の自由でしかない」と言われました。
では、これによって何が起こったか。人生に希望を失った貧しい者たちは、酒や薬物に溺れた退廃的な生活を送り、小さな犯罪を繰り返しては刑務所の内と外を行き来するということが大きな社会問題となりました。
当時の刑法理論は、合理的人間像を基礎とした「古典学派」の考え方で、犯罪によって得られる利益よりも刑罰によって失われる利益が大きければ、人は合理的に考えて犯罪をしなくなる、という考え方(威嚇予防)でした。この考え方によれば、いま行われている犯罪を将来に向かって予防するのであれば、法を改正し、予告する刑罰を重くすれば、人々は刑罰を怖れて犯罪を犯さなくなるはずです。しかし、現実には、刑罰を重くしても何の効果はありませんでした。それはなぜか?
これまでの理論では何かが違っているからでした。
では、それは何なのか?
それまでの理論はどこが違っていたのか?
こうしたところに現れたのが「近代学派」でした。近代学派は、人の自由意思を否定し、人は素質と環境とによって支配された存在であるという人間観を基礎としていました。そして、身体の丈夫な人であっても、劣悪な環境の下に長く置かれていれば病気となってしまうように、善良な人であっても、劣悪な環境に置かれていれば犯罪をするようになってしまう、と説きました。
そして「社会政策こそが最も優れた刑事政策である」と主張し、社会保障を充実させることで犯罪は減ると説きました。そして、事実、この近代学派の主張に従い、社会保障を充実させたところ、実際に犯罪が減るという効果がもたらされたのでした。
つまり、古典学派が誤っていたのは、手放しの「自由意思論」であり、手放しの「合理的人間像」だったのです。確かに、人は、自由意思をもち合理的に考えることのできる存在かもしれませんが、その自由意思や合理性は完全なものではなく、素質と環境とによって制限されたものだったのです。
こうして歴史上の成果をもたらした近代学派でしたが、その理論には様々な問題もあり、結局は主流となることなく姿を消します。しかし、近代学派が古典学派に対して投げかけたそれまでの「合理的人間像」や「自由意思論」に対する疑問は、古典学派に対して従来の理論的基礎の修正を迫ることになります。
現在の刑法理論は、古典学派の流れの延長線上にありますが、現在は、完全な自由意思論、合理的人間像を基礎とはしていません。われわれが素質と環境とに制限された存在であることを前提とし、それゆえに、自由意思にも、これに基づく合理的思考、合理的意思決定にも限界があることを前提としています。
つまり、現在では、自由意思の存在自体は否定しないものの、それは素質と環境とによって制限されたものであると理解するようになっています。
つまり、人間は理性によって合理的に考えることのできる存在ではあるものの、それは素質と環境による影響を受ける「不完全なもの」であり、人が合理的に考え、行動することができるかは、個体によっても、状態・状況によっても異なります。誰もが、どのような状態でも、どのような状況でも、常に合理的に考えることができるというワケではありません。近代学派からの問題提起を経て、古典学派は、その後このような不完全な人間像をその理論の基礎に置くようになります。
そうして人間が不完全な存在であるということになると、人間は、場合によっては合理的な判断を誤ることがあるということになります。そしてそうなると、そこには「セーフティネット」が必要ということになります。ここにパターナリズムが、憲法上の拠り所を持つことになります。
つまり、人間が完全に合理的な存在であるならば、幸福への舵取りは100%各個人に任せておけばよく、自由を保障することがそのまま「個人の尊厳」を実現することへと直結します。しかし、人間が不完全な存在であるならば、人は時として幸福の追求とは結びつかない不合理な選択をしてしまうこともある、ということになります。そしてそうなると、このような場合、自由の保障を貫くことは、必ずしも個人の尊厳を実現することには結びつかないことになります。そこで、このような場合には、自由主義よりも高次の価値である「個人の尊厳」の観点から自由を制限する必要が出てきます。このような思考による人権制限の根拠がパターナリズムです。
パターナリズムがこのようなものであるとするならば、このような場合にパターナリズムによって制限の対象となるのは「その人の理性的とは思えないような自由の行使」に限られることになります。

4 自殺関与罪・同意殺人罪はどう理解できるか?
さて、このような考察を前提として、現行法上の自殺関与罪・同意殺人罪は、どのように合理的に理解することができるでしょうか?
自殺関与罪・同意殺人罪がこのようなパターナリズムに基づく「セーフティ・ネット」を定めたものであると解するならば、これらの規定は、本来、理性的で正常な判断のできなくなってしまった被害者が、自殺したり、殺されたりすることで「不本意」に命を奪われることを防止しようとした規定であるということになります。
実際、世の中の大多数の人は「死にたくない」と考えているのであり、そうした事実に反して「死にたい」と考えてしまう人の精神状態は、正常なものでなくなっている可能性は少なくありません。「電車に飛び込めば会社に行かなくて済むと思った」という理由で自殺を図ろうとした人の思考や判断を、私たちは到底正常なものとは思えません。つまり、自殺を図る人の大多数は、合理的で正常な判断というものができなくなってしまっていると考えられます。
そうだとすると、自殺希望者から「自殺を手伝ってほしい」と言われても、周囲の人たちはこれを手伝うべきではありませんし、「殺してほしい」と頼まれてもその頼みに応じるべきではありません。その人は、おそらくは「どうかしてしまっている」のであって、正常ではない可能性が高いからです。
つまり、自殺関与罪・同意殺人罪は、このような合理的とは言えない「死にたい」という被害者の意思によって、被害者が命を失ってしまうことを防止するために存在している、と理解することができます。
もっとも、自己の自殺に対する協力を他者に頼む人や、他者に対して自分を殺してくれと頼む人の中にも、実際上は、極めて理性的で真摯な思考と判断とによって「自然死に先立って死ぬ」という結論を導いた人もいることでしょう。そして、そういう場合であれば、自殺を手伝った人やその頼みに応じてその人を殺した人を処罰する理由はない、ということになります。
ただ、問題なのは、自殺者や被殺者が死亡してしまっている場合は、自殺や同意殺の時点で、彼らが、本当に、正常な精神状態の下で、理性的で真摯な思考と判断とによって死を決意したのか、ということを確認する方法がない、ということです。
ただ単に行為時に被害者が「死にたいと言っていた」、「殺してくれと言っていた」というだけでは充分ではありません。これだけでは、仮にその発言が被害者の真摯な意思によるものだとしても、正常な精神状態の下、理性的な思考と判断とによってなされたことの確証は何ら無いからです。
しかも「自然死に先立った死」を望む人の多くは、その当時、正常な精神状態ではなかったという可能性がかなり高いと言えます。
そうなると「自然死に先だった死」を望む発言については、それを真に受けることは、社会通念に照らして、それ自体、かなり危険なことである、ということになります。
そうすると、このような自殺希望者・被殺希望者の発言を真に受けてこの者の自殺に協力したり、この者を殺したりすることは、その者の本意(正常な精神状態の下、理性的で真摯な思考と判断とに基づいて決断された意思)に基づかずにその人の命を奪ってしまう危険性があるので、このような行為を禁止した、というのが自殺関与罪・同意殺人罪の規定であると理解することができます。
このように考えることで、自殺それ自体は自己の生命の処分であって、適法行為であるにもかかわらず、他人が自殺に関与する行為や同意を得てその人を殺す行為が処罰の対象とされていることを合理的に説明することができます。
5 自殺関与罪・同意殺人罪は危険犯
では、自殺関与罪や同意殺人罪が、普通殺人罪よりも法定刑が軽く設定されている理由は、どのように説明することが可能でしょうか?
それは、これらの罪は、侵害犯ではなく、危険犯であると理解することによってその説明が可能と考えられます。
つまり、自殺した人や同意して殺された人が、正常な精神状態の下、理性的で真摯な思考と判断とによって死を決意したのかについては、その人が死亡してしまった場合は、結局のところ、不明です。正常だったかもしれないし、そうでなかったかもしれません。
この場合、仮にその人の精神状態が正常で、理性的で真摯な思考と判断とによって死を決意したのであれば、前述のとおり、これに協力した人などを処罰する理由はありません。
そして、このように事実が不明である場合、刑事訴訟法上の「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従えば、その人の精神が正常でなかったことや、その人が理性的でなかったことなどを理由として、その人の死(生命侵害)という法益侵害結果を行為者に帰属させることはできない、ということになります。
つまり、被害者の(不本意な)死を行為者に帰属させ、これについての刑事責任を問うことはできません。
ただ、行為当時、行為者の知っていた事情および行為時の行為者の立場に立って、一般人(通常の注意能力をもつ者)であれば知ることができたであろう事情を基礎として、自殺希望者・被殺希望者の精神状態が正常ではない危険性、その決断が理性的で真摯な思考と判断とによって導かれたものでない危険性が払拭できないのであれば、「不本意に人を死亡させる危険性」は(仮に真実は、自殺希望者・被殺希望者が正常な精神状態の下、理性的かつ真摯に死を望んでいたとしても)否定されません。
つまり、医師などの専門家による慎重な手続による意思確認を経るなどの例外的な場合を除いては、この「不本意に人を死亡させる危険性」は払拭されないでしょう。
そこで、自殺関与罪・同意殺人罪は、このような生命侵害の危険性を処罰根拠とする犯罪であると理解することができます。
6 殺人未遂罪との違い
このように解すると、自殺関与罪・同意殺人罪は、その処罰根拠である法益侵害性の内実において、殺人未遂罪と似ている、ということになります。つまり、殺人未遂罪も、また、(不本意な)人の死亡ではなく、その危険性を処罰根拠とするものだからです。
ただ、両者には次の2つの点で違いがあります。
(1)人の死亡以外の結果の帰属
第1は、殺人未遂罪の場合は、被害者の身体に生じた「人の死」以外の結果(=傷害)は、すべて殺人未遂罪で吸収評価されるのに対し、自殺関与罪・同意殺人罪の場合は、このような人の死へと至る中間的結果に対する評価が問題とならないという点です。
例えば、殺人未遂の態様には、行為者の撃った銃弾が被害者にはまったく当たらず、被害者は身体に傷害をまったく負わなかったという場合がある一方で、被害者は死亡こそしなかったものの銃弾が頭に命中したために重い後遺症が残り、一生寝たきりの生活を強いられることとなった、という場合までさまざまなものが含まれます。そのため、殺人未遂罪は、規定の上では、殺人既遂罪と同じだけの量刑が可能となっています。
これに対して、同意殺の場合には、仮に被害者が重傷を負ったものの、命を取り留め、その結果、被害者の同意が、正常な精神状態の下での理性的かつ真摯な思考と判断とによってなされたということが明らかとなったとすると、行為者は、被害者の負った傷害の結果についても責任を負いません。傷害の部分の違法性も、被害者の同意によって否定されるからです。ただ、このような場合でも、事後に明らかとなった被害者の真意によっては、行為時の「不本意に人を死亡させる危険性」の存在は否定されないので、同意殺人未遂罪では処罰されます。
では、逆に、被害者の同意が正常な精神状態の下でなされていないことや、理性的かつ真摯な思考と判断とによってなされたものでないことが事後明らかとなった場合には、どうでしょうか?
この場合、その行為は、客観的には、殺人未遂罪と等しい違法性の実質(殺人未遂罪の客観的構成要件に該当する事実)を備えることになります。ただ、行為者には、被害者の「不本意な死亡」の意図がなかった以上、不本意な死亡を構成要件的結果とする普通殺人罪の意図(殺人未遂罪における超過的内心傾向)はないので、行為者には、殺人未遂罪は成立せず、やはり同意殺人未遂罪が成立します。
それゆえ、同意殺の行為者は、既遂の場合でも、未遂の場合でも、結局のところ、被殺者の「不本意な死亡」という結果を発生させる現実的危険を発生させたという意味で、危険犯としての違法性の実質(法益侵害性)が帰責され、処罰されるにとどまり、侵害結果(死亡や身体の傷害)はあくまで帰責はされず、これは処罰の基礎をなしません。
この点で、殺人未遂と同意殺とは、いずれも「不本意な人の死亡」という侵害結果ではなく、その危険を処罰根拠としつつも、人の死亡以外の侵害結果(人の身体の傷害)については、これが処罰の基礎に含まれるか否かが異なり、前者では含まれ、後者では含まれないこととなるので、行為者に帰責される違法性の実質は異なる(殺人未遂のほうが重いことがある)ということになります。
(2)超過的内心傾向の有無と危険性の程度
第2に、不本意な人の死亡に対する危険性の程度も、殺人未遂罪と同意殺では異なると考えられます。すなわち、殺人未遂罪における主観的構成要件要素である「(不本意に)人が死亡することを意図している」という心理状態は、超過的内心傾向です。これは「未遂の故意」と呼ばれることもありますが、その実体は、客観的要素の主観面への反映ではないので、故意(=認識)ではなく、超過的内心傾向です。
未遂罪の成立には、このような超過的内心傾向の存在することが必要とされますが、これを主観的違法要素であるとする見解は、この主観的要素の存否が実行行為のもつ危険性の程度に影響すると説明します(平野先生など)。
ところが、同意殺の場合、行為者は(不本意に)人が死亡することは意図していません。つまり、殺人未遂罪の場合と異なり、このような超過的内心傾向がありません。そうすると、殺人未遂罪も、同意殺も、いずれも構成要件的結果発生の危険性の存在を処罰根拠とするとしても、その危険性の程度は、(超過的内心傾向が存在する分)殺人未遂罪のほうが同意殺人罪よりも大きいことになります。これも、両者の実質的な違法性の違いと言うことができます。
以上の2つの点において、殺人未遂罪のもつ違法性の実質のほうが同意殺人罪のもつ違法性の実質より大きいので、この点に、同意殺人罪の法定刑が、上限・下限ともに、普通殺人罪(およびその未遂罪)よりも低く設定されている実質的な根拠があると考えることができます。
第6 おわりに
以上のように考えると、普通殺人罪の構成要件的結果である「人の死亡」は、単なる「人の死亡」ではなく、「不本意な人の死亡」つまり、「正常な精神状態の下で、理性的で真摯な思考と判断に基づいて希望されたもの、ではない人の死亡」を意味すると解すべきことになるでしょう。
そして、自殺関与罪・同意殺人罪は、そのような「本意」の確認できない状況下において、安易に被害者の同意を信じて、被害者の自殺に関与する行為や被害者を殺してやる行為を禁止したものであり、「不本意な人の死亡」を発生させる現実的危険を処罰根拠としたものと解することになります。
そして、このように解することで、現行刑法が自殺関与罪や同意殺人罪を処罰していることや、そのうえで、その法定刑を普通殺人罪よりも上限・下限ともに軽く設定していることを合理的に説明できるだけでなく、さらには、一定の場合において「安楽死」が正当化されることなどについても同時に説明することが可能となるように思いますが、いかがでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
