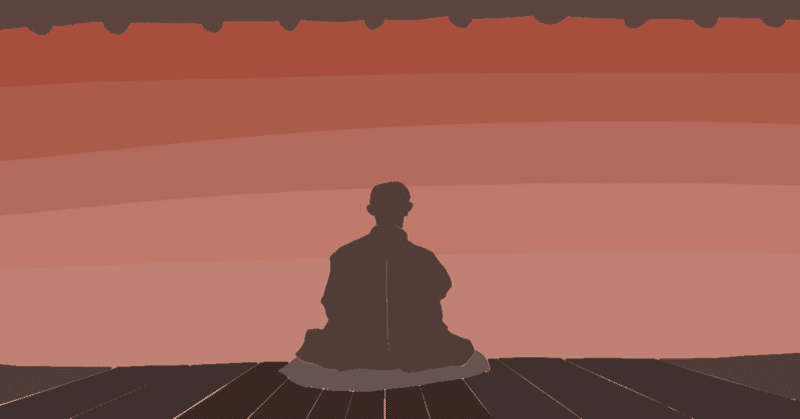
【読書感想】「前向きに生きる」ことに疲れたら読む本
眠れない夜、たまたま見つけたこの本を題名に惹かれてKindleでポチった。
私自身も「夢とか希望とか、成長とか目標とか疲れたな。そんなのいるのかな。求めるのも求められるのもなんか違うな」って思うことが最近多かったから、自然と吸い込まれた。
私は存じ上げていなかったのだが、著者の南直哉さんは曹洞宗のお坊さん。内容は仏教に基づくものであるが、平易な語り口調で、私達の視座に合わせて語られている。
自分なりの言葉で簡単にまとめると、以下の通り。
人間とは本来、その生まれからしてコントロールから外れているものである。自分を定義するのは自分ではなく、自分は他者による認識や承認によって「自分」が確立する。人生における悩みは他者との「間」にあるのだから、それを調整し、やりすごすことが大事である。人生の目標や夢などはあればいいが、なくても良い。別にそんなものなくても生きていける。大事なのは生きるか、死ぬかでそれ以外は些細なことである。なにをす「べき」かを、幻想でもいいから見出し、失敗し、修正しながら磨いていく。他者との関わりあいの中で成立する自分の存在を見極めることが重要である。
・・・私自身が日々漠然と考えていたことが集約されていた気がした。というよりも私自身が知らず知らずのうちに仏教的思想に影響を受けていたのだと思う。この本にかかれていたことが、仏教によるものなのか、宗派によるものなのか、単純に南氏の言葉なのかはわからないが、仏教への興味がより深くなった。(武者小路実篤の『釈迦』読みかけだったなぁ・・・)
個人的にとどめておきたい言葉や、読み返したい内容を以下にまとめる。
もし今、あなたの中に重苦しい気持ちがあるのなら、その思いをなくしたいと願っても難しいでしょう。「ないほうがいい」とわかっているのに持ち続けているのは、そもそも捨てられるものではないということですから。ただ、苦しみをなくすことはできなくても、悩みや問題を解きほぐしていきていくことはできます。もっと言えば、「つらくても大丈夫」と思える生き方をすることは出来ます。
そもそも、「昨日の自分」と「今日の自分」が同じだと言える根拠は2つしかありません。それは自分自身の「記憶」と「他人からの承認」だけです。<中略>人はこの世に「たまたま」生まれ、他人から「自分」にさせられたのです。その「自分」を受け入れるためには、人から認められ、褒められなければなりません。<中略>人間の最大の欲求は、自分を「自分」にしてくれた存在、つまり”他人から承認されたい”ということなのです。むりやり「自分」にさせられた自分と折り合いをつけ、苦しさに「立ち向かう」のではなく、その状況を調整し、やり過ごしていく。
「一切皆苦」という言葉が、仏教にあります。この世のすべては、「苦」である。釈迦は、そう見抜きました。<中略>この視点で物事を視ると、ある人達にとっては、強烈な救いになることがあるのです。<中略>「夢は努力すれば叶う」といった物語に乗れない人たち、自分のどうしようもなさにうんざりしていた人たちです。<中略>自分の存在はしょせん「たまたま生まれてきた借り物」にすぎないとわかると、「やっぱりそうか!」と納得するのです。
人間関係の問題を考えるときに大事なのは「つらい」「にくい」「嫌いだ」の話と、「今起きている出来事」とは、別ものだと理解することです。<中略>感情を抜きにして、自体を正確に判断できるか。そして、問題は自分の中ではなく、人との「間」にあると気づけるかです。人が直面する問題のほとんどが、人との「間」に存在します。「私の問題」とは、他人と一緒に織った織物のようなものなのです。
自分というものに対して居心地の悪さを感じるのは、当然です。私たちは生まれたいように生まれたわけではなく、気がついたらそのように生まれついていただけです。<中略>無理をしながら「自分」をやっているのですから。
自分がどの幻想を選んで生きるのかをきめることが、「べき」を決めることです。そして、「べき」が幻想だとわかったうえで、結果を期待したり見返りを求めたりせず、思い通りにならなくとも仕方がないというスタンスでやらなければいけないのです。それを覚悟でやるのが「生きる」ことです。<中略>自分を決定づけるのは、他者とのかかわりしかありません。「自分のため」ではなく「人のため」と考える。なんでも他人の言いなりになるのではありません。他人と問題を共有して取り組む。それが「やるべきこと」になるのです。「やりたいこと」ではなく「やるべきこと」をする。目指すのはそこです。<中略>「大切な自分」や「本当の自分」、「夢を叶えて生きる」といった妄想から降りて、他者とのかかわりの中で成立している自分の存在を見極める事が大事です。
生きるか死ぬか以外は大したことではない。<中略>それ以外のことで、しかも自分で決められることなど、じつはささいなことです。
大きな決断をしなければならない状況は、たいていネガティブなものです。<中略>自分の望むものであれば、人は迷いません。決断するまでもなく、その勢いに乗るだけです。ただ「これを選ぶ」といえばいいだけです。<中略>もしどちらか選べない状態が続いていたとしても、焦らず待つことです。そのうち、どちらかを選ばざるを得ないような力が必ず働きます。結果的に、自分の判断どおりにしなくてよかった。そう思うことも多いのです。
仏教では、すべての物事は、ひとつの条件によって成立している「仮のもの」だと考えます。人間関係も、仕事も、家庭も、常に一定の条件でしか成立しないあいまいなものです。今、自分がどんな場所に置かれ、どんな状況にあろうと、それは一時的な状況だと捉えるのが、仏教の視点です。
仏教ほど救いのない、ヤバい宗教はありません。要するに「自分が自分であることにしょせん根拠がない」と言っているのですから。
思い通りにいかなかったとき、夢破れたときに、人は損得から離れ、自分が本当に大事にするものを見極めます。そして、それを見極めた跡、自分の努力が報われるかどうかわからなくても、あるきはじめます。そんな人間には、ある種の凄みが備わるのです。だから、夢や希望が叶わなくても、がっかりすることはありません。
夢や希望が必要ないのと同じように、「生きがい」や「やりがい」の類いも、無くてかまわないと私はかんがえます。<中略>そんなものがなくても十分生きていけます。<中略>一生をふりかえって、「いい人生」だったか「悪い人生」だったかなど関係ありません。死に際して、「まあ、そこそこの人生だったかな」「いいことも悪いこともあったが、とりあえず生きたな」と思えれば十分だと、私は思います。そんな死を迎えるためには、「大切な自分」から降りて他人に自分を”開く”こと。損得勘定から離れ、人の縁を結んでいくことです。
人が怒るのは、「自分が正しい」と信じているからです。しかし、その「正しいこと」すらあいまいなものであって、変化するものです。それがわかっていれば、一時的にムッとすることがあっても、さほど激しい怒りにはならないはずです。
誰かに嫉妬したときは、その状況が本当に不当なのかと考えてみてください。大抵の場合は、実力どおりのことが起きているだけです。<中略>本人は不当だと思っていても、冷静に見てみれば不当でもない。自分の認識自体に錯覚があっただけ。
友だちをつくろうとしなくても、自分自身のやるべきだと思うことをやっていて、それが本当にやるべきことであれば、必ず人が集まってきます。また、同じようなテーマを持つ人間がそれを嗅ぎ分け、その相手との人間関係が自然にできていきます。
「ここまではわかるが、ここから先はわからない」といえる人と出会ったら、その人は、少なくとも自分自身の体験から語っています。信頼に値する人でしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
