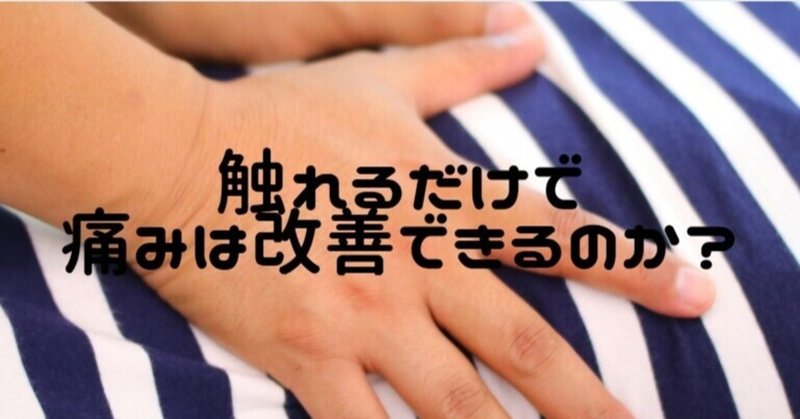
触れるだけで痛みは改善されるのか?
こんにちは!
はたらくからだ研究所 所長の丸山です。
私たちセラピストは徒手によって身体のケアをします。
しかし、実際のところ何が身体に影響を与え、症状の改善につながっているのかを理解して技術を駆使している人はあまりいません。
すべての徒手療法の基本は触れることです。
今回はこの「触れる」ことが人体にどんな影響をもたらすのか?
ということを探っていこうと思います。
徒手介入において人の体に触れる場合、押圧、牽引、伸張、軽擦、圧迫、揉捻など様々な触れ方があります。
これらの目的はいずれも筋緊張の緩和、関節可動域の増大、血流の促進であることがほとんどです。
ではなぜ、このような効果が得られるのか?それぞれの触れ方における効果性は変化するのでしょうか?
触れることを受け取るのは体性感覚
体に触れられる(刺激)を受け取る感覚は体性感覚によるものです。
ヒトの触覚受容器は4つあります。
マイスナー小体、メルケル盤、パチニ小体、ルフィ二終末です。
マイスナー小体は物体の鋭角さ、点字のような凸凹を検出します。
メルケル細胞は、垂直方向の変形に応答します。皮膚に接触した物体の材質や形状を検出します。
パチ二小体は受容野が広く、手のどこに加わった刺激にも応答します。その興奮で振動感覚を起こします。
ルフィ二終末は境界がはっきりしないため、局在的な圧迫に応じたり、局在的な遠方から皮膚をひっぱる力に応答します。
有毛部の皮膚では体毛が有毛受容器に支配され、速順応型です。遅順応型受容器としては、メルケル細胞が集合した触盤とルフィ二終末があり、ルフィ二終末は体毛周囲に存在する。
深部ではパチ二小体が関節周囲や、腱鞘、骨間膜などにあります。
徒手によって患者の体に触れるだけで、これらの小器官がはたらいて動きや温度、ブレンドされた感覚を受け取っているようです。
手掌や足底のような無毛部と有毛部では触感や神経伝達の速度が違うこともわかっています。
触れる速度によって影響与える細胞が変わってくるというのも面白いですね。
有毛部の感覚は触れられることと情動がリンクしているということも分かってきており、このようなことを理解しておくだけでも患者に触れるときに気をつけるべきポイントが深くなりそうです。
コミュニケーションに関わるC触覚線維の存在
皮膚の触覚にはC線維というものがあり、通常よく知られているものは侵害受容性のC線維で、侵害刺激に対して反応するものです。しかし、哺乳類の毛深い皮膚には無髄の低閾値機械受容求心性神経(C-LTMR)が存在していることが分かっており、人類には存在しない原始的な触覚システムであるとされてきました。
しかし、1988年にJohansson、1990年にNordinによってこの神経線維が人類にも存在していることが証明されました。これをC触覚線維と呼びます。
このC触覚線維は指先や柔らかいブラシでゆっくり撫でるような明らかに無害な刺激に高周波で反応します。
穏やかなスキンシップはC触覚線維が活性化することで鎮痛または抗不安作用を持つ可能性が高いとされています。しかし、神経障害性の疼痛に関しては軽いタッチは不快な感覚を与えるようです。
感情的なタッチは脳の島、右側頭頂接合部、および体性感覚皮質を活性化させます。
これらのことから、C触覚線維による求心性の感覚伝達は脳で処理され、触れた感覚だけでなく、社会的な結びつきや相手との信頼関係なども投影され、他者からの刺激を侵害性と判断せずに快刺激としてフィードバックできるようです。
Brain mechanisms for processing affective touch
Ilanit Gordon Avery C. Voos Randi H. Bennett Danielle Z. Bolling Kevin A. Pelphrey Martha D. Kaiser
First published: 29 November 2011 Human Brain MappingVolume 34, Issue 4 p. 914-922
筋の痛みは知覚を阻害する
2001年のPAIN6月号に意図的に筋肉痛を発生させて、皮膚感覚の変化についての研究が掲載されています。
そこで筋肉痛が痛みの部位および反対側の皮膚の機械的感受性を低下させたという結果がでています。
筋の侵害受容器の活性化は皮膚の機械的感受性を低下させたということですが、筋肉の痛みに対して徒手療法が効果的にはたらきにくい理由のひとつになりそうです。
Muscle pain inhibits cutaneous touch perception
Author links open overlay panelChristian S.StohleraCharles J.KowalskiabJames P.Lundc PAIN® Volume 92, Issue 3, June 2001, Pages 327-333
皮膚は触知した感覚を快・不快で振り分け、脳の情動系を活性化させることで、鎮痛や抗不安作用を働かせます。しかし、筋の痛みは皮膚の感覚を鈍らせたりもするのです。
ここで考えておきたいのは「痛み」の存在です。
痛みがあることで感覚系は信号が乱れやすくなります。これも痛みが脳と深く関係している故におこることでしょう。
マッサージは筋肉痛からの回復に効果はあるのか?
マッサージの効果は批判の対象として研究されます。
現在、徒手マッサージが運動後の筋肉機能の短期的または長期的な回復、または回復プロセスに関連する生理学的要因に重大な影響を与えるという科学的証拠はほとんどありません。さらに、遅発性筋肉痛はマッサージの影響を受けない場合があります。影響を受けた筋肉の軽い運動は、筋肉の血流を改善し(それによって治癒を促進する可能性があります)、遅発性筋肉痛を一時的に軽減する上で、マッサージよりもおそらく効果的です。 Manual Massage and Recovery of Muscle Function Following Exercise: A Literature Review Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
Published Online:February 1, 1997Volume25Issue2Pages107-112
この論文には徒手によるマッサージが筋肉痛の改善に影響を与える証拠はないと結論づけました。
筋肉痛を起こした場合は徒手マッサージよりも軽い運動をすることで筋肉の血流を改善し、一時的な痛みを軽減させるとのことです。
大腿四頭筋のマッサージは、動脈または静脈の平均血流速度を安静時のレベルよりも大幅に上昇させることはありませんでしたが、軽い大腿四頭筋の収縮は上昇しました。遅発性筋肉痛の知覚レベルは、運動後48〜96時間のマッサージされた脚で減少する傾向がありました。マッサージは、運動後の筋力の長期的な回復を促進するための効果的な治療法ではないと結論付けられ、運動環境でのこの目的のためのマッサージの使用は疑問視されるべきである。 Effleurage Massage, Muscle Blood Flow and Long-Term Post-Exercise Strength Recovery P. M. Tiidus, J. K. Shoemaker Int J Sports Med 1995; 16(7): 478-483
こちらの論文では時間を置いた場合は筋肉痛の減少傾向はあったものの、長期的な回復を促進するための効果ではないと結論づけられたようです。
マッサージには運動ほど血流を改善させる効果はありません。
筋肉疲労に対するVASにマッサージと休息状態の間に有意差が観察されました。腰部マッサージの投与はまた、局所領域の皮膚温度の上昇と血流の増強にいくらかの効果があるように見えました。 Effect of massage on blood flow and muscle fatigue following isometric lumbar exercise
Hidetoshi Mori, Hideo Ohsawa, Tim Hideaki Tanaka, Eiichi Taniwaki, Gerry Leisman, Kazushi Nishijo Med Sci Monit 2004; 10(5): CR173-178
筋肉疲労に対する痛みの評価(VAS)で、マッサージと休息を比較したらマッサージの方が有意であったという論文ですが、休息よりはマッサージの方が良いという程度に感じます。
マッサージには信じられているほど筋の血流を促進できる効果はなく、気持ちよさという情動的なリラックスによる効果の方が高いのではないでしょうか?
ストレッチにより、股関節の屈曲/伸展、股関節の外転、膝の屈曲、足首の背屈の範囲が大幅に拡大しました。効果は、マッサージとウォームアップを別々にまたは組み合わせて得られる効果よりも大幅に大きかった。足首の背屈のみがマッサージまたはウォーミングアップの影響を受けましたが、ストレッチはテストしたすべての筋肉群に影響しました。 Effects of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle strength in the lower extremity
Show all authors Margareta Wiktorsson-Moller, Birgitta Öberg, RPT, Jan Ekstrand, MD, First Published July 1, 1983
ストレッチとマッサージの群でウォーミングアップ中の筋力、可動域を測定したところ、マッサージの群よりもストレッチの群が可動域の変化が有意であったそうです。筋力に関してはどちらも変化がなかった。
マッサージがLBPの効果的な治療法であるという確信はほとんどありません。急性、亜急性、および慢性のLBPは、短期間のフォローアップでのみマッサージによる痛みの結果に改善が見られました。機能の改善は、非アクティブなコントロールと比較した場合、亜急性および慢性のLBPの参加者で観察されましたが、短期間のフォローアップのみでした。マッサージによる悪影響はわずかでした。 Massage for Low-back Pain Author links open overlay panelKatrinaFarberLMT, BCMTL. SusanWielandMPH, PhD EXPLORE Volume 12, Issue 3, May–June 2016, Pages 215-217
マッサージには筋肉の血流改善、筋力、可動域回復における効果はなく、筋肉痛の改善、腰痛の改善にも効果はないという結果が出ています。
マッサージの効果があるという研究結果もあります。
Effectiveness of massage therapy for subacute low-back pain: a randomized controlled trial Michele Preyde CMAJ June 27, 2000 162 (13) 1815-1820;
こちらの文献などに見られるマッサージの効果については、亜急性の腰痛患者に数週間の包括的マッサージを施した結果、筋膜施術群や運動指導のみの群よりも疼痛の改善に効果があったそうです。
慢性痛については
マッサージ療法グループは、リラクゼーショングループと比較して、痛み、うつ病、不安が少なく、睡眠が改善したと報告しました。彼らはまた、改善された体幹と痛みの屈曲能力を示し、それらのセロトニンとドーパミンのレベルはより高かった。
Lower Back Pain is Reduced and Range of Motion Increased After Massage Therapy
Maria Hernandez-reif,Tiffany Field,Josh Krasnegor &Hillary Theakston
Pages 131-145 | Received 03 Jan 2000, Published online: 07 Jul 2009
6か月の間、慢性腰痛の患者にマッサージまたはリラクゼーションの施術を週2回受けてもらうとマッサージの方がリラクゼーションよりも痛み、うつ病、不安が少なくなり、睡眠が改善したと報告しました。彼らはまた、改善された体幹と痛みの屈曲能力を示し、それらのセロトニンとドーパミンのレベルはより高かったようです。
このようにマッサージが腰痛に効果があるか、ないかという議論は非常に難しいものがあります。ここから読み取れるのはマッサージの良し悪しではなく、マッサージは有害事例も少なく、快刺激となり脳内のホルモンも活性化させますので、適度に受けることにより休息をより豊かにします。しかしマッサージの効果を過信しすぎることはマッサージ依存を生み、マッサージをしないと健康を保てないという状態になってしまうことは不健康につながるでしょう。
ストレッチの効果と目的
前の項にもストレッチはマッサージよりも可動域の拡大に効果があるといったというような研究がありますが、ストレッチが最適な症状、ケア、用途は意外とわかっていないで行っている場合が少なくありません。
接骨院、整体院では痛みのケア、トレーニングの場ではコンディショニングに用いられているように思いますが、ストレッチの対象は
・関節可動制限
・疼痛
・筋損傷
・筋委縮
この4つが主となると思います。
関節可動制限は、ギプス固定や安静臥床によって関節の固定または不動・不活動が原因となって起こる関節拘縮で、関節周囲の軟部組織の器質的変化に由来した関節可動制限であり、ストレッチが対象となるのは筋の拘縮です。
筋性拘縮は筋の短縮、線維化、筋膜を構成するコラーゲン線維網や筋線維の微細な変化によって伸張性が減少することで、関節可動域に制限が生じます。
不動や不活動によって起こる筋拘縮は、短縮した状態での不活動による筋の線維化によって骨格筋の伸張性は低下し、スティフネスが増加することが考えられます。
疼痛時については、組織の損傷がある場合ではなく、主に慢性的な筋・筋膜痛であるが、特に急性期に改善するまで必要な経過を追うことができずに過敏に痛みや硬さを触知される筋スパズムやタイトネスが、自発痛、収縮痛、圧痛を認め、脳や中枢神経系の感作によって引き起こされている場合にストレッチを活用しています。
筋の障害によって骨格筋からの侵害受容刺激がα運動神経細胞を興奮させ、筋収縮を促すことで骨格筋を緊張させます。骨格筋の過緊張は血管への機械的圧迫や毛細血管のスライドによる摩擦によって微小循環を阻害し、局所の血流低下や虚血を生じさせます。
よってストレッチは過度の収縮した筋を抑制するためにおこないます。筋収縮の抑制をすることは痛みの刺激による交感神経の過活動を抑え、ブラジキニンの血中濃度を低下させ痛みの神経系感作を低下させる狙いがあります。
それらが目的であるならば、ポイントは痛みを与えないこと、過度な筋収縮を抑制させるように角度やテンションに気をつけることが技術として求められます。
骨格筋は粘弾性を持ち、筋収縮や伸張刺激によって張力が発生すると、張力に応じて時間依存的に筋長を変化させます。これは急激な負荷や筋長変化に対する衝撃吸収機構になっています。
ギプス固定などで廃用性の筋委縮を起こした筋にストレッチを施すと、この機構がはたらきにくいために筋損傷につながることがあります。
筋損傷、筋委縮に対しては筋力トレーニングと併用しながら、関節可動域を改善する目的で実施することが現実的だと思われます。
ストレッチは触れる技術の中では伸ばすことに特化された技術です。伸ばす技術はほぐす技術と比べると、動きの改善が得意です。しかし、無暗に可動域を拡大することは症状を悪化させることにもつながります。
亜急性期の痛みを伴う、動きの制限に対して慢性化を防ぐ取り組みとして、慢性化した症状のケアとして適度にセルフケアのような使い方がベストではないでしょうか。
ここまでで疼痛の改善に触れる技術を効果的に使用するのであれば、
・亜急性期の慢性化を防ぐ
・局所の血流を促すため、動き(患者の自動運動)を伴う手技である
・疼痛改善、可動域回復は結果であり、これらを目的にすると危険
・心理的な鎮静効果や、快刺激による中枢神経系の活性化
これらは理解しておきたいポイントです。
筋膜リリースや軟部組織系のアプローチは大方、この認識で考えられます。
カイロプラクティックは有効な徒手療法であるか?
続いてカイロプラクティックに代表される触れて骨格は調整可能であるか?または必要であるか?という疑問です。
カイロプラクティックは椎骨の亜脱臼(サブラクセーション)による神経根の圧迫が神経伝達を阻害することで、心身の不調を起こすという哲学を元にして発展してきた徒手療法です。
ここから、オステオパシーや脊柱マニュピレーションなど、様々な骨格系徒手療法のベースになっています。
この哲学は100年以上前にアメリカ人D.Dパーマーが唱えたものですが、今も「100年以上の歴史ある民間療法であるから」という文句で信頼性を得ています。
The Chiropractic Vertebral Subluxation Part 10: Integrative and Critical Literature From 1996 and 1997.
Senzon SA1 Journal of Chiropractic Humanities, 01 Dec 2018, 25:146-168
こちらの論文にはカイロプラクティックの古典的な哲学、サブラクセーション(椎骨の亜脱臼)について信頼性がいかに構築されてこなかったか?ということやD.Dパーマーが当時おこなっていたことが椎骨の矯正だけでなかったことまでを言及しています。
椎骨のサブラクセーションはカイロプラクティックの最も根幹を成す考えであり哲学の中心です。この部分は現代では信頼性が低く、様々な観点から研究もされていますが、その有効性は疑問視されています。
そもそも触診における位置情報や左右の非対称性も不確実なものであり、これらの手技が有効とされるのは
・椎骨の亜脱臼というのは筋の不均衡による神経伝達の差分ではないか?
・サブラクセーションによる椎間孔の狭窄による障害ではなく、侵害受容器の感覚障害ではないか?
などが今後の研究課題になっていくようです。
触れて、骨格の異常を直すという考え自体が今の科学では否定的な見方をされていますし、椎骨の亜脱臼がサイレント・キラーといった啓蒙は非常に忌むべきものだとされています。
触れることで痛みに変化を与えることの真実
ここまでで代表的な触れる技術とそこに起こる生理学的反応について書いてみましたが、私の中でも大きな認識の変化がありました。
マッサージ、ストレッチなどと分けて考えるのではなく、軟部組織のマニュピレーションとして理解した上で、マッサージ的だったり、ストレッチ的な要素を手技の中に取り入れていくことが必要なのだと分かりました。
他動的に徒手で痛みの改善を促すことは結果として起こり得ますが、どちらかというと触れるという技術は術者とクライアントの信頼関係と安心感。
そして、共通意識によって運動や食事、生活の改善なども含めた指導をしながら他覚的、集学的にアプローチした結果、症状が改善されるという現象にたどり着くのでしょう。
そういう面ではすべての徒手療法は正解であるが、万能ではない。
こういった言い方が妥当なのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
