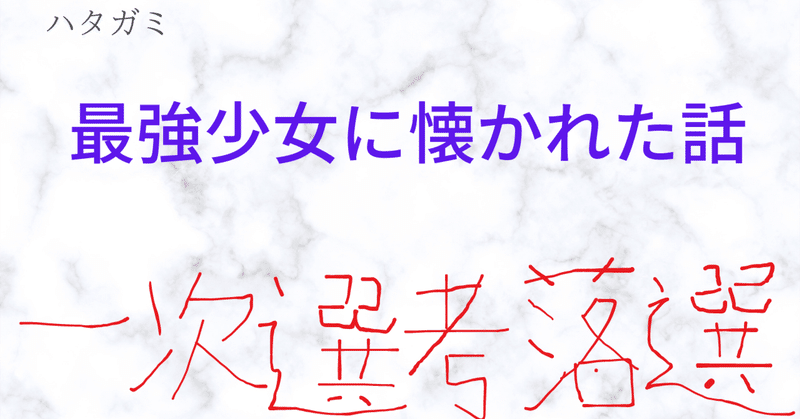
第二章|「最強少女に懐かれた話」ハタガミ|第36回後期ファンタジア大賞 一次選考落選
第二章 最強少女を奴隷にした話
「……ん……? はっ!」
ミリアムは目を覚まし、起き上がる。
「あら、起きましたか……」
ミリアムに気付いた響子が、キッチンから声を掛ける。
(……何も、されてない……?)
自分は二人の命を狙ったというのに、ミリアムの身体には拘束具一つ無かった。
それどころか、衣服もそのままで柔らかい毛布だけを掛けられているという始末。
「昼食が出来ていますから、早く食べなさい」
「……」
ミリアムはソファから出て、食卓に向かう。
幸一が座っていた席の隣に、子供用の椅子が用意されていた。
「……おかわりもあるから、好きなだけ食べなさい」
そこには、たっぷりのローストビーフとコーンスープ、サラダがあった。
そしてもう一つ。
(……何これ?)

奇妙な黄色い液体が、コップに注がれていた。
「……どうしたの?」
いつまでも食事に手をつけないミリアムに、響子は問いかける。
「……これは、私の……?」
「そうよ?」
ミリアムは一度ため息を付いてから、警戒心を剥き出しにして響子を睨む。
「……何を入れたんですか?」
「……あぁ、安心して、別に毒とか入れてないから、ただのご飯よ」
「じゃあ、この黄色いのは何ですか? おしっこ?」
ミリアムはそう言って、ガラスのコップを指さす。
「……それはグリーンティー。緑茶よ」
「リョク、チャ……?」
奇妙な単語に、ミリアムは首を傾げる。
「丁度私も昼食を食べるところだったから、一緒に食べましょう」
そう言って響子は、同じメニューをミリアムと対面側に並べる。
向かい合うように食卓について、両手を合わせた。
「いただきます……」
(……イタ、ダキ……?)
奇妙な日本語に、ミリアムは再び首を傾げる。
「今のは、日本の礼節。食事前に言う作法よ」
説明しながらも、毒が入っていないことを証明するため響子は食事に手を付ける。
「日本の作法……」
「どうしても信じられないなら、お皿を交換してもいいわよ?」
「……」
ミリアムは奇妙に思いながらも、ひとまず響子を信じることにしてフォークを握った。
ローストビーフを突き刺して、一思いに口に入れる。
「……はむ! ……んむ…………んっ!?」
そして、あまりの美味しさに驚愕する。
(う、うまぁ……!?)
柔らかい肉の感触と、温かくも甘辛いタレの味。
口の中で溶け合うローストビーフに、ミリアムは目を見開きながら咀嚼する。
「んむんむ……! はむ……! はむ……!」
ミリアムの咀嚼の速度は、瞬く間に加速していき、フォークは休む間もなく肉と口の間を往復する。
「……よく噛んで食べなさいよ?」
響子がその一心不乱な様子に、少し心配になる。
だがまるで聞こえていないようで、ミリアムの食指は加速してく。
「はむはむ……んっ!?」
だがその最中、噛み切っていない肉が喉を通りかけてつっかえる。
「んんっ!?」
「言わんこっちゃない。……ほら、お茶飲みなさい」
響子は立ち上がり、ミリアムのコップを目の前に持ってくる。
ミリアムは焦りながらお茶を流し込む。
「んく……んく……!」
お茶を飲んでいる中で、ミリアムは再び目を見開く。
(お、美味しい……!?)
緑茶という飲み物の飲みやすさに、驚愕していた。
ほのかなコクがあり、それでいてストレスを感じないこの味。
「……ぷはっ! はぐ!」
ミリアムは緑茶で詰まった肉を流し込んでから、さらに肉を食べる。
「……野菜もちゃんと食べなさいよ」
響子は微笑みながら、自分の昼食に手を付ける。
ミリアムが早々に食事を平らげて、お代わりを繰り返すこと二度。緑茶に当たっては、二リットルを飲み干した。
約三人分の昼食を終えて、お腹を膨らませたミリアムは、大きく息をついた。
「……ふぃー」
「よく食べたわね。多めに用意しておいてよかった」
「……」
食器を洗う響子を、ミリアムは膨れたお腹をさすりながら怪訝そうに見る。
「……どうかしたの?」
「……なんで、私の昼食を用意したんですか?」
「そりゃお昼時ですし」
ミリアムはずっと気がかりだった。
ミリアムが起きてから、響子はミリアムのことを微塵も警戒していない。
「……私が、またあなた達を殺そうとすると、思わないんですか?」
「思いませんね」
即答する響子に、ミリアムは訳が分からなくなる。
「……どうして?」
「そりゃあ、あなたにはもうその気が無いからね。警戒する理由が無いわ」
ミリアムはますます意味が分からない。
「……なんでそんなことが分かるんですか?」
「それが私の能力だからです」
食器洗いを終えたのか、響子は水を止める。
「それから、理由はもう一つ」
響子は立てかけられた棒に吊り下げられたバスタオルで、手を拭く。
「あなた如きなら、暴れられてもどうとでもなるから。問題ないわ」
その言葉には、流石にミリアムも納得せざるを得なかった。
(……そうだ。私……完敗したんだ……)
数秒のこととはいえ、響子には武器を使わない程の余裕があった。
ミリアムと響子の戦力差は明白。
不意打ちが通用するような相手とも思えない。
「さてと、それじゃあそろそろお腹も落ち着いてきたと思うし、移動するわよ。ついてきなさい」
そう言って、響子はリビングを出た。
「……?」
ミリアムは首を傾げながらも、響子についていく。
「……ここは……?」
響子が案内したのは、一階の最奥の部屋にある金属製の扉だった。
響子はノックをして呼びかける。
「先生? ミリアムを連れてきました」
「おう。入れ」
幸一の返事を聞いて、響子は扉を開ける。
「……っ……!?」
その光景を見た瞬間、ミリアムは立ち眩みでも起こすように力が抜けた。
そこは巨大な薬棚と長机が一つあるだけの、広々とした部屋だった。だがその机の上には、大量の書類が散乱しており、地面に落ちている紙もいくつかある。薬棚には大量の薬品の瓶が敷き詰められていた。また部屋の隅には、申し訳程度のベッドと医療器具が置いてある。
そして何よりミリアムの目を引くのは、そこら中に横たわる、大量の人体模型。特に脳の模型がいくつもあり、全て薄汚れており、使い込まれた形跡があった。
ここまでくると、不気味を通り越してマッドサイエンティストの領域だ。
「先生……人を招くのですから、掃除くらいしてください」
メイドである響子でも、ここを無許可に使うことはできない。なので掃除は幸一しかできないのだが、今はあまり利用していないのか、部屋中が埃をかぶっていた。
ここは幸一の診療室兼研究室だ。
(……そっか……そうだよね……)
やけに優しくされる理由が、ここにはあった。
あのご馳走は、最後の晩餐だったのだ。
「おぉ、来たな……取り敢えず、椅子に座ってくれ」
ミリアムが絶望的な未来に、感情を失っていると幸一が声を掛ける。
「……はい……」
錆びたパイプ椅子に座るミリアムの前に、白衣を羽織った幸一が薬棚からチューブの薬を運んできて、オフィスチェアに座る。
「起きたので昼食を食べさせました」
「おけ。んじゃ取り敢えず、さっきの戦いで燃やしていた腕を出せ。あ、抵抗しても無駄だからな?」
「はい……」
抵抗する気力もなく、ミリアムは腕を差し出す。
「ふむ。普通に火傷しているな」
幸一はミリアムの腕を観察する。
(火傷……それもかなり軽度のものだ。……やっぱ特殊体質なんだな)
人間が耐えられる温度はたかが知れている。
一九〇六年、アメリカ空軍の実験において、裸の人体が二百四度の気温に耐えられることを確認した。
だがそれでも、たかが二百度だ。火というものは最も冷たい「冷炎」と呼ばれる特殊な火でも、四百度を下回ることは無い。常人ならば着火するほどの熱量で皮膚はおろか、血管や神経までもが溶けてしまうはずなのだ。
それ故に人体発火現象は都市伝説とも言われ、その事例は全て周囲に全く火気がない状態で発見された焼死体から推測されるものだ。
「火傷の状態を見たくて、氷を腕に巻いたりはしなかったんだが、痛くないのか?」
ミリアムはその問いに、短く答える。
「もう慣れました」
「……そうか。じゃあ薬を塗っていくぞ。じっとしてろよ?」
幸一はチューブから液体を指に取り出して、火傷の傷口に塗り込んでいく。
柔らかいミリアムの腕に薬を塗り込みながら、幸一は物思う。
(これでも痛がらないんだな……というかこいつの腕、めちゃくちゃ柔らかいな。てっきり筋肉質だと思ってたんだがな……)
ミリアムは塗り終わるまで、微動だにしなかった。
「これでよし。しばらくヌメヌメするが、拭いたりすんなよ?」
「はい……」
幸一は立ち上がり、薬棚に塗り薬を戻す。
「火傷の方は問題なさそうだから、早速お前の身体を調べようと思う」
「……はい」
感情の無い瞳が、調べるという言葉に反応したように、微かに揺れた。
「ミリアム、お前はいつも【人体発火】をどうやって起動させているんだ?」
「……えと」
ミリアムは、話しかけられたことに驚いているようだった。
「……ごめんなさい、分かりません。……なんか、痛いのを想像して……」
どうやらミリアム自身にも、人体発火現象のからくりは理解できていないようだ。
「じゃあ質問を変えよう。お前の炎は、今までどんなときに起こっていたんだ?」
再びオフィスチェアに座って、幸一はミリアムと目を合わせる。
「……それは……」
ミリアムは少し悩んでから、言葉をまとめてから話し始める。
「……んと、昔はよく分からずに火が出ました。でも、いつからか痛みを感じたり、悲しかったりすると、体が燃えるようになりました。だから戦うときも、痛いのを想像すれば、自分で燃やせるようになりました」
「ふむ……痛覚か」
幸一はその言葉を皮切りに、黙り込む。
「……」
「……先生?」
「……だいたい分かった……もう大丈夫だ」
そう言って幸一は立ち上がった。
「俺は薬を作る。響子、あとは頼む」
「かしこまりました。……ほら、行きますよ」
響子はミリアムの手を引いて、研究室を出ようとする。
「……あの」
だが、その前にミリアムが幸一の袖を引っ張った。
「ん?」
ミリアムは不安げな瞳で幸一を見つめる。
「あの……私は、あなたの奴隷……なんですよね?」
その言葉に、幸一は固まる。
「……は?」
「エヴァ様から、そう聞かされました」
「……あの野郎」
幸一は納得したように眉間に皺を寄せる。
「あぁー……まぁ、そうだな。……で、それがどうかしたのか?」
幸一は弁解するのも面倒になり、取り敢えずそのまま話を進める。
響子から凄まじい視線を感じるが、気にしない。
「……私は、どうなるのでしょうか?」
「あん? どういう意味だ?」
幸一は意味が分からず首を傾げる。
「あの……先程のことは謝ります……ですから、どうか私を、殺さないでください……」
手を合わせて、祈りを捧げるように指を絡ませる。
人は文明が発展する以前から、心からの祈りや慈悲を感じたときに、自然と手を合わせる習性が存在していたという。
ずっと戦場で生きてきたミリアムだが、こうして手を合わせているということは、本気で自分が殺されるかもしれないと感じているのだ。
(エヴァめ……なんでこんなこと……)
幸一は大きくため息をついてから、ミリアムの頭に手を置いた。
「大丈夫だ。……俺は自分のものは大事にする方だからな」
「……そう、ですか」
「おう。分かったら行け、俺は忙しい」
「……はい」
ミリアムは不安げな足取りで、研究室を出た。
「……いいんですか?」
残った響子は不満そうに幸一を見ていた。
「何がだ?」
「彼女は奴隷じゃないでしょう」
「あぁ。それが何だ?」
まるで興味のないような幸一に、響子は少し声を荒げる。
「……奴隷として育てられれば、彼女はまともな人生に戻ることはできなくなります」
「だが奴隷を否定すればあいつは自分の居場所を無くすことになるぞ」
幸一の鋭い指摘に、響子は少し言葉に詰まる。
「……別に否定するわけではありません」
「いや同じことだ。ミリアムには今、居場所が無い。人間は居場所があれば、しぶとく生き延びることができる。例え劣悪でも、ミリアムが戦場という地獄で生き延びたようにな」
安全基地、という児童心理がある。
母親の膝の上や勉強机、自室など、自分の居場所を確認してから子供は外の世界に目を向けて好奇心や学習意欲を持つことが出来るという心理だ。
幸一はそれを理解して、幸一の奴隷という居場所を作った。
「……」
説明を受けても、響子はなおも不満そうだ。
「別に俺が正しいかなんて知らんし、興味もない。……俺はあいつの【人体発火】を調査するっつう仕事を、穏便に終わらせればそれでいいからな」
「……そうですか。失礼します」
響子はよそよそしく、研究室から出て行く。
張りつめた空気が無くなり、幸一は息を吐く。
「……ふぅ……さてと、調剤は久々だが、まぁ何とかなるだろ……」
幸一は伸びをしてから、薬の開発に取り掛かった。
「……ミリアム。取り敢えずあなたの部屋を紹介するわね」
響子はミリアムに空き部屋を案内する。
二階は自室や寝室、幸一の書斎などがあり、客人が来ることは無い。
その分、一階よりも掃除が行き届いていないことが多いが、その部屋だけは清潔に保たれていた。
「これが、私の部屋……ですか?」
響子の自室の隣。
空き部屋と言うだけあって、ベッドと机以外には何も置いておらず閑散としている。
「えぇ。そうよ。ベッドも好きに使って構わないわ」
「……この、ベッドを? 私は、床でも構いません……」
ミリアムの言葉に、響子はミリアムの頭に手を置いて、諭すように告げる。
「……まぁ戦場ではそうよね。私もそうだったわ。初めはふかふかし過ぎで心配になる。でもすぐに慣れるわ。ベッドで寝るのは、凄く気持ちいいから」
「……そうじゃ、なくて……私にはこんな部屋……」
自分が真っ当に扱われることに戸惑うミリアムは、この扱いが不安で仕方ない。
「いいのよ。ミリアム……」
そんな不安を溶かすように、響子はミリアムを抱きしめる。
「もうあなたを傷つける人はいないの。……だから、もう大丈夫よ」
響子の抱擁に、ミリアムは動けなくなる。
「……そんなこと……できません……」
やがてぽつりと、ミリアムは呟いた。
「……?」
「あ、いえ……ありがとう、ございます……。この部屋……ありがたく使わせていただきます」
そして、するりとミリアムは抱きしめていた響子を遠ざける。
「そ、そう……? それなら、良かったわ……」
響子は少し心配しながらも、背を向ける。
「……じゃあ、今日はもう休んでいていいわよ。夕食やお風呂の時間になったら、また呼びに来るから」
「……はい」
返事を聞いて、響子は部屋を出た。
(……大丈夫かしら……)
まだまだ不安そうなミリアムは、響子から見ても少し心配になる。
(戦場て生きてきた、テロ組織の最強少女兵……きっと私達を信用できていない……)
少女兵との生活が始まり、肝心の幸一は無関心。
(でも、エヴァさんが託したんだし、先生ならきっと何とかしてくれるわよね……!)
響子は頭を悩ませながらも、自分の主人を信じることにした。
端的に言って、ミリアムには自由意思というものが無かった。
子供ならば誰しもが持つはずの、些細なわがままやこうなりたい、こう生きたいという未来への衝動がミリアムにはない。
「おい、ミリアム」
その言葉に、ビクッとミリアムは身体を震わせてから返事をした。
「はい」
「これ、取り敢えずできるところまで解いてみろ」
遅い朝食、響子の計らいで三人は同じ食事をとるようにしていた。
そこで幸一は、小中学生用のテスト問題集を手渡した。
科目は国語と数学だ。
「必要な筆記用具があれば、響子に言ってくれ」
「はい」
ミリアムは無表情のまま、その言葉に従った。
そして数日後。
「あの……」
食事時。
ミリアムが教材を持ってきた。
「できました……」
教材を開けば、最後の設問の解答欄まで埋め尽くされていた。
「そうか。結構な量だったと思うが、もう全部やったのか? 偉いな」
そう言いながら、幸一がミリアムの頭に手を伸ばそうとする。
「っ!」
だが、幸一が手を上げた瞬間に、ミリアムはビクッと身構えた。
「あぁ、触られるのは嫌だったか?」
「……いえ」
「そうか」
幸一はできるだけ優しく、ポンポンと頭を撫でた。
「とにかくよくやった」
「……ありがとうございます」
口では礼を言うが、まるでミリアムは嬉しそうにしなかった。
それどころか、頭を撫でる幸一に怪訝な表情を浮かべるだけだった。
そんな微妙な空気の中で、一週間が経過した今でもミリアムと幸一の距離が縮まることは無かった。
そして、ミリアムが来て初めての事件が起きた。
「「「……」」」
三人でとる夕食。
そこに会話は無い。
「……ゴチソー、サマデシタ」
ミリアムが食事を終えて、日本の作法に習い、手を合わせる。
「お粗末様。食器はそのままでいいから、お風呂入ってきなさい」
「はい……」
「……」
特に幸一と話すこともないので、そのままミリアムはリビングを出る。
この一週間、ミリアムはずっとこんな調子だった。
(先生に何か狙いがあると思っていたけれど……流石に限界だわ……)
幸一があの教材を解かせたっきり、ミリアムは一日中部屋にいて窓の外を眺めて過ごすという、育ち盛りの子供とは思えない日々を過ごしていた。
「……先生?」
響子は耐えかねたように幸一に切り出した。
「なんだ?」
「どうしてミリアムと話さないんですか?」
「は? なんか話さないといけないことあったか?」
幸一は首を傾げる。
「……ミリアムは先生の奴隷なのでしょう? なにか役目を与えなくてよいのですか?」
「あー、そういえばそうだったなぁ……」
まるで関心の無い幸一の反応に、響子はため息をついた。
「それに、エヴァさんに言われたのを忘れたんですか? 先生はミリアムの治療もさることながら、ミリアムに基礎教養を教えなければならないのですよ?」
その言葉に、幸一は固まる。
「え……それって俺がやらなきゃいけないのか?」
さも当然のことのように告げる幸一に、響子は呆れた。
「……まさか私に任せるつもりで、何も準備していないんですか?」
「……いや、そうじゃなくて……あいつにちょっと問題集を解かせたんだが、基本的な読み書きや計算はできるみたいだし、書斎を使わせておけば勝手に身に付くと思って……」
再び響子は眉間に手を当てて、盛大にため息をついた。
「先生? あなたの仕事はミリアムを育てることですよ?」
「育てるって……お前も知ってるだろ? 俺が何かを教えるなんて無理だって……」
幸一はミリアムとは真逆と言ってもいい。
自由に過ごし、自由に生きる。だからすぐ泣くし、すぐに怒る。わがままも言う。
教育者としては、最悪もいいところだ。
「……それでも、エヴァさんは先生にミリアムを託したんです。その責任から逃げるおつもりですか?」
「……分かったよ。でも基礎教養なんて、何から教えたらいいんだ?」
ようやくやる気になった幸一の相談に、響子は喜んで応じる。
「そうですねぇ……」
そうして、響子が頭を悩ませていると。
タッ
「……?」
それはほんの微かな物音だったが、響子は確かにその音を拾った。
聞こえなかった幸一は、真顔になった響子に首をかしげる。
「どうした?」
「……何か、変です……一応、先生も来てください」
響子は席を立ち、リビングを出る。
「あん……?」
幸一は言われた通り、響子についていく。
「……ミリアム?」
響子はバスルームの扉の前で、中にいるはずのミリアムに呼び掛ける。
だが返答はない。
「……ミリアム? 入りますよ?」
ゆっくりと扉を開く。
「……っ!? ミリアム……!?」
「おいなんだ? どうし――……うっ!?」
遅れて入った幸一が、その臭いに絶句する。
ミリアムは、炎を纏ってバスルームに倒れていた。
床には吐瀉物がぶちまけられており、強烈な臭いが立ち込める。
そして、炎から垣間見える全身は真っ赤に染まっており、溶け落ちた表皮から、血のにじんだ中の肉が見えていた。
「……先生!」
響子は急いでシャワーをかけて、生きていることを確認してから幸一に呼び掛ける。
幸一は響子の剣幕に驚きながらも、指示を出す。
「お、落ち着け。……と、取り敢えず冷水で体を流して、服を着せて研究室へ連れてこい……!」
「はい!」
幸一は急いで研究室に向かい、ベッドと医療キッドを用意する。
(体が弱っていたのか……!? そんな風には見えなかったが……)
そして薬棚から薬を取り出していると、響子が慌ただしくミリアムを連れてきた。
「先生!」
「ミリアムをベッドへ寝かせて、熱を測ってくれ」
「はい!」
響子は迅速に幸一の指示に従う。
「……あ、れ……?」
慌ただしい二人に、ミリアムは薄っすらと目を覚ます。
「……ん? ……起きたか。ちょうどいい。まずは胃薬だ。取り敢えずこれで吐き気は収まるはずだ。飲め」
起きたばかりのミリアムに、幸一は有無を言わさず捲し立てる。
「……は、い……」
水の入ったペットボトルと錠剤を渡され、ミリアムは力無く頷いた。
「熱を測りますからね」
響子は体温計をミリアムの脇に差し込む。
「あとは俺がやるから、毛布を持ってこい」
「はい」
響子にそう言って、幸一は別の薬を取り出す。
程なくして、体温計が鳴り響く。
「……」
体温計には、四十二度と表示されていた。体温計の限界値だ。
ミリアムには【人体発火】があるから、この数値が本当の体温とは限らない。
だがミリアムが危険な状態であることは明らかだった。
幸一は何とか動揺を抑え込んで、ミリアムに話しかける。
「……次は解熱剤た。熱による頭痛や吐き気、浅い睡眠を軽減する。飲め」
再び錠剤を渡して、ミリアムに飲ませる。
「毛布、持ってきました!」
「かけてやれ」
慌ただしく戻ってきた響子が、ミリアムに毛布を優しくかける。
体温計を戻してから、幸一はまた別の薬を取り出した。
「よし、飲んだな。最後は栄養剤と睡眠剤だ。回復を早める。二錠ずつ飲め」
言われた通り、ミリアムは緩慢な動きで渡された薬を飲む。
「……全部飲んだら、もう寝ろ」
幸一は短く告げて、静かに薬を戻した。
「……」
ミリアムはそんな幸一の姿を、ずっと見つめていた。
二人はそれに気付いて、怪訝に思う。
「……どうしたの?」
「もしかして……主人の俺がいるから、寝られないのか? それか腹が減っているなら、響子にお粥でも作ってもらうが」
「……分からない、のです」
ぽつりと、か細い声で呟いた。
幸一はミリアムの視線に耐えかねて、ミリアムの側でオフィスチェアに座る。
「……何がだ?」
流石に無視する訳にもいかず、幸一はミリアムと目を合わせて話を聞こうとする。
ミリアムは天井に視線を移しながら、語り始めた。
「……私は……兵器……呪われた兵器として……たくさんの人を殺しました」
「……ただの子供だろ」
「物心ついた頃から、この呪いは私に宿っていました。最初に……私を抱きしめてくれた両親が……死にました。……それからも色んな人を殺しました。……呪いで居場所が無くなって……村を追い出されてからは、スラムのストリートで食いつないで……その中で、『衛星特攻兵団』に兵器として、雇われました」
「……そんな」
テロ組織に至るまでの壮絶な過去に、響子は返す言葉が思いつかない。
「……それからは毎日……毎日……痛くて、苦しくて……誰も助けてくれなくて……ただ耐えるしかなくて……」
ミリアムの声が震え始める。
「……ミリアム」
響子は哀れむようにミリアムの手を握る。
「……だから思ったんです。これは罰なんだって。色んな人を殺した罰なんだって。……だから、私に悲しむ資格なんか……無いんだって。……だから、ずっと何も感じないようにしていたんです……これ以上、悲しまないようにって……」
ミリアムが、自分が涙を流していることにも気付かずに、話し続ける。
いつからか、ミリアムの全身から湯気が出ていた。
響子の握っていた手は、みるみる温度を上げる。
「ここに来て、初めは……今までと同じように、酷いことをされるんだって……体中調べられるんだって……思っていました。だから、ずっと眠れなくて……」
(弱っている原因はそれか……)
ミリアムは不安げな瞳で、幸一を見る。
「でも……あなたは、あなた達は……優しくって……暖かくって……私……どうすればいいか、分かりません……また大切な人を信じて、愛して……裏切られたら……また私が殺してしまったら……それが怖くて……」
その言葉に、幸一は困惑していた。
(優しい……だと……?)
幸一は意図的に優しくした覚えはないし、そもそも衣食住を保障した以外に、幸一がミリアムに何かをしてあげた記憶はない。必要以上に関わらないようにしていた。
つまり、ミリアムはそんなものを優しいと認識してしまう世界で今まで過ごしていたということだ。
「私……信じていいんですか……? あなた達は……死なないでいてくれますか?」
離れている幸一すらも汗が出る程の熱気が、ミリアムから放たれる。
(……こりゃ、相当弱っているな……)
幸一は慎重に言葉を選んで、答えた。
「……死なねぇよ。俺も、響子も。……そんで俺が必ず、お前の呪いを治してやる」
幸一はミリアムの頭に手を乗せる。
焦げ付いた髪の毛は、炎であぶられた鉄板のように熱い。
「……」
「だから、安心して眠れ。俺達はどこにも行ったりしない。……信じろ」
強い言葉と、強い視線。
そして大きな幸一の掌が、ミリアムに心からの安心を与えた。
「………………」
やがて目を閉じて、ミリアムは程なくして寝息を立て始めた。
「……眠ったか」
幸一はゆっくり息を吐いて、手を離す。
「……そのようですね」
「後で冷やしたタオルを首か額に置いてやれ。それから、卵粥も作っとけ」
「……はい。……手の方は、大丈夫でしたか?」
「いや、普通に火傷した。超いてぇ。……つーか、なんでお前は余裕そうなんだ?」
幸一は赤くなった自身の掌を、涙目になりながらプルプルと震わせる。
「そこは強がってみせてくださいよ、全く。……ふふ」
響子はミリアムの手を握りながら、小さく笑う。
「お前は平気そうだな。……なんだよ?」
「いえ……先生はまだまだ現役の薬剤師なのだと、安心しました」
咄嗟に見せた、薬を処方するときの癖。
薬の名前と、その効能を説明しながら患者に手渡し、決して患者の前で慌てる素振りは見せることなく、的確な指示を迅速に下す。
それは薬剤師の性だ。
幸一はアホらしいと言わんばかりに、背を向ける。
「……俺はただ、ミリアムの病気を早く治すために言っただけだ」
病気は身体にも苦痛を与えるが、精神にも負担をかける。
逆に精神の負担を和らげるものがあれば、それは身体にも影響して治癒を加速させる。
病の歴史において誰にも治せないはずの不治の病を、毎日必死に親や恋人が呼びかけることで完治したという事例は、数え始めたらきりがないほど存在する。
だからこそ、幸一の言葉には大きな意味があった。
「……ふふ。そういうことにしておきます」
その説明を聞いてもなお、響子は嬉しそうに笑う。
「ふん……俺は夕食に戻る」
幸一は気恥ずかしくなり、その場を後にする。
歩きながら、幸一は先程のミリアムの言葉を思い返していた。
(優しい……俺が……?)
少なくともミリアムはそう感じていた。
そして幸一の優しさを信じてくれた。
今まで何もしなかった自分に、ほんの少し罪悪感が湧き上がる。
(俺の責任……だよな……)
ミリアムはその日、ここへ来て初めて熟睡することができた。
反対に幸一はその日、一睡もできなかった。
はい。これで第二章は終了です。
ミリアムとの距離を縮めるエピソードが下手すぎましたね。アクシデントではなく、もっと幸一の能力を強調するエピソードにすれば良かったと思います。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
