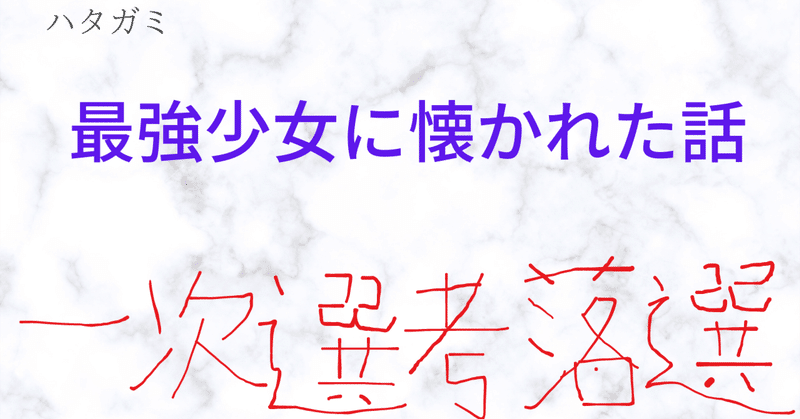
第三章|「最強少女に懐かれた話」ハタガミ|第36回後期ファンタジア大賞 一次選考落選
今回ちょっと長いです。(2万字程度)
第三章 最強少女兵がただの子供になる話
翌朝。
「……ん」
ミリアムが目を覚ます。
少し遅い時間のようで、寝すぎたせいか頭が少し重い。
「私……」
研究室に、昨日のままの姿でミリアムは寝ていた。
額に濡れたタオルが置かれている。
「……治った……のかな……」
昨日まであった、強烈な倦怠感が無くなっている。
ミリアムが調子の良くなった自分の体を見ていると。
「お、起きていたんだな。丁度良かった」
研究室の扉が開き、幸一が入ってきた。
いつもどおり、着崩れたパジャマ姿だ。
「あ……あの……」
幸一の顔を見て、ミリアムは昨日のことを思い出す。
「調子はどうだ?」
「……もう、大丈夫です……」
「そうか。食欲はあるか?」
「はい」
「んじゃ、顔洗ってリビングに来い。響子が朝食を用意している。一緒に食べるぞ」
「分かりました」
幸一はそれだけ告げて、研究室を出て行こうとする。
ミリアムは言われた通り、目を擦りながらもベッドから出る。
そして幸一が研究室を出る前に、声を掛けようとする。
(なんて呼ぼう……?)
流石に呼び捨てにするわけにもいかなので、ミリアムは考え込む。
「じゃ、俺は先にリビングで待ってるから」
しかしその間に、幸一は扉に手を掛けた。
咄嗟にミリアムが思いついたのは、響子の呼び方だった。
「あの、センセー!」
「ん……?」
ミリアムのカタコトの日本語に、幸一は振り返る。
「その……」
「……なんだよ?」
「えと……おはよう、ございます……」
ミリアムは絞り出すように、か細い声で言った。
「……おう。おはよう」
ぶっきらぼうに幸一も返して、リビングへ向かった。
(響子の真似か? まぁ何でもいいや……)
幸一の返事を聞いたミリアムは、トタトタと小走りで洗面所へ向かった。
「……んふふ」
いつも無表情だったミリアムだが、張り詰めたものが無くなったかのように、どこか緩んだ表情をしていた。
「……あら、ミリアム。起きたのね」
顔を洗ってからリビングへ向かうと、幸一と響子が朝食を摂っていた。
「はい……朝食を摂りにきました」
「待っていて、すぐに用意するわ」
響子は元気そうなミリアムの姿を見て、嬉しそうに朝食を並べる。
「病み上がりだから、消化にいいものを用意しました。遠慮せず食べなさい」
「はい」
響子が出したのは卵粥とホットココアだ。
「……おいしい」
マイルドな昆布だしの味は口当たりが良く、それでいて塩味が効いている。
ミリアムはホットココアにも手を伸ばす。
「……甘い」
ミルクの甘みが口の中に広がり、それでいてココアのコクが喉の奥まで染みわたる。
「……ふふ」
ミリアムが朝食を食べていると、響子が微笑んだ。
「?」
「いえ、あんまりにも美味しそうに食べてくれるものだから、嬉しくて」
響子の言葉に、ミリアムは何を言っているのか分からなかったが、音を立てずに上品に食べる二人を見て、自分がはしたなく音を立てて食べていることに気付いた。
もっとも、響子は本当にただ嬉しかったのだが、ミリアムは少し頬を赤くする。
「……す、すいません」
「どうして謝るの? たとえ上品でも、先生みたいに仏頂面で食べるより、喧しくもおいしそうに食べるほうが、私は嬉しいんですよ?」
「おい、さりげなく俺を引き合いに出すんじゃねぇ」
「……」
いつも通りの二人の掛け合いに、ミリアムは頬を緩ませる。
「……よし、全部食べたな。そんじゃ……ついて来い。響子も後で来てくれ」
「はい」
「かしこまりました」
幸一は二人の返事を聞いてから、リビングを出た。
「……じゃあ、適当に座ってくれ」
幸一がミリアムを連れてきたのは、研究室だった。
「んじゃミリアム。早速だが、俺が分かった範囲でお前の人体発火現象のことを説明する」
幸一がオフィスチェア、ミリアムがパイプ椅子に座り向き合って話を始める。
「えっと、すいません……じんたい……何ですか?」
ミリアムは困惑したように首を傾げる。
「ん……人体発火現象……お前の呪いの正体だ。エヴァから聞いていないのか?」
「はい……ずっと、消えない呪いだと思っていました」
(エヴァのやつ……なんで何も言ってないんだよ……)
幸一はここには居ないエヴァに不信感を募らせた。
「あの……この呪いは……病気なんですか?」
ミリアムの不安げな顔に、幸一は改めて説明する。
「病気じゃねぇよ……人体発火現象は、身体が突然燃え始める現象だ。この現象は現在でも原因や原理が全く解明されていない。ときには怪奇現象とも言われる代物だ。まぁ現状は、呪いといっても差し支えない」
「……そんな」
「まぁ聞け。この人体発火現象にはいろんな学説が唱えられているが、その内の一つに、特殊体質ってのがある。生まれつき可燃性の物質を大量に体内に宿し、何らかの発火性遺伝子によって人体発火現象が起こるという説だな」
幸一はもともと、人体発火現象に対する学説をどれも信じていなかった。
どの学説も、根拠と呼ぶには薄く、偶然が重なって火災が人にのみ起こった事故と言われた方が遥かに納得できるからだ。
「ミリアム、お前を見て確信できた。この説が恐らく正しい。少なくともお前はこのケースだ。お前は生まれつき、人体発火現象を引き起こし、そして人体発火現象に耐えられる特殊体質なんだ」
「……私の、特殊体質」
ミリアムはその科学的な専門用語が、呪いの代名詞に聞こえていた。
「例えばお前の皮膚。本来、人体は炎に耐えられるようにはできていない」
「……そうなんだ」
「だが、お前には大量の水分を含んだ皮下脂肪があった」
「ひか、しぼう……?」
ミリアムの疑問を浮かべた反応に、幸一は乱雑に落ちてある人体模型を取り上げる。
「俺達が普段触れている表皮の下にあるのが皮下脂肪だ。皮下脂肪の主な働きは二つだ。一つは栄養や老廃物を運ぶこと。もう一つは、外からの衝撃や熱から体を守ること」
人体模型の表皮のパーツを外して、幸一は説明する。
皮下脂肪は脂肪という名前の通り、柔らかい肉の塊だ。もしも大量の水分を含んだ皮下脂肪の層があるならば、表皮の上で炎が発生しても軽症で押さえられるし、四十二度という危険な体表温度でも、活動できる。
「衝撃や熱……って……!」
話が繋がって、ミリアムは目を見開く。
「あぁ、そうだ。個人差はあるが、常人の皮下脂肪は一番分厚いところでも、精々十ミリ程度だ。だがお前の場合は、明らかにその倍はあるだろう。その分厚い皮下脂肪が、お前を炎から守っていたんだ」
幸一はミリアムに触れたとき、異様な柔らかさを感じ取った。戦場を生き抜いた筋肉質な肉体が、まるで赤子の肌のように肉厚で柔らかい感触というのは、まずあり得ない。
「……守って、くれた」
奇妙な言い回しに、ミリアムは困惑するしかない。
この呪いに何度も激痛を味わったし、いっそこの炎に焼かれて死んでしまいたいと願ったこともある。その身体が、自分を守っている。
「それと、肝心の発火する原理だが、これに関しては正直よく分からなかった」
幸一がこの一週間、色々と調べていたのはこのことだ。
しかし結局それを解明することはできなかった。
「だが何が着火の燃料になっているかは分かった。……結論から言うと、汗だ」
「汗……?」
幸一はミリアムの疑問に答えるように、付け加える。
「つっても、ただの汗じゃねぇ。精神性発汗ってやつだ」
「精神性発汗……?」
再び出てきた知らない専門用語に、ミリアムは首を傾げる。
「通常、俺達が暑かったり、身体を動かしたりして出てくる汗っつーのは、無味無臭の透明な汗だ。成分はほとんど尿と変わらない。だがお前の出している汗は少し違う」
昨日、ミリアムが倒れたときに、ミリアムは信じられない程に身体が熱くなっていたし、湯気が出る程に発汗していた。
白人の白い肌で見えにくかったが、幸一は確かにそれを見つけた。
「お前が出していた汗は、少し白く濁った汗だ。通常の汗と違って、その汗は油分を含んでいるんだ」
汗を出す汗腺には、エクリン線とアポクリン腺がある。通常の無味無臭の汗はエクリン腺から分泌されるが、アポクリン腺から分泌される汗は、タンパク質や脂質を含んでいるので、特有の臭いがする。
もしミリアムの汗が、大量の油分を含んでいるのだとしたら、それが着火の燃料になることも十分に考えられる。
「この白い汗は、ストレスや緊張によって出てくるもんだ。出る場所も脇や掌などの限られた場所だ。だがお前は、この白い汗が全身に出ていた。頭も含めてな。……んで、この白い汗が、恐らくお前の【人体発火】の燃料だって訳だ」
つまりミリアムは、アポクリン腺を身体中の至るところに保有しているというわけだ。
一通り説明を終えて、幸一は人体模型を元に戻して放り捨てる。
「……ここまでが、俺が分かったことだ」
「……そう、ですか……」
幸一の説明を聞いたところで、呪いが無くなる訳ではない。
そう物語る表情のミリアムに、幸一は自信たっぷりの笑みを向ける。
「おいおい、そんな顔すんなよ。お前の【人体発火】は……まぁ解明できていない部分もあるが、ちゃんと科学的なからくりがあるんだ」
「……でも、病気じゃないなら……特殊体質なら、治せないんでしょう?」
「あぁ。病気じゃないからな。少なくとも今の薬学では治すことはできない。お前が来てからの一週間は、なんとか特効薬を作ろうと俺も色々と試してみたんだが、無理だった」
それは先天性の障害と同じだ。治すことは不可能に近く、受け入れてその症状と向き合って生きていく必要がある。
「でも、対策はできる」
「……え?」
幸一は薬棚からプラスチップ製の薬品を取り出す。
「からくりが分かったからな……対策は簡単だったぜ」
さらに奥の机の引き出しから、常備してある使い捨ての注射器を二本取り出す。
「……ミリアム、腕を出せ。これから注射をする」
「は、はい……」
ミリアムが困惑しながらも、袖をまくっているとノックがされる。
「先生、響子です」
「おう。入れ」
「……先生、そんな恰好でミリアムの治療に当たっていたのですか?」
会って早々に小言を言う響子に、幸一は鬱陶しそうに告げる。
「うるせぇな。治療じゃねぇ、注射を打つんだよ。手伝え」
幸一の返事を効いて、いつもと違う薬剤師としての空気を響子は感じ取る。
「……ミリアム。注射をしたことはありますか?」
「……いえ」
「そう、分かったわ」
それを聞いて、響子は濡らしたガーゼを準備してから、ミリアムの服をまくった。
「針を刺すから、最初はチクッとするけど、頑張って耐えてね?」
「分かりました……あっ」
準備をする中で、ミリアムは響子の手に包帯が巻かれていることに気付いた。
「あの……その手は……もしかして」
ミリアムはずっと握っていてくれた手の温もりを思い出す。
「あら、覚えているの?」
響子の問いに、ミリアムは顔を赤くする。
「……はい。その……」
「よし。んじゃ打つぞ?」
注射の準備を終えた幸一がミリアムの前でしゃがむ。
「あ、はい……」
「これからお前に打つのは、汗を止める薬だ。【人体発火】の燃料が汗なら、それを止めちまえばいい。といっても、完全に止められるわけじゃないがな」
幸一は汗腺の働きを鈍くする薬をミリアムに打つ。
「っ……」
「痛いか?」
「いえ、思ったほどではありません」
「……よし、終わりだ。もう一本打つからな」
幸一は直ぐにもう一つの薬品から注射の準備をする。
「もう一つは、鎮痛剤だ。痛覚を鈍らせる。お前は痛覚を刺激されると【人体発火】を暴発してしまうからな……これで暴発を抑えられるはずだ」
ミリアムが倒れていたとき、間違いなく【人体発火】は発動していた。
それが意図してのものではないことは明らかだった。
さらにはミリアムに【人体発火】について質問したとき、痛みを想像することで発動していると答えていたことから、幸一はミリアムが精神的にも、肉体的にも痛みを感じるときに【人体発火】を暴発してしまうと考察した。
「……よし」
幸一は注射器をミリアムの腕から抜いた。
響子は手早く濡らしたガーゼをミリアムの腕に巻いて止血する。
「しばらくしたら効いてくる。汗を止めているから、慣れない倦怠感を覚えるだろうが、直ぐに慣れる。それと、痛覚を鈍らせているから、私生活には気を付けろよ?」
「は、はい……」
ミリアムはこんなに自分のために考えて、動いてくれる二人に困惑するしかない。
「あ、あの……センセー……」
「……なんだ?」
「あの……ありがとうございます。……私なんかのために……呪いを治してくれて」
ミリアムは頭を下げて、薬品や注射器を片付ける幸一にお礼を言った。
「治してねぇよ。それに、まだ対策は不十分だ」
「え?」
「お前の【人体発火】を完全に止めるには、精神性発汗を止める必要がある。さっきの薬は汗腺の働きを鈍くするだけで、完全に止められるわけじゃない」
幸一は片づけを終えて、腰に手を当てながら告げた。
「つーわけで、お前には勉強をしてもらう」
「……勉強?」
「ついて来い」
幸一はミリアムを二階にある書斎に案内した。
壁中に存在する本棚には、ぎっしりと本が埋め尽くされていた。
中央に一人分のオフィスチェアが置かれており、奥に広々とした机があった。
よく見ると奥の本棚は机の上だけで、机の下には足を伸ばせるスペースがある。
「ここは防音になっていて、集中するにはもってこいだ。これからはここをお前との勉強部屋とする。俺が使わないときは好きに使え」
「はい。ありがとうございます」
幸一はそこで中学生用の教材をいくつか机に並べる。科目は数学だ。
「俺がこれから、基本的な学業を教えていく。まぁ腐っても俺は薬剤師だ。それなりに頭もいいと思うから、分からないことがあれば遠慮なく言えよ?」
そう告げる幸一は、自信満々に口角を上げている。
「……はい……!」
その顔を見たミリアムも、期待せずにはいられない。
「んじゃ、早速始めていくぜ。先ずは図形からだ」
数時間後。
「……先生? お菓子を持ってきました」
「お、おう……入ってくれ」
響子はココアとコーヒー、クッキー、チョコレートパイを乗せたお盆を片手に、書斎に入って二人の姿を目にする。
「……頑張っているようですね。……先生が」
そこには、首をかしげて説明を待っているミリアムと、冷や汗を垂らしながら参考書のページをせわしなくめくっている幸一の姿があった。
「なんで学校の勉強ってこんなに難しいんだよ……ちくしょう……!」
勉強を始めて数分で、幸一はミリアムにドヤ顔で説明しようとして、図形の定理やら公式やらをすっかり忘れていることに気付いた。
「まぁ……頑張ってください」
何とか大人の矜持を守ろうと、分からないと白状しないところが余計に惨めだった。
響子は呆れながらも、幸一にコーヒーを渡す。
「はぁ……取り敢えず、これは明日解説する。次は円の問題だ。ここを解いてみろ」
「はい」
ミリアムは再び教材の問題に立ち向かう。
「ミリアム、ココアを持ってきました。洋菓子もどうぞ」
「ありがとうございます」
子供の好物である洋菓子を置いたというのに、ミリアムの視線は教材から離れない。
「素晴らしい集中ですね」
「あぁ。初めて学ぶ分野の三十分の小テストを十分で解きやがった。おかげで教えるこっちの気が休まらねぇ」
幸一はバリボリと洋菓子を貪りながら、ミリアムの凄まじい学習速度を愚痴る。
「……私に手伝えることがあったら言ってください」
「……そうする」
二人が話していると、ミリアムが顔を上げた。どうやら解き終えたようだ。
「……できました」
「ふむ、違うな」
幸一は鋭く言い放つ。
「その角には、円周角の定理を使うんだ」
幸一は面倒くさそうにミリアムの間違いを指摘しながら、補助線を引く。
コーヒーを片手に、手慣れたように計算式を書いていく。
(……ちゃんと見ていたんですね……ん……?)
くだらない愚痴を言っているように見えて、ちゃんとミリアムの勉強を見守っている幸一に、響子は嬉しそうに二人の背中を見る。
「んで、ここの角度を持ってきたら、補助線で直角三角形ができる。んで、……できた」
「いや、違います」
鋭く言い放ったのは、響子だった。
「そこは円周角だけで答えが出せますし、その定理は角の二等分線の定理ですよ?」
「……そういえばそうだった」
「……センセー……?」
流石に不信感を覚えたのか、ミリアムが幸一を怪訝そうに見る。
「……あぁもう……! 響子が教えてやれよ。俺はこんなクソの役にも立たん学業なんてとっくに記憶から消えたよ……!」
「……ミリアムの前でなんてことを言うんですか」
響子は幸一を諫めながら、幸一の間違えた問題を解いていく。
「言ったはずです。これは先生の仕事です。私ができるのは手伝いだけです。……はい。これで答えになります」
幸一の汚い字と違って、小綺麗な響子の計算式は遥かに分かりやすい。
「……ふん」
幸一はすっかりやる気をなくしたようで、そっぽを向いてコーヒーを飲み干した。
「……ありがとう、ございます」
「お礼は要らないわ。私はメイドだから、あなたと身分はそう変わりません」
その言葉に、ミリアムは思いついたように口に出した。
「……キョーコ」
「……はい?」
「それじゃあ、キョーコ……って呼んでいい、ですか?」
その言葉に、響子は目を丸くする。
(先生の真似かしら……? まぁいいでしょう)
ミリアムの拙い日本語に、響子は微笑みながら答えた。
「えぇ。ご自由に」
「やっぱ響子が面倒見た方がいいだろ」
どう見ても適任な響子に、たまらず幸一は愚痴った。
「いいえ、私は手伝いだけです」
「……手伝いねぇ」
「センセー、次はどうしますか?」
ココアをチビチビと飲むミリアムに、幸一は思案する。
(俺が教えられること……なんてあるのか……?)
少し考えこんでから、妙案を思いついたようにコーヒーカップを置いた。
「……そうだな、それじゃあ響子に手伝ってもらうか」
「はい?」

三人は庭に出た。
芝生でできた庭は広大で、小さく見積もっても六十平方メートルはある。
アメリカの豪邸ならではの広さだ。
「はっ、はっ、はっ」
「……」
ジャージ姿の幸一とミリアムは、シャトルランのように庭の端から端までを走っていた。
「まだ十往復もしていませんよ。頑張ってください」
三十メートル程の距離を何往復かしている内に、早くも幸一は息が切れてきた。
ミリアムは走る速度を幸一に合わせながら、息一つ乱さずに走っている。
二人が八往復したころに、幸一は崩れ落ちるように芝生に倒れ込む。
「……も、もう無理ぃ……!」
僅か数分のランニングで、幸一は地面に座り込んだ。
「……流石に運動不足ですよ。お水です」
「あぁ……」
響子の小言に反応する余裕もなく、幸一は水を飲む。
ミリアムには幸一が、とても体を動かすのが好きな性分の者とは思えなかった。
「……センセー……どうして運動を?」
「……免疫力を上げるには、十分な食事と睡眠……それ以外にも、運動が不可欠だ」
幸一は息を整えながら答える。
「……私のため、ですか?」
「まぁ俺も最近は体を動かしてなかったからな。いい機会だと思ったんだ」
幸一は立ち上がり、軽くストレッチを始めた。
「それよりミリアム、体は温まったか? ストレッチしておけ」
「はい」
軽く温まった体で、二人は体をほぐしていく。
「ストレッチできたら、これを付けろ」
幸一は響子から受け取った大人用のヘッドギアや膝当てなどの防具を装着する。
「これは……?」
ミリアムは初めて目にするそれらを、興味深そうに見つめる。
「体を守るための防具だ。……まぁお前が戦場で見てきた装備に比べたら紙切れみたいなものだろうが、一応つけておけ」
「ミリアムのは私が付けますから、こっちへ来なさい」
ミリアムは響子にされるがままに、幸一と同じように防具を装着した。
「これから組手をする」
「くみ、て?」
「格闘のみを用いた戦闘だ。相手を殺すことも、殺されることもない状態で戦うんだ。特にルールはないが……あ、でも【人体発火】は使うなよ?」
戦場で生きてきたミリアムには、組手の概念が良く分からない。
「……どうして、そんなことを?」
ミリアムにとって、戦いとは相手を殺して生きるか、殺されるかの勝負だ。
故に戦いは相手を傷つけるという絶対的な性質をよく理解していたし、だからこそ幸一と戦うことには強烈な抵抗感があった。
「あん? 別に大した意味はない。ただの軽い運動だ。どうせお前はスポーツなんてやったことないだろ? 組手なら手っ取り早く体を動かせるからな」
不安げな表情のミリアムに、幸一は構えをとる。
「……まぁ、安心しろよ」
「……?」
幸一は、不敵な笑みでミリアムに告げた。
「加減はしてやるつもりだ。全力で来な……揉んでやる」
軸足を半歩引いて半身になり軽く膝を曲げる。緩く脱力を効かせた右手を眼前に上げ、左手は発射に備えて脇元にしぼる。
その堂に入った風貌に、ミリアムは得体のしれない威圧感を覚えて、認識を改める。
(そうだ……この人は、キョーコの主人なんだ……!)
まるで歴戦の手練れのような、この余裕。ここへ来てまだ一週間程度の自分ごときが幸一を弱者と断ずるなど、軽率が過ぎる。
「……はい……!」
様になっている幸一の姿に、ミリアムは手加減が不要であることを悟る。
ミリアムは幸一の胸を借りるつもりで、臨戦態勢に入る。
「……いきます」
一度深呼吸をしてから、ミリアムは駆け出した。
同時に幸一も小走りで間合いを計る。
数秒の間に、二人の距離が潰れる。
「……ふっ!」
間合いに入った瞬間、ミリアムは飛び上がった。
「っ!? へぶっ!?」
そして驚くほどきれいに、ミリアムの飛び膝蹴りが幸一の顔面に炸裂した。
「あだっ!? ……ぐふっ」
吹っ飛んだ幸一は受け身も取れず芝生を転がり、うつ伏せに静止した。
「……あれ?」
あまりに一方的な瞬殺劇に、ミリアムは驚愕するしかない。
「……や、やるじゃねぇか。……げほっ」
鼻を強打された痛みで涙目になりながら鼻血をまき散らす幸一は、なんとかドヤ顔を維持しようとしているが、どこからどう見ても効いていた。
「はぁ……先生。鼻血」
響子はため息を付いてから、タオルを持って幸一に駆け寄る。
「あ、あの……センセー……?」
ミリアムは拍子抜けるよりも早く、幸一を傷つけてしまった罪悪感に襲われる。
「いいんですよミリアム。先生の自業自得です。ほら、鼻チーンしてください」
まるで子供の鼻水を拭きとるように響子は幸一の鼻をタオルで押さえる。
「大丈夫ですか? 一応、医療キッドも持ってきていますけど」
「……いや、なんとか、大丈夫だ……ぐすっ」
(うわぁ……泣くくらいなら最初からやらなければよかったのに……)
とうとう泣き始めた幸一に、響子は何とも言えない気持ちになる。
「とにかく、後は私が相手をしますから、先生は休んでいてください」
「……うん」
涙目の幸一は震える足で立ち上がり、トボトボ歩いていく。
「ミリアム、選手交代よ。先生じゃ、いくら病み上がりのあなたも運動にはならないでしょうし、私が相手になります」
そう言って響子はコキコキと軽く首や肩を捻り、骨を鳴らす。
特に構えたようには見えないが、既に臨戦態勢は整っている。
ミリアムもそうだ、本物の戦場に幸一のような堂に入った構えなど無い。
ただ戦う覚悟を決めた瞬間、戦士はそれが構えとなる。
「……全力で、いきますね……?」
流石に響子が相手となれば、ミリアムに遠慮はいらない。
響子は幸一が十分に離れたことを確認してから、ミリアムに告げた。
「えぇ。いつでも来なさい。もちろん武器は使わないから」
「……ふっ!」
先程と同じように……否、先程以上の速力でミリアムは踏み込む。
「やぁ!」
一直線に踏み込んだミリアムは吠えながら拳を放つ……と見せかけて音もなくしゃがみ込み、響子の足首を刈り取るようにローキックを仕掛ける。
響子は飛び上がってそれを避ける。
(本命はこっち……!)
ミリアムは脚を振った勢いを利用して軸足を入れ替える。
「はぁ!」
降りてきた空中の響子に、絶対に避けられないタイミングで後ろ回し蹴りを放つ。
「っ!?」
だが響子は、ミリアムの足首を掴んで止めた。
「くっ……!」
ミリアムは瞬時に飛び上がって、踵落としの体勢に入る。
「むんっ!」
対して響子は着地と同時に旋回。
ミリアムが足を振り下ろすよりも早く、投げ飛ばす。
「わっ!?」
遠くまで飛ばされたミリアムは、背中から地面を転がる。
「くぅ……!」
辛うじて体を回転させることで衝撃を逃がし、ミリアムはすぐに立ち上がる。
「はぁ……はぁ……!」
柔らかい芝生を転がっただけなのでかすり傷すら無さそうだが、ミリアムは肩で息をしながら冷や汗を垂らす。
「ほう……? 受け身を教える必要はなさそうですね」
投げ飛ばされたミリアムを見て、響子は感心したように呟く。
「……キョーコ……一体何者なんですか……?」
ミリアムは戦慄するしかない。
ここまで自分の動きを先読みされ、完璧と言える対処をされたことは無かったからだ。
「ふふん。響子は未来が分かるからな。普通にやっても勝てねぇよ」
そんな響子を自慢するかのように、幸一は声を掛ける。
「なんで先生が自慢げなんですか……」
「……え……未来……?」
幸一の不可解な言葉に、ミリアムは固まる。
「共感覚、絶対音感、スーパーテイスター、スーパービジョン、映像記憶、電磁波感知」
幸一が呪文のように並べたそれらは、ごく一部の人間に宿る特殊能力。
しかも、それらには共通点があった。
「……まぁ説明しても分からんだろうから、ざっくり言うとだな……響子は、身体に備わる感覚が、俺達常人のそれとは次元が違う」
そう、響子の特殊能力は全て感覚に関わるものばかり。
「そのおかげで、響子は生まれながらに人の未来が予知できるんだ」
響子の持つ超人的感覚から得られる情報は、もはや我々常人の世界で説明することは不可能だ。知覚される情報の全てが、文字通り次元が違う。
「もっとも、その莫大な情報を戦闘に活かせるのは、響子ぐらいだけどな」
【未来予知】。
響子は、視界内にいる他人の数瞬先の未来の動きや狙いを全て感知する。
「先生? あまり女性のプライベートを喋るのはよくないと思いますよ?」
幸一の憎たらしいドヤ顔に、響子は小言を告げる。
「ミリアムは【人体発火】を使えないんだし、いいだろ。……まぁとにかくだ、ミリアム。俺じゃ教えられないから、響子に色々と教えてもらえ……身体の使い方ってやつをな」
響子の実力を知る幸一は、何の心配もせず二人の組手を眺めていた。
「……すごい……!」
自分の目指すべき未来を見た気がして、ミリアムは興奮気味になる。
「……さ、無駄話は終わりよ。ミリアム、かかってきなさい」
「はい!」
そして今までよりもさらに苛烈な肉弾戦を、二人は繰り広げる。
ミリアムは芝生の砂を蹴り上げ、手に持った砂を投げつけ、響子の死角に石ころを落として、その反対方向から音もなく踏み込む。
この庭で出来る限りの五感では対処できない攻撃を、ミリアムは即座に実践していた。
(お見事です……が、この程度ならば経験済みです)
実力差は明白。だからこそ、ミリアムは嬉々として全力をぶつけられた。
「やぁ!」
投げつけた砂の中からミリアムは何度も拳を繰り出す。
響子はバックステップを繰り返しながら、その全てを避ける。
「ふっ!」
そのラッシュの中で、ミリアムは落ちていた石ころを蹴っ飛ばす。
不意を突いたその石ころすらも、響子は軽く掴み取る。
めげずにミリアムは身に付けていた肘当てを投げつける。
響子はそれも掴む。
「はぁ!」
両手の塞がった響子に、ミリアムは足払いを仕掛ける。
響子は飛び上がって避ける。
ミリアムは軸足を入れ替えて、後ろ回し蹴り。
奇しくも、最初の攻防と同じ展開だ。
(……同じ手を二度も使うとは……いや、違う……)
空中で響子はミリアムへの【未来予知】が途切れたことを予知した。
その予知通り、ミリアムは後ろ回し蹴りをする様に見せて、踵で砂を蹴り上げた。
「っ」
一瞬だけ、響子の視界が砂にまみれる。
予知していた未来が訪れて、この一瞬だけ完全な実力勝負となる。
(……来ないっ!?)
落下しながら響子はあらゆる攻撃を予測して手に持っていた肘当てを手放して備えるが、ミリアムの攻撃は来なかった。
「っ!?」
着地と同時に響子は、足場に配置された膝当てがあることに気付くが、もう遅い。
「ふっ!」
ミリアムは膝当てから伸びるマジックテープを引っ張る。
足をずらされて、響子は重心が傾いた。
「やああああっっ!!」
間髪入れずにミリアムは踏み込んで、渾身の力で響子の頭を地面に叩きつけようとする。
響子の頭が落下する先には石ころが置かれていた。
バランスを崩した響子は防ぎようが無い。手をつこうにも間に合わない。
「……っ!」
響子は持っていた石ころを踏み込んできたミリアムに投げた。
「っ!?」
ミリアムはその石ころに被弾。
「はっ!」
さらに投げた勢いを使って反対の前腕で着地、と同時にその状態からドロップキックでミリアムを吹っ飛ばした。
「がはっ!?」
脇腹に響子の蹴りを喰らって、ミリアムは芝生を転がっていく。
「ふぅ……本当にお見事です。まさかたった数分でここまで追い詰められるとは」
起き上がった響子が、ミリアムを称える。
この攻防においてミリアムは、完全に響子の虚をついていた。
(【人体発火】を封じられて、武器も無いのに私を追い詰めるとは……末恐ろしい天賦の才ですね……)
自分とは次元の違う底知れない才覚に、響子は戦慄しながらミリアムを見る。
「……ミリアム……?」
倒れ伏すミリアムが無反応なことに、響子は怪訝に思う。
「……これは……!? 先生っっ!!」
超人的感覚から、気絶したミリアムの左目から血が出ていることを感じ取った響子は大声で幸一を呼んだ。
「おわっ!? なんだ……?」
暢気に寝転んで居眠りをしていた幸一は、驚きながら二人を見る。
「ミリアムが目を負傷しました! 手当してください!」
「……分かった。研究室へ連れてこい」
すぐに事態の緊急性を感じ取り、幸一は冷静に対処する。
「はい!」
響子は焦燥感と罪悪感に駆られながらも、ミリアムを運んだ。

「……んぅ……?」
ミリアムは、自室のベッドで目を覚ました。
妙な違和感を覚えながらも周りを見渡す。傾いた西日が差し込んでおり、部屋をオレンジに染め上げている。時計を見ると、時刻は十七時を回っていた。
「これは……包帯……?」
ミリアムは違和感の正体である頭に巻かれた包帯を触って、左目を覆うように頭部全体に包帯が巻かれていることに気付いた。
「そうか、私……負けたんだ……」
戦場での敗北は死と同義だ。
ミリアムは敗北したのに生きていることを不思議に感じながらも、ベッドを降りる。
(ん……頭にダメージを受けたんだ……あの石ころだけで……)
ミリアムはふらつく足取りのまま、自室を出てリビングに向かう。
「ん、起きたのか」
リビングには、料理中の響子とソファで山積みの漫画を読んでいる幸一がいた。
「ミリアム……目を覚ましたのね……」
響子はミリアムを見るなり、気まずそうな顔をする。
「もうすぐ夕食ができるから……待っていてください」
気のせいか、その言葉も妙によそよそしく感じられる。
「はい」
ミリアムは自室へ戻ることなく、なんとなく食卓について待っていた。
「んく……ふぅ」
常備してある水をちびちび飲みながら、息を吐いた。
「……」
響子は何かを言おうと口を開いては閉じることを繰り返しながら、誤魔化すように黙々と料理を続ける。
「……あー……そう言えば、ミリアム」
そんな響子を見かねたのか、幸一は思い出したかのようにミリアムに話しかける。
「傷の方は大丈夫か? 左目を打ったらしいが」
「大丈夫だと思います。特に痛みもありません。ただ、少し頭が痛いです。足元がふらつくので、今は戦闘に支障が出ると思います」
言ってからミリアムは、それが不要なことだと気づいた。
自分の体調を正確に伝えるのは、テロ組織に叩き込まれた習慣だ。
「別に戦闘はしねぇよ。護衛も響子一人で十分だからな」
だが幸一は特に気に留めることもなく告げた。
「まぁ、明日は念のため病院に行くから、大丈夫だろ」
「え……?」
ミリアムは首を傾げる。
「知らないか? 病院。人の病を治すところだ」
「いえ、それは知っています。……でも、私なんかが」
「まぁ心配すんな。今回の治療費は全額響子持ちだ。それに身元不明でも受け付けてくれる医師がいる。あいつは天井知らずのお人好しだからな。治してくれるさ」
ミリアムは権利や治療費のことではなく、奴隷の身分でそんな待遇を受けてもよいのかという意味で言ったのだが、幸一はまるで気付いていない。
「……いいのですか? キョーコ」
ミリアムは料理中の響子の背中に話しかける。
「……えぇ」
しばらくしてから、響子は素っ気なくそうポツリと返事をする。
「別に無理をしなくてもいいですよ。この程度の傷なら、放っておいても」
ミリアムは、響子が治療費を出すことを嫌がっているのだと思った。
「いえ、無理をしているわけではありません」
「でも……」
「あなたは治療を受けて、早くその傷を治しなさい」
「……怒っていますか?」
「え?」
ミリアムは響子の妙な違和感の正体が分からず、素直に聞いてしまう。
「私が……弱いから、怒っているのですか?」
「……」
「……ぷっ、ははっ」
響子が呆気にとられる中、幸一はつい噴き出した。
「?」
「初めてお前の子供っぽいところを見られたな。……まぁ、大丈夫だ。響子はお前に怒ってなんかいねぇよ」
「……じゃあ、どうして」
「どうしてムスッとしているのかって? ……別に不機嫌なわけじゃねぇよ。逆だ……お前を傷つけて申し訳ないと思っているんだ」
「え……キョーコが……?」
大人が子供を傷つけてしまったことを申し訳なく思う。
そんな当たり前がミリアムの生きてきた世界には無かった。
少し顔を赤くしながら、響子は無言で料理を続ける。
「……あの、キョーコ。聞きたいことがあるのです」
「……何?」
ミリアムは気になっていたことを聞いた。
「……あのとき、確実に仕留めたと思いました。【未来予知】を使うにも不十分な状態だったと思います。……どうして、対応できたのですか?」
それは、先程の組手に関する話だ。
「あぁ……それはですね、私も【未来予知】だけなら負けていましたよ。確実にね」
響子は肩をすくめながら告げた。
「私には、今までの経験がありましたから。【未来予知】が通用しない経験がね」
響子は今までの戦場で【未来予知】が通用しない相手など、腐る程経験してきた。
ミリアムの攻撃に対応できたのは、その経験があったからだ。
「【未来予知】が途切れた瞬間に、あなたの次の一手を考えていました。でも何となくわかっていたのです。最強少女兵のあなたならば、必ず私の予知を超えて虚をついてくると」
「……どういうことですか?」
「虚をつかれることを想定して動いていたのです。着地したときから、あなたのことは見ずに、ずっと周りを観察していました」
だから響子は直ぐに石ころを投げる体勢に入り、対処した。
「砂をかけられてから、【未来予知】は使わなかったのですか?」
「えぇ。どうせ使ってもあなたはその予知を超えてくるでしょうしね」
「……予知を超えることなんて……」
「いくらでもあるわ。特に先生なんか、本当に予知が通じませんもの」
「おい、それ絶対意味違うだろ」
響子は呆れたように笑いながらそう言った。
「……あはは……私の、完敗ですね」
ミリアムも釣られて笑う。ミリアムにとって初めての組手だったが、双方が生存したままの勝負は、人生で味わったことが無い爽快感があった。
「ミリアム、これからも響子と組手はしたいか?」
「……はい」
「そりゃ良かった。明日病院に言って、怪我が治ったらまたするぞ」
「はい……!」
「……先生、夕食ができましたので、そろそろ食卓についてください。ミリアム、配膳を手伝って」
三人はいつになく和やかな空気の中で、夕食をとった。
翌朝。
「よし、んじゃ俺は支度するから。響子、ミリアムの支度を頼む」
「かしこまりました。ほら、行きますよ」
「え、支度って……?」
ミリアムの疑問に、洗面所へ向かう幸一が答える。
「これから外へ出るから、準備するんだ」
「え……?」
ミリアムは困惑したまま、響子に連れられて自室で着替えさせられた。
「ほら、あなたにも似合いそうなものを見繕いましたから、着なさい」
ミリアムは生まれて初めて、女性用の衣服を身に纏った。
「すごい……」
それは可愛らしいフリルのついた焦げ茶色のミニスカートの上に、ピンクのブラウス。首元にはチャーミングな水色の蝶ネクタイを響子に締めてもらった。足には火傷を覆い隠すような黒のスパッツを履かされた。
「これいくらしたのですか? ……こんなの、私には……勿体ないです」
「金銭面は気にしなくていいわ。全部先生が出しますから」
ミリアムは自室にある大きな姿見で自分の容姿を見る。
「……私には、似合いません」
ミリアムには顔を含めた大きな火傷の跡がある。それに頭部は火傷のせいで髪が伸びず、見栄えの悪い坊主のような格好だ。自分の醜さに涙が出そうになる。
「これでどう?」
そんなミリアムに、響子は大きめの黒いキャスケットをかぶせた。
目深にかぶれば、髪はほとんど気にならなくなる。
「……これは……?」
「キャスケットよ。日本では、探偵帽なんて言われたりもするらしいわ」
随分とマシになった自分の姿にミリアムが感動していると、響子が手を引いた。
「ほら、行くわよ」
リビングでは幸一も準備を整えたようで、寝癖を直したスーツ姿となっていた。
「うし、準備できたら出るぞ。響子、運転を頼む」
「かしこまりました」
響子が戸締りを終えてから、三人は外へ出て庭に止めていた一台の自動車に乗り込む。
響子が運転席に乗り、都心の方へ車を走らせる。
しばらくすると、都会の中の一際大きな高層ビルが見えてくる。
「着きました」
響子は窓を開けて、警備員に告げる。
「予約を入れた、早瀬です」
金属製のゲートの前には警備員が二人。
ゲートの横にいる開閉係がマイクを通じて話しかけてくる。
「確認します。……ハヤセ様ですね。どうぞ」
そう言うとボタンでゲートを開けて、警備員は車に道を開けた。
「ここは……確か……」
見覚えのある場所に、ミリアムは呟いた。
「ここは『ソリッド・シールド』のカリフォルニア支部だ。ミリアムは、俺の屋敷に来る前はここにいたのか?」
「はい、恐らく」
響子は地下の駐車場に車を止めた。
「さてと……」
三人は車を出て、エレベーターに乗る。
「あいつ、何階だったっけ?」
「二十八階です」
響子がボタンを押して、三人は上に向かう。
目的の階は、清潔な白い廊下が続く場所だった。左右には部屋がいくつもある。
ときたま通る人は、ディープグリーンのスクラブを纏っていた。
「病院……?」
「この階はある人物が隊長を務める『ソリッド・シールド』の医療部隊の診察室だ」
この階すべてが診察室という凄まじいスケールに、ミリアムは驚く。
三人は廊下を進み、とある部屋へと向かった。
幸一はノックと共に声を掛ける。
「ノア、居るか?」
「いるよ~」
中から聞こえてきたのは、性別の判別がつかない美声だった。
その返事に、幸一がスライド式の扉を開ける。
「やぁ、幸一、響子」
「おう」
「お久しぶりです。ノアさん」
中には机とパソコン、ベッドのみの簡素な部屋だった。
その中心、机の前のオフィスチェアに座るノアと呼ばれた人物に、ミリアムは目を奪われた。
それはエヴァとも響子とも違う種類の美貌だった。真っ白のケーシーに身を包むその人物は、緩やかなウェーブのかかった肌色のミディアムヘアをセンター分けにしており、精緻に整った相貌は丸みを帯びた童顔で、少し垂れ目な二重の瞳は藍色に輝いている。
纏う空気は穏やかで、その笑みは自然と人を安心させる。気品ある落ち着いた所作の中には聖母のような温かい包容力を感じさせた。
「こんにちは、お嬢さん」
そんな美女がミリアムと目を合わせ、にこりと柔らかく笑いかけた。
「こ、こんにちは……」
あまりの美しさにミリアムは少し緊張しながらも、ノアに挨拶を返す。
「ノア、さっそくミリアムの健康診断をしてほしい。少し前に嘔吐して倒れたんだ。んで、響子と組手をして左目を負傷した」
「それは大変だったね」
ノアはミリアムを見る。
「初めまして、僕の名前はノア。ノア・デビットマン。『ソリッド・シールド』の医療部隊の隊長をしているんだ。よろしくね」
「ミリアム・エイダンです。……センセーの、奴隷です……よろしくお願いします」
「奴隷……?」
ノアは幸一を怪訝そうに見る。
「あぁー……」
幸一はどう説明したものかと、頬をかく。
「……まぁいいいや。それよりミリアムちゃん、顔と爪をよく見せてくれるかな」
ノアはミリアムの身体に手を伸ばし爪の色やツヤ、目の血管や瞳の濁りなどを視診する。
「ふむふむ……まぁ、だいたい分かったよ」
たった数秒、ノアはちらっと見ただけでミリアムから手を離した。
「まず、慢性的な疲労があるね。特に精神面の疲労は最悪と言ってもいい。肉体的なことを言うと、免疫力の低下が挙げられるかな。……あとは、その火傷のことだね」
「あぁ、そっちは問題ない。……というか、俺が何とかする」
すかさず口を挟んだ幸一に、ノアは肩をすくめる。
「……そっか。なら、後は言うことはないかな。薬としては、解熱剤かな。少し熱があるみたい。それから免疫力が落ちているから、ビタミン剤や栄養剤も忘れずにね」
そしてノアは、ミリアムに巻かれている包帯に目を向けた。
「それじゃあ……ミリアム、包帯を取ってもいいかい?」
「……はい」
ミリアムはキャスケットを取った。
「ふむ……」
ノアは毛髪の無いミリアムの頭部に特に反応することもなく、慣れた手つきでミリアムに巻かれた包帯を優しくとった。
「……ふむ……」
ミリアムの左目は、閉じたまま大きく腫れ上がり、青く変色している。
血が滲んている状態で、火傷の跡も相まってとても痛々しい。
響子がその光景に罪悪感を覚える中、ノアは左目に手を伸ばす。
「少し触るね?」
ノアは瞼に触れて、目を開けて眼球を視診する。
「……この傷は、どうやってできたんだい?」
「私が石を投げて、ヘッドギアの隙間に被弾しました」
「……まず、眼球には問題は無いよ。視力にも支障はないと思う。問題は瞼の方だね。傷口からばい菌が混入して炎症を起こしているんだ。それに筋膜が再生した形跡がある。恐らくは瞼の一部が、千切れていたんだと思う」
「……マジか」
「ただの石ころでこの傷を作るとは……流石だね、響子」
ノアは素直に響子を称賛するが、響子は気まずそうな顔で尋ねる。
「治りますか?」
「もちろんだよ。痛々しいけれど、十分自力で回復できる範囲内だよ。ただ、さっきも言ったけど免疫力を含めて、身体が弱っているからね。運動も程々に、温かいお風呂に浸かってしっかり休んでね」
「……ありがとな。ノア」
幸一はノアに礼を言って、響子に目配せをする。
響子は内ポケットから封筒を取り出す。中にはぎっしりと札束が入っていた。
「これくらい別にいいよ」
「いやそうじゃない。これからある治療をしてほしい。その前金だ」
受け取ろうとしないノアに、幸一が告げる。
「ある治療?」
「ミリアムの精神性発汗を止めて欲しい。ミリアムは元少女兵……戦場で生きてきたんだ。俺達じゃ手に負えない……頼む」
「なるほどね……」
その言葉に、ノアは遠慮がちに封筒を受け取った。
「それじゃあ、やってみるね……んんっ」
そう言って、ノアはパソコンを操作して音楽を流した。
咳払いしてから、一際美しい声でノアは話し始めた。
「……ミリアムちゃん。こっちへおいで?」
自然の森を思わせる川の流れ、落ち葉、虫の鳴き声などがパソコンから流れ始める。
「え……?」
するとミリアムはまるで目の前の空間が、世界から切り離されたような錯覚に陥る。
「ほら……おいで?」
「あ……」
気づけば、ミリアムは涙を流していた。
思い出すのは最後に両親に甘えた記憶。
「……っ」
どうしようもなく、甘えたいという気持ちが溢れ出てくる。涙を流しながらミリアムはふらふらとノアの懐へ歩いていく。そして倒れ込むように、ノアの胸元へ顔を沈めた。
「ほぉら、よしよし……」
ノアは優しく受け止めて、ミリアムの頭を撫でる。
「……あ……あぁ……!」
「……頑張ったね。でも、もう大丈夫」
ミリアムは自分でも理解が追い付かないが、とにかく涙が止まらなかった。
(なんなの……!? 私、一体どうしちゃったの……!?)
ノアはその後もミリアムを優しく撫でながら、穏やかな声色で大丈夫と唱え続けた。
ミリアムは声を殺しながらノアの胸元で泣き続けた。
どれくらいの時間が経ったのだろうか。
時間を忘れてノアの抱擁に身を任せていたミリアムは、いつしかミリアムは澄み渡るような落ち着きを取り戻した。
「ふぅ……ふぅ……! ……もう、大丈夫です……」
「……そっか。じゃあ、離すよ?」
一瞬、ミリアムはこの温かい抱擁を失うことに後悔しそうになるが、すぐに幸一と響子の存在を思い出して、何とか離れる決意を固める。
「……はい」
ノアはその返事を聞くと、ゆっくりと手を離した。
「……すげぇな」
「お見事です」
二人の様子を見守っていた幸一と響子は、ノアに心からの称賛を送る。
「えへへ。それほどでも」
可愛らしく微笑んで照れるノアに、ミリアムは尋ねる。
「……一体、何をしたんですか? 私……普段はあんなに泣き虫じゃありません。それに……ノアさんの声を聞いていると、何だか体が……」
「体が軽くなったみたい……だろ?」
言葉にできないミリアムの疑問を、幸一が言語化する。
「センセー、知っているんですか?」
「まぁな。ノアが使ったのは、F分の一ゆらぎ。……癒しの声だ」
F分の一ゆらぎの声。
人体にリラックスを与え、自律神経を整え、精神を安定させるヒーリング効果を持つ癒しの声色。ピンクノイズとも言われ、小川のせせらぎや心拍音などはヒーリングミュージックとして用いられる。パソコンで流していたのはこの音だ。
これは生体のリズムがF分の一の周波数と共鳴することで起きる。
「んで、ノアはこのF分の一ゆらぎを自在に操ることができるんだ」
「すごい……でも、音だけでこんな……」
ミリアムはにわかには信じられない。
「ノアのゆらぎは特別製だ。患者の生体リズムに完璧に合わせたゆらぎの声は、人体をあり得ない速度で超回復させる。……もはや超能力の領域だ」
「あはは、そんな大層なものじゃないよ」
「そうでなくとも、ノアは包容力の塊だからな。……いつ見ても、同じ男とは思えん」
「え……?」
さらりと告げた衝撃的な事実に、ミリアムは固まる。
そんなミリアムにノアは苦笑する。
「あはは……やっぱり勘違いされていたんだね」
「そりゃそうだろ。お前の美貌は、俺でも惚れそうになる」
幸一の素直な誉め言葉に、ノアは顔を赤くして俯いた。
「……先生、セクハラは辞めてください」
響子は冷徹に幸一を諫める。
「え、あ、すまん……冗談だ」
妙な空気になり、幸一は焦ったように謝罪する。
「う、うん……分かっているよ」
ノアは気まずそうに愛想笑いをする。
そんな二人に、ミリアムはエヴァとの会話を思い出し、幸一にそういう趣向があるのかと素直に疑問に思った。
「センセー……もしかして、男の人が好きなんですか?」
「なわけあるか! ……というか、同性愛者でも流石におじいちゃんは射程圏外だろ……」
「むぅ……」
おじいちゃんという言葉に、ノアは不機嫌になる。
「え、おじいちゃん?」
何処からどう見ても、ただの美少女……いや、美少年だ。
肉体年齢は高く見積もっても二十代だろう。十代と言っても通じるくらいだ。
「そうだ。実年齢は誰も知らんが、少なくとも俺の倍以上は生きているぞ」
「え……でも……」
「ノアさんは不死細胞の持ち主ですから。寿命が無いんですよ」
「不死、細胞……?」
出身も人種も不明なノアに、確かに言えること。
それはノアが【特別】な細胞を持っていることだ。
「老化しない細胞。無限に細胞分裂を繰り返すことができる。……まぁ要するに、老いることなく活動し続ける細胞ってこっだ」
不死細胞。
一九五一年にヘンリエッタ・ラックスという女性が癌により、わずか三十一歳という若さで亡くなる。だが彼女の細胞はこの時代はおろか、今現在も生きている。
通常人の細胞は死ぬまでに四十回ほどの分裂を繰り返す。だが病院で腫瘍から細胞のサンプルを入手され、実験室の中で生き続ける彼女の細胞は、未だに分裂を続け、不死身の細胞として世界中で医学の発展に寄与している。
彼女のそれは子宮癌という病気から突然変異で生まれたほんの一部の細胞だ。
だがノアは、その【特別】な細胞を生まれつき、心臓と脳に持っていた。
故にノアに寿命の概念は存在しない。それどころか臓器移植や輸血、人工骨などの医学の力を持った今、ノアはどんな大怪我を負っても生き永らえる肉体と化した。
「人呼んで、【不老不死】。正真正銘の不死身さ。羨ましいもんだ」
あまりにも衝撃的な説明に、ミリアムが驚愕に固まっていると。
「すげぇだろ? 昔計算したんだが、だいたいノアの実年齢は――
「はいはい! もう僕のことはいいでしょ! 要件が終わったなら、さっさと帰ってよね。僕はこれでも隊長で、結構忙しいんだから!」
年齢の話をされ、慌てて幸一の言葉を遮ってノアは三人を追い出そうとする。
「あ、あぁ……。色々とサンキューな。また来るよ」
追い出される中、幸一は口早にお礼を告げた。
「……うん」
また来る、という言葉にノアは頷いてから、扉を閉めた。
「……あ、ミリアムちゃん」
だが閉めきる前、思い出したようにノアはミリアムと目を合わせる。
「はい?」
そしてミリアムにだけ聞こえる声量で、優しく告げた。
「二人を信じて、頼って……思いっきり甘えていいんだよ? 僕なんかよりもずっと頼りになると思うからさ」
「……わかりました」
ミリアムは頷いてから、診療室を出た。
「んじゃ、帰るか」
「かしこまりました」
「はい」
帰り道、ミリアムはノアの言葉を思い返していた。
(……信じる……か)
もう疑う余地はない。
幸一と響子は、ミリアムにとって味方だ。
安心を与えてくれる、素敵な人だ。
(……)
その日。ミリアムは人知れず、二人を信じる決意を固めた。
第三章終わりです。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
いやぁ、ダメダメ主人公にしようと思って色々と脇役を練りすぎたせいで、主人公があまりにも空気ですね。それに響子やノアの能力はあまりストーリーに絡んでこないので、もっとさらっと流してしまってよかったと思います。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
